親から受け継いだ空き家や古いアパートをどうするか、悩んでいませんか。不動産投資に興味はあっても、相続物件の扱い方や借入を伴うレバレッジ戦略には不安がつきものです。本記事では、相続物件を活用する利点と注意点を整理し、レバレッジ効果を安全に高める方法を具体例で解説します。読み終えるころには、手元の資産を成長させる第一歩が踏み出せるはずです。
相続物件を活用するメリットと課題
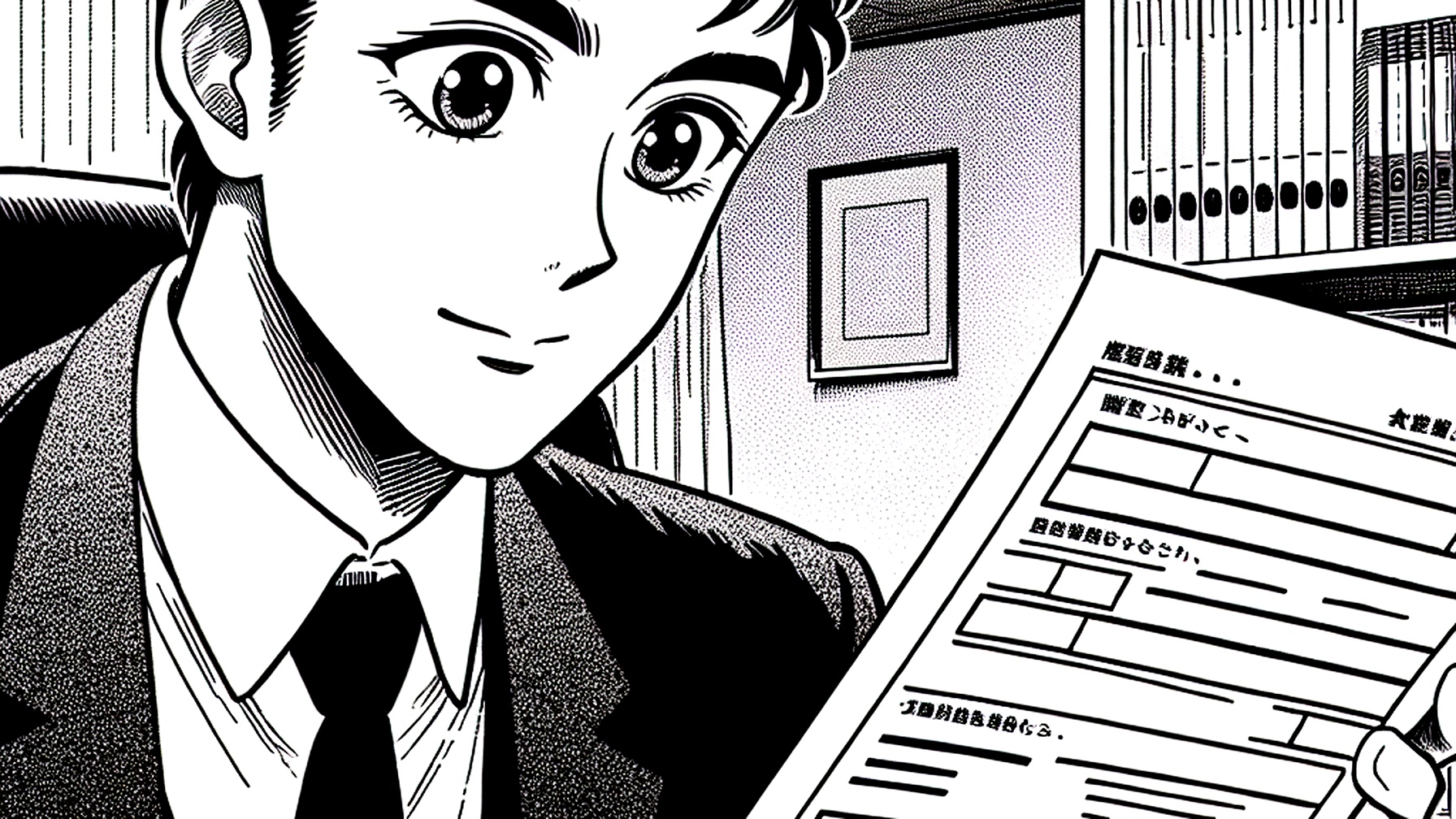
まず押さえておきたいのは、相続物件には取得費がほぼ不要という大きな利点がある点です。購入資金がかからないため、賃料がそのままキャッシュフローに反映されやすく、投資回収期間が短くなります。一方で、築年数の経過や立地の陳腐化により、空室や修繕コストが重荷になるケースも多いのが現実です。
国土交通省の「住宅・土地統計調査(2024年)」によると、築40年以上の賃貸住宅の空室率は全国平均で24%に達しています。つまり、相続した建物が老朽化している場合、そのまま運用すると収益性が下がるリスクが高いのです。また、相続人が複数いる場合は共有状態が権利調整を難しくし、意思決定の遅れが機会損失につながります。
重要なのは、物件の現況を冷静に診断し、再投資か売却かを早期に判断することです。外壁や配管の劣化が進んでいれば、リノベーションによる価値向上を検討するほかありません。逆に立地が悪い、需要が乏しいなど将来の収益期待が薄いなら、売却して別の投資へ組み替える決断も合理的です。
レバレッジを効かせる資金計画の基本
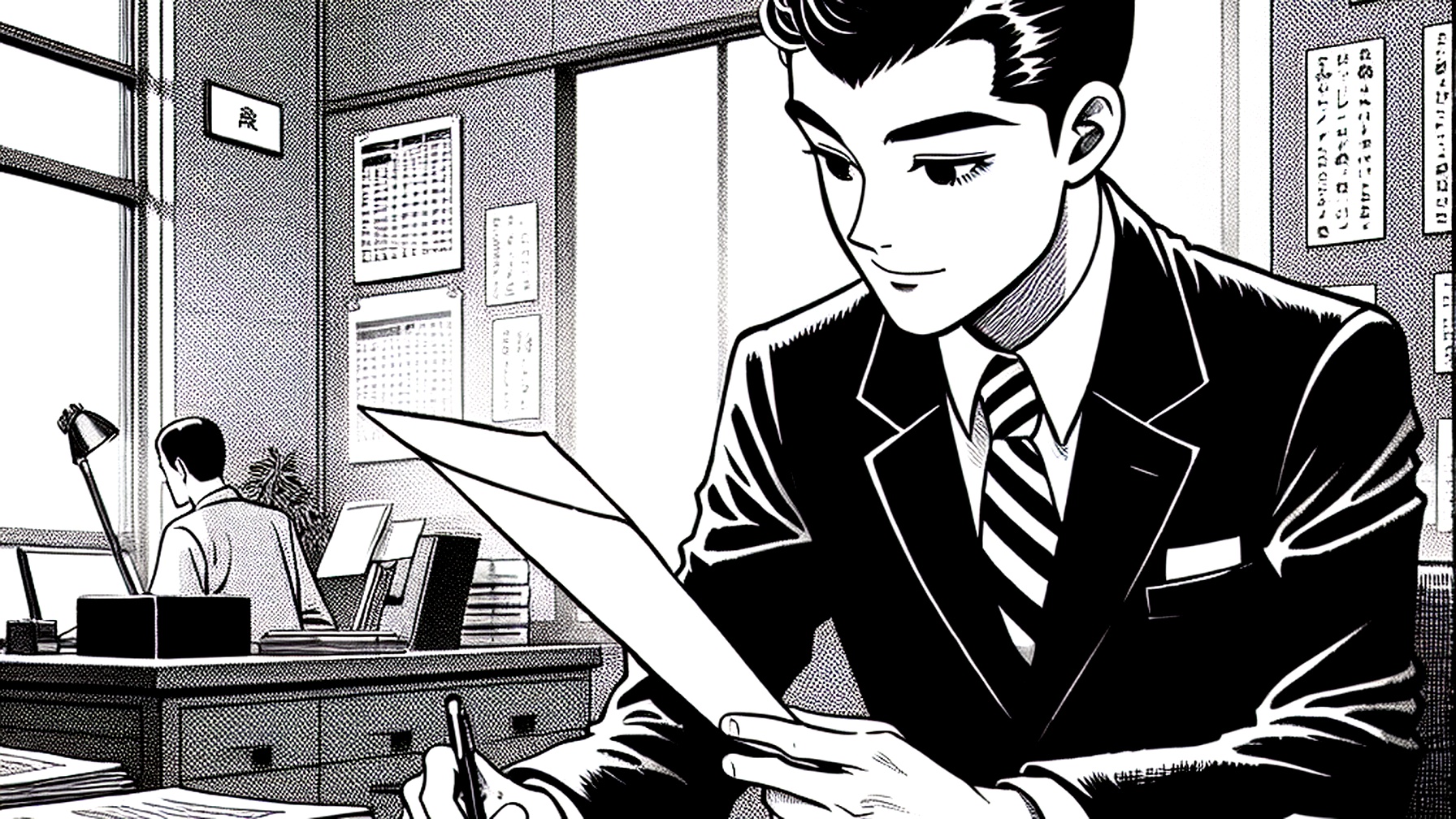
ポイントは、自己資金ゼロでも始められるからこそ、借入比率を慎重にコントロールすることです。相続物件を担保に追加融資を引き出せば、複数物件への拡大が可能になります。しかし、返済負担がキャッシュフローを圧迫すると、本末転倒になりかねません。
一般に金融機関は、相続物件の評価額の70%程度まで融資する傾向があります。例えば評価額3,000万円の物件なら、2,100万円までの追加借入が現実的です。金利を1.5%、期間20年と仮定すると、年間返済額は約123万円となり、月々10万円程度の家賃収入があれば返済比率が50%を下回ります。つまり、利回りと返済額のバランスが鍵を握るのです。
さらに、レバレッジ効果を高めるには固定・変動金利の使い分けが有効です。長期保有を前提とする場合、2025年10月時点で大手銀行の固定金利は2%前後、変動金利は1%前後に収まっています。利上げ局面を想定しつつ、複数行に相談し条件交渉を行うことで、総返済額を大幅に削減できます。
収益シミュレーションとリスク管理
実は、シミュレーションを保守的に作るほど、レバレッジの恩恵を安全に受けられます。まず家賃下落率を年2%、空室率を20%、修繕費を年間家賃収入の10%として試算し、それでも黒字になるか確認しましょう。この厳しい条件をクリアできれば、実際の運用はより安定する可能性が高まります。
空室リスクに備える方法として、法人契約の推進やペット可へのリノベーションなど、差別化戦略が有効です。また、家賃保証(サブリース)の導入は一見安心に映りますが、保証賃料の減額条項があるため、契約内容を細部まで確認する必要があります。
キャッシュフロー計算書を毎月更新し、予算と実績の差異を可視化する習慣も欠かせません。収益性が悪化する兆候を早期に察知できれば、リフォームや賃料改定といった対策を速やかに打てます。言い換えると、数字に強いオーナーこそ、レバレッジを味方にできるのです。
2025年度の税制と法改正ポイント
まず押さえておきたいのは、2025年度も「小規模宅地等の特例」が継続している点です。被相続人の自宅を賃貸に転用する場合でも、一定要件を満たせば評価額が最大50%減額され、相続税が軽減されます。ただし、取得後3年以内に賃貸を開始しなければ適用できないので、計画的な行動が必要です。
2025年1月からは、固定資産税の経年減価率が見直され、築30年以上の木造住宅の課税評価が平均7%上昇しました。一方で、耐震改修を行った場合の税額控除は延長されているため、古い建物ほど改修による節税効果が相対的に高まります。
なお、賃貸住宅の省エネ改修に対する「住宅省エネ2025補助金」は、工事請負契約が2025年12月31日までの案件が対象です。補助上限は一戸あたり60万円ですが、ZEH基準を満たせば最大100万円まで拡張されます。資金繰りと合わせて検討すると、レバレッジ効果をさらに高められるでしょう。
- 2025年度主要改正の影響
– 小規模宅地等の特例:適用要件維持 – 固定資産税評価:築古物件の上昇 – 省エネ改修補助:12月末契約が期限
成功事例に学ぶ運用戦略
ポイントは、相続物件を核にポートフォリオを組み立て、段階的に拡大する姿勢です。都内で築35年のワンルームマンションを相続したAさんは、リノベーション費用500万円を借入でまかない、家賃を2万円アップさせました。年間家賃12万円の上乗せに対し、返済負担は年36万円程度で、手残りがプラス6万円となっています。
さらにAさんは、賃料アップ後に物件評価が向上したタイミングで追加融資を獲得し、郊外に戸建て賃貸を購入しました。ここでも自己資金はほぼゼロですが、二つの物件のキャッシュフローを合算することで、返済比率を45%に維持しています。つまり、レバレッジを効かせつつも、現金収入で安全域を確保する好例といえます。
一方で、築50年の木造アパートを相続したBさんは、全面建替えを選択しました。解体費と新築費用を合わせて1億円の借入を行い、表面利回り8%の物件に変貌させたのです。建物が新しいため修繕コストが抑えられ、長期固定金利1.4%で借りられたことで、安定収益を実現しています。
まとめ
結論として、不動産投資 相続物件 レバレッジの三つを組み合わせると、自己資金を抑えながら資産拡大を狙える強力な戦略が生まれます。ただし、物件診断、資金計画、税制把握という三つのステップを飛ばすと、レバレッジは逆効果になりかねません。まずは現況を冷静に分析し、数字に基づいたシミュレーションを重ねることが成功への近道です。読者の皆さんも、相続物件というチャンスを活かし、2025年度の制度を味方につけて一歩前へ踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅・土地統計調査2024 – https://www.stat.go.jp/
- 国税庁 小規模宅地等の特例 2025年度版 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省 固定資産税評価基準改正2025 – https://www.soumu.go.jp/
- 経済産業省 住宅省エネ2025補助金概要 – https://www.meti.go.jp/
- 日本銀行 金融機関貸出動向2025年9月 – https://www.boj.or.jp/

