パンデミックが沈静化し経済活動が再開した今、住宅市場は再び熱気を帯びています。しかし、物価高や金利上昇のニュースを聞くたびに「今から買って本当に大丈夫だろうか」と不安になる人も少なくありません。本記事では、アフターコロナの環境下でマンションを一棟買いするメリットと注意点を、初心者でも理解できるように整理します。最後まで読むことで、自己資金の組み方から出口戦略まで一連の流れがつかめ、具体的な次の一歩が見えてくるはずです。
アフターコロナで変わった市場環境
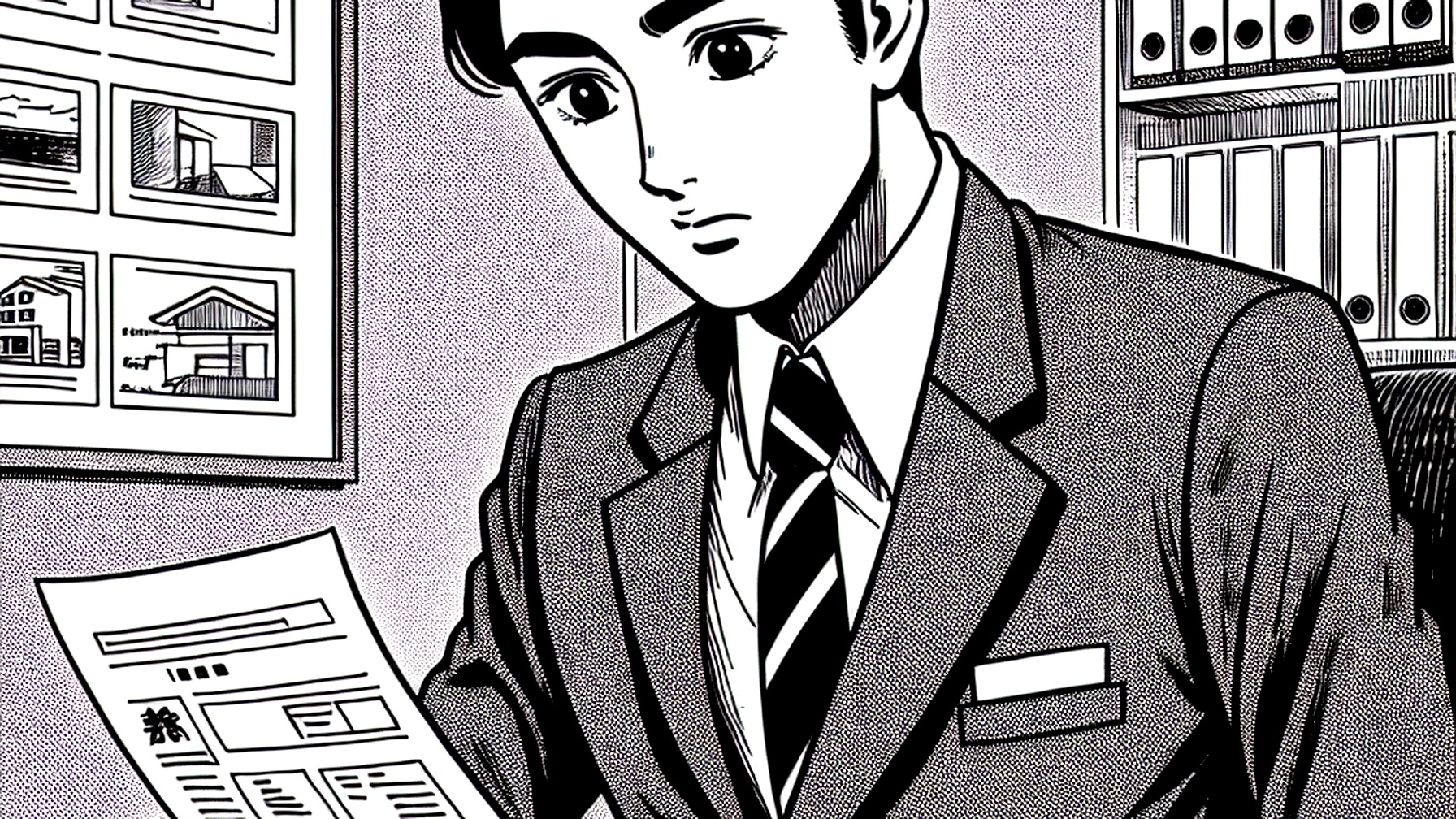
まず押さえておきたいのは、需要と供給のバランスがコロナ前とは大きく変わった点です。出社回帰が進む一方で在宅勤務は根付き、都心の駅近物件と郊外の広めの間取りが同時に求められる二極化が進みました。
東京23区の新築マンション平均価格は2025年10月時点で7,580万円となり、不動産経済研究所のデータによると前年比3.2%上昇しています。つまり、資産価値が底堅いエリアでの投資は依然として有効です。また、外国人観光客が急増しホテル需要が高まる中、民泊用途での運用を視野に入れる投資家も増えました。
一方で建築コストは資材高騰の影響を受け、特にRC造(鉄筋コンクリート造)の建築費はコロナ前比で15%程度上昇しています。その結果、中古の一棟マンションに資金が流れやすく、利回りの目安も表面6〜7%で落ち着いてきました。重要なのは、購入価格が上がっても賃料が一定水準を保てるエリアかどうかを見極めることです。
一棟買いと区分所有の違い
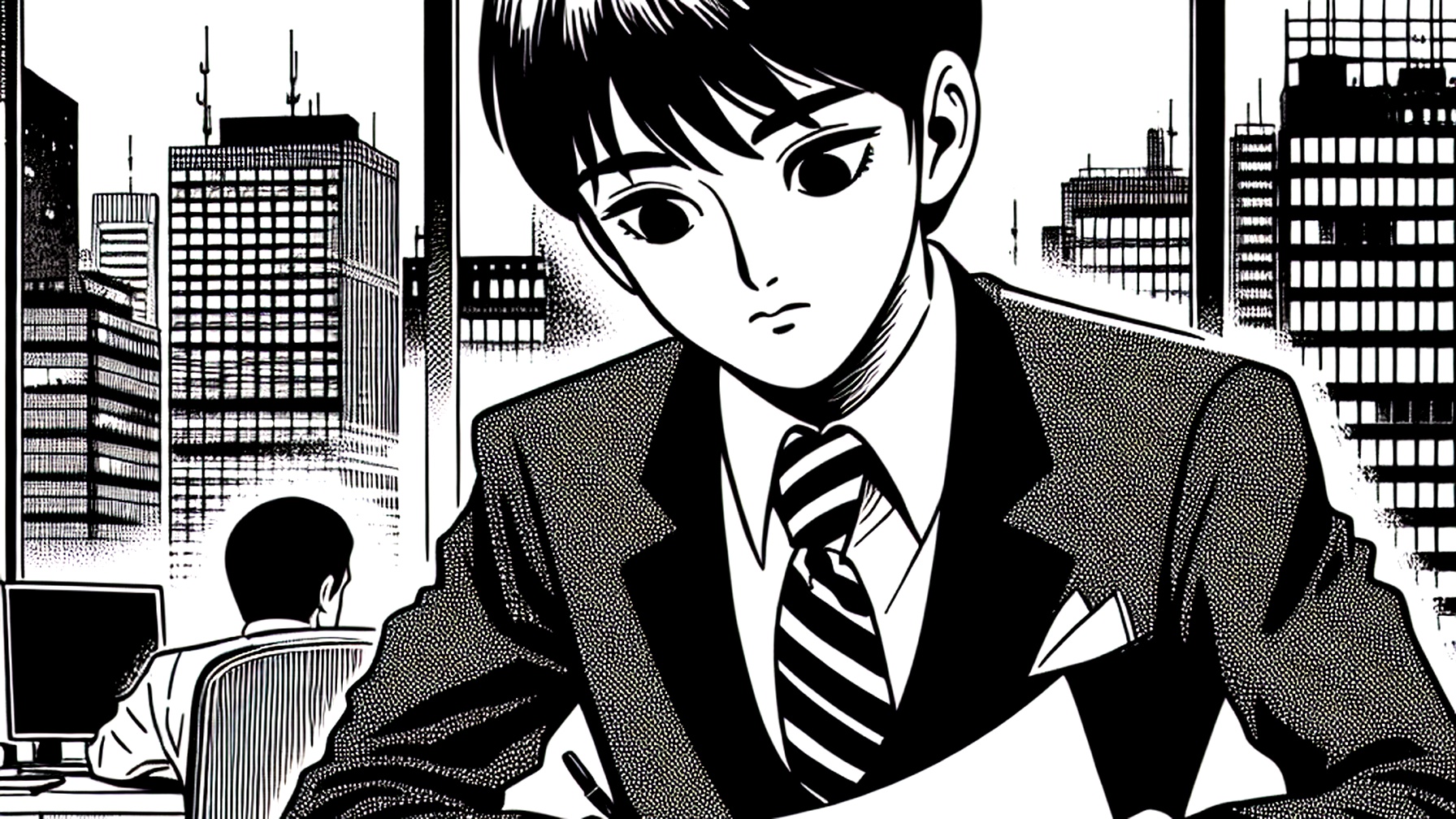
ポイントは、収益の安定性と運営コントロールの度合いがまったく異なるところにあります。区分所有は少額から始められますが、管理方針を自分だけで決められません。
一棟買いの場合、修繕計画や賃料設定を自ら主導できるため、長期的な資産価値を高めやすくなります。例えば、築20年木造アパートを購入し、外壁塗装や室内フルリフォームに1,200万円を投じた投資家は、家賃を1戸あたり月1万円アップさせ、年間収入を120万円増やしました。運営の自由度が直接収益に跳ね返る好例と言えます。
また、土地と建物をまとめて評価してもらえるため、金融機関の担保認定額が高く出やすい点も見逃せません。さらに、入居者が複数いるため一部屋が空いても収益全体への影響が限定的です。ただし、初期投資が大きくなる分、融資期間が長期化すると総支払利息が膨らむ点には十分注意しましょう。
資金調達と金利動向
実は、金利がじわりと上昇傾向にある今こそ金融機関の選定が成果を左右します。住宅ローンより高めの金利が適用される投資用ローンでも、地方銀行と信用金庫では0.5%前後の差が珍しくありません。
2025年現在、多くの金融機関が一棟RC造であれば最長35年、木造であれば最長25年の融資期間を設定しています。ここで重要なのは、返済比率を家賃収入の50%以内に抑えることです。例えば年間家賃が1,000万円なら、元利返済の上限を500万円と設定し、空室や修繕費に備える余裕を確保します。
変動金利を選ぶ場合、金利上昇リスクをヘッジするため、固定と変動を半分ずつ組み合わせるミックスローンが効果的です。また、2025年度も継続する「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金を活用すれば、耐震改修や省エネ化工事に対し最大250万円の補助が得られ、実質的な自己資金を圧縮できます。
収益シミュレーションの考え方
まず押さえておきたいのは、楽観シナリオだけで判断しないことです。年間家賃収入に対して10%の運営費、15%の空室率、さらに金利上昇2%という厳しめの数字を設定し、キャッシュフローが黒字になるかを検証します。
たとえば購入価格1億円、表面利回り7%、自己資金2,000万円、金利2%・期間30年で計算すると、空室率15%でも年間手残りは約170万円です。ここに大規模修繕として15年後に1,500万円かかると想定し、毎年100万円を修繕積立に回すプランを組み込めば、突発費用にも耐えられます。言い換えると、現金のクッションが収益の寿命を延ばす鍵になるのです。
また、火災保険と家賃保証会社の費用も忘れずに計上します。保険料は物件規模や構造で異なりますが、年間40万円前後が目安です。家賃保証に加入すれば滞納リスクを抑えられる半面、初年度家賃の50%程度の費用が発生します。これらを含めた実質利回りで投資判断を行いましょう。
リスク管理と出口戦略
重要なのは、投資開始時点で出口を想定しておくことです。一棟買いは売却時に買い手が限定されるため、表面利回り6%以上を保つ状態で運営し続けると売却しやすくなります。
修繕履歴を細かく残し、エネルギー効率の改善などESG(環境・社会・ガバナンス)要素を取り入れた運営を行うと、金融機関の評価がアップし、次の買い手がローンを組みやすくなります。結果として高値売却につながるケースが増えています。
一方で、災害リスクは年々高まっているため、水害ハザードマップを確認し、浸水想定区域外を優先することが望ましいです。加えて入居者ターゲットを明確にし、学生エリアならオンライン内見を積極活用するなど、時代に合わせた募集方法を試すことで空室期間を短縮できます。
まとめ
本記事では、市場環境の変化から資金調達、シミュレーション、出口戦略まで一棟買いの流れを総点検しました。アフターコロナでも都心を中心に需要は底堅く、適切なエリア選定と保守的な収支計画を行えば、安定したキャッシュフローが期待できます。次の行動としては、気になるエリアの家賃相場と金融機関の融資条件を具体的に調べ、簡易シミュレーションを作成してみてください。実際の数字を動かすことでリスクとリターンのバランスが見え、投資判断が格段にクリアになります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku
- 日本政策金融公庫 – https://www.jfc.go.jp
- 総務省 統計局 – https://www.stat.go.jp
- 気象庁 ハザードマップポータル – https://www.jma.go.jp/jp/flash_hazard_map/

