人口減少時代でも安定収入を得たい、けれど区分マンションでは物足りない。そんな悩みを抱える方に向け、私は実際に築18年の4階建てマンションを一棟買いし、運営5年目を迎えています。本記事では購入の決断理由から資金調達、運営中のトラブルまでリアルな数字を交えながら公開します。読了後には、一棟買いのメリットとリスクを具体的に把握し、自分に合った投資スタイルを判断できるようになるでしょう。
一棟買いを選んだ理由と戦略
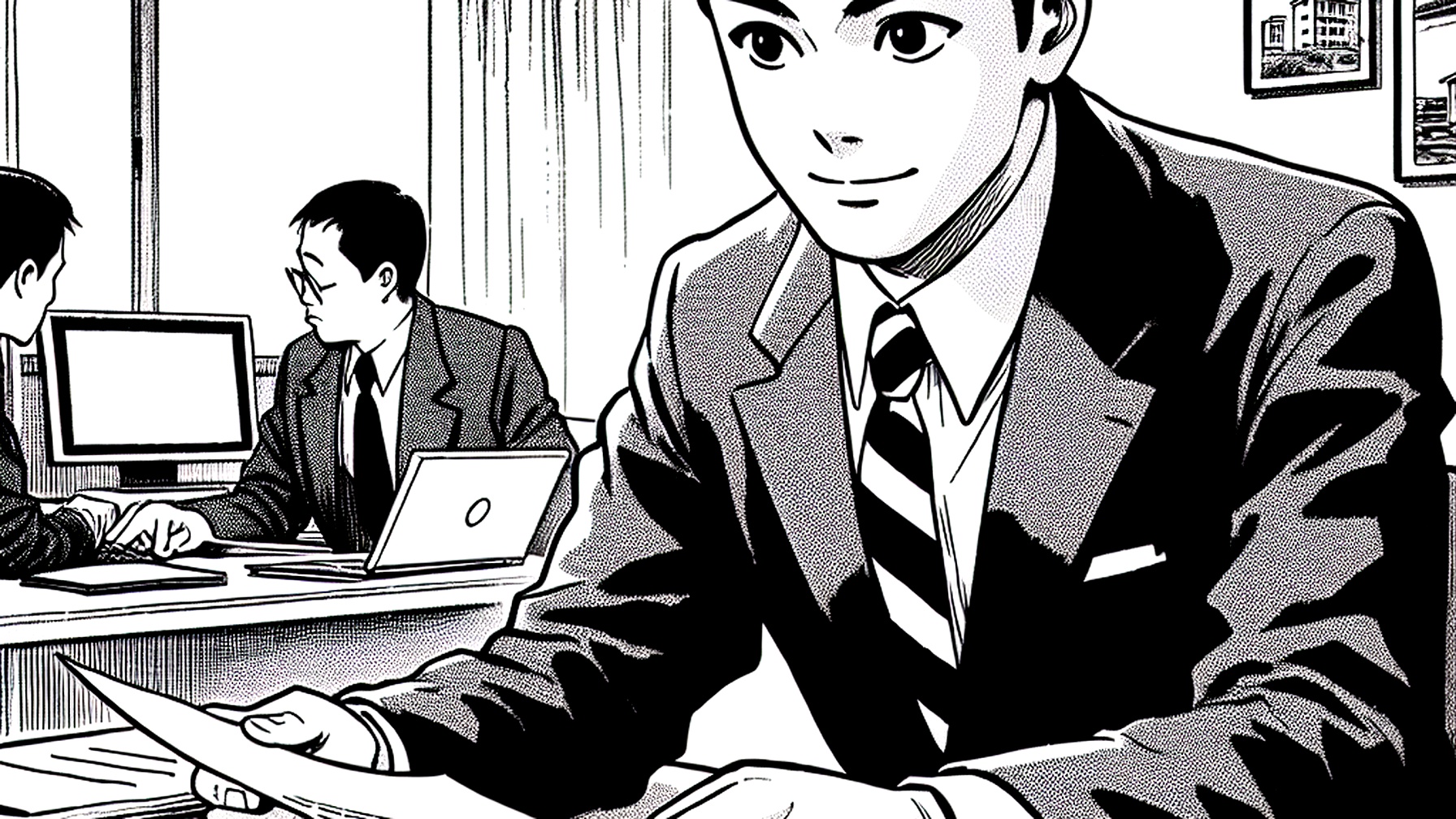
ポイントは、収益のコントロール幅と将来の出口戦略を自分で描けるかどうかです。区分所有では管理組合の決定に左右されますが、一棟買いなら修繕時期から賃料設定までオーナーが主導できます。
まず私は東京都心の平均利回り4%前後に対し、城南エリアの駅徒歩10分物件で表面6.1%を確保しました。都心プレミアムの空室リスクが低い点を重視しつつ、築年数による価格調整で利回りを底上げした格好です。また、一棟買いは土地割合が大きく減価償却費が抑えられますが、土地活用の自由度が高いぶん将来の建替えプランを描きやすいという利点もあります。つまり、初期投資こそ大きいものの、建物寿命全体を使ったキャッシュフロー設計がしやすいのです。
さらに、入居者層を単身者と若い共働きカップルに絞り、Wi-Fi無料と宅配ボックスを導入しました。2025年の国交省「住宅市場動向調査」でも、単身者が物件を選ぶ決め手は通信環境と配送利便性が上位を占めています。実際、私の物件でも月額1万円弱の設備投資で退去率が年間4%まで下がり、長期リースを実現できました。
購入前の資金計画と金融機関交渉
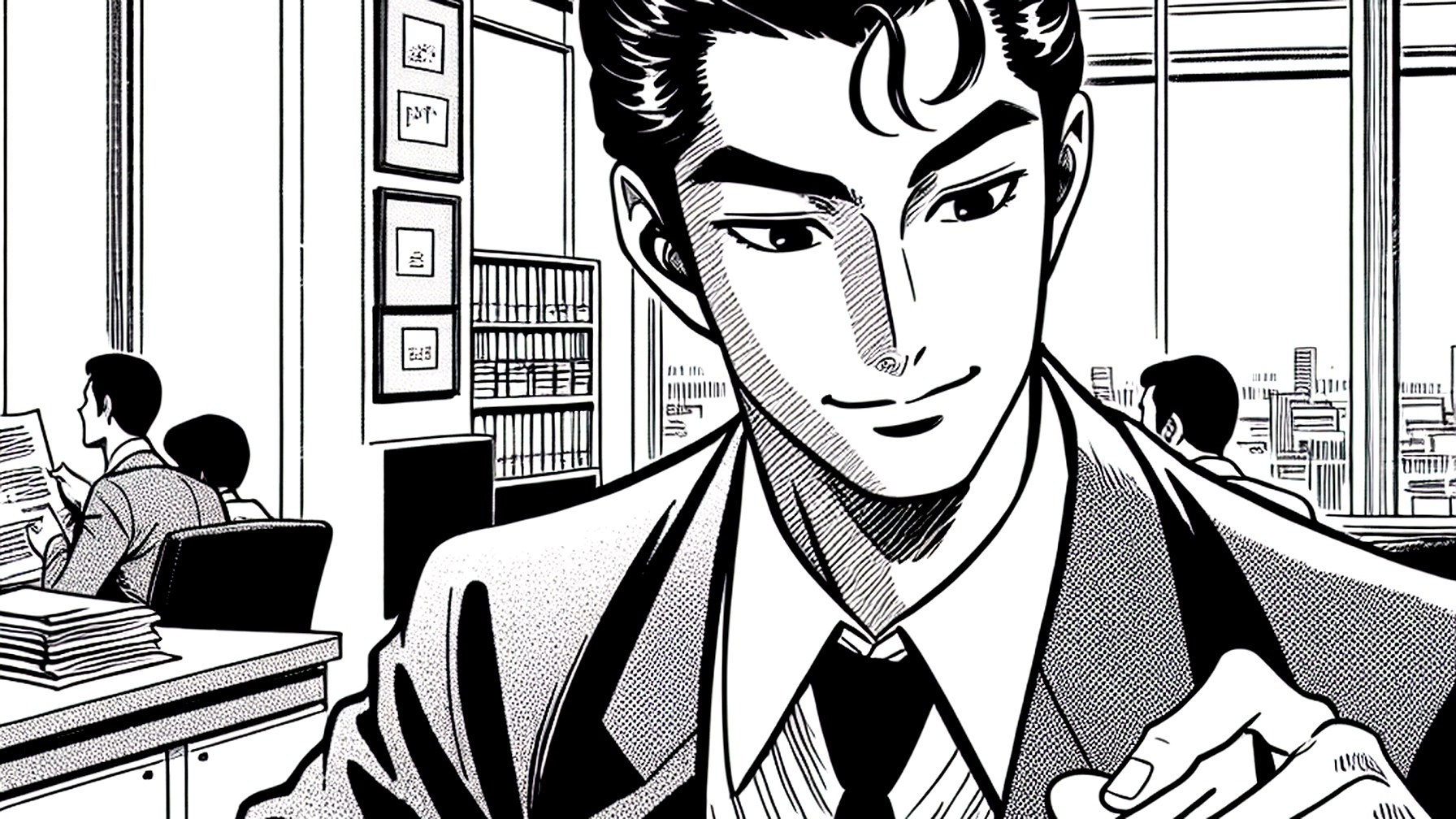
実は、一棟買いのハードルは物件選定よりも融資条件にあります。私が選んだのは築18年・価格1億9,800万円、土地評価比率48%という銀行好みの案件でした。自己資金は4,000万円を投入し、残りは地方銀行で金利1.4%、期間25年のローンを引きました。
金融機関との交渉では、賃料下落を年1%で見積もった厳しめの収支計画を提示しました。日本銀行の貸出動向データによれば、投資用不動産ローンは2025年上期も残高が前年比+1.8%と小幅増にとどまっています。競合が増えにくい今こそ、保守的な計画を示すことで低金利を引き出す余地が大きいのです。また、火災保険と地震保険を10年一括で付帯し、リスクマネーを保険料に含める形で自己資本比率を高める提案も行いました。その結果、頭金比率は20%台ながら、金融機関の審査をスムーズに通過できました。
購入前には修繕積立金相当を別口座に300万円確保しました。これは東京都「建築物の定期調査制度」への対応費を想定したものです。運営開始後に急な大規模修繕が生じてもキャッシュフローを圧迫しない態勢を整えることが重要でした。
運営一年目のリアルなキャッシュフロー
まず押さえておきたいのは、表面利回りと実質利回りの差です。購入翌年の総家賃収入は年間1,212万円、空室損と管理費を差し引いた実質収入は1,080万円でした。一方、ローン返済と固定資産税を合わせた支出は約910万円。結果として手残りは170万円、実質利回りは約3.6%となりました。
この数値だけを見ると低く感じるかもしれません。しかし、減価償却費として建物価値の80%相当を定率法で計上し、課税所得を250万円圧縮できたため、税引後キャッシュフローは約230万円に増えました。国税庁の所得税速算表を参照すると、課税所得が400万円以下なら税率は20%未満で済むため、実効利回りはさらに改善します。
また、2025年度の固定資産税軽減措置(新築から3年間1/2)こそ対象外ですが、耐震改修促進法による税額減免を申請し5年間で総額60万円の削減効果が得られました。つまり、税制優遇を踏まえた実質利回りで評価しないと、一棟買いの真価を見誤る恐れがあります。
想定外のトラブルと解決策
基本的に、トラブルは複合的に発生します。私の場合、外壁タイルの浮きと給水ポンプの故障がほぼ同時に起こり、見積額は合計280万円でした。ここで役立ったのが事前に積み立てた修繕準備金と管理会社とのパートナーシップです。
タイル修繕は国交省の長寿命化診断基準を満たす硅砂吹付け工法を採用し、費用を20%削減しました。給水ポンプはエネルギー消費効率の高いモデルへ更新し、東京都の「中小ビル省エネ改修助成金(2025年度上限300万円)」を申請。結果として補助金120万円が交付され、自己負担を半減できました。この制度は申請時点で締切があるため、管理会社と連携し書類作成を前倒ししたことが奏功しました。
さらに、入居者対応では24時間コールセンターを外部委託し、一次対応コストを年間36万円に抑制。物件レビューサイトでの評価が向上し、新規募集時の賃料を逆に2,000円アップできるという、副次的なメリットも生まれました。
2025年度制度を活用した出口戦略
重要なのは、運営しながら売却のシナリオを描くことです。私は購入時から10年後の建替えもしくは売却を想定し、土地評価の上昇余地があるエリアを選定しました。東京都の都市計画によると、2028年に最寄り駅が再開発地区に指定され、容積率緩和が見込まれています。これにより敷地活用の向上が期待でき、売却価格の押し上げ要因となります。
また、2025年度税制改正で維持された「長期譲渡所得の軽減税率(所有5年超で20.315%)」を活かし、保有期間7年以降の売却で税コストをミニマイズする方針です。加えて、法人名義での買い手を想定し、毎年の修繕履歴と省エネ性能評価書をクラウドで共有できるよう整備しています。透明性が高い物件は、銀行評価が伸びやすく価格交渉を有利に進められるためです。
出口を意識したバリューアップ策として、屋上を太陽光パネルとルーフトップガーデンに転用する計画も検討中です。都内では再エネ設備による固定資産税減額措置が継続しており、2025年時点で最大3年間1/2の軽減が適用可能です。キャッシュフローの底上げと売却時の付加価値向上を同時に狙う戦略が功を奏すかどうか、引き続き検証していきます。
まとめ
マンション投資で一棟買いを選ぶハードルは高いものの、運営と資産価値の両面で主導権を握れる点が大きな魅力です。資金調達では保守的なシミュレーションと税制優遇の活用が欠かせず、運営段階ではトラブルを先読みした修繕計画と助成金申請が収益を守ります。そして、出口戦略を早くから描くことで市場変動に左右されにくい投資が可能になります。本記事を参考に、皆さんも自分に合った立地と資金計画を練り、一棟買いの可能性を現実的に検討してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2025 – https://www.mlit.go.jp
- 不動産経済研究所 新築マンション市場動向2025 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 日本銀行 貸出動向統計2025年上期 – https://www.boj.or.jp
- 東京都 建築物省エネ改修助成事業 2025年度要綱 – https://www.metro.tokyo.lg.jp
- 国税庁 所得税の税率表 令和7年度 – https://www.nta.go.jp

