不動産投資を始めたばかりの方から「ローンの金利が高いままでも大丈夫か」「RC造のマンションは本当に長持ちするのか」といった相談をよく受けます。金利がわずか1%下がるだけでも、30年ローンでは数百万円の差が生じるため、借り換えは利益を左右する重要な判断材料です。本記事では、RC造(鉄筋コンクリート造)物件に投資するメリットと、2025年10月時点の最新金利を踏まえた不動産投資ローンの借り換え戦略を解説します。読み終える頃には、借り換えで得られるキャッシュフロー改善効果と、手続きの注意点が具体的にイメージできるようになるはずです。
RC造が投資家に選ばれる理由
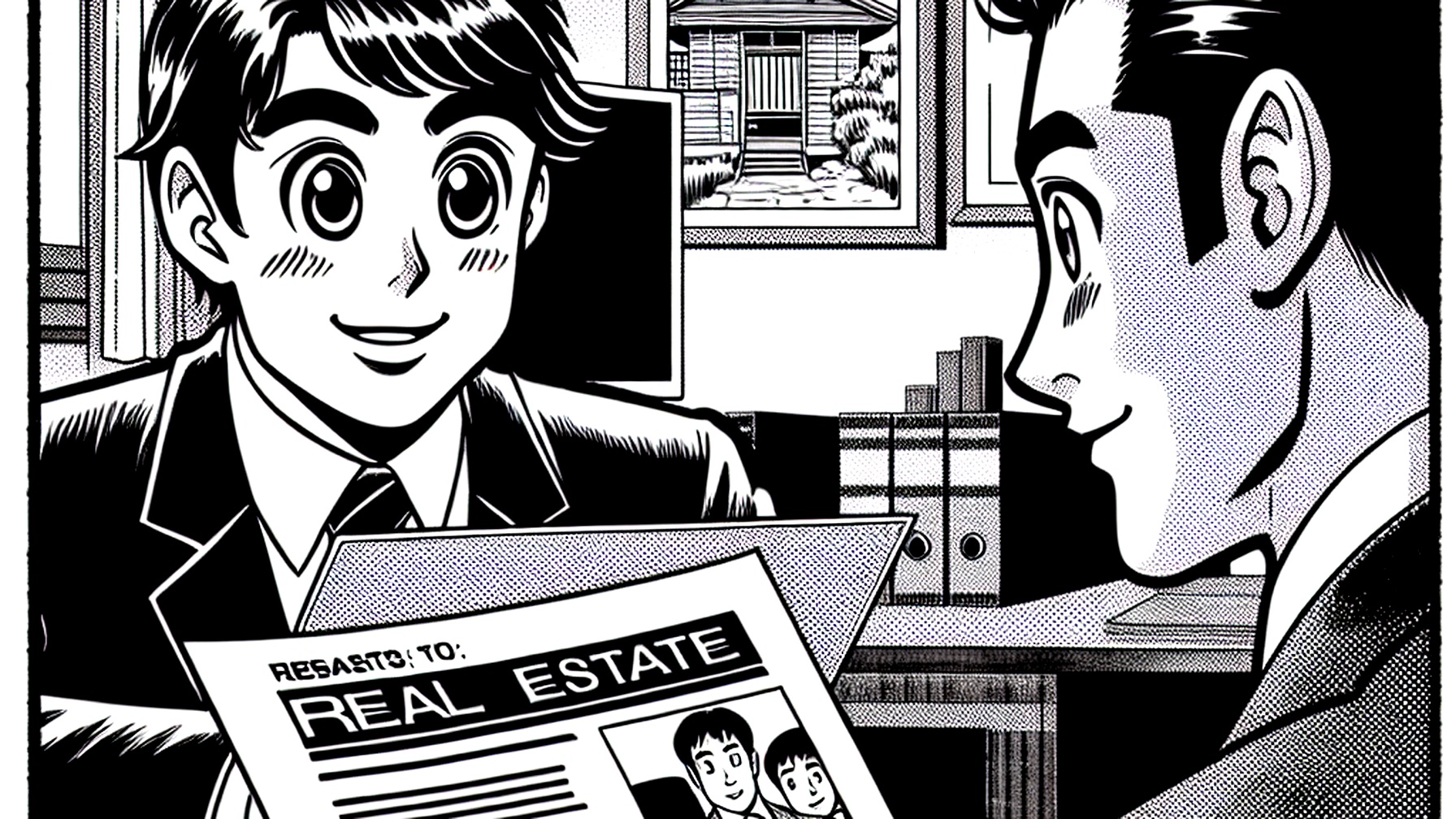
重要なのは、RC造が持つ耐久性と金融機関からの評価の高さを正しく理解することです。RC造は木造や軽量鉄骨造に比べて耐用年数が長く、国税庁の法定耐用年数では47年に設定されています。つまり、築25年のRC造でも残存期間が長く、融資期間を取りやすい点が大きな強みになります。
一方で、建設コストは重く、同じ規模でも木造より2〜3割ほど高くなる傾向があります。しかし長期的には修繕回数が少なく、年間の維持費を平準化できる場合が多いです。2024年度の国土交通省調査では、RC造賃貸の平均修繕費は年間坪当たり2,800円と、木造の約3,200円を下回りました。初期投資こそ大きいものの、長期保有を前提とするなら優位性が際立つというわけです。
さらに、災害リスクを巡るテナントの意識変化も追い風です。大規模地震や水害が頻発する中で、耐震性と防火性に優れたRC造へ需要がシフトしています。金融機関も空室率の低下を見込みやすいため、評価額が伸びやすく、借り換え時の担保査定でも高得点を得やすい点がポイントになります。
借り換えを検討すべきタイミング
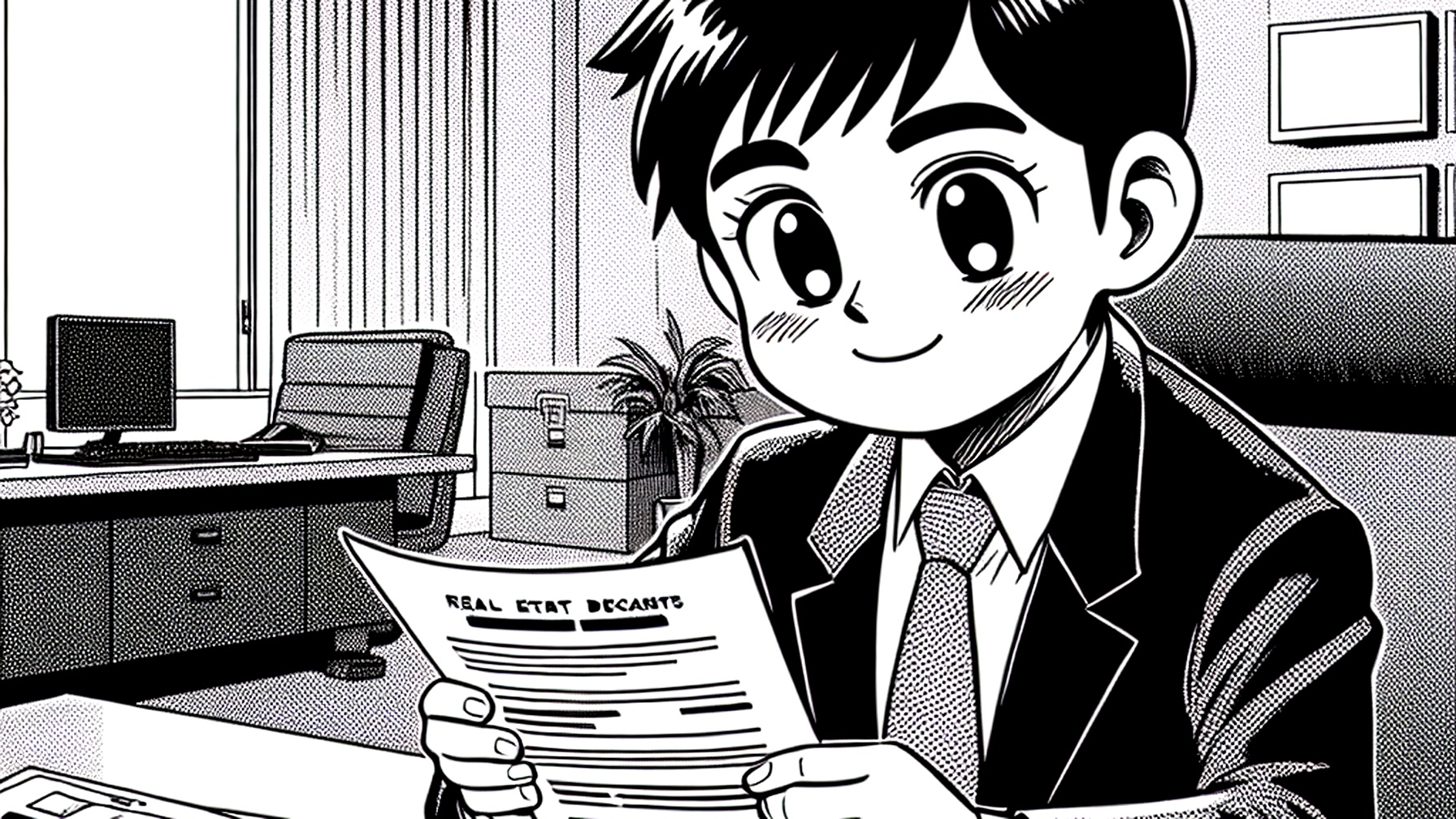
まず押さえておきたいのは、借り換えの判断基準が「金利差」だけではないことです。返済期間の残年数、手数料、そして物件価値の上昇・下落が複合的に影響します。一般的に残期間が10年以上あり、金利差が0.5%以上あれば具体的に試算する価値があります。
2025年10月の変動金利は平均1.5〜2.0%、固定10年は2.5〜3.0%です。仮に2017年に2.9%の固定金利で組んだローンを残25年で1.7%へ借り換えると、5,000万円借入の場合、総返済額は約600万円減少します。ここから新たな諸費用を差し引いても、手取りキャッシュフローが年間20万円程度改善するケースが珍しくありません。
しかし、残期間が短いと効果は薄れます。金融機関が設定する違約金(繰上げ返済手数料)は平均1.5%前後で、さらに登録免許税や司法書士報酬が加算されます。残り7年未満の場合、これらのコストでメリットが相殺されるため、手数料体系を細かく確認する姿勢が欠かせません。
金利差と総返済額の具体的な比較
ポイントは、金利差だけでなく融資期間変更による影響も合わせて試算することです。以下は例示です(数字は試算値、単位:万円)。
| 項目 | 現行ローン | 借り換え後 | | — | — | — | | 金利 | 2.9% 固定 | 1.7% 変動 | | 残期間 | 25年 | 25年 | | 毎月返済 | 23.6 | 20.6 | | 総返済額 | 7,080 | 6,170 | | 手数料等 | – | 120 | | 差引効果 | – | 約790減 |
この比較で明らかなように、総返済額は約13%削減されます。ただし、変動金利に切り替える場合は将来の金利上昇リスクを織り込む必要があります。日本銀行は2025年春に長期金利操作のレンジを見直しており、今後も緩やかな上昇が予想されます。言い換えると、0.5%の金利アップでも効果が半減するシミュレーションを併用し、最悪シナリオでもキャッシュフローが黒字を維持できるか確認することが肝心です。
また、RC造物件の場合、築年数が進むと大規模修繕費が増える点も計算に入れましょう。一般的に築30年を超えると外壁補修に1,000〜1,500万円かかります。借り換えによって生まれたキャッシュフローの一部を修繕積立へ回すと、資本的支出に備えやすくなり、長期保有の安全性が高まります。
借り換え手続きの実務と注意点
実は、借り換えは新規融資と同水準の審査が行われるため、書類準備が鍵を握ります。必要書類には決算書や確定申告書、レントロール(入居状況表)のほか、RC造なら耐震診断報告書を求められることもあります。過去に区分所有で瑕疵が発覚した事例が増えたため、金融機関のチェックは年々厳格化しています。
手続きがスムーズに進むよう、物件の収支状況をグラフ化し、修繕履歴も整理して提出すると好印象です。特にRC造は長寿命ゆえに修繕計画の有無が重視されます。築20年超で防水工事や共用部照明のLED化を済ませていれば、金利優遇幅が0.1〜0.2%上乗せされるケースも確認されています。
一方で、個人属性の変化にも注意が必要です。新規借入時より年収が下がっていたり、他のローン残高が増えていたりすると、希望額を満たせない場合があります。借り換えを検討する際は、直近2期分の所得を安定させ、カードローンなど小口債務を事前に整理しておくと審査通過率が高まります。
2025年度の制度と金融機関の動向
まず、2025年度に有効な代表的支援策は「住宅ローン控除の投資用適用除外」が続く点です。投資用不動産は控除対象外のため、金利控除に頼らず収支改善を図るには借り換えが一層重要になります。また、「登録免許税の軽減特例(電子申請)」は2026年3月まで延長が決定しており、電子移行すれば物件持分移転の税率が0.3%から0.15%に下がります。RC造の高額物件ほど恩恵が大きいため、電子申請への対応が必須と言えるでしょう。
金融機関側では、地方銀行が事業性評価を強化し、長期固定金利を縮小する動きが顕著です。対照的にネット銀行はAI審査を拡大し、変動1.5%前後の低金利を提示しています。総務省「住宅・土地統計調査」によると、賃貸住宅の空室率は全国平均13.1%で下げ止まりの傾向を示しており、RC造の需要安定が裏付けられています。つまり、投資家にとっては、低金利を維持しながら安定入居が期待できるRC造へ資金を集中させる好機といえます。
金融機関の金利引き下げ競争は2025年後半も続く見込みですが、金利上昇リスクは常に存在します。固定移行や金利上限キャップ付きプランなど、複数商品を比較したうえで、自身のリスク許容度に合った選択を行うことが成功への近道です。
まとめ
ここまで、RC造物件の特徴と不動産投資ローンの借り換え効果を見てきました。耐久性と金融機関評価が高いRC造は、長期保有でこそ真価を発揮します。その利点を最大化するには、残期間10年以上・金利差0.5%以上を目安に借り換えを検討し、諸費用を含めた総返済額で判断することが重要です。手続きでは修繕計画と個人属性を整え、電子申請を活用して税負担を抑えましょう。読者の皆さんも本記事を参考に、自身のポートフォリオを点検し、最適な資金戦略で安定したキャッシュフローを実現してください。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023年 – https://www.stat.go.jp
- 国税庁 耐用年数表 – https://www.nta.go.jp

