60代で投資を始めると「今さら間に合うのか」「ローンは組めるのか」と不安を抱く方が少なくありません。しかし、年金だけに頼らず、長生きリスクに備える手段として不動産は有力な選択肢です。本記事では、マンション投資 ファミリー向け 60代の視点から、物件選びや資金計画、修繕・相続までを総合的に解説します。読み終えたとき、安心して次の一歩を踏み出せる知識と判断軸を得られるはずです。
60代でもマンション投資は遅くない理由
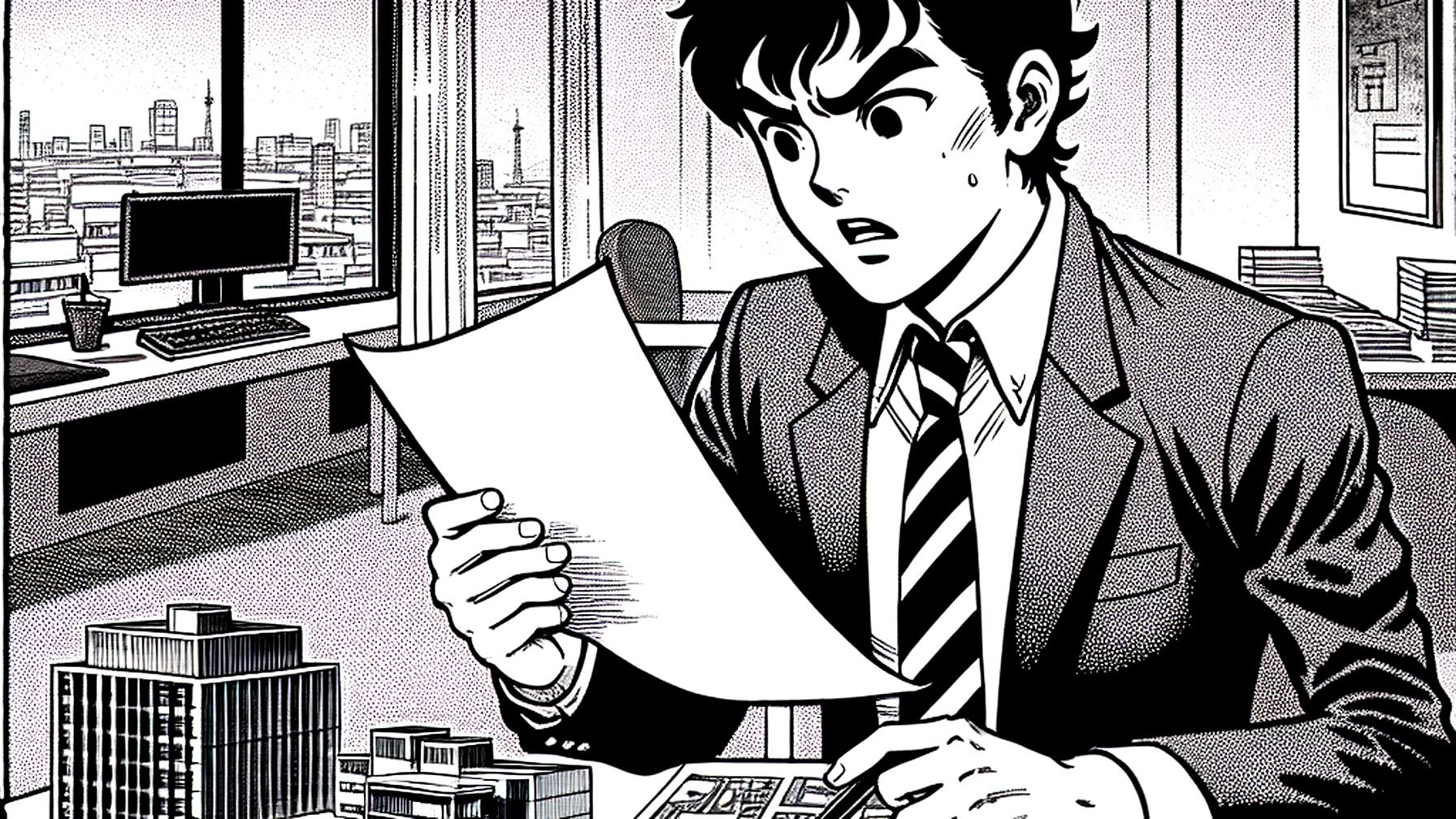
重要なのは、投資期間とリスクを見極めた上で収益と資産保全の両方を狙うことです。結論として、家賃収入が定年後の生活費を補完し、将来の医療費や介護費をまかなう“第二の年金”になり得ます。
まず、60代は子育てや住宅ローンが一段落し、自己資金を比較的多く用意しやすい時期です。自己資金を厚くすれば融資期間を短縮でき、返済完了時期の不安を抑えられます。また、金融機関は返済比率だけでなく担保評価も重視します。築浅の区分マンションであれば担保価値が下がりにくく、年齢によるハードルを補えます。
さらに、厚生労働省の「簡易生命表2024」によると、60歳時点の平均余命は男性22.9年、女性28.7年です。20年以上の運用期間を想定できるため、家賃収入と売却益の両取りが狙えます。つまり、適切な物件を選びさえすれば、60代でも長期戦略が十分成立します。
ファミリー向け物件が生む安定収益
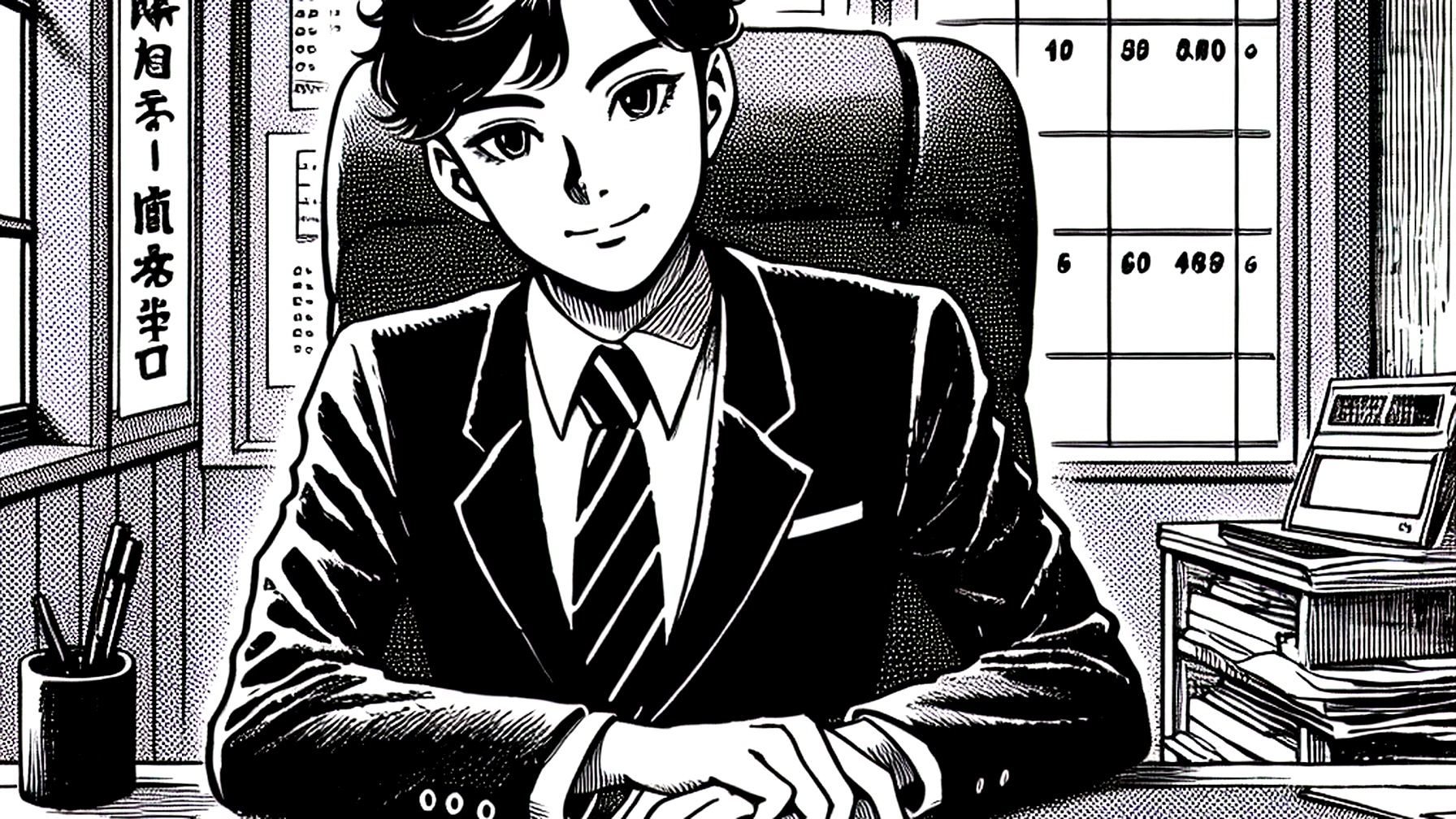
ポイントは、家族世帯をターゲットにすることで平均入居期間が延び、空室損失を抑えられる点です。国土交通省「賃貸住宅市場概況2025」によれば、単身向けの平均入居期間が3.2年なのに対し、ファミリー向けは5.8年と約1.8倍です。
東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円(2025年10月、不動産経済研究所)ですが、郊外駅徒歩10分圏の築10年程度なら4,000万円台で購入可能です。家賃相場は月16万〜18万円で、表面利回りは約5%前後を見込めます。単身向けワンルームに比べて利回りはやや低くても、長期的な入居継続がキャッシュフローを安定させるため、実質利回り差は縮まります。
一方で、広い間取りは修繕費が高くつく傾向があります。リフォーム会社の統計では、3LDK全体改装の平均費用は約250万円と1Kの2倍近い金額です。購入時に管理修繕積立金の水準や過去の大規模修繕履歴を確認し、将来の支出を予測しておくことが欠かせません。
資金計画と融資のポイント
実は、60代でも金融機関から融資を受ける道は残されています。重要なのは、完済年齢を75歳までに設定する金融機関が多い点を踏まえ、自己資金を増やしてローン期間を短縮する戦略です。
例えば、4,000万円の物件を頭金1,600万円(40%)入れて2,400万円借入、金利1.5%、期間15年で組むと、月々の返済は約14.8万円になります。家賃18万円を得られれば管理費・修繕積立金2万円を差し引いても1万円以上の黒字が見込めます。つまり、頭金を厚くするほどキャッシュフローは安定し、金利上昇リスクにも耐えられます。
退職金をすべて投資に回すのは避け、生活防衛資金と医療・介護予備費を別枠で確保することも大切です。金融庁「家計調査2025」によると、60代夫婦世帯の年間支出は約360万円、医療費は月1.5万円程度が平均です。これらを参考に、家賃収入と年金で支出を賄いつつ、手元流動性を保つ計画を立てましょう。
空室と修繕リスクへの備え方
まず押さえておきたいのは、空室と修繕は避けられないコストであり、事前の準備こそ最大の対策になる点です。
空室リスクを下げるためには、駅距離10分以内、保育園や小学校が徒歩圏内という立地条件を厳守すると効果的です。子育て世帯は通勤と教育環境を重視するため、この2条件が揃うだけで内見数が増え、入居決定率が高まります。また、ペット飼育可や宅配ボックス付きなど、生活利便性を高める設備も長期入居を促進します。
修繕コストについては、国交省「長期修繕計画作成ガイドライン」に基づいて設定された修繕積立金が適正か確認することが重要です。目安として、延べ床面積1㎡あたり月額250円以上が安心ラインとされています。積立不足があると将来の一時金徴収につながり、想定外の支出を招きます。管理組合の総会議事録を取得し、積立状況と大規模修繕の実施履歴をチェックしましょう。
相続と出口戦略を見据える
基本的に、不動産は評価額が時価の70%程度まで圧縮されるため、現金よりも相続税負担を抑えやすい資産です。60代で購入すれば、子どもが独立後に住み替え先として使う、または売却・賃貸継続という複数の選択肢を確保できます。
2025年度の税制では、相続発生から10か月以内に申告・納税が必要な点に変更はありません。マンションを複数人で共有相続すると運用に支障が出る場合があるため、生前に遺言や家族信託を活用して権利関係を整理することが肝要です。司法書士報酬は信託契約で20万円前後が相場ですが、物件規模や複雑さで変動するので早めの相談が得策です。
出口戦略としては、築20年を超えた段階で売却益よりも運用益を優先する「保有継続型」と、修繕コスト増加前に売却してキャピタルゲインを確定させる「短期回収型」の二択になります。首都圏ファミリー向けの取引事例を見ると、築15年までなら購入時価格の9割前後で成約するケースも多く、適切なタイミング判断が利益を大きく左右します。
まとめ
ここまで、マンション投資 ファミリー向け 60代の視点で、物件選びから資金計画、リスク管理、相続対策までを解説しました。要は、自己資金を厚くし返済期間を短縮することで融資のハードルを下げ、家族世帯が長く住みやすい立地と間取りを選ぶことが成功の鍵です。加えて、修繕積立金の健全性を確認し、将来の出口戦略を家族と共有しておけば、安定収益と資産保全を同時に実現できます。今日学んだ視点を踏まえ、まずは気になるエリアの相場調査から始めてみてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国土交通省「賃貸住宅市場概況2025」 – https://www.mlit.go.jp/
- 厚生労働省「簡易生命表2024」 – https://www.mhlw.go.jp/
- 金融庁「家計調査2025」 – https://www.fsa.go.jp/
- 国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」 – https://www.mlit.go.jp/common/000234321.pdf

