長時間勤務と不規則なシフトに追われる医師の方にとって、給与以外の安定収入を持つことは将来設計を大きく支えます。しかし、投資の勉強をする時間が限られ、情報も断片的だと感じている人は少なくありません。本記事では「収益物件 医師」というキーワードを軸に、限られた時間でも実践できる不動産投資の基本から最新の税制メリットまでを網羅します。読み終えるころには、物件選びの視点や資金計画の作り方が具体的にイメージできるはずです。
医師が不動産投資を選ぶ背景と強み
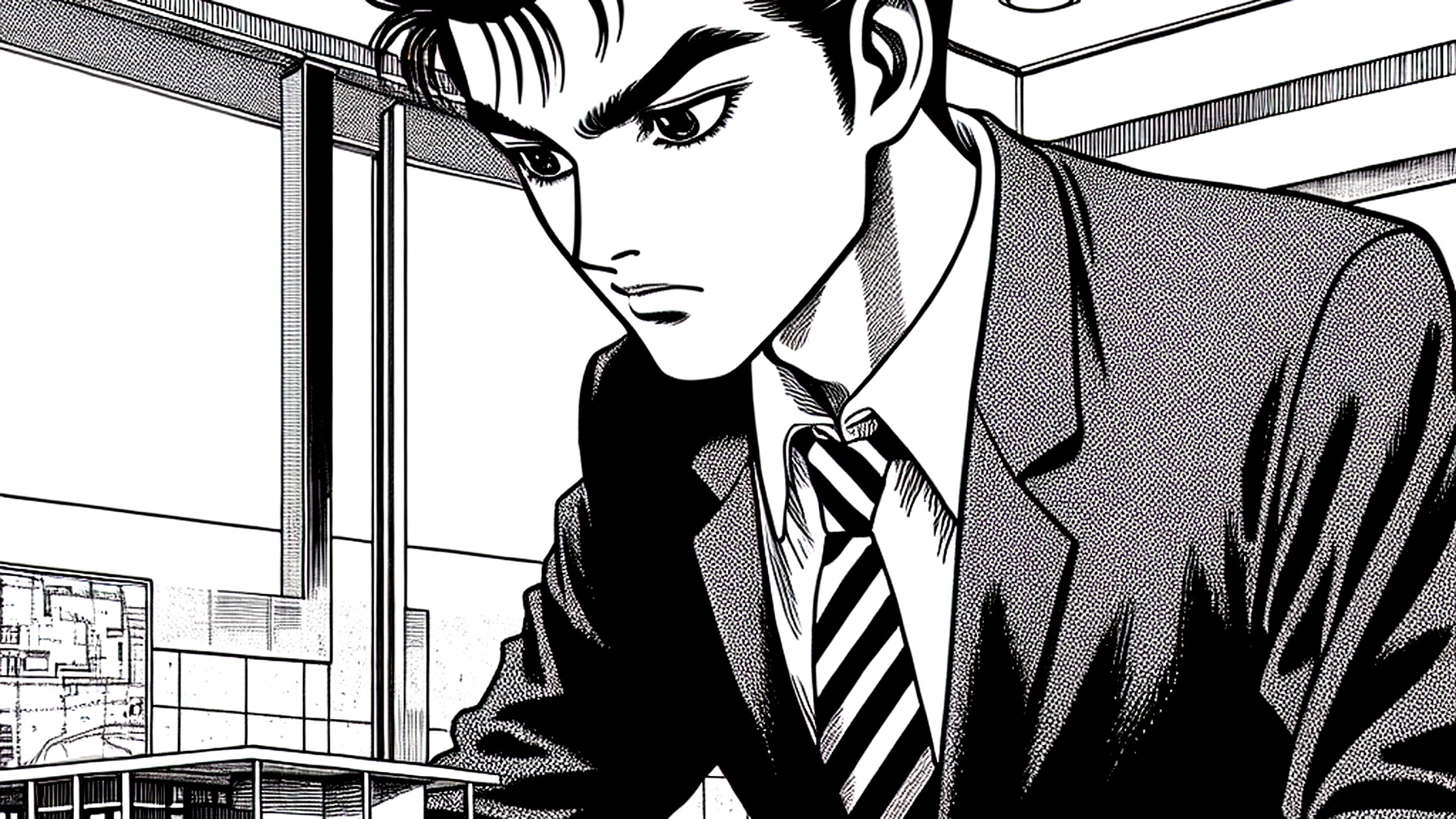
ポイントは、医師という職業ならではの信用力と時間制約をどう生かすかです。まず医師は高い年収と安定した雇用契約を背景に、金融機関の融資審査で好条件を得やすい傾向があります。一方、拘束時間が長いため、物件管理や市場調査に割ける時間は限られます。つまり、信用力を活かしてレバレッジを効かせつつ、運用の手間を最小化する戦略が求められます。
日本政策金融公庫の2024年度融資データによると、医師の不動産投資向け融資承認率は全業種平均より約18%高い結果が出ています。これは勤続年数が短くても年収が高い層が多いことが主因です。また、日経メディカルの調査では、医師の副収入源として不動産を選ぶ割合が2018年から2024年で1.7倍に増加しています。
しかし、実際にキャッシュフローが赤字化してしまうケースも後を絶ちません。背景には「立地が良いから安心」と短時間で判断し、詳細な収支シミュレーションを怠る傾向が指摘されています。そこで、次章では短時間でも確認できる物件選定の基準を整理します。
まず押さえておきたい収益物件の選定基準
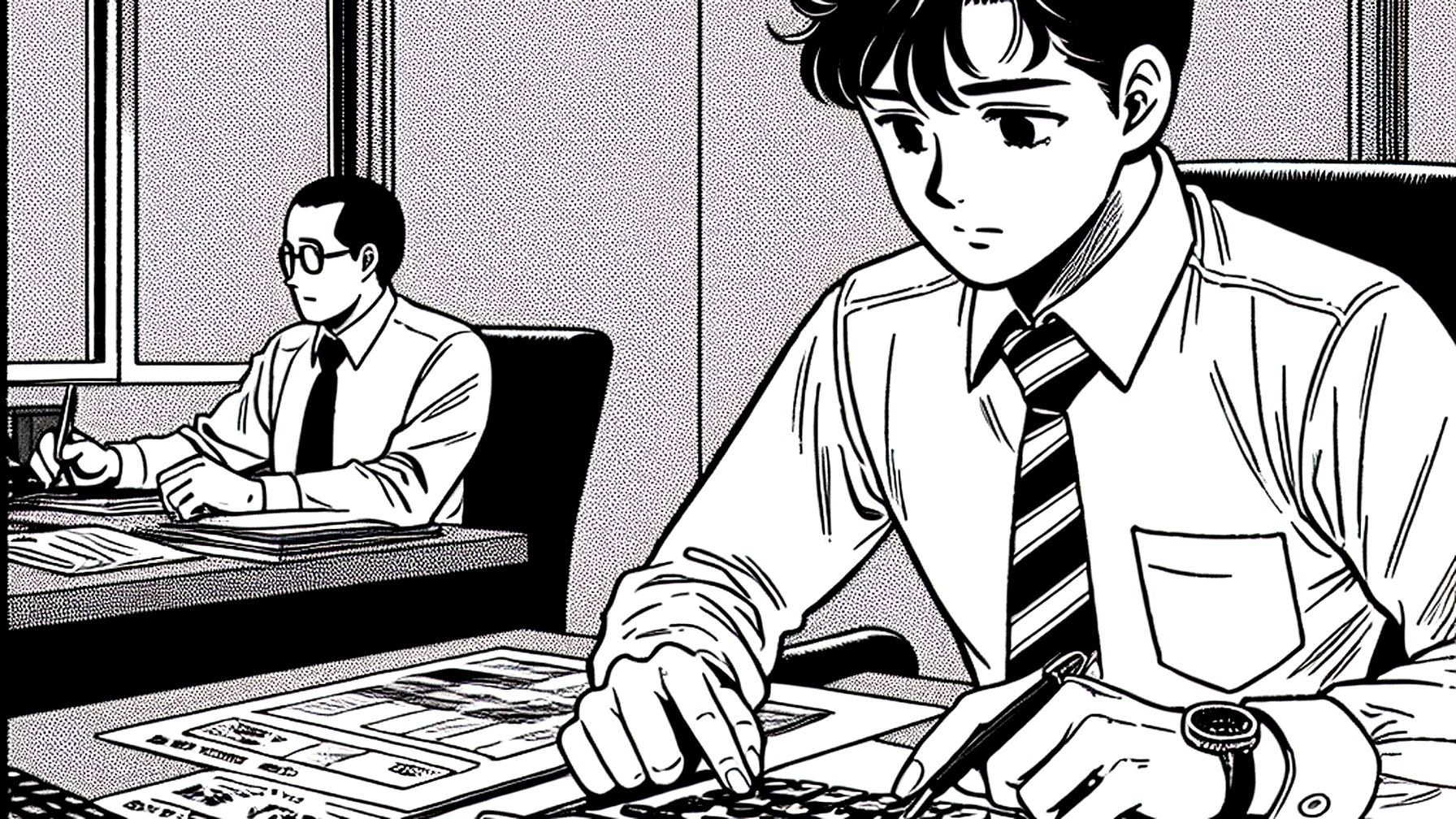
まず押さえておきたいのは、立地と利回りのバランスです。都心のワンルームマンションは空室リスクが低いものの、表面利回りが4%台にとどまる物件が多く、ローン金利次第ではキャッシュフローが出にくくなります。一方、地方の築浅アパートは利回りが7%を超える例もありますが、人口減少の影響を受けやすい点に注意が必要です。
実は、厚生労働省の「医師偏在指標」を重ね合わせると、医療過疎地域に近い郊外エリアは今後も診療所や看護師寮のニーズが高まる可能性があります。こうしたエリアでファミリー向けの賃貸を提供することで、医療従事者の長期入居を狙う戦略も取れます。言い換えると、医療需要の多寡を人口動態とセットで分析することで、一般の投資家が見落としがちなニッチ市場を確保できるわけです。
次に確認すべきは修繕履歴と設備更新計画です。築20年を超えるRC造マンションでも、大規模修繕積立金が潤沢なら突発的な支出リスクを抑えられます。国土交通省の「マンション長寿命化ガイドライン」は、築25年時点で30%の共用部を更新するとランニングコストが平均15%削減できると示しています。つまり、数字だけでなく管理組合の運営実態まで調べることが重要になります。
最後に、医師が時間を節約するためには、物件情報プラットフォームを使い分ける工夫も役立ちます。例えば、レインズ(不動産流通標準情報システム)は仲介会社を通じないと閲覧できませんが、専門家と連携して随時抽出条件を更新すれば、市場に出回る前のオフマーケット物件を見つけるチャンスが広がります。
融資戦略とキャッシュフロー管理のポイント
重要なのは、融資条件を最適化し、長期的なキャッシュフローを守ることです。医師の場合、年収に対する返済負担率を35%以下に収めれば、メガバンクでも1%前後の低金利で借りられるケースが多いです。一方で、自己資金を物件価格の20%ほど投入すると、審査を一段と通しやすくなります。これは金融機関が「医師=安定収入」という評価に加え、自己資金割合が高いことでリスクを低く見積もるためです。
返済計画を立てる際は、金利上昇シナリオを必ず組み込みます。日本銀行が2024年3月にマイナス金利を解除し、短期プライムレートが0.75%へ上昇したことを踏まえると、今後も長期金利が1%程度動く可能性があります。そこで、固定金利選択型や長期固定ローンを併用し、返済額が急上昇しない仕組みを先に設計することが肝心です。
キャッシュフロー管理には、家賃収入の10%を「予備費」、さらに5%を「税金積立」として別口座にプールする方法が有効です。これにより、突発的な修繕や税負担に備えられ、生活費と投資費用が混在することを避けられます。また、クラウド型会計ソフトを導入し、レシートをスマホで即時取り込むだけで損益計算書が更新される仕組みを整えると、月次の収支確認が5分程度で完了します。限られた時間のなかで数字を見える化することで、早期に経営判断を下せるようになります。
税務メリットと2025年度の制度活用
実は、医師が不動産投資で得られる最大の利点は税務面にあります。給与所得が高いほど所得税と住民税の負担が重くなりますが、減価償却費を活用することで課税所得を圧縮できるためです。たとえば、RC造マンション(法定耐用年数47年)の築30年物件を購入し、短期償却を選択すると、年間数百万円規模の減価償却費を計上できます。
さらに、2025年度の住宅ローン控除は、自ら居住する住宅用ローンが対象ですが、収益物件を兼ねた賃貸併用住宅にも一定条件で適用されます。条件は「床面積が50㎡以上」「自己居住部分が全体の2分の1以上」などで、控除期間は13年、控除率は年末残高の0.7%です。期限は2025年12月31日までに入居した場合に限られます。これを活用すると、実質的な支払利息を抑えられるため、自己居住兼投資という選択肢が具体性を帯びてきます。
また、国土交通省が2025年度も継続する「既存住宅購入かつ一定の省エネ改修を行う場合の登録免許税軽減措置」は、耐震・断熱工事を行った収益物件にも適用可能です。税率が本則の2%から1.5%に下がるため、登記時点のコスト削減につながります。
一方で、医師は業務に関する書籍や学会費の経費計上が難しい分、不動産経営の赤字と損益通算できる余地が大きい点も見逃せません。医師としての手取りを守りつつ、中長期的に資産形成を進めるためには、税理士と連携したプランニングが効果的です。
トラブルを防ぐ管理体制と出口戦略
まず意識すべきは、遠隔管理体制の質です。医師が夜間や休日に突発対応することは現実的ではないため、管理委託契約で24時間コールセンターと巡回点検をセットで組み込みます。管理費は家賃の5%が目安ですが、首都圏のワンルームで月額1万円未満に抑える事例も増えています。コストだけでなく、レポートの頻度やオンライン閲覧が可能かを確認すると安心です。
空室対策では、医療・介護従事者向けにターゲットを絞った広告展開が効果的です。看護大学の近隣エリアで「夜勤明けでも静かな環境」を訴求すると、女性入居者の平均居住年数が1.3年伸びたという東京カンテイの2025年調査結果があります。つまり、入居者属性を分析し、物件のメリットを具体的に提示することで、広告コストを抑えながら長期入居につなげられます。
出口戦略としては、売却益型とインカム継続型の二択に加え、相続対策としての保有も選択肢に入ります。医師家庭は相続財産が大きくなりやすいため、相続時精算課税や小規模宅地特例を適用することで、資産移転と税負担軽減を同時に図れます。日本不動産研究所のシミュレーションでは、相続開始前に賃貸経営を開始して評価額を圧縮すると、現金保有に比べて相続税負担を平均22%減らせるとされています。
売却を選ぶ場合は、医師の勤務先や関連病院が拡張するタイミングを見計らい、周辺の医療スタッフ向け需要が高まる時期に合わせると、実勢価格が10%以上上昇する例もあります。需要トレンドを読み取り、長期譲渡所得の税率20%が適用される5年超保有後に売却する流れを計画的に作ることが重要です。
まとめ
ここまで、医師が収益物件を活用して安定した副収入を得るための視点を整理しました。重要なのは、高い信用力で好条件の融資を引き出しつつ、時間制約を補う管理体制を構築することです。物件選定では医療需要との相関を読み解き、修繕計画まで確認すれば大きな失敗を避けられます。さらに、2025年度の住宅ローン控除や登録免許税軽減などの制度を活かし、税務メリットを最大化することで投資効率が高まります。今日からできる行動として、まずは金融機関に事前審査を申し込み、自身の借入余力を把握することから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 中小企業融資統計 2024年度 – https://www.jfc.go.jp
- 厚生労働省 医師偏在指標 2024年公表データ – https://www.mhlw.go.jp
- 日経メディカル 医師の副業実態調査 2024 – https://medical.nikkeibp.co.jp
- 日本不動産研究所 不動産投資インデックス 2025年 – https://www.reinet.or.jp
- 東京カンテイ 賃貸市場レポート 2025年上期 – https://www.kantei.ne.jp

