事業を拡大させながら資産も築きたいと考える経営者は多いものの、「変動だと金利が読めない」「固定にすると返済が重いのでは」と踏み切れずにいる方が少なくありません。実は会社経営と不動産投資は資金調達の考え方が似ており、仕組みを理解すれば固定金利でもキャッシュフローを安定させる方法があります。本記事では「不動産投資ローン 固定金利 経営者」という三つの視点から、最新の金利動向、法人と個人の使い分け、資金計画の立て方を具体的に解説します。読後には、ご自身のビジネスに最適なローン戦略を描けるようになるでしょう。
経営者がローンを組む前に押さえる資金計画
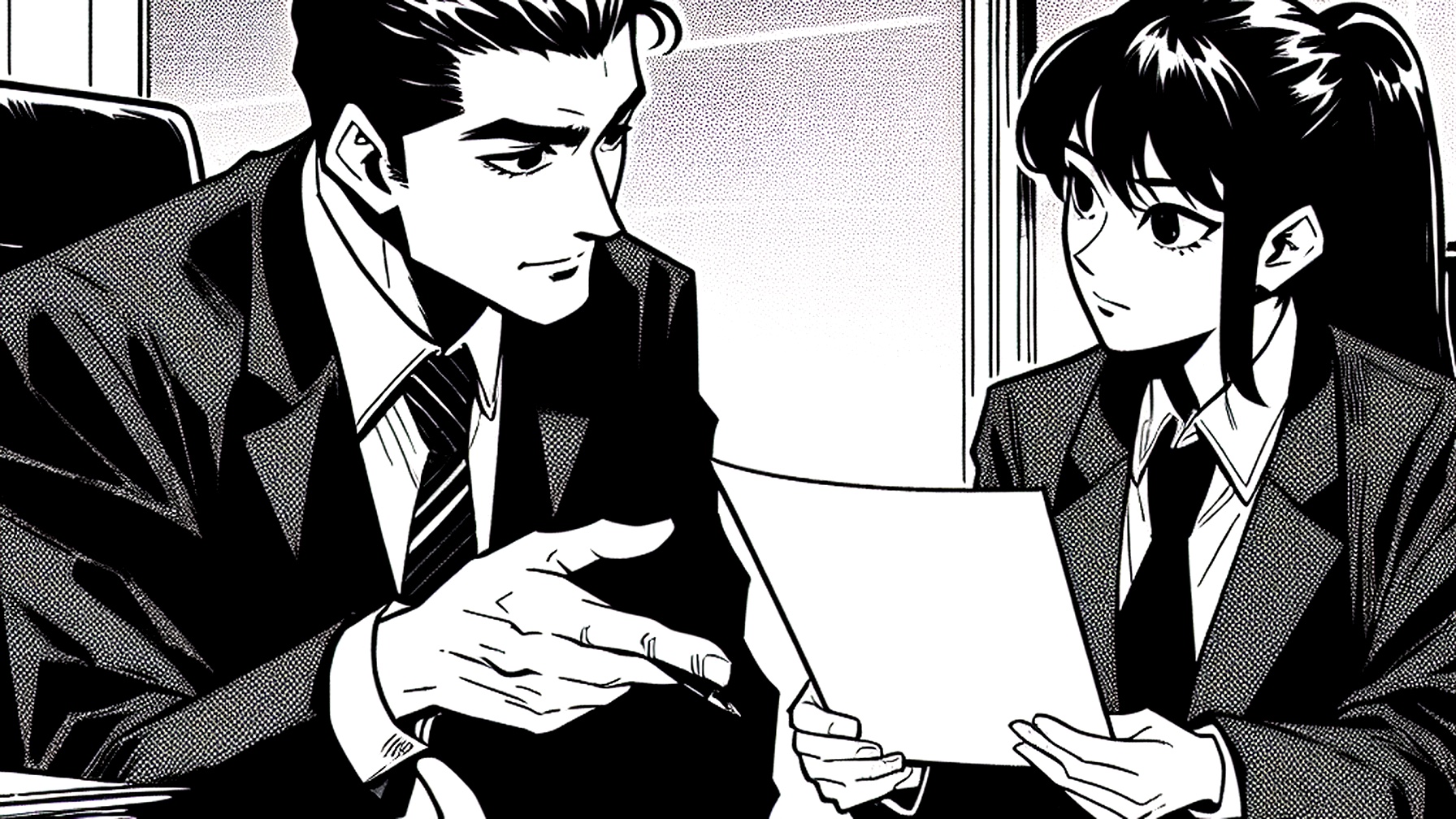
重要なのは、物件価格だけでなく諸費用や運転資金まで含めた総予算を可視化することです。
まず自己資金の目安を整理します。事業と同様、レバレッジをかけすぎると資金繰りが一気に厳しくなるため、物件価格の25%前後を頭金として確保すると安全域が広がります。とはいえキャッシュは本業にも必要です。そこで決算書を踏まえた資金繰り表を作り、物件購入後一年間の運営費や突発修繕費を含めてシミュレーションします。
次に融資条件を洗い出します。2025年10月時点で主要都市銀行の固定10年金利は2.5〜3.0%で推移しており、変動金利(1.5〜2.0%)との差は約1%です。返済額が増える部分を、退去時の原状回復費や広告料など不確定費用のバッファとしてとらえれば、固定のメリットが見えてきます。
さらに、経営者の場合は法人決算が金融機関の審査ポイントになります。自己資本比率が高いほど融資条件が有利になることが多いので、物件取得前に不要在庫の圧縮や役員貸付金の返済を行い、財務体質を整えておくことも忘れないでください。
固定金利の特徴と変動金利との違い
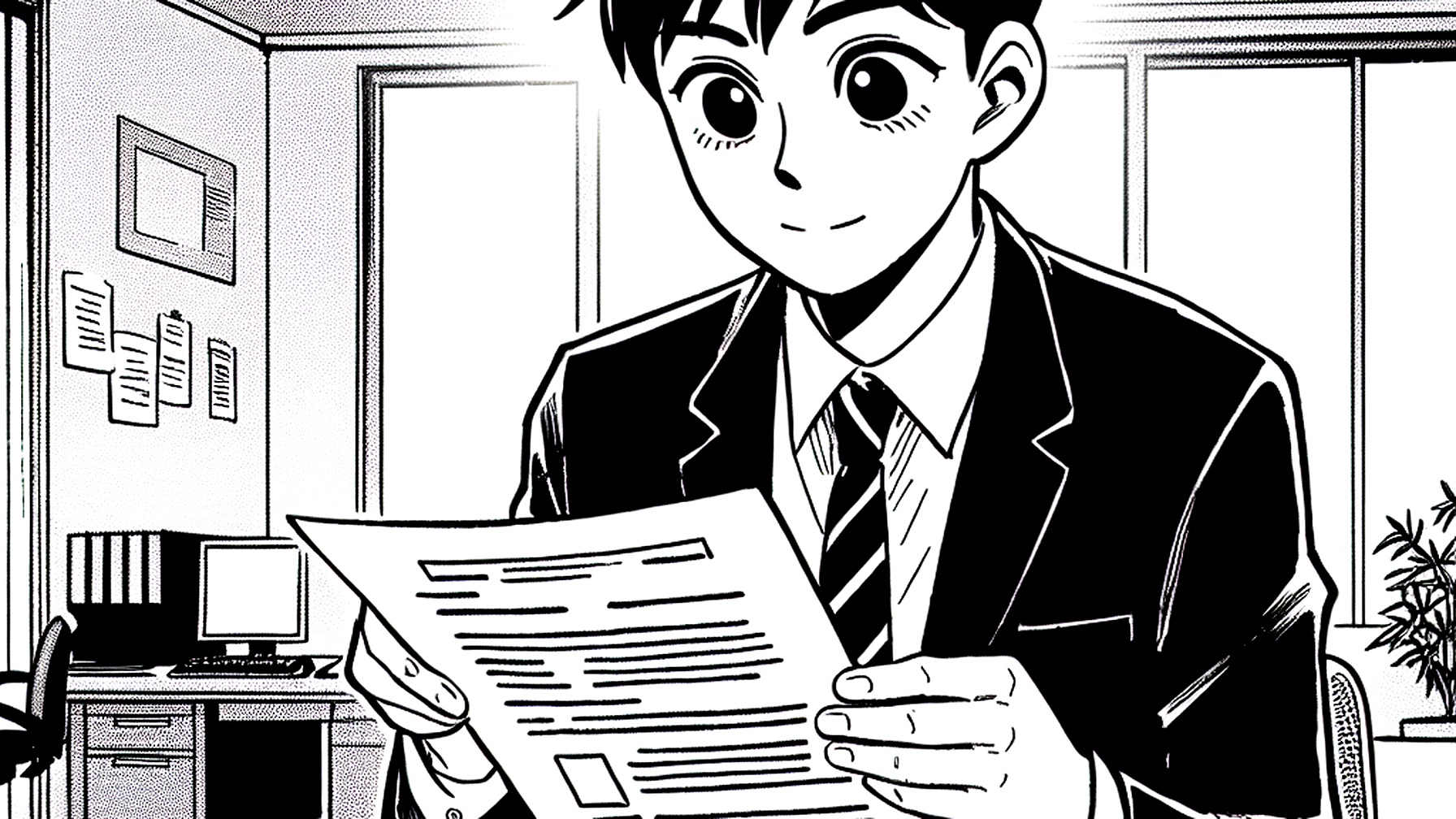
ポイントは、金利リスクを誰が負担するかという視点で違いを把握することです。
固定金利は契約時に完済までの利率が確定するため、月々の返済額を長期で読みやすい仕組みです。一方で借入当初の金利は変動型より高くなるので、投下資金の回収期間が長引く可能性があります。また、途中返済する場合は「固定特約期間中の繰上げ手数料」が発生する金融機関もあるため、出口戦略を想定したうえで契約条項を確認しておく必要があります。
変動金利は半年ごとに適用金利が見直されます。日銀が金融正常化に向けて政策金利を年0.5%引き上げれば、変動金利も同幅程度上昇するのが一般的です。返済額の増加は5年ルール・125%ルールで緩やかに表れますが、最終的な利払い総額は膨らむ恐れがあります。
つまり経営者が固定を選ぶか変動を選ぶかは、本業のキャッシュフロー変動と合わせて考えることが大切です。本業が景気変動の影響を受けやすい場合、不動産収益まで変動金利に依存すると資金繰りが同時に悪化するリスクが高まります。逆にインフレ局面で売上が伸びやすい業種なら、変動を選んで金利上昇リスクを吸収する戦略も成り立ちます。
法人名義と個人名義、経営者の選択肢
実は名義の選択で、節税効果と資金調達力が大きく変わります。
法人名義を選ぶと、建物分の減価償却費を経費計上できるため、税引後キャッシュフローを厚くしやすい特徴があります。さらに本業の利益と通算することで実効税率を引き下げる余地も生まれます。ただし銀行は本業の損益と不動産収益を合わせて審査するため、赤字決算が続くと追加融資を受けにくくなる点に注意が必要です。
個人名義のメリットは、住宅ローン型の低金利商品を活用できるケースがあることです。2025年10月時点で居住兼賃貸の「セカンドハウスローン」は固定10年2.0%前後の商品も見られます。ただし個人所得が増えると累進課税で税負担が急増するため、給与所得が高い経営者ほど法人名義が有利になる傾向があります。
また、法人と個人でダブルローンを組む方法も存在します。たとえば個人で区分マンションを取得しつつ、法人で一棟アパートを保有するといった形です。この場合、担保と資金源が分散されるため金融機関の与信枠を拡大できる可能性があります。もっとも管理や会計が複雑になるため、税理士と連携して収支表を一本化できる体制を構築しておきましょう。
キャッシュフローを安定させる返済戦略
まず押さえておきたいのは、元利均等返済と元金均等返済の違いです。元利均等は毎月返済額が一定で、初期段階の金利負担が大きい代わりに資金計画が立てやすくなります。元金均等は利払い総額を抑えやすいものの、当初の返済額が高めになるため開業間もない事業には負担が重いかもしれません。
経営者にとって重要なのは、物件収益だけで返済するのではなく、本業キャッシュを上手に活用してローン残高をコントロールすることです。たとえば繁忙期の粗利を活かして年1〜2回のスポット繰上げ返済を行えば、固定金利でも総利息を数百万円単位で削減できます。なお、繰上げ時は手数料と残期間短縮効果のバランスを確認し、償還表を用いて計算しておくと安心です。
さらに、空室リスクを下げる施策もキャッシュフロー安定化には欠かせません。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の2025年調査によると、リノベーションを実施した物件は空室期間が平均2.3カ月短縮しています。賃料を維持したまま稼働率を高めれば、固定金利による返済総額と実質利回りのバランスが改善し、長期的な利益確保につながります。
最後に保険の活用です。団体信用生命保険(団信)に加え、家賃保証保険や設備故障保険を組み合わせれば、経営者不在時や突発トラブルのリスクを抑えられます。保険料は経費計上できるため、税負担をコントロールしながらリスクヘッジできる点も魅力です。
2025年度の優遇制度と金融機関の最新動向
まず押さえておきたいのは、金融機関各社が2025年度に導入した「固定金利選択型優遇プラン」です。これは、環境性能の高い賃貸住宅を取得する場合に固定金利を最大0.3%引き下げる仕組みで、申し込み期限は2026年3月末となっています。適用条件として、BELS評価★3以上の省エネ性能を満たす証明書が必要です。
一方で、国の直接的な補助金は賃貸住宅向けには限定的です。ただし中小企業庁の「事業者支援融資保証制度」を利用すれば、経営者保証を外しつつ保証料を0.1%軽減できる場合があります。固定金利プランと併用することで、元本据置期間を2年間確保し、物件稼働率が安定するまでの資金負担を抑えられます。
また、地銀や信金が提供する「プロパーローン」では、事業実績が3期以上で自己資本比率25%以上の法人に対し、最長25年・固定2.7%前後の長期融資が実行されています。日本政策金融公庫の不動産投資向け貸付は、2025年4月に上限額が7,200万円へ拡大され、固定15年2.3%の商品が利用可能です。
金融正常化の潮流を受け、長期固定金利は今後じわりと上昇する可能性があります。全国銀行協会のデータでは、10年固定金利が過去一年で0.2%上昇しました。経営者はこのタイミングで資金調達を前倒しし、古い高金利ローンを借り換えることで、トータル支払利息を圧縮できる余地があります。
まとめ
ここまで、不動産投資ローンを固定金利で組む際に経営者が押さえるべき資金計画、金利選択、名義の使い分け、返済戦略、そして2025年度の優遇制度を解説しました。固定金利は返済額を読みやすくし、本業の資金繰りと合わせたリスク管理を容易にしてくれます。物件収益と事業収益をバランスさせ、繰上げ返済や保険を活用すれば、安定した資産形成が見込めるでしょう。まずは決算書とキャッシュフロー表を手元に、金融機関との対話を始めてみてください。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 日本賃貸住宅管理協会 – https://www.jpm.jp
- 中小企業庁 – https://www.chusho.meti.go.jp
- 日本政策金融公庫 – https://www.jfc.go.jp
- 国土交通省住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku

