不動産に興味はあるけれど物件を持つのはハードルが高い、そんな悩みを持つ人が増えています。そこで選択肢になるのが上場不動産投資信託、通称REITです。しかし、手軽さの裏には税金やリスクに関する注意点が隠れています。本記事では「REIT 注意点 税金」をキーワードに、2025年10月時点で有効な制度を踏まえながら、初心者でも理解しやすい形でポイントを整理します。読み終えるころには、分配金と売却益の税負担をイメージでき、自分に合った投資戦略を描けるようになるでしょう。
REITとは何か、株式投資とどこが違うのか
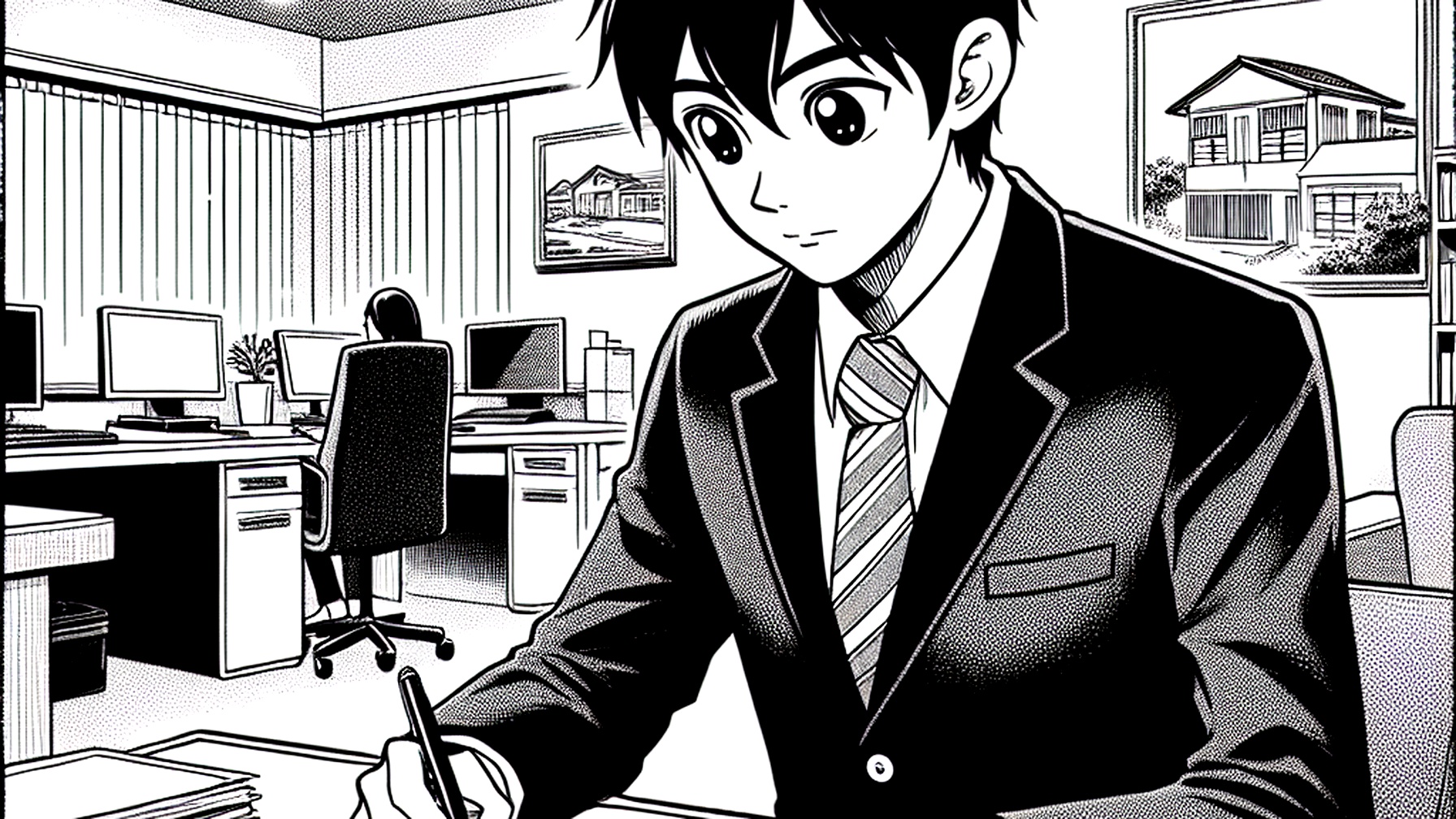
まず押さえておきたいのは、REITが「複数の不動産に少額で分散投資できる仕組み」だという点です。上場REITは東京証券取引所に上場しており、売買は株式と同じように行えます。ただし利益の源泉は賃料収入と物件の売却差益であり、経営主体が不動産運用会社である点が株式と異なります。
次に、分配金の水準とその原資を理解しましょう。法律上、REITは利益の九〇%超を分配すれば法人税が課されません。そのため分配利回りは三〜五%と相対的に高く、配当重視の投資家に人気です。一方で、内部留保が少ないため修繕費や空室による収益変動の影響を受けやすいという特徴もあります。
注意点として、価格変動はオフィス賃料や金利動向に左右されることが多いです。例えば国土交通省の不動産価格指数によると、都心オフィス賃料が一〇%下落した年には、オフィス特化型REITの価格も平均一六%下落しました。つまり不動産市況の影響を織り込む必要があります。
分配金にかかる税金と節税の基本
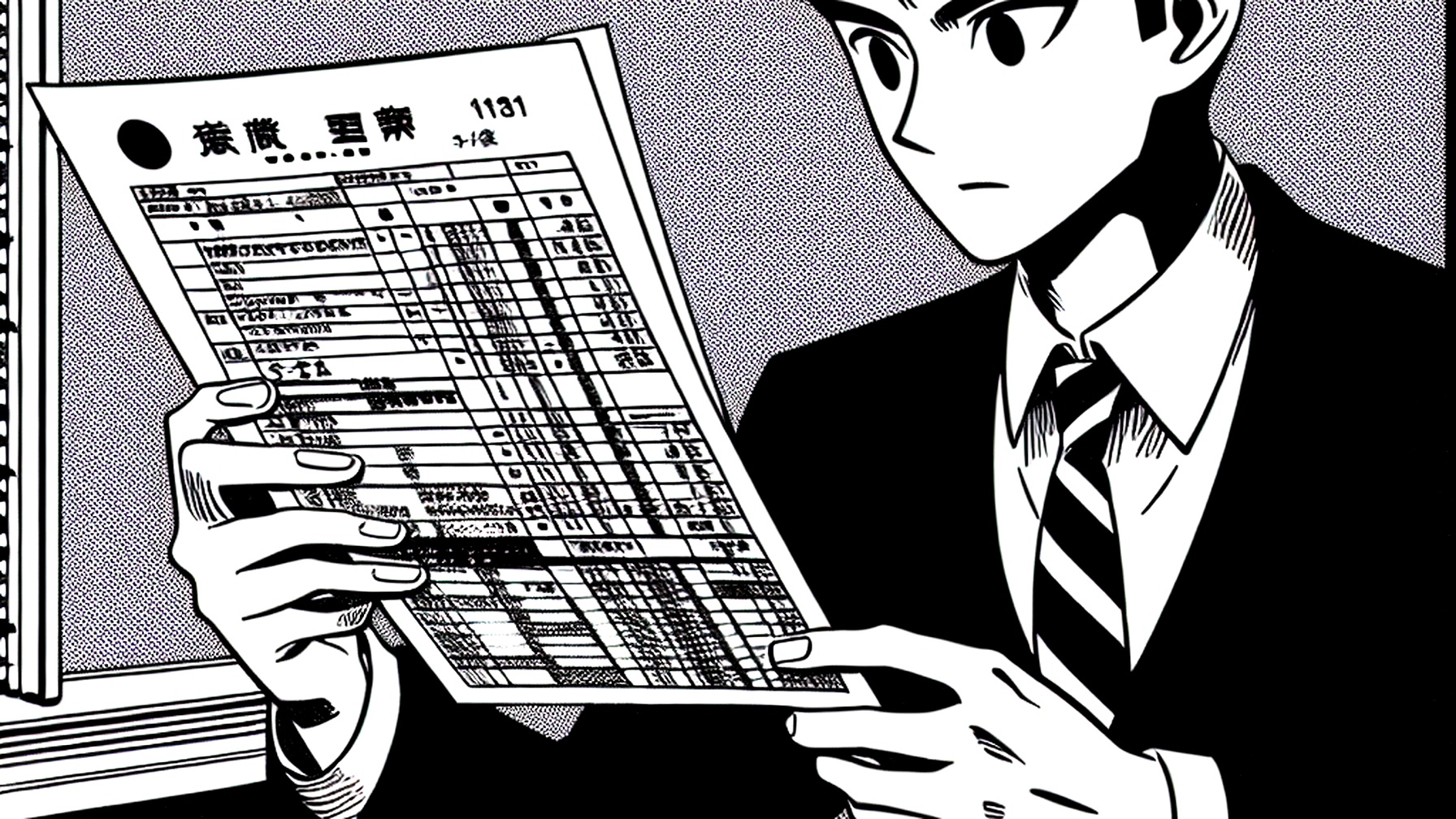
重要なのは、REITの分配金が「配当所得」とみなされ、原則として二〇%強の税率で源泉徴収される点です。内訳は所得税一五・三%、住民税五%で、株式配当と同じ扱いになります。源泉徴収で完結させる「申告不要」を選べば手続きは簡単ですが、他の株式配当や譲渡損と損益通算したい場合は確定申告が必要です。
課税を抑える手段としてまず検討されるのが、2024年から恒久化された新NISAです。累計一八〇〇万円の非課税枠のうち、「成長投資枠」を使えば上場REITにも投資でき、分配金・売却益とも最長五年間は非課税になります。2025年度の制度では非課税期間終了後もロールオーバーが可能で、実質的に長期非課税運用が可能です。
一方で、分配金自体を受け取らず再投資する「自動積立サービス」を使っても税制上の優遇はありません。分配金が支払われた瞬間に課税されるため、再投資を選んでも税負担は変わらないことを覚えておきましょう。つまり節税効果を狙うならNISA口座の活用が最もシンプルで確実です。
売却益と損益通算のポイント
ポイントは、REITの売却益が「株式等の譲渡所得」に分類されることです。税率は分配金と同じ二〇%強で、上場株式やETFの損益と自動的に通算されます。この仕組みを利用すると、株式で出た損失をREITの利益と相殺し、税金を抑えることができます。
実は、損益通算だけでなく「損失の繰越控除」も使えます。確定申告を行い、翌年以降三年間にわたり株式やREITの利益と相殺できるため、下落局面での損出し戦略が有効です。ただし、特定口座(源泉徴収あり)でも繰越控除を使うには確定申告が必須となります。
売却タイミングを検討する際は、分配落ち日にも留意しましょう。分配落ち直後は価格が分配金額相当下がる傾向があり、短期売買では思わぬ損失が出る場合があります。金融庁の月次データによれば、分配落ち日の下落幅は平均一・三%ですが、個別REITでは三%を超える例もあります。長期投資なら影響は限定的ですが、短期売買を前提とするなら注意が必要です。
投資リスクと税金面の注意点
まず、REIT価格は政策金利に敏感に反応します。2025年10月時点で日銀はマイナス金利を解除し、政策金利〇・七五%で推移していますが、もう一段の利上げ観測がくすぶっています。利回り競争が激化するとREIT価格は下落し、含み損が膨らむ恐れがあります。含み損が大きい状態で売却すると、配当で得た利益を相殺しても手元資金が減少する点を認識しましょう。
また、災害リスクも無視できません。上場REITの約四割が首都圏物件に集中しており、首都直下地震が発生した場合の影響が懸念されています。火災保険や地震保険はREITが加入しますが、甚大な被害が出れば分配金の減少や特別損失計上につながり、価格と分配金が同時に減る可能性があります。
税金面では、REITは減価償却費を計上できるため、会計上の利益よりキャッシュフローが高い構造を持ちます。言い換えると、分配金が増えても帳簿上の利益は限定的な場合があるため、分配金利回りだけでなく、運用報告書に記載される一口当たりNAV(純資産価値)も確認するとリスクを抑えられます。
2025年度NISAでのREIT活用術
基本的に、新NISAの成長投資枠は投資上限が年間二四〇万円、累計一八〇〇万円まで非課税です。この枠内でREITを組み込めば、分配金と売却益が非課税となり、課税口座に比べ手取り利回りが約二五%高まる計算になります。例えば年利四%のREITに三〇〇万円投資すると、課税口座では年間約九万六千円の手取りですが、NISAなら十二万円満額を受け取れます。
さらに、2025年度の制度改正では、NISA口座内で得た配当を自動的に再投資しても非課税枠を消費しない「成長投資枠の再利用」が可能になりました。これにより複利効果が高まり、長期での資産形成に適した環境が整っています。一方で、NISA枠は相続時にみなし譲渡課税が発生しないものの、口座開設者の死亡時点で非課税が終了する点には注意しましょう。
また、NISAでは損益通算ができません。非課税である代わりに、損失が出ても他の口座と相殺できないため、個別REITではなく分散性の高いREIT ETFを組み込む方法も検討するとバランスが取れます。総務省統計局の家計調査では、REIT保有世帯の平均投資額が年々増えている一方で、値動きに不安を感じる初心者が多いと報告されています。分散投資でリスクを抑えつつ、非課税メリットを最大化する戦略が現実的です。
まとめ
REIT投資で押さえるべき最重要ポイントは、分配金と売却益がともに二〇%強課税される一方で、NISAを使えばその負担をゼロにできるという事実です。税金の仕組みを理解せずに高利回りだけを追うと、分配落ちや金利上昇で手取りが目減りする危険があります。まずはNISA口座を活用し、損益通算のルールを把握したうえで、自身のリスク許容度に合ったREITやETFを選ぶことが、安定したキャッシュフローを得る近道と言えるでしょう。
参考文献・出典
- 国土交通省不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁 新NISA制度説明資料(2025年度版) – https://www.fsa.go.jp
- 日本取引所グループ 月次REIT市況 – https://www.jpx.co.jp
- 総務省統計局 家計調査年報 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp

