これから不動産投資を始めたいものの、「将来の相続でもめたくない」「物件の管理が不安」という悩みを抱く人は少なくありません。特に親世代が築いた自宅や賃貸物件を引き継ぐ場合、適切な準備を怠ると、家族関係や財産価値に大きな影響が及びます。本記事では、不動産投資を活用した相続対策の基本と、2025年10月時点で有効な制度を踏まえた管理方法を、初心者にも分かりやすく解説します。読み終えるころには、具体的に何から手を付ければよいかが見えてくるはずです。
不動産投資が相続対策につながる理由
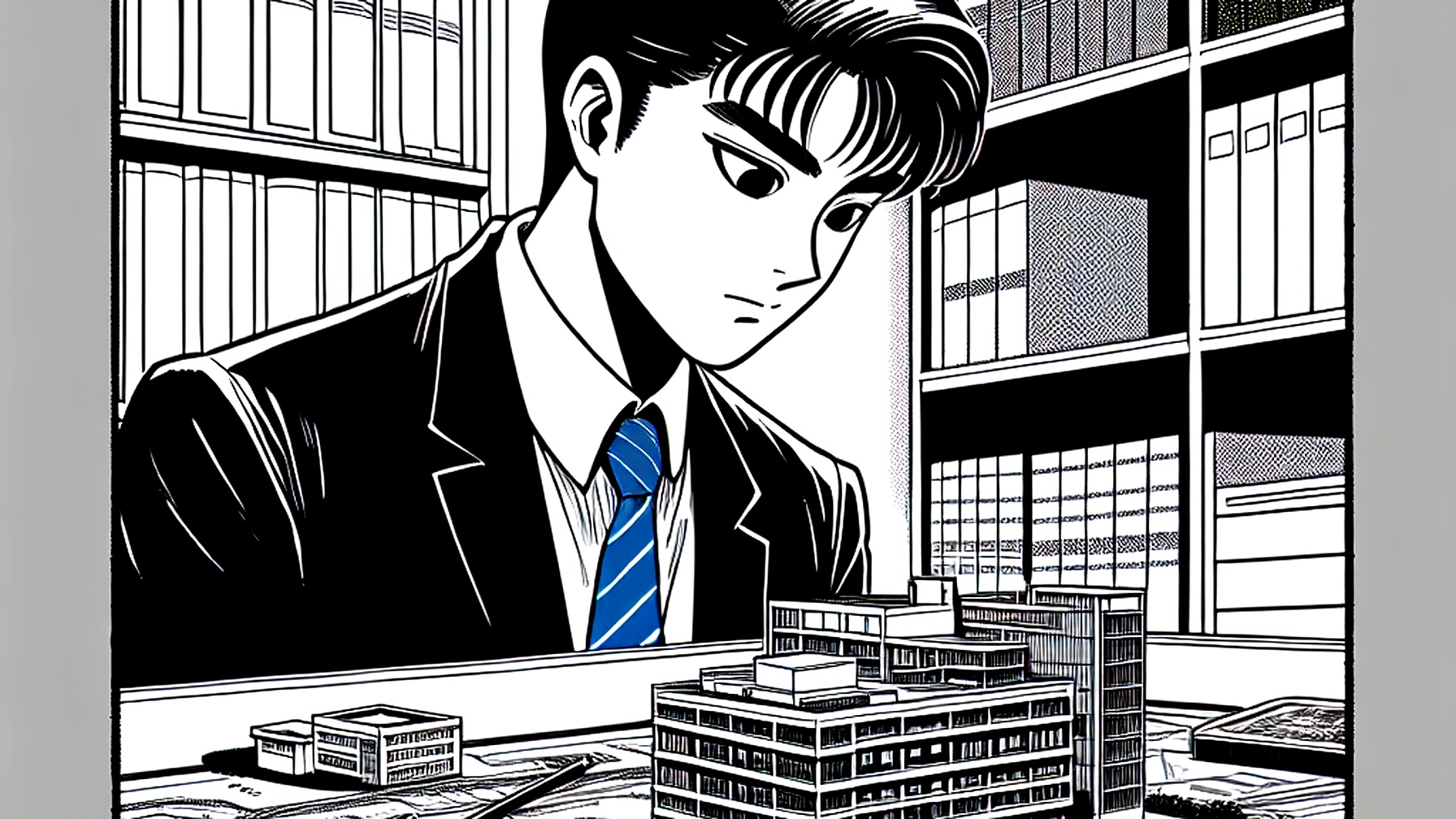
重要なのは、不動産が「現物資産」であると同時に「収益資産」であるという点です。相続時の評価は現金より低く抑えられる傾向があり、さらに賃料収入があれば納税原資にもなります。
まず、国税庁の路線価データによると、相続税評価額は実勢価格の約7〜8割が目安です。つまり同じ1億円でも、現金より相続税の負担が軽くなる可能性があります。また賃貸物件では、貸家建付地の評価減や貸家の評価減が適用され、さらに課税価格を圧縮できます。
一方で、単に評価を下げるだけでは不十分です。空室が多ければ収益が途絶え、納税のための資金繰りが苦しくなります。そこで安定したキャッシュフローを生む物件を選び、長期的に管理を続ける仕組みが欠かせません。
つまり、不動産投資は「資産価値の維持」「相続税圧縮」「納税原資の確保」という三つの課題を同時に解決できる手段なのです。
物件選びと資金計画で管理負担を抑える
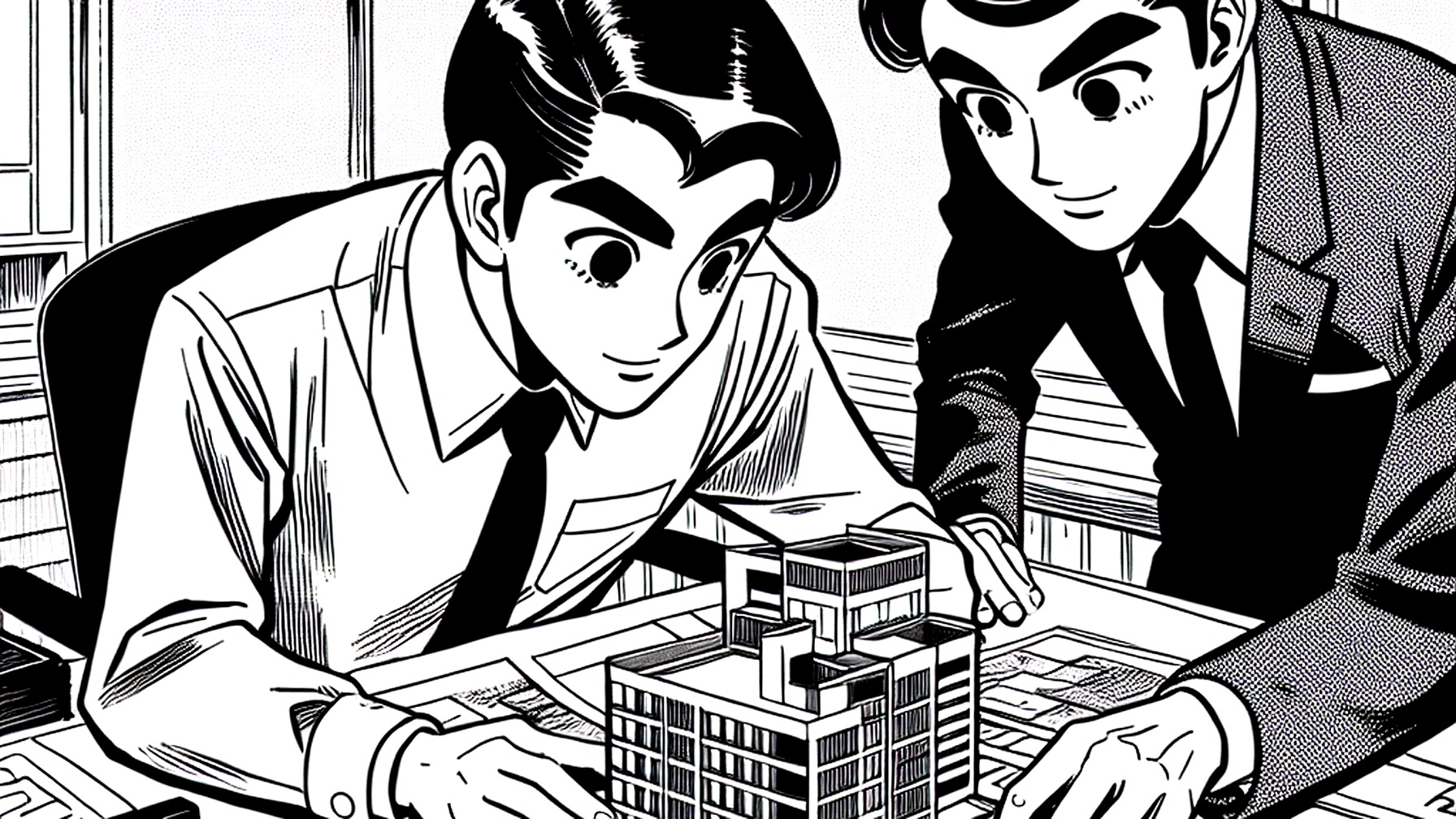
ポイントは、購入段階から出口戦略と管理負担を意識することです。物件の立地、築年数、構造はもちろん、将来の修繕コストまで具体的に試算する必要があります。
たとえば、築浅のRC(鉄筋コンクリート)造マンションは価格が高めですが、長期修繕計画が明確な管理組合があれば突発的な費用リスクを減らせます。一方、木造アパートは初期投資を抑えられる反面、10〜15年ごとに屋根や外壁塗装が必要になりやすく、資金計画に修繕費の積立を組み込むことが大切です。
資金調達では、金融庁「家計調査」によると変動金利型住宅ローンの平均金利は1%前後で推移していますが、2025年以降は金利上昇リスクが指摘されています。返済比率を家賃収入の50%以内に設定し、金利が2%上昇してもキャッシュフローが黒字で残るかシミュレーションしておくと安心です。
さらに、空室リスクに備え、家賃保証会社の制度内容や更新料を比較検討することが管理ストレスの軽減につながります。
税制を味方にする2025年度のポイント
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続される「相続時精算課税制度」の活用です。60歳以上の親から18歳以上の子へ、累計2,500万円まで非課税で贈与できるため、将来の相続財産を前倒しで移転し、賃料収入を子世代に移すことが可能になります。
また、賃貸物件の取得や新築に伴う「不動産取得税」の軽減措置は2027年3月まで延長が決まっています。登記後に届く課税通知書を見ると、住宅用地の評価が1/2に軽減されていることが分かり、初期費用を抑えられます。
所得税面では、青色申告特別控除が最大65万円適用されるほか、家族に支払う給与を経費計上できるメリットがあります。これにより、家族を管理業務に参画させながら節税効果を高められ、相続発生前から資産承継の意識を共有できます。
ただし、税制は毎年改正されます。国税庁のウェブサイトを確認し、制度の期限や適用要件を必ずチェックしてください。
安心の管理体制を構築するステップ
実は、物件の管理体制が相続対策の成否を左右します。オーナーの突然の病気や死亡時に、入居者対応や家賃の入金管理が止まると、物件価値が一気に下がるからです。
まず、管理会社との間で「管理委託契約書」を作成し、業務範囲と権限を明文化します。家賃集金、滞納督促、修繕手配のフローを契約書に盛り込むことで、相続後もスムーズに運営を継続できます。
次に、重要書類をデータ化し、クラウド共有しておくと家族が状況を把握しやすくなります。固定資産税納付書、火災保険証券、賃貸借契約書などをフォルダごとに整理し、パスワード管理を徹底すれば情報漏えいも防げます。
さらに、年1回は家族を交えた収支報告会を開き、賃料収入、修繕積立金、残債残高を共有しましょう。家族が物件の状況を把握していれば、相続時の引き継ぎもスムーズです。
家族への引き継ぎと遺言・信託の活用
まず押さえておきたいのは、「遺言書」と「家族信託」を併用することで相続トラブルを防げる点です。遺言書で不動産の具体的な分け方を示し、家族信託で管理・運用権限を託せば、認知症リスクや代替わりに伴う混乱を最小限にできます。
たとえば、委託者である親が受益者兼管理者の子に賃料収入を渡す形で信託契約を結ぶと、親が判断能力を失っても物件管理が途切れません。信託財産は親の相続財産ではないため、遺産分割協議の対象外となり、兄弟間のトラブルを回避できます。
公証役場で作成する公正証書遺言は、検認手続きが不要でスムーズに効力を発揮します。費用は内容により数万円から10万円程度ですが、後々の紛争コストを考えれば十分な投資といえるでしょう。
結論として、早めに家族を巻き込み、専門家と連携して仕組みを整えることが、不動産投資を相続対策に生かす最短ルートになります。
まとめ
不動産投資は、相続税の圧縮、納税原資の確保、資産価値の維持という三つの利点を持ちます。2025年度の税制や軽減措置を活用しつつ、物件選びと資金計画を慎重に行い、信頼できる管理体制を築くことが成功の鍵です。さらに、遺言や家族信託で権限と収益を整理しておけば、世代をまたいで資産を守れます。今日から情報整理と家族への共有を始め、将来の安心を手に入れましょう。
参考文献・出典
- 国税庁 路線価図・評価倍率表 – https://www.rosenka.nta.go.jp
- 国税庁 相続時精算課税制度の手引 – https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2025
- 総務省 家計調査年報 2024年版 – https://www.stat.go.jp/data/kakei
- 国土交通省 不動産取得税の軽減措置について – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo
- 法務省 家族信託・民事信託に関するガイドライン – https://www.moj.go.jp/KMIN_FRONTEND/chiiki/minjishintaku

