多くの20代が「給与だけでは将来が不安」と感じる中、アパート経営が資産形成と相続対策を同時にかなえる方法として注目されています。とはいえ、自己資金の少なさや経験不足から一歩を踏み出せない人も少なくありません。本記事では現役オーナーとして15年以上の実務を経た筆者が、20代でも理解しやすい最新情報を整理します。読めば、アパート経営で得られるメリットとリスク、さらに2025年度時点で活用できる制度までを体系的につかめるはずです。
アパート経営が20代に向く理由
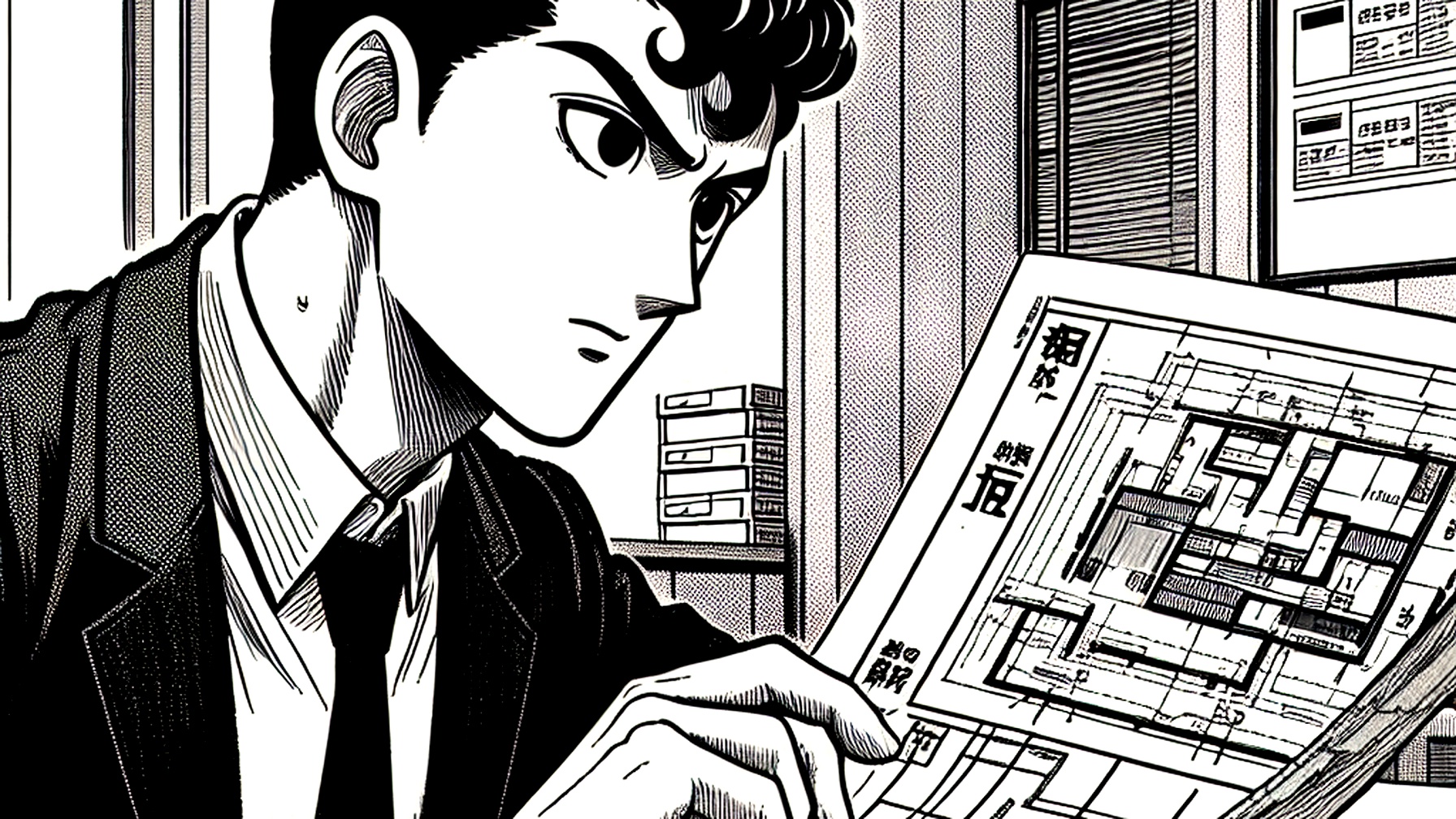
ポイントは、時間という最大の武器を早期に活用できることです。20代で始めれば複利効果が長く働き、ローン返済後の家賃収入を丸ごと老後資金に回せます。
まず若い世代は、金融機関から見て「返済期間を長く設定できる」という強みがあります。住宅ローン同様に35年融資を組めれば、月々のキャッシュフローに余裕が生まれ、無理なく運営できます。また、返済期間を通じてインフレが進めば、借入は実質的に目減りし、家賃収入は上昇する可能性があります。つまり、時間を味方にできる点が大きいのです。
一方で、若さゆえのハードルも存在します。自己資金が少なければ金利が高めに設定される場合があり、空室リスクへの備えが欠かせません。国土交通省住宅統計によると、2025年8月時点の全国アパート空室率は21.2%と依然高水準です。だからこそ立地と管理手法を磨き、早期に経営感覚を養うことが成功の鍵になります。
相続対策としての効果と注意点
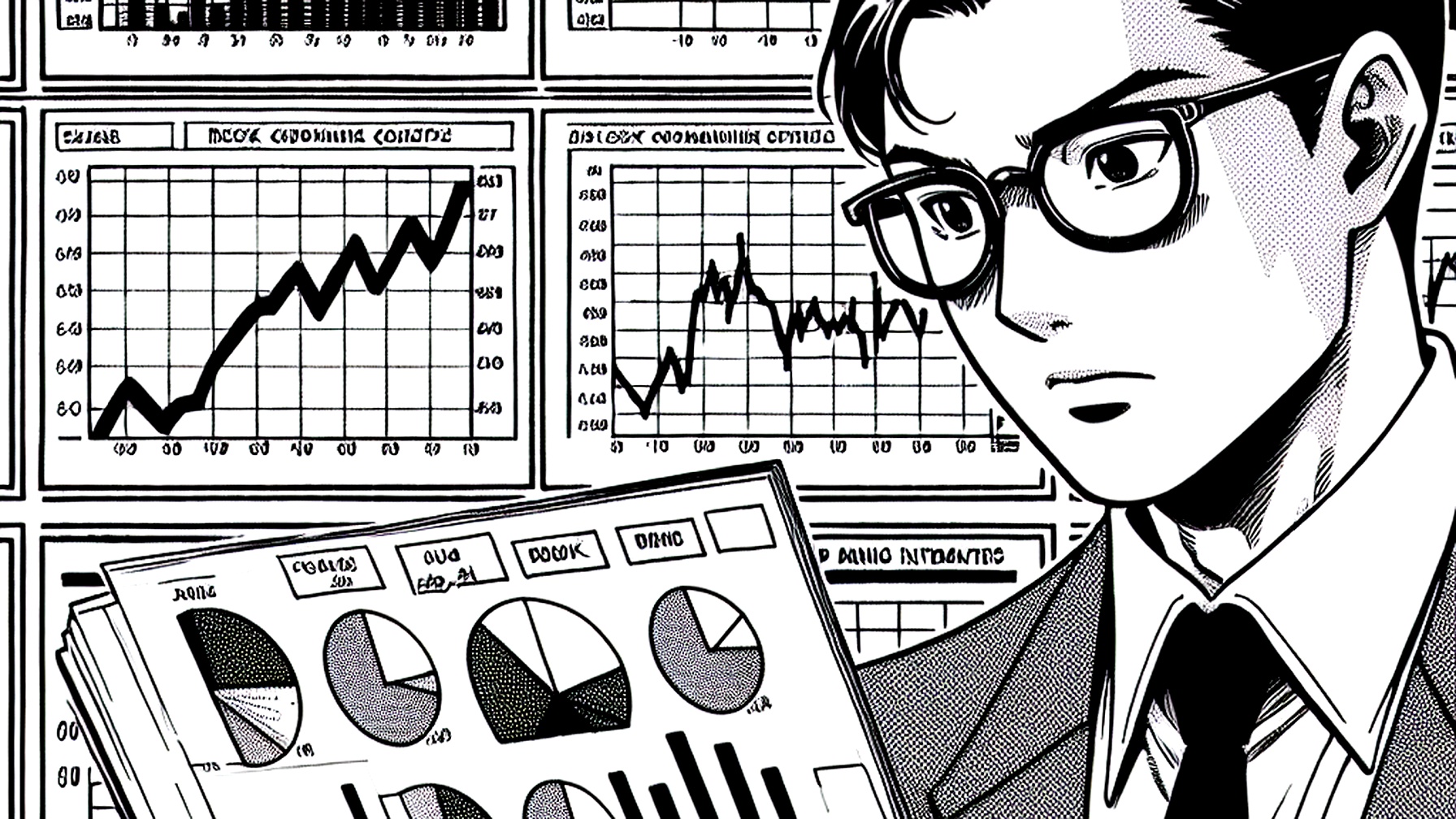
実は、アパート経営は相続税評価額を圧縮できる点で有利です。建物部分は固定資産税評価で計算され、更地より評価が低くなるため、相続税を抑えられます。
さらに、賃貸中の土地は「貸家建付地」として評価が下がり、家族にとって節税効果が大きくなります。20代で建物を建て、30~40年後に相続が発生するケースでは、減価償却が進み建物価値が目減りしているため、評価額はさらに低く計算されます。ただし、相続人が複数いる場合は共有トラブルが起こりやすいので、事前に遺言や家族信託を検討しておくことが重要です。
2025年度も引き続き利用できる「相続時精算課税制度」は、贈与税を原則2,500万円まで非課税にできる仕組みです。親世代が持つ土地に子がアパートを建てる場面で活用すれば、相続時の課税額を圧縮しつつ経営を若年層へ承継できます。ただし、一度選択すると暦年贈与非課税枠が使えなくなるため、税理士とシミュレーションを行った上で判断しましょう。
2025年度の融資環境と資金計画
まず押さえておきたいのは、金利水準が歴史的に見ても低位で推移している点です。日本政策金融公庫の2025年7月平均金利は2.05%前後、メガバンクのアパートローンは変動で1.3%台が中心です。
この環境を踏まえ、自己資金は物件価格の20%を目安に用意するのが安全圏です。例えば8,000万円の木造アパートなら頭金1,600万円、諸費用400万円、運転資金として100万円を別途確保すれば、空室や修繕が発生してもキャッシュフローが崩れにくくなります。また、返済比率(年間返済額 ÷ 年間家賃収入)は50%以下に抑えると、空室率が25%に達しても収支が赤字になりにくい計算です。
一方で、金融機関は2023年以降、物件の収益性を厳格に審査する傾向を強めています。家賃設定が周辺相場から大きく乖離していないか、修繕積立計画が実行可能かを示せなければ、希望融資額が削減される場合があります。事前に長期修繕計画書と空室シミュレーションを用意し、担当者に具体的な数字で説明することが結果的に融資承認を早める近道となります。
物件選びと管理のコツ
重要なのは、立地と間取りの需給バランスを見極めることです。都心部は価格が高いものの、人口流入が続くため空室リスクが低めです。一方、郊外は購入単価が下がりますが、長期的な人口減少に注意が必要になります。
間取りは単身向けワンルームが回転率は高いものの、退去コストも頻発します。20代オーナーなら、入居期間が平均4~6年と長めの1LDKや2DKを選ぶことで、管理の手間とコストを抑えられるケースがあります。さらに、Wi-Fi無料や宅配ボックスなど付加価値設備を導入すると、家賃1,000円の上乗せが可能なエリアも多いです。
管理会社選びも収益を左右します。手数料は家賃の5%が相場ですが、単に安さで決めると緊急対応や入居者トラブルへの対処が遅れ、結果的に空室期間が延びる恐れがあります。定期巡回の頻度、修繕提案の質、退去時の原状回復ルールまで比較し、自分の考え方と合う業者を選びましょう。
長期的に資産を守る出口戦略
ポイントは「保有」「売却」「建て替え」の三択を常に意識し、選択肢を残しておくことです。築20年を過ぎると大規模修繕や家賃下落が進みますが、債務が減っているため売却益を確保しやすくなります。早めに市場価格を査定し、利回りが低下する前に売却するのも合理的な判断です。
一方で、土地の将来価値や駅再開発計画があるエリアでは、建て替えて再度高い家賃を狙う作戦が有効になります。2025年度も利用できる「長期優良住宅化リフォーム推進事業補助金」を活用すれば、耐震改修や省エネ設備導入に対し一戸あたり最大100万円の補助が期待できます。期限や要件は毎年見直されるため、最新の募集要領を確認しながら計画を立てることが賢明です。
結論として、出口戦略を事前に描き、融資期間と修繕計画をリンクさせることで、キャッシュフローを失わずに次世代へ資産を承継できます。家族と定期的に情報共有し、共有名義や法人化のメリット・デメリットを吟味する姿勢が、長期的なリスク管理につながります。
まとめ
この記事では「アパート経営 相続対策 20代 最新版」という視点で、若い世代が押さえるべき基礎と2025年度の最新動向を整理しました。時間を味方にした長期運用、相続税評価圧縮の仕組み、低金利を生かした資金計画、そして適切な物件選びと出口戦略が成功の四本柱です。今日できる行動として、まず自己資金の目標額を設定し、金融機関の融資条件を調べ、興味あるエリアの空室率をチェックしてみてください。小さな一歩を積み重ねれば、将来の安心と家族への資産承継が現実的な目標へと変わります。
参考文献・出典
- 国土交通省住宅統計 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策金融公庫 金利情報 – https://www.jfc.go.jp
- 国税庁 相続税評価基本通達 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 人口推計 2025年8月 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業 – https://www.mlit.go.jp/house/longlife

