不動産投資を始めると、同じ物件でも査定価格が会社ごとに大きく違うことに戸惑う方が少なくありません。「なぜここまで差が出るのか」「どの数字を信じればいいのか」と悩むうちに、購入や売却のタイミングを逃してしまうケースもあります。本記事では、代表的な三つの査定方法を軸に評価プロセスを整理し、違いを理解するための視点を提示します。読み終えたとき、あなたは複数の査定書を冷静に比較し、投資判断に自信を持てるようになるでしょう。
収益還元法とは何か
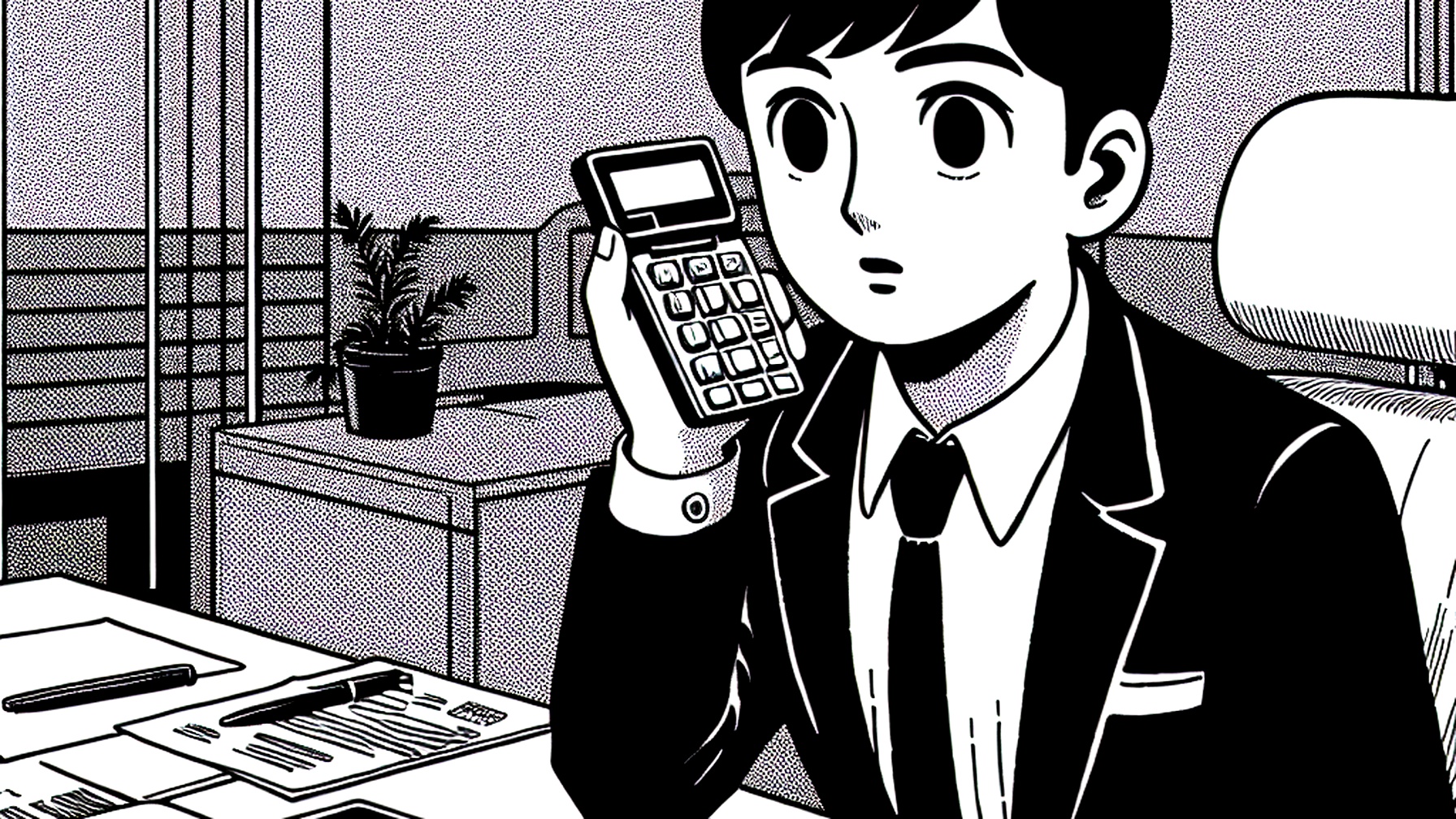
重要なのは、収益物件を「将来生み出すキャッシュフローの現在価値」として評価する考え方です。収益還元法では、賃料や更新料、売却益などの収入から運営費用を差し引き、割引率で現在価値へ換算します。
まず、国土交通省の不動産鑑定評価基準では収益還元法を二つに分けています。直接還元法は年間純収益を還元利回りで割り、DCF(ディスカウント・キャッシュフロー)法は複数年にわたるキャッシュフローを年ごとに割り引く手法です。直接還元法は計算が簡単で、実務では小規模アパートの査定に頻繁に使われます。一方、DCF法は大型の一棟マンションや商業施設など、長期の運営計画が重視される案件で採用されることが多いです。
次に、還元利回りの設定が価格を大きく左右します。民間金融機関の平均融資金利にリスクプレミアムを上乗せする方法が一般的ですが、2025年10月時点で東京23区の一棟レジの市場利回りは3.5%前後、地方主要都市では5〜6%という調査結果が公表されています。この幅をどう解釈するかが査定額の差につながります。
さらに、収益還元法は空室率の想定が肝心です。総務省の住宅・土地統計調査によると、全国平均空室率は14%台と高止まりしています。楽観的な空室率を採用すれば査定額は簡単に一割以上上振れします。つまり、空室リスクを保守的に見積もるかどうかで査定額に大きな隔たりが生まれるのです。
取引事例比較法をどう読み解くか
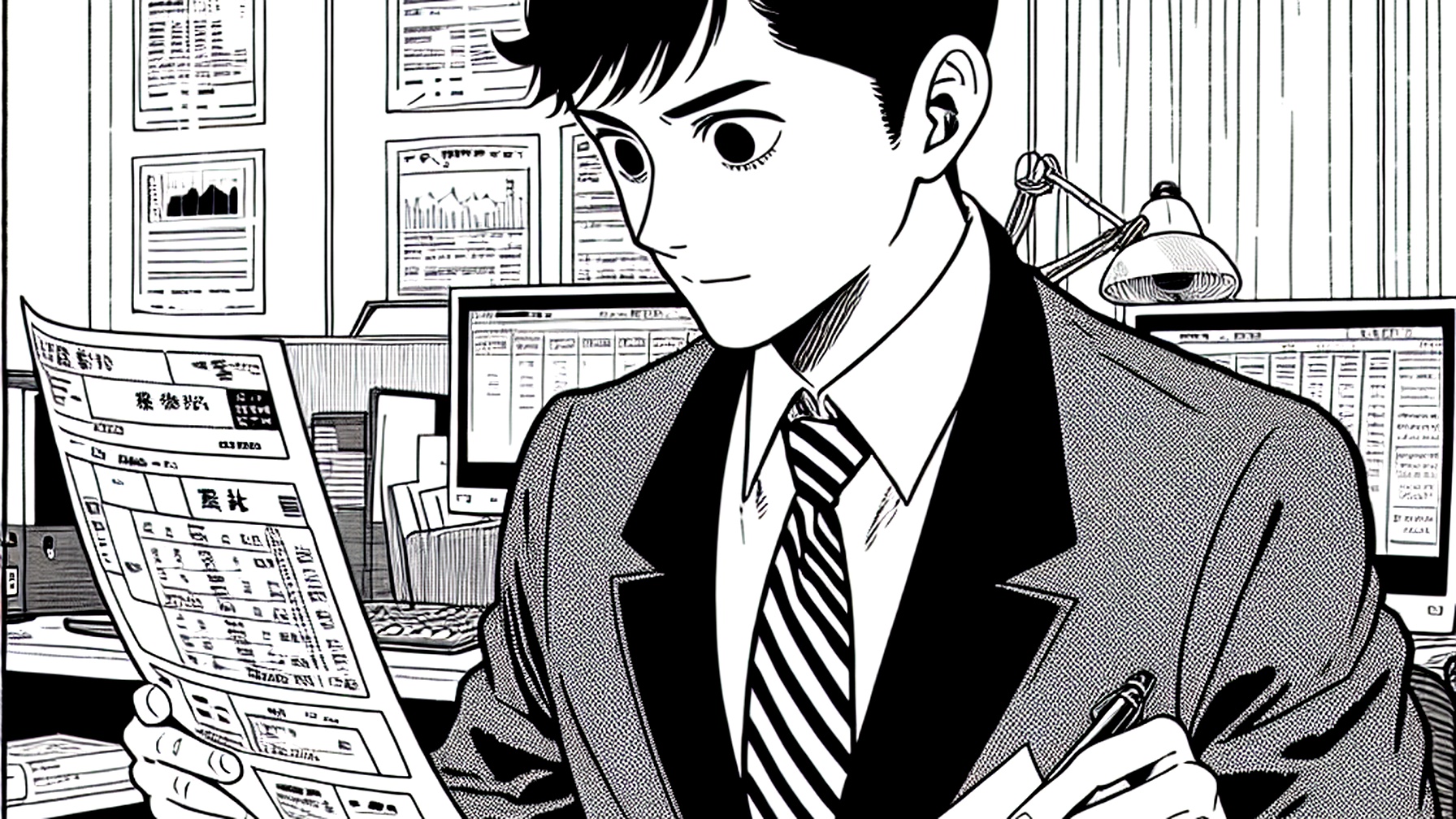
ポイントは、市場で実際に成立した売買事例を基準に「相場」を導き出す点にあります。似た物件の成約価格を集め、面積や築年数などの差を補正して価格を推定するのが基本的な流れです。
まず押さえておきたいのは、事例の鮮度と件数が結果を左右するという事実です。国土交通省のレインズデータでは毎月数万件の取引が登録されますが、半年前の事例と直近の事例では市況感が違います。特に金利が動く局面では成約価格が数%単位で変化するため、査定担当者がどの期間の事例を採用したかを確認することが重要です。
また、補正作業の仕方にも鑑定士ごとの癖があります。築年差による価値の減衰を「経年減価率」で横並びに調整する方法のほか、内外装のリフォーム状況を加点方式で評価する流派もあります。そのため、同じ築15年のRCマンションでも、補正後価格に1,000万円を超える差が出る場合があります。
最後に、市場流動性の観点も見逃せません。取引事例が豊富な都心ワンルームと、事例数が少ない地方の一棟ビルでは精度が違います。事例が不足すると、査定担当者は収益還元法や原価法を併用して補完します。その際、どの手法を重視したのかを質問すると、査定書の裏にあるロジックが明確になります。
原価法が活きる場面
実は、原価法は築浅物件や特殊用途物件の査定で不可欠です。土地と建物を別々に評価し、建物は再調達原価から減価を差し引いて価値を求める手法だからです。
まず、築5年以内の木造アパートでは市場に十分な取引事例がないことが多く、収益も安定していません。この場合、建物を新築した場合のコストを基準に評価する原価法が合理的です。国土交通省が公表する建築費指数によると、2023年から2025年にかけ木造建築費は約12%上昇しています。新築価格が上がれば、原価法による査定額も連動して高くなります。
一方で、築20年を超えると減価のウェイトが大きくなり、原価法は低めの評価になりがちです。鉄筋コンクリート(RC)の耐用年数は法定で47年ですが、内装や設備の劣化が激しい場合は追加減価を行うため、築30年を超えた区分マンションの査定額が他の手法より2割低く出るケースもあります。
さらに、ホテルや医療モールなど特殊用途の物件では取引事例が乏しいため、原価法がベースとなります。ただし、特殊設備の減価計算は専門性が高く、査定者の見解で数字がぶれやすい点に注意が必要です。このように、原価法は対象物件の性質に合わせて使うべき「補助線」として理解すると活用しやすくなります。
査定額が変わる三つのチェックポイント
まず押さえておきたいのは、査定方法そのものより前提条件の違いが価格差を生むという事実です。ここでは、とくに影響度が大きい三点を整理します。
第一に、空室率と家賃下落率の設定です。日本銀行の金融システムレポートによれば、2024年以降都心部でも家賃上昇が鈍化しており、多くの査定書が将来家賃を横ばいで置いています。しかし、郊外の築古アパートでは年1%の下落を想定するだけでDCF法の現在価値が5〜7%低下します。
第二に、割引率・還元利回りの取り扱いがあります。金融庁が2025年3月に発表した地銀貸出金利の平均は1.1%でしたが、リスクプレミアムの見積もりは査定会社ごとに大きな幅があります。リスクを3%と見るか4%と見るかで査定額が一気に下がるため、設定根拠を必ず確認しましょう。
第三に、修繕費の計上方法です。国交省「長期修繕計画作成ガイドライン」では、RCマンションの外壁補修は12年周期が目安とされています。ところが、査定書の中には修繕費をほとんど見込まず、実質利回りを高く見せるものもあります。収益物件 査定方法 違い を理解するには、この修繕費の見積もり方を見るだけでも大きなヒントが得られます。
目的別に見る査定方法の使い分け
基本的に、購入前の投資判断では収益還元法を中心に据え、市場価格とのギャップを事例比較法で検証する流れが最適です。売却を検討する場合は、買主が金融機関から融資を受けることを想定し、還元利回りをシビアに設定することで現実的な価格帯を把握できます。
また、築浅で市場事例が少ない物件を担保に融資を受けるときは、原価法の結果が重視される傾向にあります。金融機関は貸倒リスクを抑えるため、建物の残存耐用年数と再調達原価に注目するためです。つまり、融資審査で有利に進めるには、原価法の数字を意識したリフォーム計画を提示すると効果的です。
さらに、複数の査定結果をどう読み解くかが実務上のポイントになります。高い査定額だけを採用するとリスクが膨らみますが、最も低い査定額を下回らなければ資金繰りの安全度は高まります。複数手法の平均値を取る方法もありますが、資産ポートフォリオ全体の目標利回りやキャッシュフロー目標と照らし合わせて判断することが大切です。
最後に、投資戦略によって重視すべき指標が変わります。インカム重視なら純収益と還元利回り、キャピタルゲイン狙いなら事例比較法をベースに価格上昇余地を探る――このように目的に合わせて査定方法を組み合わせることで、数字に振り回されず主体的な投資判断が可能になります。
まとめ
結論として、査定方法の違いを理解することは価格の妥当性を見極める最短ルートです。収益還元法は将来キャッシュフローを、取引事例比較法は市場相場を、原価法は再調達コストを映し出します。三つの手法が示す数字の開きこそがリスクとリターンのヒントになると意識しましょう。査定書を受け取ったら、前提条件と計算根拠を必ずチェックし、自分の投資目的に沿った価格帯を導き出してください。それが、不透明な市場でも安心して一歩を踏み出すための確かな指針になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産鑑定評価基準 – https://www.mlit.go.jp/
- 国土交通省 建築費指数調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 住宅・土地統計調査 2023 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/
- 金融庁 地方銀行融資金利統計 2025年3月 – https://www.fsa.go.jp/
- 国土交通省 レインズ市況レポート 2025年上期 – https://www.reins.or.jp/

