マンション投資に興味はあるものの、「表面利回りと実質利回りの違いが分からず判断できない」と悩む声をよく耳にします。確かに広告に大きく書かれた利回りは魅力的ですが、その数字だけで物件を選ぶと想定外の出費に後悔することもあります。本記事では、利回りの計算方法と活用のコツを基礎から丁寧に解説し、2025年10月時点の最新データを交えながら失敗しない物件選びの視点を提供します。読み終える頃には、数字の裏側を読み解き、自分に合ったマンション投資戦略を立てられるようになるはずです。
表面利回りとは何か
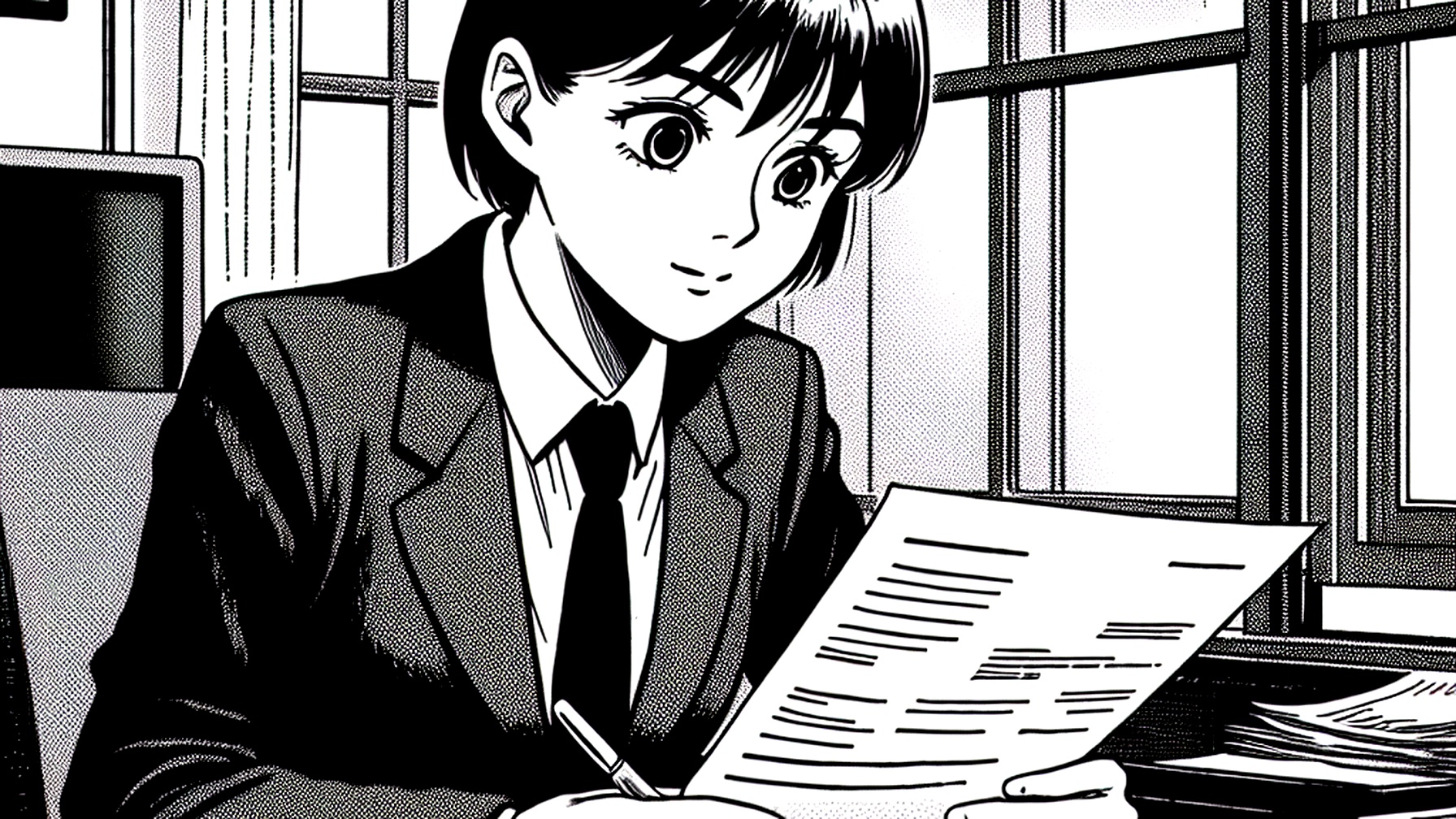
まず押さえておきたいのは、表面利回りが「年間家賃収入 ÷ 物件価格」で求められる非常にシンプルな指標だという点です。日本不動産研究所の調査によると、2025年10月の東京23区平均表面利回りはワンルームで4.2%、ファミリータイプで3.8%となっています。つまり、この数字は家賃が途切れず、諸費用が一切かからない理想的な前提で計算されたものに過ぎません。広告で強調される理由は、投資初心者に分かりやすくインパクトがあるからですが、実際の収益を正確に示すわけではない点に注意が必要です。
次の段落では、表面利回りの長所と限界を整理します。長所は物件同士の比較が手早くできることです。特に候補物件が多い都市部では、ざっくりとしたスクリーニングに役立ちます。しかし、管理費や固定資産税などのランニングコストが考慮されていないため、数字だけを鵜呑みにするとキャッシュフローを見誤ります。初心者ほど「高い利回り=高収益」と短絡的に考えがちですが、リスク見合いでない物件を選ぶ原因になりかねません。
そこで、表面利回りは第一段階のふるいとして活用し、詳細分析の入り口と位置付けることが大切です。具体的には、駅徒歩や築年数など条件が似た物件の中で大まかな優劣を判断する用途に適しています。その上で次に紹介する実質利回りを計算し、リアルな収益を把握する流れを習慣づけましょう。
実質利回りが示す本当の収益力
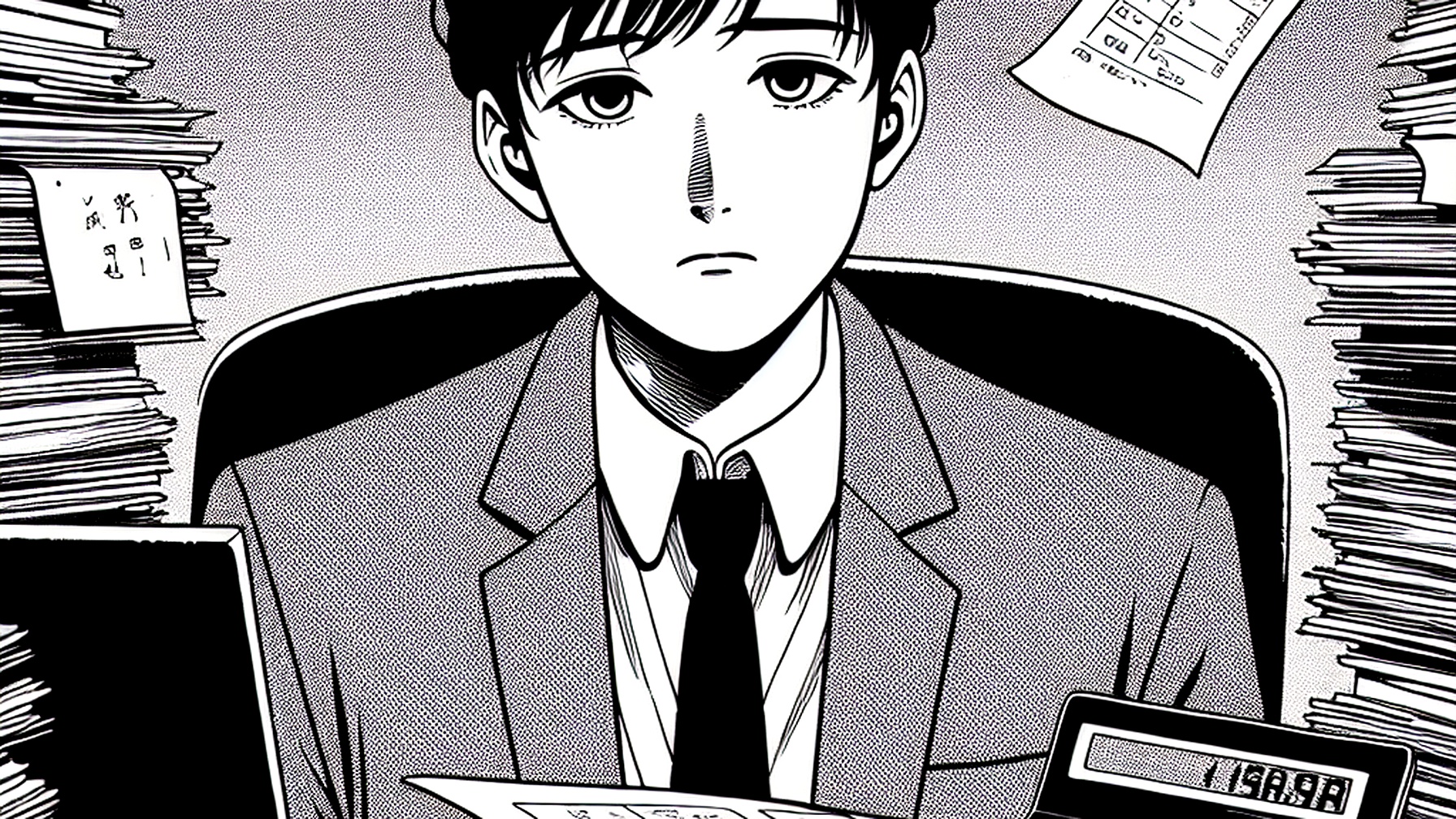
重要なのは、実質利回りが「(年間家賃収入 − 年間経費) ÷ 総投資額」で求められる点です。ここでいう経費には管理費、修繕積立金、固定資産税、火災保険、入居付けの広告料などが含まれます。また、総投資額には購入時の仲介手数料や登記費用も組み込みます。言い換えると、実質利回りは手取りベースの利益を示すため、銀行口座に残る現金をイメージしやすい指標なのです。
実際に計算してみると、表面利回り4.2%のワンルームでも、管理費と修繕積立金で月1万円、固定資産税が年5万円かかると仮定すると、実質利回りは約3.0%まで低下します。さらに購入時諸費用を物件価格の7%と仮定すれば、総投資額が膨らみ、利回りは2%台後半に落ち込むケースも珍しくありません。こうした差は、物件を長期保有するほど大きな影響を及ぼします。
一方で、実質利回りはシミュレーションの設定次第で変動します。空室率を何%にするか、修繕費を築年数に応じてどう見込むかなど、前提条件の置き方が結果を左右します。そのため、複数シナリオを用意し、悲観的なケースでも手元資金が枯渇しないかを確認することが不可欠です。また、家賃下落率を年1%とするのか据え置くのかでも、30年後の総収入に数百万円の差が出ることを忘れないでください。
数字の落とし穴を避けるチェックポイント
ポイントは、利回り計算の裏に潜むコストを洗い出し、漏れなく反映させることです。購入時には仲介手数料3%、登記費用0.3%前後、ローン手数料や火災保険料が加算されます。加えて、築20年を過ぎた物件では外壁修繕が避けられず、一度に100万円単位の負担が生じる場合があります。これらを「いつ」「いくら」支払うかを時系列で整理することで、実質利回りをより現実的に算出できます。
さらに、ローン金利の影響も大きいといえます。金融機関が提示する変動金利は2025年10月現在で0.45%〜0.80%の幅が一般的ですが、金利が1%上がると返済額はおよそ15%増える試算があります。つまり、実質利回りが高くても、返済比率が上がれば毎月のキャッシュフローは簡単にマイナスに転じます。物件比較の際には、想定金利を統一したうえでシミュレーションを行いましょう。
最後に、賃貸需要を測るデータにも目を向けてください。総務省の住民基本台帳移動報告では、東京都23区の転入超過数は2024年比で微増にとどまっています。人口増が鈍化すると空室リスクが増し、想定家賃を維持できなくなる可能性があります。利回り計算の精度を高めるには、行政統計や再開発計画の情報を組み込み、5年後10年後の賃貸市場を見通す視点が欠かせません。
物件タイプ別の利回り相場と選び方
実は、利回りの高さは物件タイプによって傾向が異なります。前述のとおり、東京23区の平均表面利回りはワンルーム4.2%、ファミリー3.8%、アパート5.1%です。アパートが高めに映るのは、木造で建築費が抑えられる一方、入居者の入れ替わりが激しく空室リスクが大きいからです。数字だけに惹かれて郊外のアパートを選ぶと、退去後の原状回復費用が家賃数カ月分に達し、実質利回りが急落することもあります。
一方、都心のワンルームは価格が上昇傾向にあるものの、単身者ニーズが底堅く、空室期間が短い点が魅力です。不動産経済研究所のデータでは、2025年10月の新築マンション平均価格が7,580万円に達し、前年比3.2%上昇しています。購入価格が高いぶん利回りは低下しますが、資産価値の下支えが期待できるのが強みです。
ファミリータイプは、学区や周辺環境の影響が大きいため、立地の選定が成否を分けます。例えば駅徒歩8分以内、小学校まで徒歩10分圏内など、子育て世帯のニーズを押さえた物件は賃料が下がりにくく、長期入居も期待できます。逆に立地や設備が平凡だと、ファミリーは引っ越しコストを厭わず郊外の新築に流れる傾向があるため、空室期間が長くなりやすい点に注意が必要です。
物件タイプを選ぶ際は、利回りだけでなく、自己資金の量、融資条件、保有期間の長さ、リスク許容度を総合的に考慮しましょう。たとえば、安定収入を重視する人が、短期売却益を狙うディベロッパー向け案件に手を出すとミスマッチが生じます。ターゲットを明確にし、そのニーズが将来どう変わるかを調べることが、長期的な収益安定につながります。
利回り以外に注目すべき指標
また、利回りと並んでチェックしたいのがキャッシュフローと自己資本比率です。キャッシュフローとは、家賃収入からローン返済や経費を差し引いた純粋な手残り金額を指します。実質利回りが高くても、ローン返済比率が高ければキャッシュフローは圧迫され、突発的な修繕に備える余裕がなくなります。安全圏としては、家賃収入のうちローン返済が60%以内に収まる形が望ましいといえます。
自己資本比率は「自己資金 ÷ 総投資額」で求められ、金融機関の審査だけでなく投資家自身の安全マージンを測る指標です。20%を超えると空室や金利上昇に対する耐性が高まり、資金繰りに余裕が出るとされています。また、出口戦略を検討する際には「価格変動率」も目安になります。都心では再開発やインフラ整備が進むエリアを選ぶと、将来的に売却益でキャピタルゲインを得られる可能性が高まります。
最後に、貸し出し需要を示す「賃貸付帯サービスの伸び率」も見逃せません。2025年上期の国土交通省調査では、家具付き・Wi-Fi付きなどの付帯サービスを求める入居希望者が前年同期比で12%増えました。こうしたトレンドを捉え、設備投資に回すことで家賃を上げ、結果的に実質利回りを向上させる手法も有効です。
まとめ
本記事では「マンション投資 表面利回り VS 実質利回り」をテーマに、数字の意味と活用法を解説しました。表面利回りは物件比較の第一歩として便利ですが、経費や空室リスクを加味した実質利回りを計算しないと真の収益力は見えてきません。さらに、キャッシュフローや自己資本比率といった指標を組み合わせ、複数シナリオで検証することで投資判断の精度を高められます。まずは手元の候補物件で実質利回りを試算し、数字が語る現実を確認するところから始めてみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳移動報告 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局 再開発情報 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

