家賃収入で将来の不安を減らしたい、しかし「自分にアパート経営 できるのか」と悩む人は多いです。運用コストや空室リスクを考えると、失敗例ばかりが頭に浮かびます。けれども基礎を押さえたうえで市場データを読み解けば、サラリーマンでも安定収益を得られる手段になります。本記事では2025年10月時点の最新情報をもとに、初心者がつまずきやすいポイントから成功の具体策まで順を追って説明します。読み終えたとき、あなたは最初の一歩を踏み出すための判断基準と行動計画を手に入れているはずです。
アパート経営ができる人の共通点
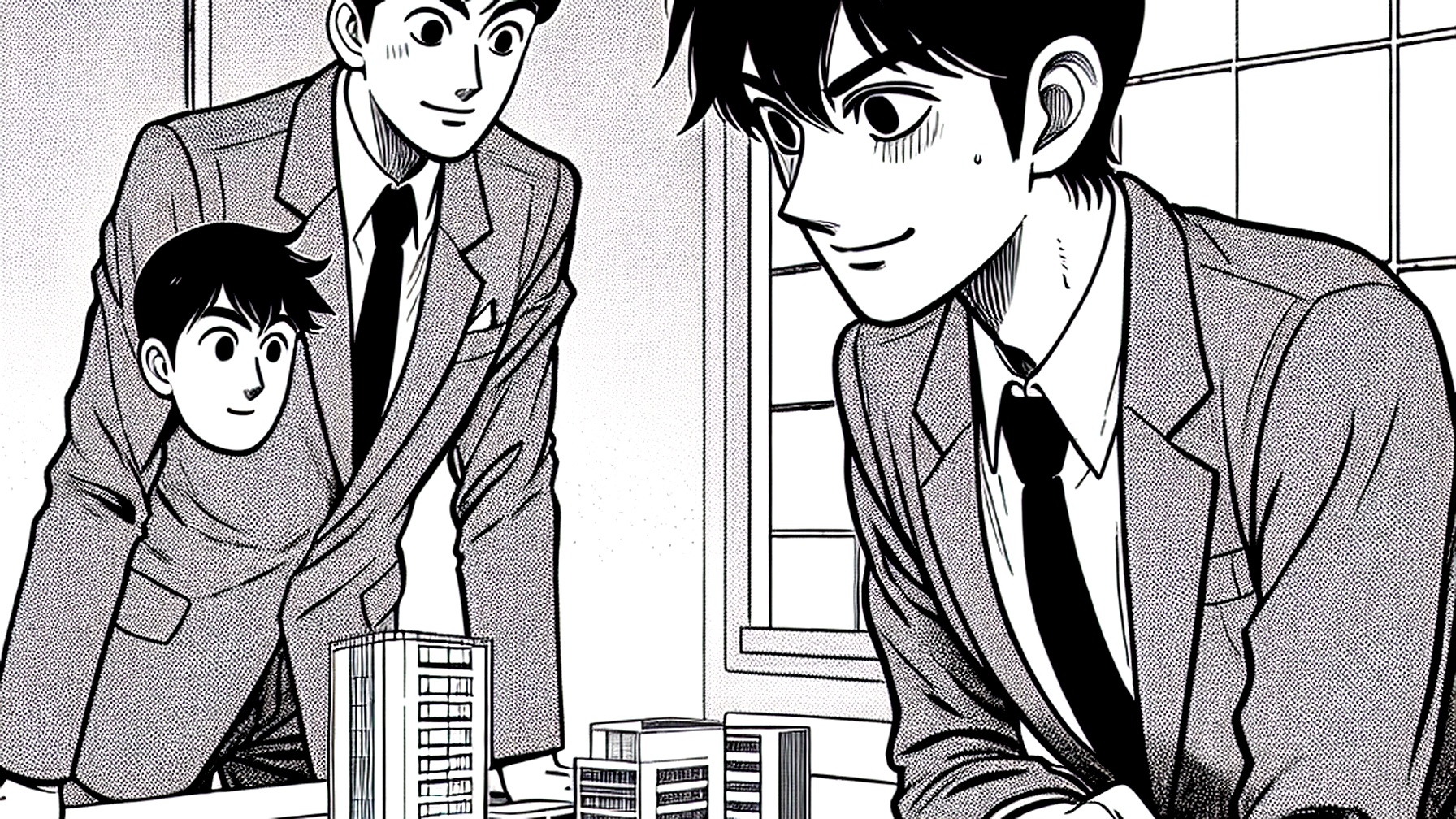
重要なのは、特別な才能よりも「数字を素直に受け止める姿勢」です。実際に長期で黒字を続けるオーナーを観察すると、多忙な会社員でも家計簿の延長線上で収支を管理しています。つまり高度なファイナンス知識より、毎月の入出金を見える化し、早めに手を打つ習慣が決定的に効いているのです。
次に、リスクの棚卸しを怠らないことが挙げられます。たとえば空室率、修繕費、金利上昇の三つを定期的にチェックし、数値に変化があれば融資条件の見直しやリフォーム計画を前倒しします。また家賃保証など外部サービスを盲信せず、契約内容の改定履歴まで確認している点も共通しています。
一方で、すべてを自分だけで決めないのも特徴です。税理士や管理会社と役割分担し、本業の時間を確保しながら経営判断の質を高めています。こうした姿勢は初心者でも再現可能であり、むしろ会社勤めの経験がプラスに働く場面が多いと言えます。
2025年の市場動向とチャンス
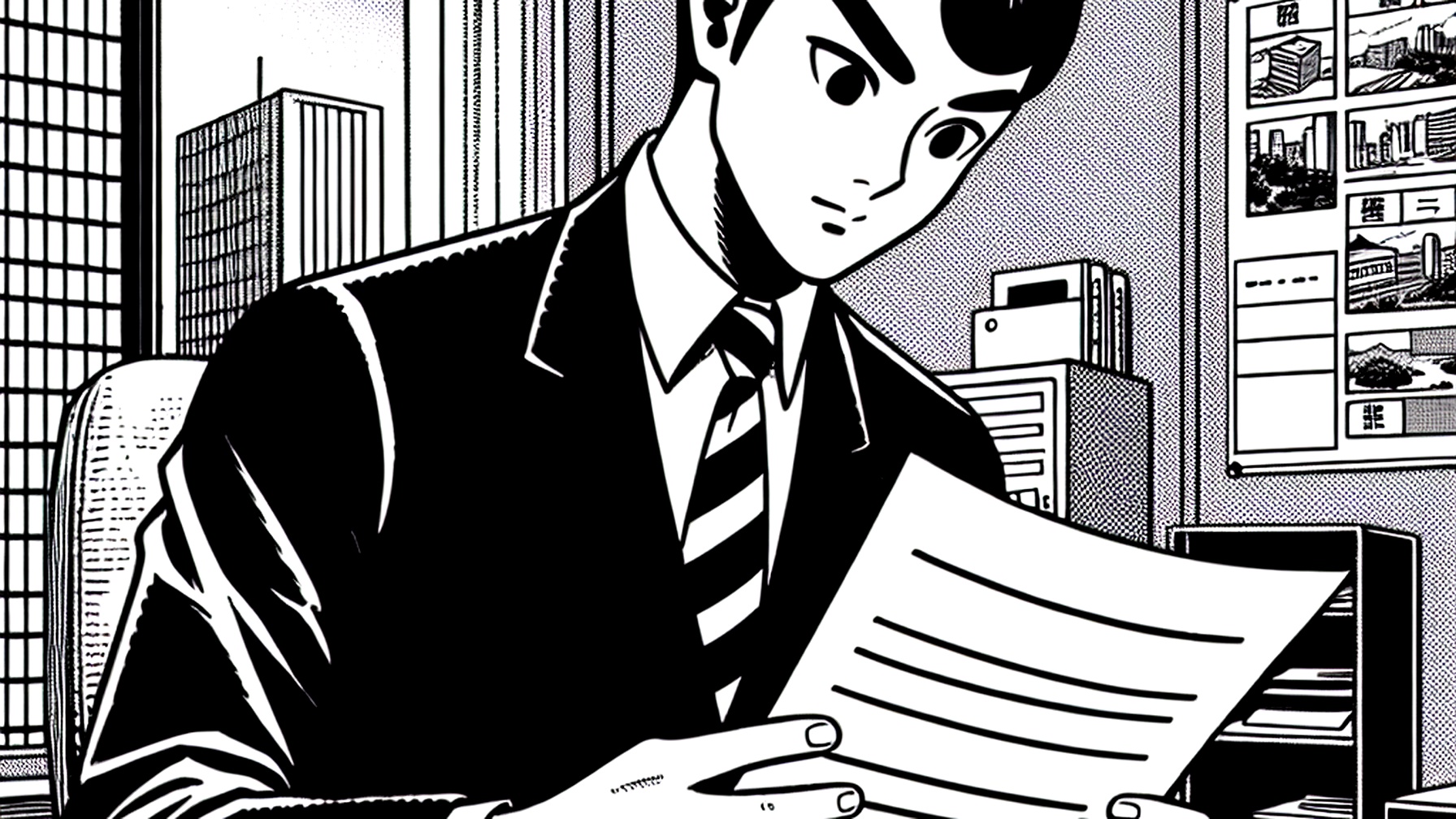
まず押さえておきたいのは、賃貸需要が一律に落ち込んでいるわけではない点です。国土交通省住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しています。都市再開発に伴う単身者流入と、リモートワーク普及で柔軟な住み替え需要が重なり、駅徒歩10分圏内の築浅物件は依然として競争力を保っています。
一方で郊外や築古の物件は二極化が進みます。家賃を下げても成約に時間がかかるケースが増え、実質利回りは都市中心部との差が広がっています。しかし、地方中核都市で大学や工業団地が集まるエリアは人口減少の影響を受けにくく、土地値も抑えられるため初期費用を削減できます。ここにリフォームを組み合わせると、表面利回り9〜10%が現実的に狙えます。
2025年度の住宅ローン減税は、投資用物件には直接適用されませんが、個人の資金繰りに影響する金利水準を下支えしています。長期固定金利(フラット35投資用)は1.8%台を維持し、変動型も1%前後で推移しています。低金利環境が継続するあいだに固定化を進めておくことが、中期的なリスクを抑える鍵になります。
まず押さえておきたい資金計画
ポイントは、表面利回りより「キャッシュフロー」を最優先することです。表面利回り8%でも、管理費や修繕積立を差し引いた手残りが月1万円では生活を変える力はありません。そこで毎月の実質手残りがプラス3万円以上になる形を目標にします。
第一に自己資金です。物件価格の20%を自己資金として用意すれば、金融機関の審査が通りやすく、借入金利も0.2〜0.4%低くなる傾向があります。たとえば3,000万円の木造アパートなら、600万円を頭金、諸費用150万円、予備費100万円で合計850万円が一つの目安です。
次に融資条件を比較しましょう。地方銀行が提示する20年返済2.3%と、信販系の30年返済1.9%では、月々の返済額こそ後者が低いものの、総返済額は逆転する場合があります。言い換えると、金利だけでなく返済期間と団体信用生命保険の有無まで含めて総合判断する必要があります。
最後にシミュレーションです。空室率15%、金利上昇1%のストレスシナリオでも年間キャッシュフローが黒字になるか確認します。ここで赤字になるなら、頭金を増やすか物件条件を見直すべきです。保守的な試算を経てこそ、突発的な修繕費が生じても経営を継続できます。
成功する物件選びのポイント
実は、築年数より将来の修繕コストを予測できるかどうかが肝になります。築30年でも大規模修繕済みなら当面の支出を抑えられますが、未修繕の築20年は購入直後の出費で利回りが半減しかねません。売買契約前に共用部の配管や屋根を専門業者へ調査依頼し、見積書を取得する姿勢が欠かせません。
立地については、駅距離と生活利便施設の双方を見ることが大切です。徒歩10分を超える場合でも、スーパーや病院が近いエリアは高齢者需要を取り込めます。逆に都心駅近でも夜間の騒音や治安が悪化している地域は、長期入居にマイナス要因となります。
物件規模にも注意が必要です。総戸数6〜8戸の木造アパートは初期費用が抑えられ、満室時の利回りは高めです。ただし1戸空いたときの収支インパクトが大きく、家賃交渉に弱い側面があります。総戸数20戸以上の鉄骨造は空室リスクを平準化できますが、固定資産税が上がり、融資期間が長く取れないケースもあります。
選定の最終段階では、近隣の募集家賃と成約家賃を比較しましょう。インターネット上の賃料は上乗せされていることが多く、実際の成約水準は5〜7%低い場合があります。管理会社にヒアリングし、リアルな成約データを取得することが着実な判断を後押しします。
長期安定経営へ向けた運営術
まず押さえておきたいのは、入居者満足度を高める小さな施策の積み重ねです。たとえば共用灯をLEDに交換すると電気代を30%削減でき、夜間の明るさが向上して防犯効果も期待できます。費用は1戸あたり数千円で、家賃アップ交渉のきっかけにもなります。
家賃滞納への対策も欠かせません。家賃保証会社と連携しつつ、入居者と顔が見える距離感を保つことでトラブルは減ります。年に1度の設備点検の際に簡単なアンケートを実施し、Wi-Fi速度や宅配ボックスへの要望を聞き取ると、早期に改善策を講じられます。
また、修繕積立を毎月の家賃収入から自動的に分別する仕組みが有効です。全体収入の8〜10%を別口座にプールしておけば、10年周期の外壁塗装時にも追加借入を避けられます。金融機関によっては「リフォーム積立口座」を無利息で提供しており、確実に資金を確保できます。
結論として、経営を自動化しつつ要所で判断できる体制が、アパート経営を「できる」状態へ導きます。管理会社任せではなく、月次レポートを読み解き、目標利回りと乖離があれば即時に家賃改定や広告強化を指示するスピード感こそが、長期的な差別化要因です。
まとめ
本記事では、アパート経営 できる人に共通する行動、2025年の市場動向、資金計画、物件選定、そして運営術を順に解説しました。数字を正確に把握し、低金利を活かして固定化し、修繕費を前もって積み立てることで、空室率21.2%という統計値を恐れずに挑戦できます。まずは自己資金の準備と、信頼できる専門家チーム作りから始めましょう。今日行動を起こせば、家賃収入はあなたの将来に安定と選択肢をもたらすはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp/statistics/
- 日本銀行 金融経済月報 2025年9月 – https://www.boj.or.jp/
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年上半期 – https://www.soumu.go.jp/
- 独立行政法人 住宅金融支援機構 金利情報 2025年10月 – https://www.jhf.go.jp/
- 公益財団法人 日本賃貸住宅管理協会 賃貸住宅市場データ 2025年度版 – https://www.jpm.jp/

