マンション投資に興味はあるものの、医師として多忙な日々を送りながら資産形成まで手が回らない──そんな悩みを抱えていませんか。勤務時間が不規則で情報収集の時間が限られる医師にとって、手堅い投資手段を選ぶことは大きな課題です。本記事では「マンション投資 ファミリー向け 医師」という観点から、忙しい医師でも取り組みやすい投資モデルを具体的に解説します。読めば、物件選びから融資、税制優遇の活用法まで一連の流れが理解でき、限られた時間でも安定収益を目指す方法が見えてくるでしょう。
忙しい医師にマンション投資が合う理由

まず押さえておきたいのは、現役医師がマンション投資に向いている背景です。医師は高い信用力と安定収入を兼ね備えており、金融機関からの融資審査で優遇されやすい傾向があります。これは自己資金を厚く用意できなくても、レバレッジを効かせた投資が実現しやすいことを意味します。
さらに、不動産投資は株やFXのように四六時中チャートを見る必要がありません。専門の管理会社に日常業務を委託すれば、夜間当直や緊急オペで忙しい日でも運用を継続できます。つまり時間的制約の大きい医師にとって、マンション投資は「手間をお金で買う」ことで成果を最大化しやすい手段といえます。
一方で、放置すれば勝手に利益が生まれるわけではありません。物件の選定、資金計画、管理会社の質など、初期段階での判断が長期収益を左右します。そこで、ファミリー向け物件に焦点を当てる理由を次章で詳しく見ていきましょう。
ファミリー向け物件の需要と立地戦略
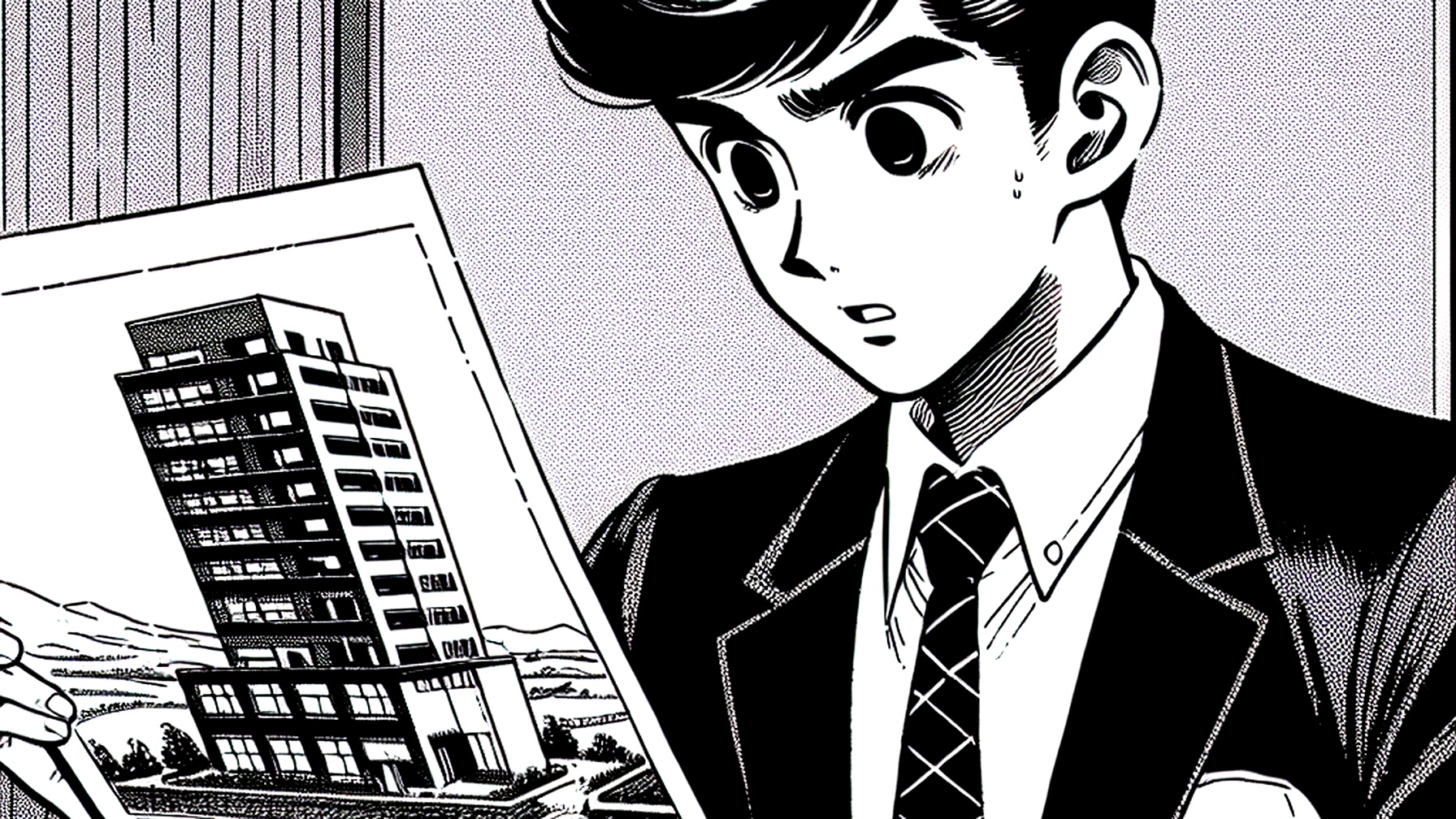
ポイントは、賃貸市場で長期入居者を確保できるかどうかです。ファミリー世帯は子どもの学区や通勤時間の兼ね合いで転居回数が少なく、平均入居期間が単身者より長いと総務省の住宅・土地統計調査でも示されています。空室リスクを小さくしたい医師投資家にとって、この安定性は大きな魅力です。
実際、2025年10月時点で東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円と高止まりしていますが、郊外でも教育環境が整う駅近エリアは賃料が下がりにくい傾向があります。都心勤務の共働き世帯が増え、保育園や小学校へのアクセスの良さが重視されていることが背景です。言い換えると、郊外でも「駅徒歩10分以内」「学区ブランド」「スーパーや病院の近接」という三拍子がそろう場所は、価格が手頃で利回りを確保しやすいのです。
ところが、ファミリー向けは専有面積が広いため、ワンルームより購入価格が高くなる点がネックです。そこで後述する融資戦略とキャッシュフロー管理が欠かせません。また、築浅より築10年前後の物件が狙い目です。設備仕様は現代基準を満たしつつ、価格が落ち着いて表面利回りが高くなるからです。
キャッシュフローと融資の考え方
重要なのは、初年度から手残りをプラスに保つ資金計画です。医師の場合、年収1,500万円前後であれば、フルローンやオーバーローンの提案を受けることも珍しくありません。しかし、返済比率が高すぎると本業の収入を圧迫し、ストレスが増えるだけです。
目安として、毎月のローン返済額が家賃収入の70%以内に収まる設定を推奨します。例えば、家賃25万円の3LDKを購入する場合、月返済17万円以下なら管理費・修繕積立金を差し引いても手残りはプラス圏を維持しやすくなります。日本銀行の統計によれば、2025年10月の住宅ローン固定金利(35年)は1.3%前後で推移しています。医師向けの優遇金利が適用されればさらに低い数字が期待できるため、シミュレーションでは金利2.0%のストレスシナリオも組み込み、利上げ局面への備えを忘れないことが大切です。
また、将来の大規模修繕や設備更新に備えて家賃の5%を毎月積み立てると、急な出費にも動じない資金クッションが作れます。空室損失や修繕費を折り込んだネット利回り4%を確保できれば、長期での資産拡大が視野に入ります。
2025年度の税制・優遇策を活用するコツ
実は、税メリットを最大限に活かすことで実質利回りを底上げできます。2025年度も医師が利用できる代表的な制度は「住宅ローン控除」「固定資産税の新築軽減措置」「不動産所得の損益通算」です。住宅ローン控除は自ら居住する物件が対象ですが、マイホーム用と投資用を組み合わせる“住み分け”を計画すると、控除枠を活かしながら投資効率を高められます。
一方、賃貸用マンションについては減価償却費を計上して所得税と住民税を軽減する手法が有効です。医師の高所得層にとって、実効税率は40%近くになることもありますが、減価償却を活用すると課税所得を圧縮し、キャッシュアウトを抑制できます。国税庁の「所得税基本通達」に基づく耐用年数27年(RC造)を超える中古物件なら、短期で償却が進み節税効果が早期に出やすい点も見逃せません。
さらに、2025年度は子育て支援の一環として「こどもエコすまい支援事業(賃貸併用住宅対応型)」が継続されており、省エネ性能を満たす新築ファミリー向け物件を購入すると、最大60万円の補助金が得られます。申請期限は2026年3月末までとされているため、検討中の医師は早めに事業者と打ち合わせておくと安心です。
安定運用へ導く管理体制と出口戦略
基本的に、ファミリー向けマンションは管理の質が収益の安定度を左右します。長期入居者が求めるのは清潔な共用部と迅速なトラブル対応です。管理組合が機能していない物件や修繕積立金が不足している物件は、将来の大規模修繕時に一時金が発生しやすく、キャッシュフローを圧迫します。購入前に「長期修繕計画」「積立金の残高推移」「理事会議事録」を確認し、トラブルの芽を摘んでおくことが不可欠です。
また、出口戦略として「売却」と「相続」の二択を早い段階でイメージしておくと戦略にブレが生じません。都心アクセスが良く学区評価の高いエリアは購入需要も根強く、インフレ局面では価格上昇益も狙えます。子どもが医学部進学を目指す時期に売却益を教育資金に充てる、あるいは家族信託を利用して次世代へスムーズに資産承継する──医師ならではのライフプランに沿った出口が描けるでしょう。
管理会社選定では、家賃送金サイクルの短さよりも入居者対応の品質を優先するとトラブル低減につながります。顧問税理士やファイナンシャル・プランナーと連携し、物件管理と税務対策を一体で考える体制が安定運用への近道です。
まとめ
ここまで、医師がファミリー向け物件でマンション投資を行うメリットと注意点を見てきました。高い信用力を武器に低金利融資を引き出し、長期入居が見込める立地を選び、税制優遇を駆使することで、忙しい診療の合間でも堅実に資産を積み上げることが可能です。まずは試算表を作り、返済比率と税引後キャッシュフローを確認するところから始めてみてください。行動を起こすことで、不労所得の柱が将来の選択肢を広げ、医師としてのキャリアと家族の幸せを同時に支える力になるでしょう。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅局「住生活基本計画」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行「金融経済統計月報」 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁「所得税基本通達」 – https://www.nta.go.jp
- 東京都都市整備局「住宅市場動向」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

