マンションを丸ごと一棟で購入する方法は、区分所有より大きな家賃収入を得られると聞き、興味を持つ方が増えています。しかし「空室が続いたら返済はどうなるのか」「古い建物を買っても修繕費は大丈夫か」といった不安も尽きません。本記事では一棟買い特有のリスクを整理し、回避のために押さえるべき視点を解説します。初めての方でもポイントをつかめるよう順序立てて説明しますので、読み終えるころには自分に合った投資判断ができるようになるはずです。
一棟買いが区分投資と決定的に違う点
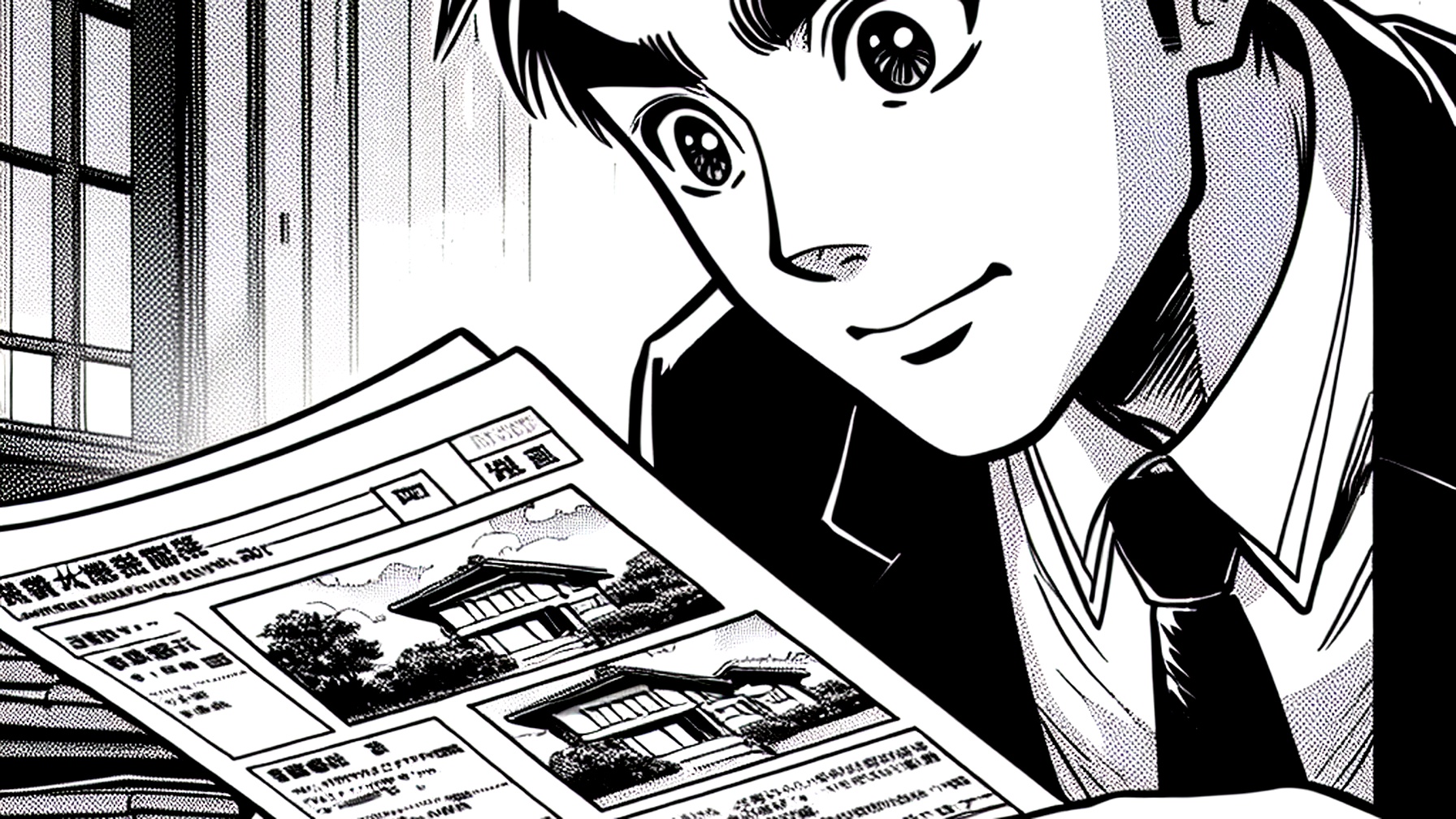
重要なのは、一棟買いでは「経営者の視点」が不可欠になることです。区分投資は管理組合が共用部分を維持しますが、一棟買いではオーナーが建物全体の責任を負います。つまり収益と同時にコストの全体像を理解しなければなりません。
まず、共用部の電気代やエレベーター点検などランニングコストは毎月発生します。東京23区の築20年・15戸規模の鉄筋コンクリート物件で共用部費用は月平均7〜10万円が目安です。空室が増えたときでもこれらの支出は減らないため、自己資金で補填できる余力が必要です。
また、金融機関の審査基準も区分とは異なります。一棟買いでは個人の属性だけでなく事業計画の妥当性が厳しく問われ、2025年時点で多くの銀行が金利2%前後・借入期間25〜30年を上限としています。返済比率の目安は家賃収入の50〜60%以内が推奨されており、この範囲を超える計画は承認が難しくなります。
さらに、売却出口の狭さも意識しましょう。区分マンションは実需層へ売却できますが、一棟物件は投資家に限定されます。不動産経済研究所の調査では、築30年超の一棟RCマンション成約期間は平均9.7か月と、区分の約2倍です。流動性が低い点は資金計画に織り込む必要があります。
見落としがちなリスクとその拡大メカニズム
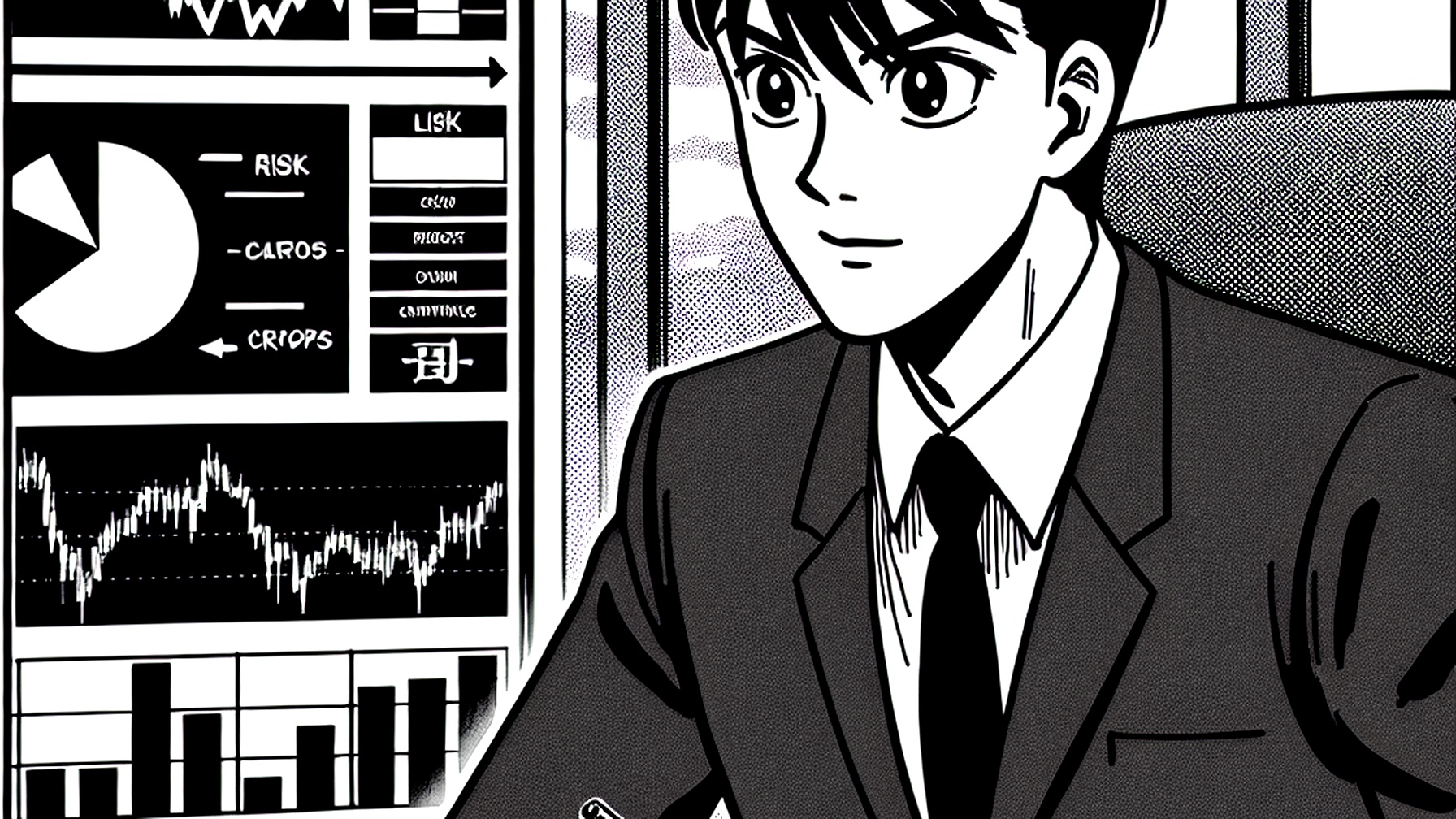
まず押さえておきたいのは、リスクが連鎖しやすい構造です。空室が増えると家賃収入が減り、十分な修繕ができず建物の魅力が低下し、さらに空室が増えるという負のサイクルに陥りやすくなります。
空室率について、総務省「住宅・土地統計調査」2023年速報では全国平均13.6%ですが、築30年以上かつ駅徒歩15分超の賃貸住宅は18%を超えます。利回りの高さに目を奪われ、築古で立地条件が劣る物件を選ぶと、表面利回りは良くても実際の手取りは大きく下振れします。
家賃下落リスクも見逃せません。国土交通省の賃貸住宅新規成約データでは、築25年を過ぎると都心部でも平均家賃が年1%弱下がる傾向があります。家賃が下がると返済比率が急上昇し、資金繰りが逼迫します。実は、家賃が1万円下がるだけで年間収支は12万円減少しますから、複数戸を抱える一棟物件では影響が大きくなります。
火災や災害のリスクも拡大要因です。建物全体が被災した場合、家賃停止と復旧費用が同時に発生します。2025年度の地震保険は保険期間5年で料率が平均約0.1%上がりました。保険料の増加と免責金額を踏まえ、自己資金の安全余裕を確保することが欠かせません。
融資とキャッシュフローの落とし穴
ポイントは、銀行融資が組めるかどうかが投資成否を左右する点です。一棟買いでは自己資金を20〜30%投入し、残りを融資で賄うケースが一般的です。しかし金利上昇や返済期間短縮の影響を受けやすく、キャッシュフローが薄い計画は極めて危険です。
日本銀行の「貸出金利動向」では、2025年6月の投資用不動産向け平均金利は2.48%で、前年より0.27ポイント上昇しています。仮に金利が1%上がると、元金1億円・残期間25年のローンでは年間約90万円の返済増となり、家賃1室分が吹き飛ぶ計算です。ストレステストとして金利+1.5%でも耐えられるか確認する習慣を持ちましょう。
また、元利均等返済は返済初期に利息割合が多く、実際に手元に残る現金が少なくなります。融資条件を比較するときは「元金返済比率」に注目し、初年度で20%を超えるプランは手元キャッシュが枯渇しやすいので避けるのが無難です。
経費計上の見込み違いにも注意が必要です。減価償却で税負担を抑えられるといわれますが、RC造の耐用年数47年を超えた物件では残存価値が小さく、減価償却による節税効果も限定的です。税理士と連携してシミュレーションを行い、手取りベースでプラスになるかを確認することが大切です。
修繕計画と老朽化リスクへの備え
実は、一棟買いで最も後悔が多いのが修繕費の読み違いです。区分投資なら修繕積立金が毎月決まっていますが、一棟物件の積立はオーナー次第となります。計画が甘いと突発的な支出が発生し、資金がショートしやすくなります。
国土交通省「長期修繕計画ガイドライン」によると、RC造15戸規模で30年周期の大規模修繕費は平均1,800万円程度が目安です。毎月の積立額に換算すると約5万円となり、空室リスクを見ても月間家賃収入の7〜10%を修繕積立として確保する必要があります。
外壁改修や屋上防水は後回しにすると雨漏りにつながり、結果的に原状回復費用が跳ね上がります。また入居者からの評判が下がり、募集コストが増える負の連鎖が起きます。つまり「修繕費を削ると空室リスクが増し、さらに収益が悪化する」という構造を理解しなければなりません。
2025年度には、省エネ性能を高める改修に対して最大200万円の税額控除が受けられる国土交通省の既存建築物省エネ化推進事業が継続中です(申請期限は2026年3月)。エコ設備への更新は空室対策にも直結しますので、活用を検討すると資金計画の幅が広がります。
2025年の市場動向と安全な戦略
まず、市場の現状を把握しましょう。不動産経済研究所によると、2025年10月時点で東京23区の新築マンション平均価格は7,580万円と前年比3.2%上昇しています。一方で中古一棟マンションの利回りは緩やかに低下し、都心部で6%前後、郊外で8%台が目安です。価格上昇と利回り低下のダブルパンチで、購入判断はより慎重さが求められます。
安全策としては、①駅徒歩10分以内、②築20年以内、③戸数15〜30戸規模の物件を選ぶと、賃料下落と修繕費のバランスが取りやすい傾向があります。また、地価が上昇しにくいエリアでは出口戦略が難しくなるため、周辺人口の5年後推計を総務省オープンデータで確認する手順を投資フローに組み込みましょう。
賃貸需要を把握するツールとしてポータルサイトの掲載戸数推移をチェックすると、競合物件の増減がつかめます。例えば掲載戸数が3か月連続で10%以上増えたエリアは供給過多の兆候がありますので、購入時期をずらす判断が有効です。
結論として、2025年の一棟買いは「利回りより質」を重視し、収益性の裏付けとなるデータを多面的に確認することが成功の鍵です。焦って買わず、融資情勢やエリア動向を待つ選択肢を持つことが、長期の資産形成につながります。
まとめ
ここまで、一棟買い特有のリスクと回避策を見てきました。オーナーが建物全体を管理する以上、空室・修繕・金利の三大リスクが連鎖する仕組みを理解することが第一歩です。そのうえで、余裕のある自己資金、現実的な返済計画、そして長期修繕積立の3本柱を整えれば、危険は大幅に減らせます。不透明な市場だからこそ、データに基づき冷静に行動する投資家が成果を手にします。この記事を参考に、自分の資金力と目標に合ったマンション投資戦略を組み立ててください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudosankeizai.co.jp
- 国土交通省「長期修繕計画作成ガイドライン」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省「住宅・土地統計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行「金融機関貸出金利動向」 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「既存建築物省エネ化推進事業」 – https://www.mlit.go.jp/kenchiku/energy

