不動産投資信託(REIT)の魅力は、物件を直接持たずに賃料収入のような分配金を受け取れる点にあります。しかし、「REIT いくら 分配金をもらえるのだろう」と疑問に感じている人も多いでしょう。本記事では、分配金の計算方法から期待利回り、さらに2025年度のNISA活用術までをやさしく解説します。読めば、毎月いくら投資すれば目標額に届くのかを自分で試算できるようになり、将来設計の第一歩を踏み出せるはずです。
REITとは何かと分配金のしくみ
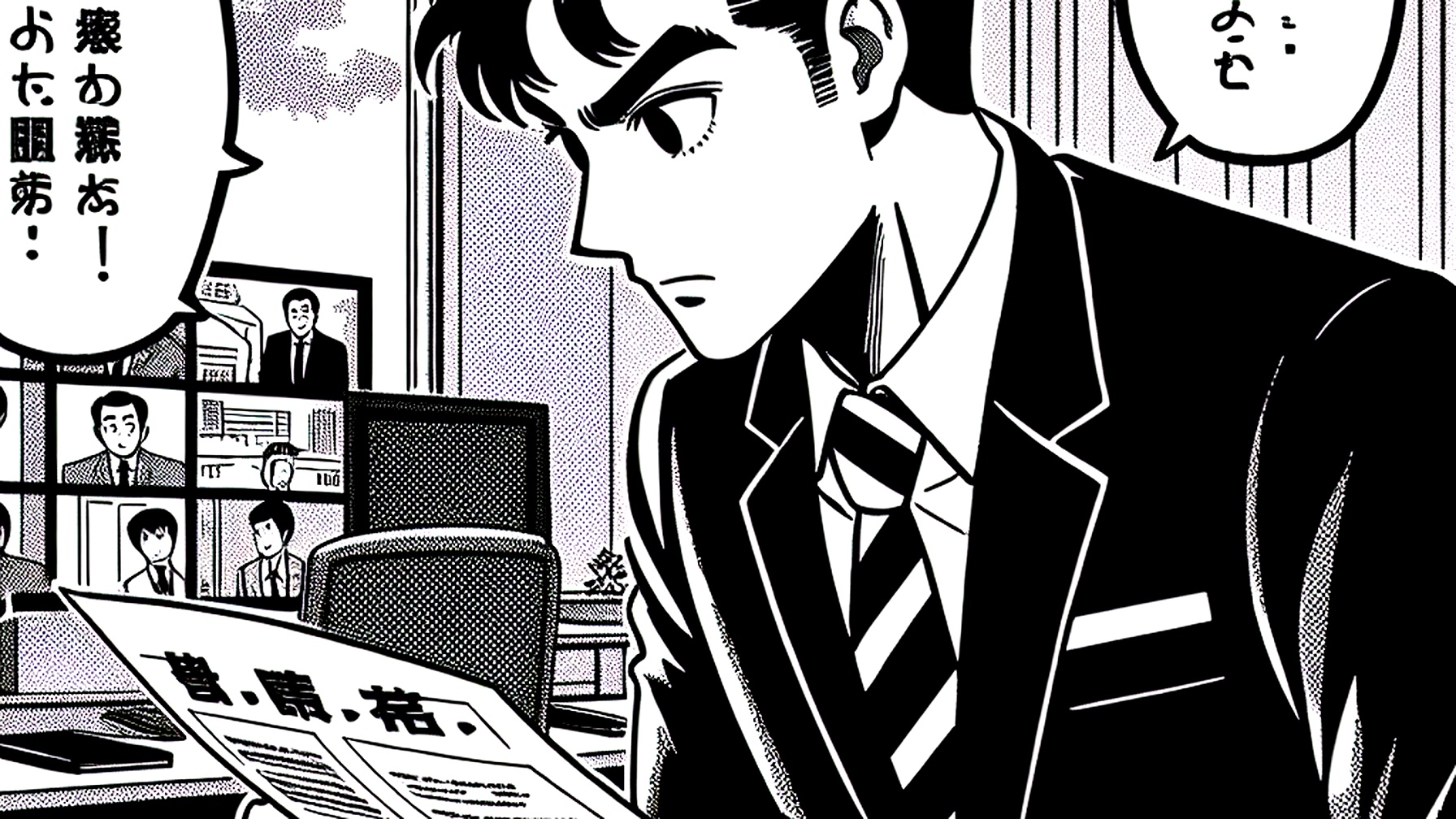
まず押さえておきたいのは、REITが上場株式に似た仕組みでありながら、実物不動産を裏付け資産とする点です。REITはテナントからの賃料や物件売却益を得て、それを原資に年2〜4回分配金を支払います。投資家は一口数万円の投資で複数物件の家賃収入をシェアでき、物件管理の手間もかかりません。
重要なのは、税法上REITが利益の90%以上を分配すれば法人税が軽減されるため、運用会社は積極的に利益を還元する仕組みになっていることです。つまり分配金は株式配当よりも安定的かつ高水準になりやすい傾向があります。また、価格変動は不動産市況と金利動向の影響を受けやすく、株式ほど業績サイクルに左右されにくい点も特徴です。
実は、この安定性こそ初心者にとって大きなメリットです。日銀が公表する東証REIT指数の分配金利回りは、直近10年間で平均3.6%前後を推移しました。低金利が続く中、相対的に魅力的な利回りと言えるでしょう。
分配金は実際いくら受け取れるのか

ポイントは、投資金額と分配金利回り、そして課税後の手取り額です。例えば分配金利回り4%のREITに100万円投資した場合、年間4万円が税引前の分配金になります。
ここで覚えておきたいのが、特定口座の源泉徴収ありを選ぶと、所得税15.315%と住民税5%が自動的に差し引かれる点です。このケースでは約4万円のうち約8千円が税金となり、手取りは3万2千円ほどに減少します。つまり、同じ利回りでも課税方法次第で実際に受け取る金額は変わるわけです。
さらに、分配金を年4回出す銘柄なら1回あたりの入金は8千円程度になります。副収入として実感が湧くのは、月平均1万円を超えてからと言われますが、そのためには税引後12万円、つまり税引前で15万円ほどの分配金が必要です。利回り4%を前提にすると、おおむね375万円の投資が目安となります。もちろん利回りが3%に下がれば必要元本は500万円に増えます。
分配金を左右する三つの指標
実は、分配金を見極める際に注視したい指標は三つあります。まず「NOI利回り」は物件がどれだけ効率的に家賃を生み出しているかを示し、ここが高ければ分配原資が厚いと判断できます。
次に「LTV(Loan To Value)」は総資産に対する借入金の割合で、50〜60%が健全とされます。LTVが高すぎると金利上昇局面で分配金が減りやすく、逆に低すぎると成長余地が小さくなるためバランスが肝心です。一方でLTVが適正でも、分配金の安定度はテナント構成に大きく依存します。
そこで第三の指標「稼働率」が登場します。国土交通省のデータによると、東京オフィスの平均空室率は2025年上期で4%台まで改善しましたが、郊外物流施設はわずか1%前後と極めてタイトです。このように用途や立地で空室リスクは大きく変わるため、稼働率が高い銘柄ほど分配金のブレが抑えられます。つまり、NOI利回り・LTV・稼働率の三つを組み合わせて判断することで、将来の分配金をより精度高く予想できるのです。
分配金を増やす投資戦略
まず、銘柄を分散して景気や金利の変動に強いポートフォリオを組むことが基本です。オフィス系と物流系、さらに住宅系をバランス良く保有すれば、どれか一つのセクターが不調でも分配金全体への影響を軽減できます。
さらに、価格調整局面での買い増しも有効です。東証REIT指数が金利上昇懸念で調整した2023年秋、利回り4.5%を超える銘柄が散見されました。このタイミングで購入し持ち続けた投資家は、2025年現在も高い分配利回りを享受しています。
また、DRIP(分配金再投資)をコツコツ行うことで、複利効果が期待できます。分配金で追加口数を買い付ければ元本が雪だるま式に増え、将来の分配金も拡大するからです。日本の証券会社では自動再投資サービスを提供する例はまだ少数ですが、手動でも年4回続ければ長期的な差は大きくなります。
2025年度NISAと税制のポイント
2024年に刷新された新NISAは2025年度も継続しており、年間360万円までの投資枠において分配金・譲渡益が非課税です。ここで得られるメリットは、課税口座と比べて分配金が約20%増えることに等しいため、配当利回り重視のREITとは極めて相性が良いと言えます。
一方で、非課税期間は恒久化されたものの、売却しても枠が再利用できない点には注意が必要です。長期保有に向かない銘柄を入れてしまうと、枠が固定化されてしまうからです。そのため、LTVや稼働率が安定し、将来の成長施策も明確な大型銘柄を選ぶのが賢明と言えるでしょう。
また、住民税の課税所得が多い人は、特定口座とNISAを組み合わせて使い分けることで手取りを最適化できます。国税庁のシミュレーションでは、課税所得900万円の世帯が利回り4%のREITを300万円分NISAで保有した場合、10年間で税負担を30万円以上削減できる結果が示されています。税制を味方につけることで、実質利回りを大幅に押し上げられるのです。
まとめ
本記事ではREITの分配金が「実際いくら受け取れるのか」を中心に、利回り計算の基本から税制メリットまで解説しました。キーワードはNOI利回り・LTV・稼働率、この三つを見極めつつ、NISAなどの非課税制度を最大限活用することです。目標金額から逆算して必要投資額を把握し、買い増しと再投資を続ければ、分配金は着実に成長します。今日から情報収集を始め、自分のライフプランに合ったREIT投資を実践してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ 東証REIT指数データ – https://www.jpx.co.jp
- 日銀 金融政策レポート – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 NISA制度概要 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 住民税統計データ – https://www.soumu.go.jp

