不動産投資信託(REIT)は、少額から分散投資ができる手軽さで人気を集めています。しかし「REIT 誰が買い、誰が運用し、誰が利益を得るのか」と疑問を抱く初心者も多いでしょう。本記事では運用主体や投資家層の違いを解説し、2025年時点で押さえておきたい制度や税制まで整理します。読み終えれば、REITの舞台裏がクリアになり、資産形成の一歩を安心して踏み出せるはずです。
REITを動かすプレーヤーとは何者か

重要なのは、REITが複数の専門家と投資家によって成り立つ点を理解することです。実際の不動産管理を担う運用会社と、資金を出す投資家がそれぞれ異なる役割を持ちます。
まずREIT本体は「投資法人」と呼ばれ、法律上は株式会社に近い器です。投資法人自体には社員がいないため、運用業務は外部の「資産運用会社」に委託されます。この運用会社は金融商品取引法の登録を受けたプロ集団で、物件の取得や売却、テナント管理の方針を決めます。
一方で、物件の日常管理は「プロパティマネジメント会社」が担当します。テナント募集や修繕計画を実行する存在であり、運用会社とは契約で結ばれます。さらに会計監査人や資産保管会社がガバナンスを支え、投資法人の資産を客観的にチェックします。つまりREITは複数の専門家がレイヤー構造で関わり、個人投資家は上場株式と同じ感覚で証券会社を通じて取得できるのです。
個人投資家は誰がどこで買っているのか
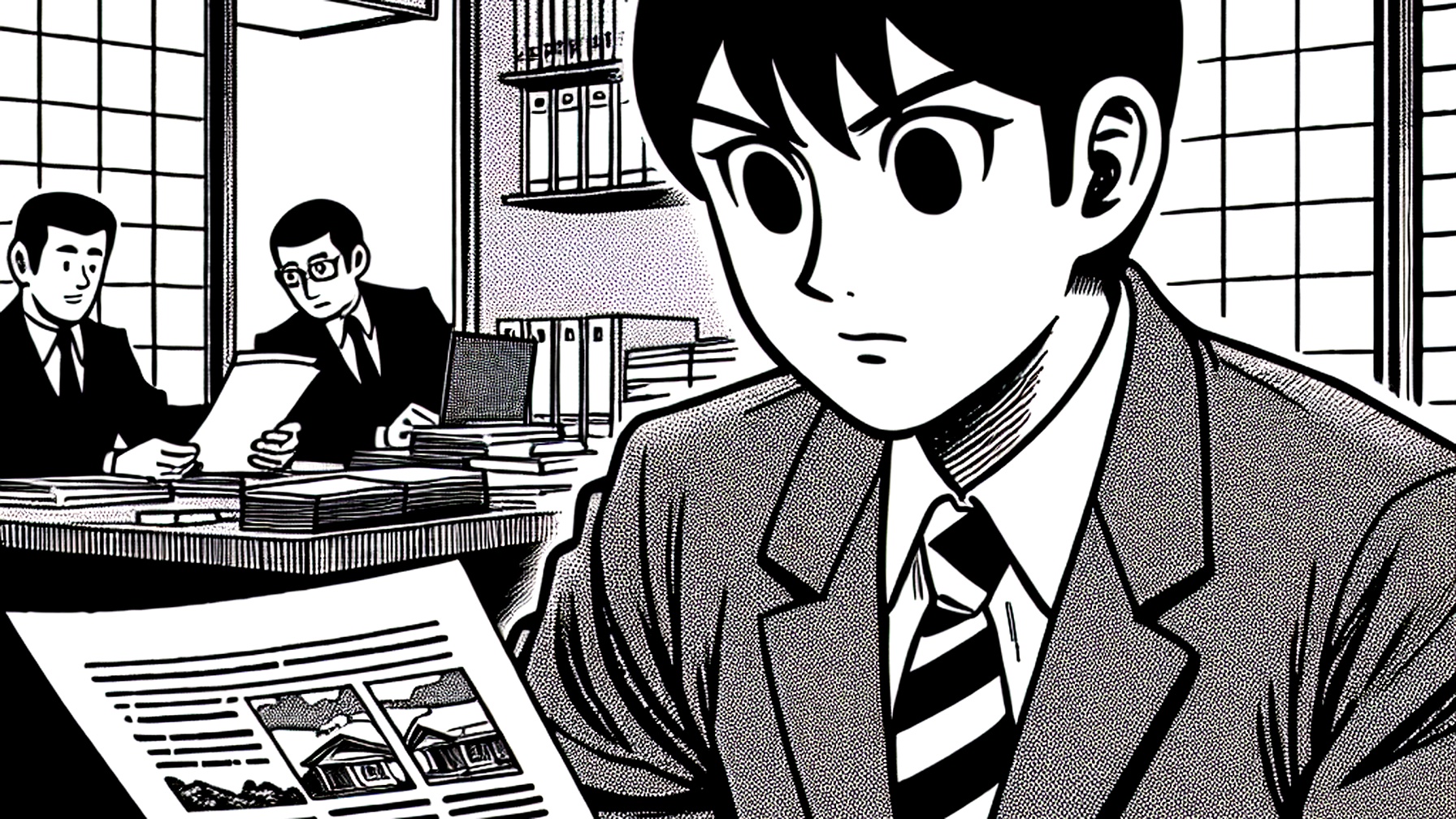
まず押さえておきたいのは、REITの投資口は東京証券取引所の「J-REIT市場」で売買される点です。金融庁の2024年度統計によると、J-REITの売買代金の約四割を個人投資家が占めています。
個人投資家の多くはネット証券を利用し、株式と同じ画面で注文を出しています。最低投資額は銘柄によって異なりますが、2025年10月時点の平均購入単価は一口当たり12万円前後です。これにより区分マンションを買うよりはるかに低コストで不動産収益を得られます。
ただし、流動性にはばらつきがあります。出来高が少ない銘柄は売却時に価格が大きく動くリスクがあるため、東証が公表する「日次売買代金ランキング」を参考に流動性の高い銘柄を選ぶと安心です。またNISA口座を利用すれば分配金にかかる税率20.315%が非課税になるため、2024年に恒久化された新NISAの年間投資枠を活用する人も増えています。
利益は誰がどのように受け取るのか
ポイントは、REITが「分配金」によって投資家へ利益を戻す仕組みです。投資法人は不動産から得た賃料や売却益を合算し、原則として毎期の利益の九割超を分配金として支払います。
この高い分配率は「投資信託及び投資法人に関する法律」で定められた優遇税制が背景にあります。投資法人が九割超を分配すると、法人税が実質的に課税されないため、課税コストを投資家に転嫁せずに済むのです。言い換えると、税務上のメリットが高い分配金の原資を厚くしていると理解できます。
個人投資家は年二回の分配金を受け取り、証券会社から交付される「支払通知書」で確認します。分配金の平均利回りは2025年10月時点で3.7%前後ですが、オフィス系や物流系など業種ごとにばらつきがあります。したがってポートフォリオを組む際は、利回りだけでなく物件タイプと地域分散を意識することが長期的な安定収益につながります。
法人・機関投資家はどんな役割を果たすのか
実は、REIT市場の価格安定を支えているのは保険会社や年金基金などの機関投資家です。日本取引所グループの公表データでは、2025年の保有比率は機関投資家がおよそ五割を占めています。
機関投資家は巨額資金を運用するため、住宅ローン金利や空室率の長期予測を基に銘柄を選定します。さらに、ESG(環境・社会・ガバナンス)を重視する傾向が年々強まっており、施設の省エネ性能やテナントの働き方改革を評価指標に組み込んでいます。これにより上場REIT各社も環境性能を示す「GRESB」という国際評価で高得点を取るための改修を進めています。
一方で、機関投資家はマーケットが急落したときに買い支える存在にもなります。ボラティリティが低下しやすいため、個人投資家は長期保有の安心感を得やすいのが特徴です。ただし、海外ファンドの資金フロー次第で短期的に価格が大きく動く局面もあるため、日銀や米FRBの金融政策をチェックし、長期金利の方向性を掴む習慣が大切です。
2025年度の制度と税制のポイント
まず2025年度もNISAおよびiDeCoの併用が可能で、REITを含む上場投資信託の分配金はNISAなら非課税、iDeCoなら課税繰り延べが適用されます。年間投資枠360万円のうち成長投資枠にREITを組み込むことで、賃料収入相当のキャッシュフローを非課税で受け取れるメリットがあります。
また、2025年度税制改正で「REIT投資口の相続時評価額の見直し」は行われませんでした。相続税評価は市場価格の八割相当が目安のままであるため、現金よりも評価額を抑えやすい点は変わりません。将来的に資産承継を考える人にとっては、依然として有効な選択肢と言えるでしょう。
さらに、上場インフラファンドとREITの情報開示ルールが一本化され、2025年4月からESG関連情報の記載が義務化されています。この改正により、投資家は環境性能やテナント満足度を比較しやすくなりました。つまり、数字だけでなく非財務情報にも目を向けることで、銘柄選定の精度が一段と高まります。
まとめ
REITは「誰が運用し、誰が支えるか」を把握することで、仕組みへの理解が深まりリスク管理も容易になります。運用会社や管理会社が専門性を発揮し、機関投資家が市場のクッションとなるため、個人でも少額から安定した賃料収入を享受できる仕組みが整っています。2025年度もNISA非課税枠やESG情報開示といった追い風が続くため、まずは流動性の高い銘柄から少額で試し、分配金と値動きのバランスを肌で感じてみましょう。資産形成の選択肢としてREITを賢く活用することが、将来の安心につながるはずです。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp/
- 国土交通省 不動産証券化市場統計 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省 統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp/
- GRESB公式サイト – https://gresb.com/

