投資用マンションやアパートを検討するとき、多くの初心者は「家賃が高ければ利益が出るだろう」と直感で判断しがちです。しかし実際には、購入価格や融資条件だけでなく、空室率、修繕費、税金といった多面的な要素が収益に影響します。本記事では、2025年9月時点で有効な制度に触れながら、収益物件の収支計算を基礎から解説します。読み終えるころには、手元の電卓と公開情報だけで、おおまかなキャッシュフローを自力で組めるようになるはずです。
収支計算の全体像をつかむ
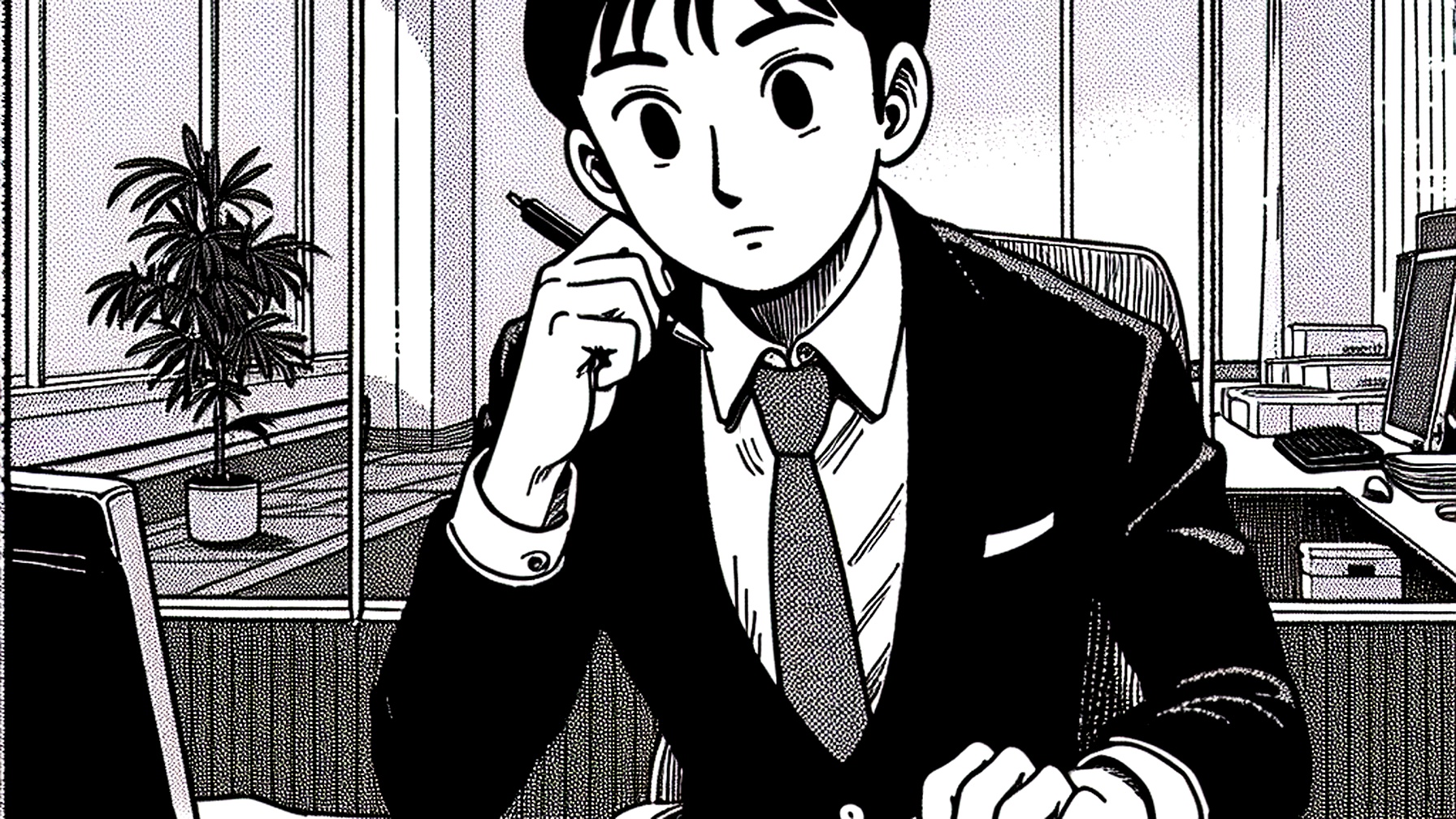
まず押さえておきたいのは、収支計算が「年間家賃収入-年間支出」というシンプルな式に見えて、実は細かな内訳の積み重ねだという点です。家賃収入には空室期間を織り込み、支出には管理費や保険料などの固定費と、修繕費のような変動費を含めます。国土交通省の2024年度空家率データによると、都市部ワンルームの平均空室率は約10%です。つまり想定家賃が月8万円でも、年間では約86万円しか入らない可能性があります。こうした現実的な前提を置くことが、堅実な投資への第一歩です。
次に総投資額を算出します。物件価格のほか、仲介手数料や登記費用、不動産取得税など諸費用が7~9%程度発生するのが一般的です。たとえば3,000万円の中古マンションを現金購入する場合、諸費用だけで約240万円が必要になります。融資を使うときは、ローン保証料や団体信用生命保険料も加算され、金利が上乗せされるケースもあるため要注意です。
さらにキャッシュフロー計算表を作成し、表の右端に「自己資金回収年数」を入れると効果的です。自己資金500万円を投入して年間CF(キャッシュフロー)100万円なら、単純計算で5年で回収できます。一方、家賃下落や金利上昇のシナリオを設定し、同じ表を再計算すればリスク耐性を客観視できます。こうした多角的な試算こそが、長期で安定した不動産投資のカギになります。
キャッシュフローを読み解くコツ
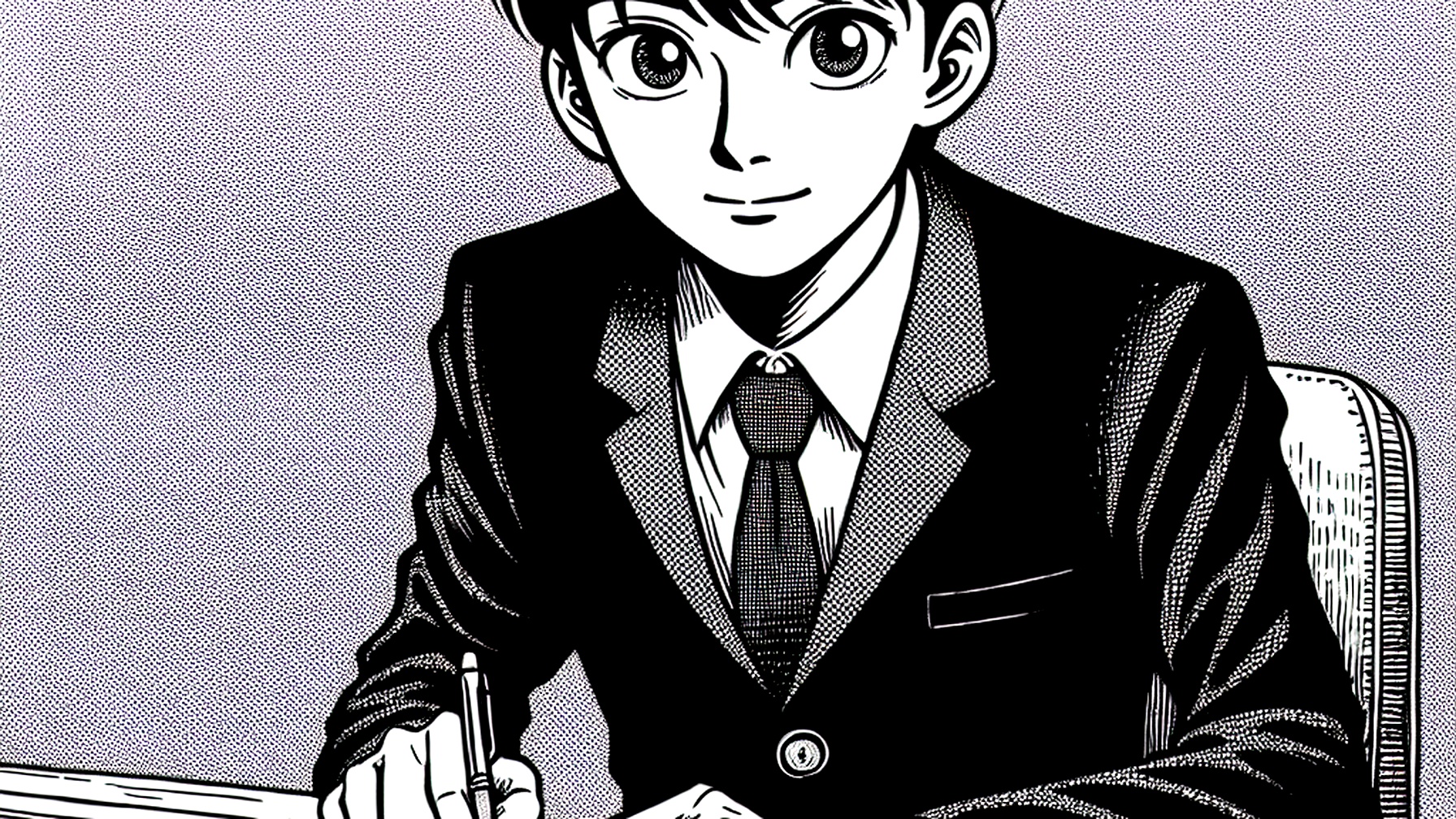
ポイントは、表面利回りと実質利回りを混同しないことです。表面利回りは購入価格と満室想定家賃から算出する一方、実質利回りは空室率や諸費用を差し引いた後の指標です。日本銀行の「貸家業向け融資平均金利」(2025年7月時点)では、変動金利タイプがおおむね年2.1%前後で推移しています。金利が1%変動するだけで、35年ローンの場合は総返済額が数百万円変わるため、金利も実質利回りに大きな影響を与えます。
実はキャッシュフロー計算では「見えない支出」を織り込むかどうかで精度が大きく変わります。その代表例が原状回復費です。国交省の資料ではワンルームの平均原状回復費が約23万円と報告されており、入退去のたびに発生します。退去率を年15%と想定するなら、毎年約3.5万円を引き当てる必要があります。こうした積み上げが収支をリアルにします。
また、キャッシュフローを月単位だけでなく年単位で管理すると、季節変動の影響を平準化できます。たとえば繁忙期の3月が満室でも、閑散期の11月に空室が出れば年間では収益が削られます。四半期ごとに計画と実績を比較することで、管理会社への改善要望や賃料調整をタイムリーに行えるようになります。
ランニングコストを見落とさない
重要なのは、購入後に継続的に発生するコストを細かく把握することです。管理費・修繕積立金は、マンションなら月額200~300円/㎡が目安です。例えば30㎡の区分所有なら月6,000~9,000円、年間では最大108,000円が固定費として消えます。火災保険料は2025年度も国土交通省の標準料率見直しが続いており、築年数が古いほど割高になる傾向があります。
次に計上すべきは大規模修繕費です。築20年を過ぎると外壁や設備交換に数百万円単位の費用がかかることも珍しくありません。投資家が区分所有者一人の場合でも、修繕積立金の不足分を一括徴収されるリスクはゼロではないため、長期保有前提ならシミュレーションに加えましょう。
一方で、ランニングコストを抑える施策も存在します。2025年度の国税庁通達に基づき、耐用年数超の中古木造アパートでは4年での加速償却が認められています。これにより初年度の税負担を軽減でき、キャッシュフローを押し上げる効果があります。ただし税効果で赤字を先送りしただけにならないよう、減価償却後のCFも必ず試算しておくことが大切です。
税金と減価償却のインパクト
まず押さえておきたいのは、税金がキャッシュフローを左右する最大の変動要因である点です。不動産所得の課税所得は「総収入-必要経費-青色申告特別控除」で算出されます。青色申告で65万円控除を受けると、個人の所得税率が20%でも約13万円の節税につながります。
また、減価償却は現金支出を伴わない経費として貴重です。例えば築30年の木造アパート(耐用年数22年超)を2,000万円で取得すると、4年間で毎年500万円を償却できます。所得税率が30%なら、年間150万円の税負担が減る計算です。この差額がキャッシュフローを大きく改善し、次の投資資金の原資になります。
一方で、償却期間終了後は毎年の税額が急増する「デッドクロス」に注意が必要です。デッドクロスを回避するには、あらかじめ償却終了年に向けて繰上返済や物件売却の出口戦略を組み込む方法があります。出口戦略を入れた試算表を作ることで、最終的な手残りがどの水準で落ち着くか、視覚的に把握できます。
なお、2025年度の不動産取得税軽減措置は、床面積が50〜240㎡の住宅用区分に限り存続しています。投資用区分マンションでは対象外になるケースが多いので、購入前に県税事務所へ確認することが賢明です。制度を正しく理解し、過度な税制メリットを期待しすぎないことがリスク管理につながります。
シミュレーションとリスク管理の実践
実は、収支計算の最終チェックは「複数シナリオの検証」が肝心です。まず表面利回り8%・金利2%・空室率10%というベースケースを作り、次に金利3%・空室率20%のストレスケースを設定します。この二つのシナリオ差がCFでマイナスに転じないか確認することで、耐久力のある投資かどうか判定できます。
さらに、ストレスケースでCFがマイナス30万円まで許容できるのか、自己資金や副収入とのバランスで検討します。総務省家計調査(2024年)のデータによれば、世帯平均の貯蓄率は年7.5%です。生活費とローン返済が競合しないよう、貯蓄率が下がりすぎない範囲で投資額を調整すると、家計全体のリスクを抑えられます。
最後に、管理会社の選定もリスク管理の一部です。国土交通省の「賃貸住宅管理業者登録制度」は2021年に始まり、2025年9月時点で登録業者は約10,800社になっています。登録業者から選ぶことで、家賃送金遅延や退去時トラブルのリスクを減らせます。こうした周辺リスクも収支計算に内包して考えると、数字の裏にある実務が見えてきます。
まとめ
本記事では、収益物件の収支計算を「収入の現実的見積もり」「支出の網羅」「税金対策」「シミュレーション」の四つの視点で解説しました。重要なのは、表面利回りだけでなく実質利回りを把握し、金利変動や空室リスクまで含めてキャッシュフローを組むことです。また、減価償却や青色申告など2025年度も有効な制度を活用しつつ、デッドクロスに備えた出口戦略を早期に描くことで、長期的な資産形成が可能になります。まずは一件の物件を仮定し、本記事の手順で試算表を作成してみてください。数字がクリアになるほど、次の行動が具体的に見えてくるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数・空家率統計 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 貸出約定平均金利等 2025年7月 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 青色申告特別控除の手引き(2025年度) – https://www.nta.go.jp
- 総務省 家計調査報告 2024年平均結果 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅管理業者登録制度 公表一覧(2025年9月) – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo

