不動産投資は堅実な資産形成の手段として注目されていますが、「空室リスクが怖い」「修繕費が読めない」といった不安も根強いです。特に初心者はデメリットばかりが目につき、最初の一歩を踏み出せないことが少なくありません。本記事では、そうした悩みに寄り添いながら、不動産投資の代表的なデメリットを整理し、長期投資という視点でどのように克服できるかを具体的に解説します。読み終えるころには、リスクを踏まえた上で着実に行動できる指針が手に入るはずです。
不動産投資のデメリットを正しく把握する
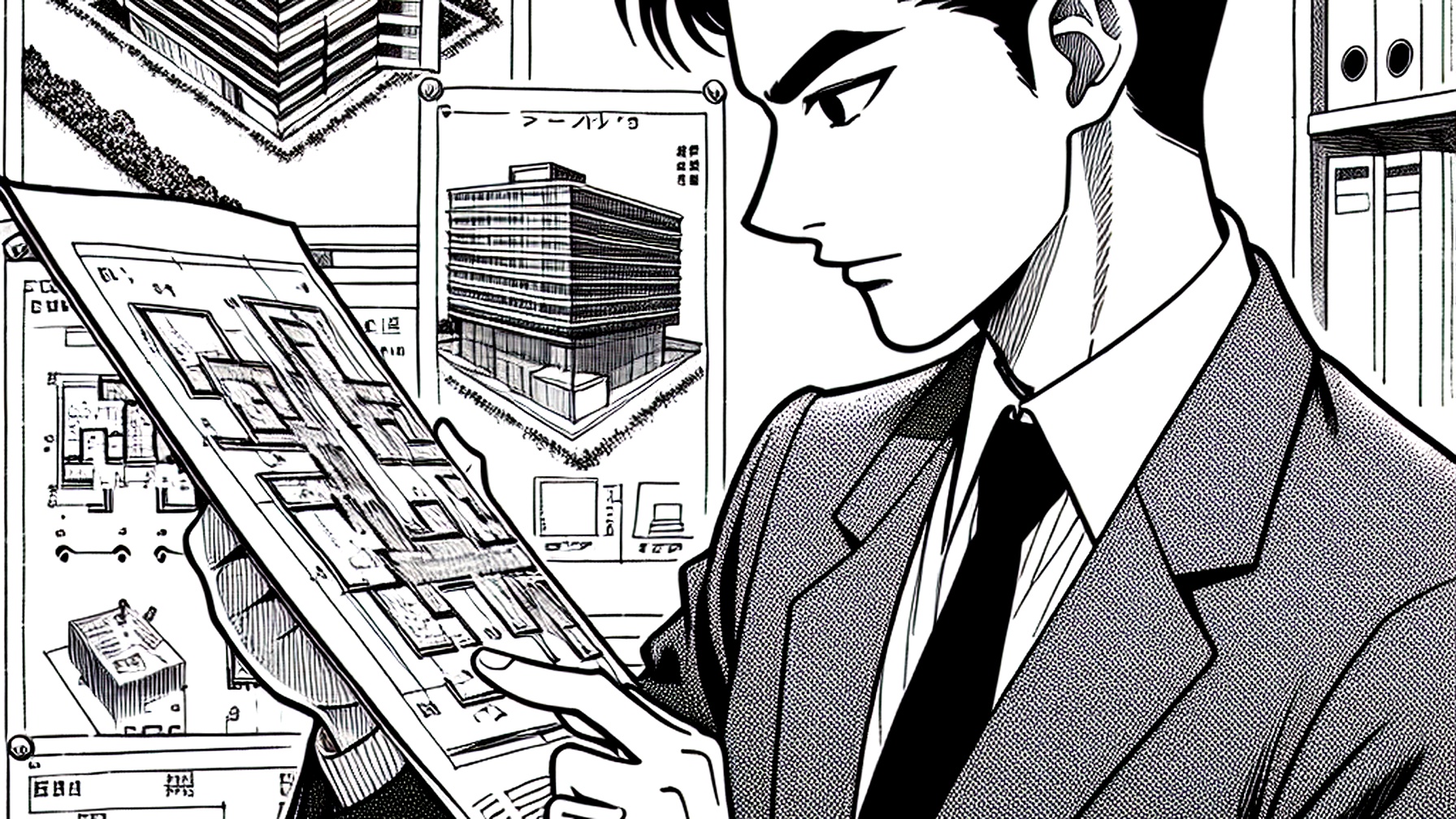
まず押さえておきたいのは、デメリットを曖昧にせず具体化することです。リスクの正体を数値で捉えれば、対策も立てやすくなります。
最も知られているのが空室リスクです。国土交通省の「住宅市場動向調査(2024年)」によると、全国平均の空室率は13%前後で推移しています。ただし都市部と地方では乖離が大きく、東京都区部のワンルーム空室率は7%台にとどまるのに対し、人口減少が進む地方圏では20%を超える地域もあります。
次に考慮すべきは修繕費です。2025年版「建物維持保全ガイドライン」によれば、RC造(鉄筋コンクリート)のマンションで20年間に必要な修繕費は、延床1㎡あたり平均1.5万円とされています。70㎡の区分所有なら210万円が目安となり、計画的に積み立てていないと突発費用が家計を圧迫します。
さらに流動性の低さもデメリットです。不動産は株式のように即日売却できず、成約まで平均3〜6か月を要します。急な資金需要が生じたときの出口戦略を明確にしておかないと、資金繰りに行き詰まる恐れがあります。
長期投資がもたらす安定効果とは
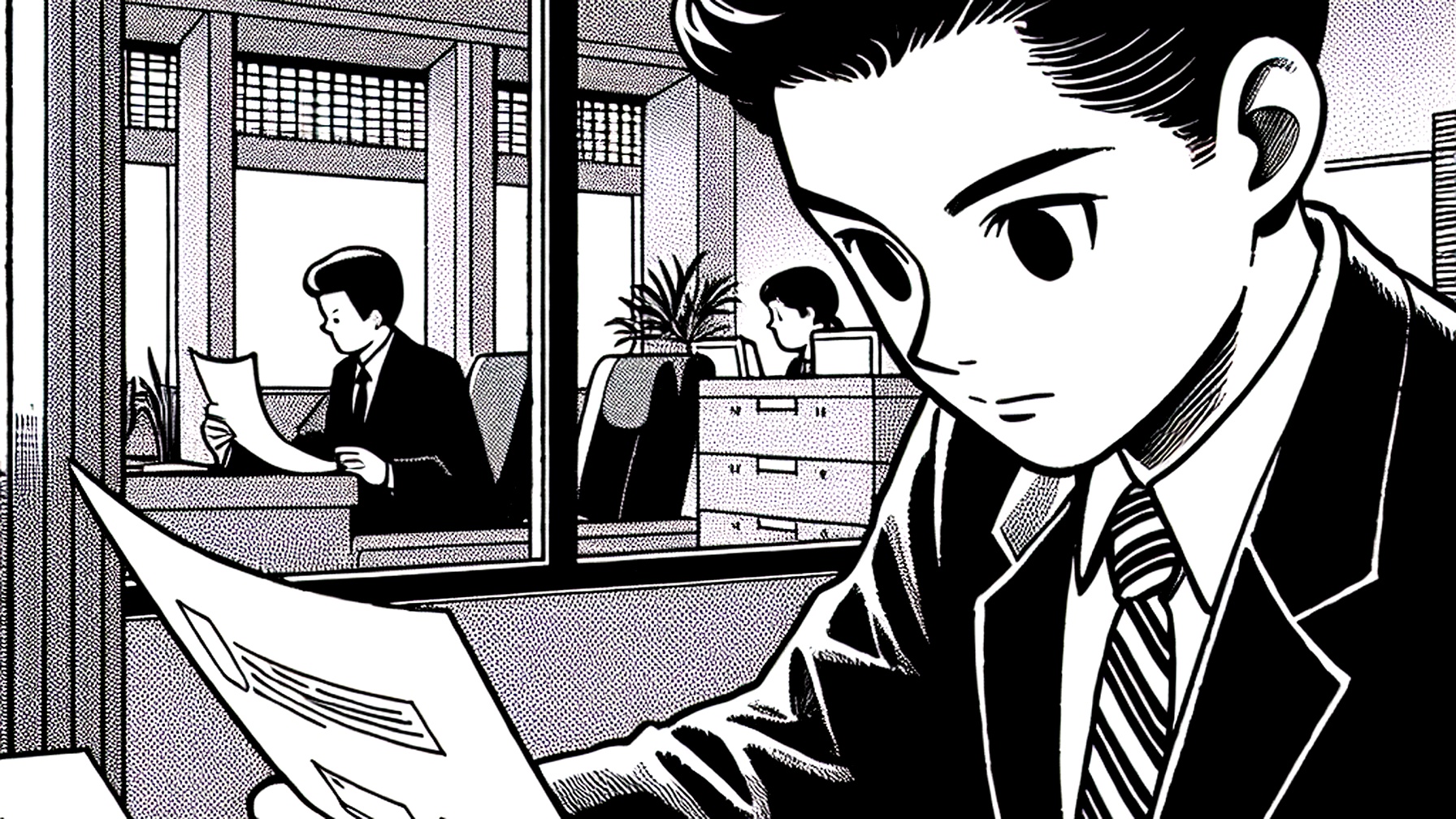
重要なのは、デメリットを時間軸でならすという発想です。長期投資にすることでリスクを分散し、収益を平準化できます。
家賃収入の推移を30年スパンでみると、短期的な空室による損失は平均家賃に吸収される傾向があります。都市再生機構の「民間賃貸住宅家賃動向(2025年上期)」では、首都圏の平均家賃は過去10年間で年率0.8%ずつ上昇しており、この緩やかな上昇が長期保有の安定剤になります。
また、減価償却費による節税メリットは保有期間が長いほど恩恵が続きます。木造アパートの耐用年数22年に対し、RCマンションは47年と長く、長期投資戦略と親和性が高いです。長期保有なら売却益よりインカムゲイン(家賃収入)を重視しやすく、相場変動の影響を受けにくい点も安心材料になります。
長期投資は複利効果も見逃せません。10年間で得たキャッシュフローを再投資すれば、20年後には複数物件に分散でき、単一物件のリスクを薄めることが可能です。つまり、時間を味方につければ、不動産投資 デメリット 長期投資 具体的な克服策が現実味を帯びてきます。
デメリットを軽減する具体的な戦略
ポイントは、リスクを数値化し対策を仕組み化することです。ここからは実務で役立つ具体策を紹介します。
まず空室対策ですが、家賃設定を相場の95%に抑えるだけで入居決定までの平均日数が20%短縮するという管理会社の内部データがあります。さらに内装のカラーコーディネートを明るいグレージュに統一すると、内見後の申込率が1.3倍になるとの報告もあり、コストを抑えながら効果を上げやすい施策です。
修繕費については、長期修繕計画を初年度に作成し、毎月家賃収入の5〜10%を積み立てる方法が推奨されます。例えば家賃月8万円の区分所有なら、月4000〜8000円を別口座にプールするだけで20年後の大規模修繕費をほぼ賄えます。自動積立設定にすることで心理的な負担を軽減できるのが利点です。
流動性リスクに対しては、出口価格を保守的に査定し、LTV(Loan to Value:物件価格に対する借入割合)を70%以下に抑えます。こうすることで売却時の残債割れリスクを軽減し、賃料下落局面でも柔軟に身動きが取れます。平均金利が上昇基調にある2025年は、固定金利で10年以上の長期ローンを組み、キャッシュフローの予見性を高めておくと安心です。
ケーススタディで学ぶリスク管理
実は、成功している投資家ほど失敗事例から多くを学んでいます。ここでは2つの事例を通じて、リスク管理の実践方法を確認します。
事例Aは、地方中核市の築25年RCマンションを取得したケースです。購入時の利回りは9%と高水準でしたが、エリア人口が年1%減少しており、5年目に空室率が30%まで悪化しました。オーナーは家賃を10%下げ、同時に宅配ボックスを設置して若年層のニーズを掴んだ結果、3年で空室率を15%にまで改善し、総収益は当初計画の92%で着地しました。
事例Bは、都心ワンルームを2戸保有する会社員のケースです。ローン残高に対して自己資金が薄く、金利上昇局面でキャッシュフローが赤字に転落しました。しかし早期に一戸を売却し借入を半減させたことで、残り一戸の家賃収入が毎月2万円の黒字に戻り、資金繰りが安定しました。このように、損切りを含む柔軟な判断が長期投資を継続させる鍵になります。
両事例に共通するのは、デメリットを早期に数値で把握し、対策を段階的に実行した点です。机上のシミュレーションと実際の運営にはギャップが生じますが、PDCAを繰り返すことでリスクは抑え込めるとわかります。
2025年度の制度を活用した補完策
基本的に、制度や税制優遇を活用することでデメリットを補完できます。2025年度も利用可能な制度を確認しておきましょう。
まず所得税の損益通算は引き続き有効です。赤字が生じた場合、給与所得と合算できるため、節税により実質的なキャッシュフローを改善できます。ただし新築木造アパートの過度な節税スキームは税務調査が厳格化しているため、健全な収支計画を立てることが前提になります。
小規模企業共済等掛金控除は個人事業として不動産所得を申告する場合に活用可能で、年間84万円まで所得控除を受けられます。将来の退去や大規模修繕に備える資金として積み立てながら節税効果を得られる点が魅力です。
さらに、2025年度の「賃貸住宅省エネ性能向上補助金」は、既存賃貸の断熱改修や高効率給湯器導入に対し、費用の最大1/2、上限120万円の補助が受けられます。省エネ性能を高めれば光熱費を抑えたい入居者の支持を得やすく、空室リスク低減と家賃維持に直結します。期限は2026年2月申請分までなので、早めの計画が必要です。
まとめ
本記事では、不動産投資の代表的なデメリットを空室・修繕・流動性の三つに整理し、長期投資の視点から具体的な克服法を示しました。空室率や修繕費を数字でつかみ、家賃設定や積立ルールを仕組み化すれば、リスクは大幅に低減できます。また、制度活用や出口戦略の準備を怠らなければ、市場環境が変化しても柔軟に対応できます。不安を行動に変える第一歩として、この記事で得た知識をもとに自分の投資計画を練り直し、信頼できる専門家に相談するところから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024年版 – https://www.mlit.go.jp/statistics/details/house_market.html
- 国土交通省 建物維持保全ガイドライン2025 – https://www.mlit.go.jp/maintenance/guide2025.html
- 都市再生機構 民間賃貸住宅家賃動向2025上期 – https://www.ur-net.go.jp/research/rent2025.html
- 総務省 人口推計2025年4月確定値 – https://www.stat.go.jp/data/jinsui/2025.html
- 中小企業庁 小規模企業共済制度パンフレット2025 – https://www.chusho.meti.go.jp/kyosai/kyosai2025.pdf

