会社勤めを続けながらアパート経営に挑戦したいと考えても、「空室が埋まらなかったら返済はどうなるのか」「本業と両立できるのか」と不安は尽きません。しかし入居者募集の仕組みを理解し、数字に基づいた計画を立てれば、会社員でも安定した副収入を得ることは十分可能です。本記事では最新の空室率データや実務経験から得たノウハウを交え、物件選びから入居者募集、資金管理までを体系的に解説します。読み終えた頃には、自分に合った運営戦略を描けるようになるはずです。
会社員がアパート経営を始める前に押さえる基本
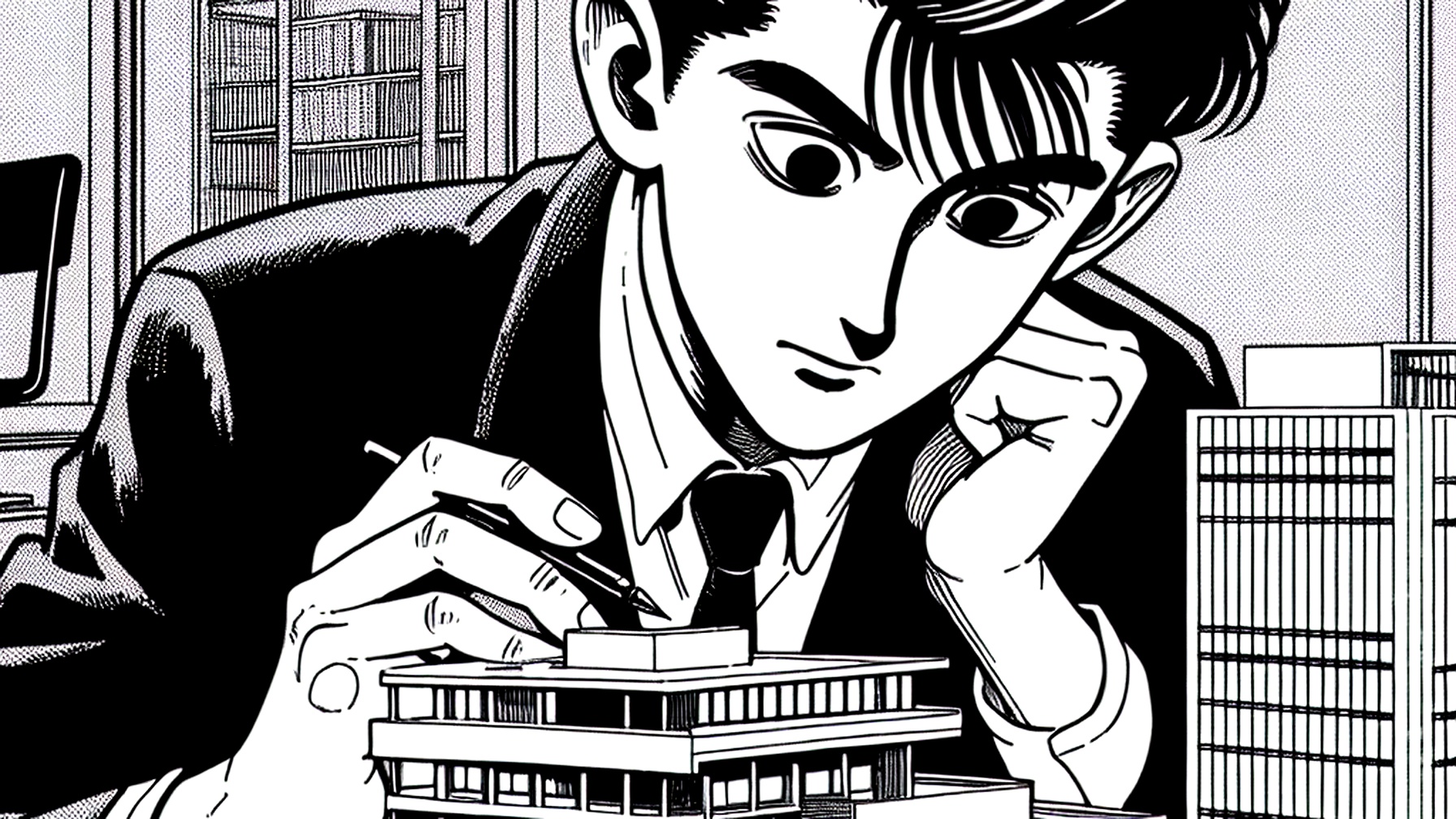
まず押さえておきたいのは、会社員ならではの強みと制約を正しく認識することです。時間的制約を補う仕組みづくりが収益を左右します。
会社員の最大の強みは、安定した給与収入による高い信用力です。金融機関は返済原資の安定を重視するため、勤続年数が5年以上であれば金利を0.2〜0.3%下げて提案されるケースも珍しくありません。一方で平日は勤務時間が固定されるため、突発的なトラブル対応は管理会社へ委託する前提で資金計画を組む必要があります。
初期費用には物件価格の20〜30%を自己資金として準備し、さらに修繕や空室に備えて家賃の6か月分を運転資金として確保すると安心です。日本銀行の2025年4月マネーサプライ統計によると、住宅ローン平均金利は変動型で年1.2%前後を維持しています。変動金利を選ぶ場合でも、長期的な金利上昇リスクを想定し、返済比率を手取り収入の30%以内に抑えることが基本となります。
加えて不動産取得税や固定資産税などのランニングコストを試算し、キャッシュフロー表に織り込むことが必須です。税金は購入翌年度にまとめて請求されるため、想定外の出費に慌てないよう計画段階で資金を取り置きましょう。こうした準備が、後の入居者募集活動に集中できる環境を整えます。
入居者のニーズを見抜く市場調査の進め方
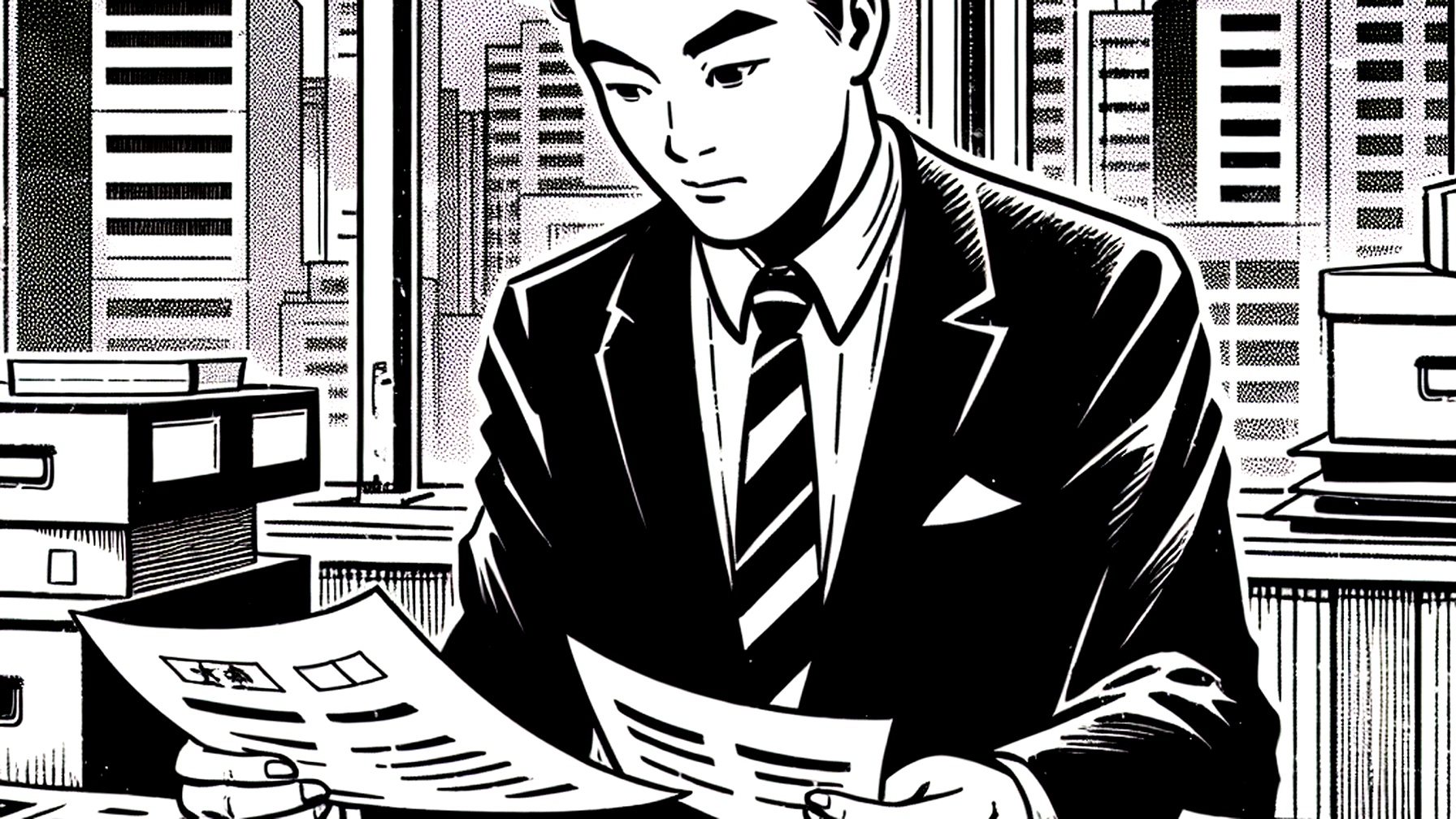
ポイントは、定量データと現地感覚の両面から需要を読み解くことです。数字だけでは掴めない生活動線を把握すると、長期入居につながります。
国土交通省住宅統計が2025年8月に公表した全国アパート空室率は21.2%で、前年より0.3ポイント改善しました。ただし都市部と地方では差が大きく、東京都23区の空室率は14%台、地方中核市では25%を超える地域もあります。まずは物件所在地の市区町村が公開する人口動態、将来推計、企業立地動向を確認し、世帯数が増えているエリアを優先しましょう。
次に現地調査です。平日夜と週末昼の両方に足を運び、駅からの経路、街灯の明るさ、コンビニや病院までの距離を体感してください。入居希望者は通勤や子育ての利便性を重視するため、徒歩10分圏内に生活インフラが揃うかどうかが成約に直結します。さらに不動産仲介店を3店舗訪問し、客層と成約賃料の実例を聞き取ることで、募集賃料の上限下限を具体化できます。
最後に競合物件の設備を確認し、自物件との差を一覧化します。近年はインターネット無料や宅配ボックスが標準化しつつあり、初期投資を掛けずに導入できるサービス型Wi-Fiや簡易型ロッカーで差別化する手法が浸透しています。需要データと現地で得た肌感覚を統合し、「誰に」「いくらで」「何を提供するか」を明文化することで、次章の募集戦略がぶれなくなります。
効果的な入居者募集戦略と広告手法
重要なのは、ターゲット層に合わせた媒体選定と情報設計を一貫させることです。単に広告量を増やすだけではコストが膨らみます。
まずオンライン集客では、不動産ポータルサイト上位5媒体への同時掲載を基本とし、写真は昼間と夜間を計10枚以上用意します。SUUMOが2025年2月に行ったユーザー調査では、内見予約につながる決め手として「写真の枚数・明るさ」が64%を占めました。またキャッチコピーには「駅徒歩5分」「独立洗面台」のように検索フィルターで絞られるキーワードを先頭に置くと閲覧数が増えます。
次にオフライン施策です。会社員を主ターゲットにする場合、最寄り駅からオフィス街へ向かう動線上の仲介店へ物件資料を手渡しし、店頭POPに掲載してもらう交渉が有効です。仲介担当者評価制度を導入している管理会社を選べば、案内件数に応じたインセンティブが付与されるため、優先的に紹介してもらいやすくなります。
またIT重説(重要事項説明のオンライン化)が本格運用されて2年が経過し、遠方からの申込が増えました。VR内見動画を用意し、申込から契約まで非対面で完結できるフローを整えると、転勤族や地方の単身赴任者といった会社員層を取り込めます。募集開始から30日で成約に至らない場合は、賃料を3%下げる、フリーレントを1か月付与するなど、事前に定めた条件変更ルールを実行し、長期空室化を防ぎましょう。
会社員ならではの資金計画とリスク管理
実は本業の収入が安定している会社員だからこそ、攻めと守りのバランスを取った資金計画が求められます。返済余力を生かしつつ、突発コストに耐える仕組みを持つことが鍵です。
まずキャッシュフロー表には、満室想定家賃収入からローン返済、管理費、固定資産税、火災保険、修繕積立を差し引いた手残り額を月単位で記載します。年間手残り額が年間返済額の30%を下回る場合、物件条件または融資条件の見直しが必要です。
次にリスクシナリオ分析です。空室率20%、金利上昇2%、賃料下落5%という三つの悪条件を同時に設定し、赤字が出ないかを確認します。赤字が生じる場合でも、給与収入と合わせた年間収支がプラスであれば経営は継続可能です。ただし赤字が2期連続する場合は、売却価格を査定し、早期出口も選択肢に含めましょう。
さらに2025年度税制改正で、小規模不動産オーナー向けの青色申告特別控除65万円が継続適用されています。帳簿をクラウド会計で毎月更新し、経費計上を漏らさないことが節税につながります。また家賃保証会社に加入する際は破綻リスクを考慮し、保証債務の上限と支払い時期を必ず確認してください。こうした多層的なリスク管理が、本業への影響を最小限に抑えます。
管理会社との協働で長期安定を築くコツ
まず押さえておきたいのは、管理会社を「外注先」ではなく「共同経営者」と捉える姿勢です。信頼関係が入居者満足度を左右します。
管理委託契約を結ぶ際は、入居者募集力、家賃集金代行実績、24時間対応体制の三点を比較しましょう。月額管理料は家賃の3〜5%が相場ですが、単に低コストを選ぶと広告料や修繕費が割高になることもあります。年間総コストで評価すると、結果的に収益が高くなるケースが多いです。
定期的な情報共有も欠かせません。毎月の空室率、問い合わせ件数、苦情内容をオンラインで確認できるシステムを導入すると、会社員でも昼休みや帰宅後に状況を把握できます。私は担当者と月1回オンライン面談を行い、改善策を共同で策定しています。例えば入居者アンケートでWi-Fi速度への不満が出た際は、即座に回線増設を決定し、退去抑制に成功しました。
また管理会社の担当者を物件に招き、オーナー自ら改善の要望を聞く「逆ヒアリング」を行うと、現場のモチベーションが上がります。国交省の2025年管理業務実態調査では、オーナーと月1回以上コミュニケーションを取る担当者の物件は、空室期間が平均12日短縮するという結果が出ています。協働体制を強化することで、アパート経営の安定度は確実に高まります。
まとめ
本記事では、会社員がアパート経営で入居者募集を成功させるための流れを、資金計画、市場調査、広告戦略、リスク管理、管理会社との協働の五つの観点から整理しました。重要なのは、安定した給与収入という強みを生かして慎重に数字を積み上げ、実地調査とオンライン施策を組み合わせてターゲットを絞り込むことです。ぜひ今日からキャッシュフロー表を作成し、管理会社や仲介店とのネットワークを広げる一歩を踏み出してください。継続的な改善を続ければ、本業と両立しながら安定収益を得る未来は必ず実現します。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報版 – https://www.mlit.go.jp/
- 総務省統計局 人口推計 2025年7月分 – https://www.stat.go.jp/
- 日本銀行 マネーサプライ統計 2025年4月 – https://www.boj.or.jp/
- SUUMO 住み替えトレンド2025 – https://suumo.jp/
- 国税庁 タックスアンサー 不動産所得と青色申告 2025年度 – https://www.nta.go.jp/

