高収入会社員や個人事業主の方から「マンション投資で税金を大幅に減らせると聞いたけれど、本当に得なのか」と相談を受ける機会が増えました。確かに家賃収入を得ながら所得税や住民税を抑えられれば理想的です。しかし仕組みを誤解したまま契約すると、期待したほどの節税にならず、ローン返済だけが残る場合もあります。この記事では2025年10月時点の税制を踏まえ、マンション投資の節税効果の「本当」と「誤解」を整理し、損をしないための判断基準を解説します。
節税効果が生まれる仕組みを押さえよう
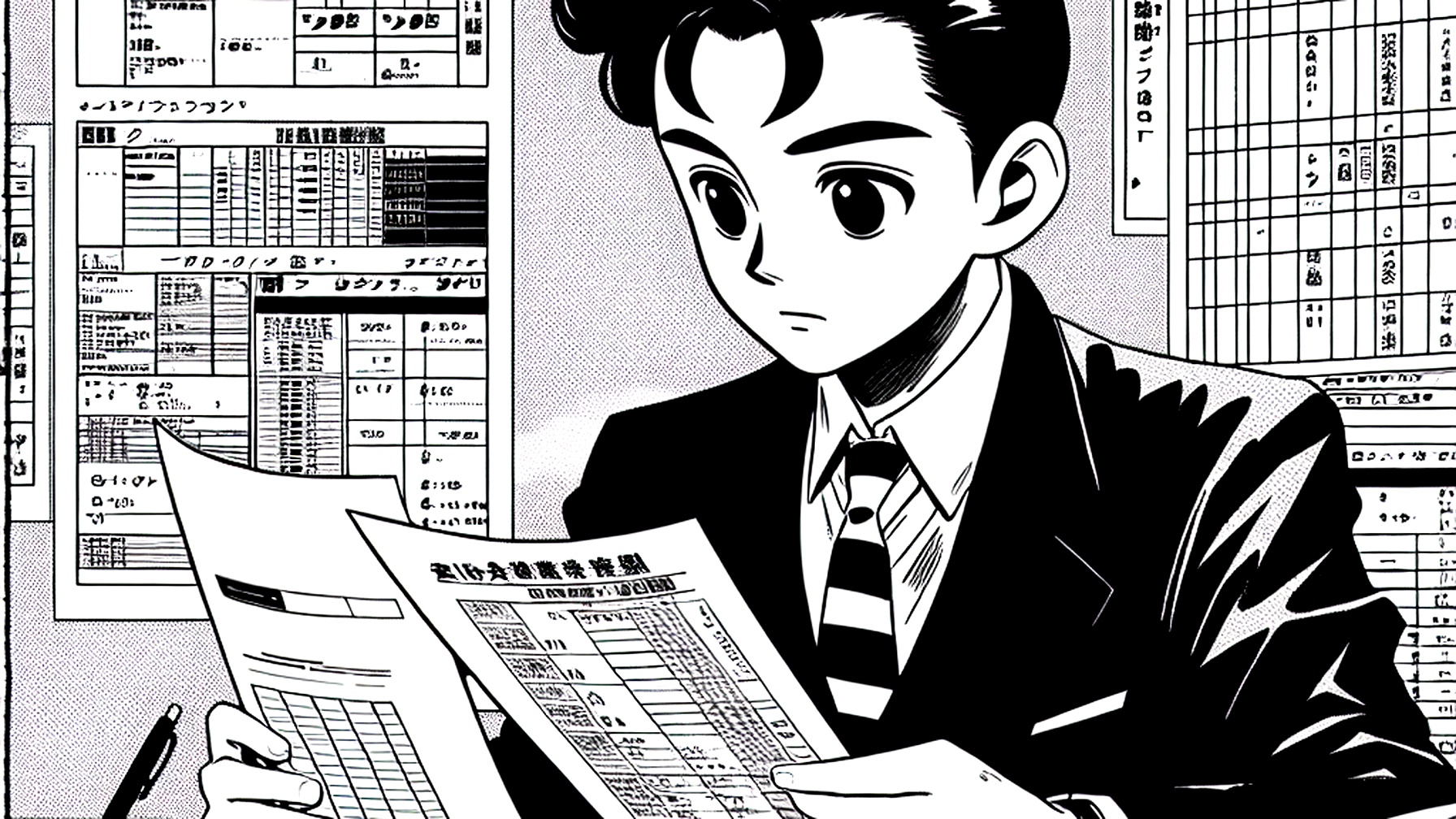
ポイントは、税務上の赤字が必ずしもキャッシュの赤字ではないという事実です。マンション投資では家賃収入から経費を差し引き、さらに減価償却費を計上することで所得を圧縮できます。
まず、減価償却費とは建物の取得価格を法定耐用年数にわたって毎年経費化する仕組みです。鉄筋コンクリート造(RC)の耐用年数は47年で、新築価格の約70〜80%が建物部分とされるのが一般的です。たとえば建物価格4,000万円なら、年間約85万円を非現金費用として計上できます。つまり実際の支出を伴わずに課税所得を減らせるわけです。
さらに、管理費や修繕積立金、ローン金利、固定資産税も経費に含められます。国税庁の統計によれば、築浅区分マンションの平均経費率は家賃収入の35〜40%です。経費と減価償却を合算すると、購入当初は帳簿上の赤字が生じやすく、その分が給与所得などと損益通算されます。
しかし、赤字額が大きいほど良いとは限りません。家賃収入を上回るローン返済や修繕費が発生すれば本当にキャッシュが減ります。仕組みを理解し、キャッシュフローと節税メリットを切り分けて考えることが重要なのです。
減価償却と損益通算はどこまで有効か
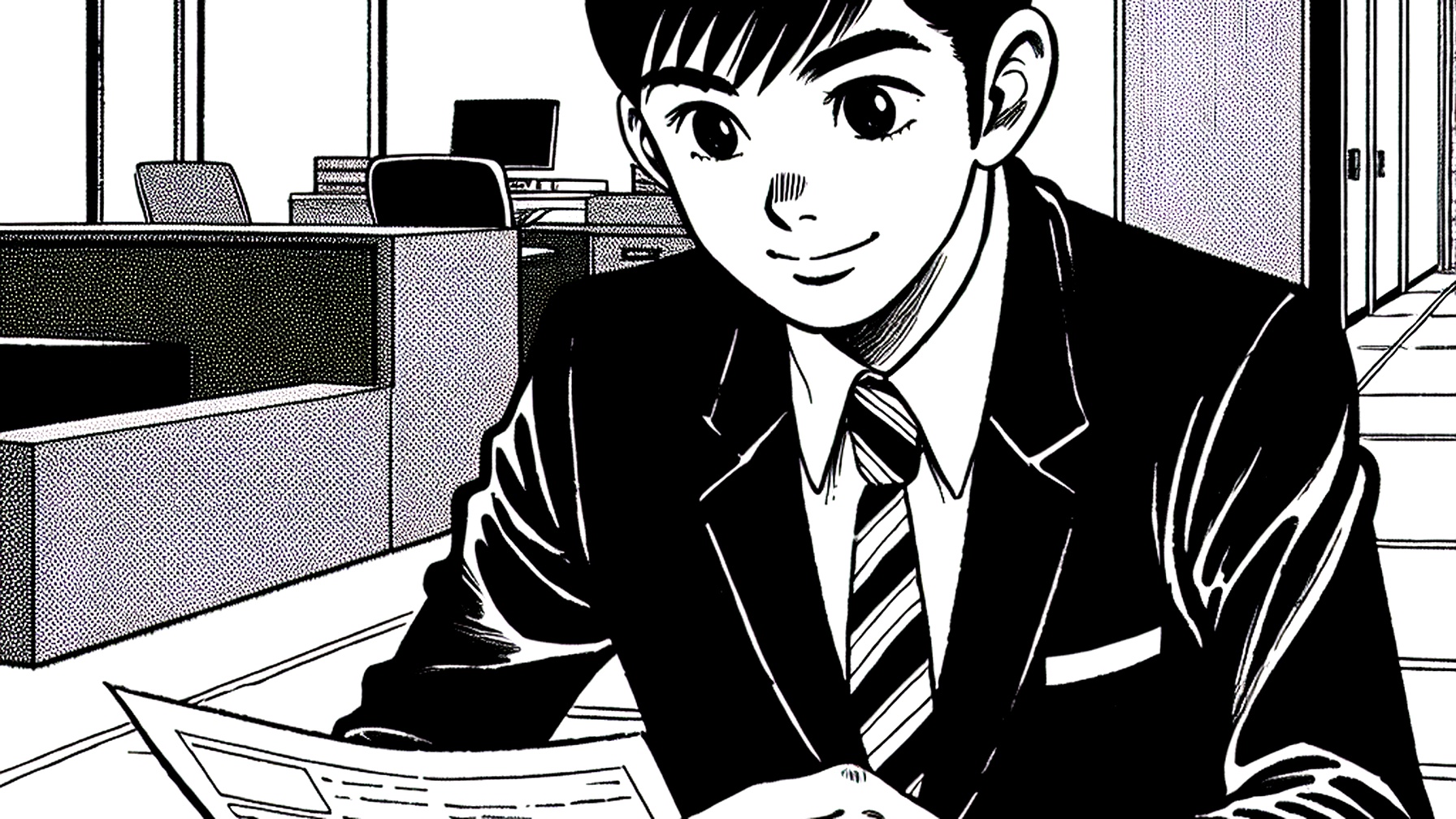
実は、減価償却で圧縮できる期間と金額には明確な上限があります。耐用年数を経過した後は償却費が減り、課税所得が増えるため税負担は上昇します。たとえば築10年の物件を購入した場合、残存耐用年数は37年です。最初の10年で得た節税効果は、11年目以降に反動として返ってくる構造なのです。
一方、損益通算にも制約があります。税務署は近年“土地値より高額な中古マンションの過大償却”に注目しており、適正な区分割合の資料を求められるケースが増えました。国税不服審判所の裁決事例でも、根拠の薄い割合が否認された例があります。資料が不十分だと減価償却費の一部が経費として認められず、追徴課税につながる点に注意しましょう。
さらに、損益通算で赤字を出しても、給与所得全体が900万円以下なら住民税の軽減幅は年数十万円にとどまることが一般的です。節税額と投下資金、ローン返済額を比較し、総合的な収益性をシミュレーションすることが欠かせません。
2025年度税制改正で押さえておきたい点
2025年度の税制改正では、個人大家に大きな影響を及ぼす変更は限定的でした。ただし、細則に目を向けると注意点があります。
まず、青色申告特別控除65万円の要件が厳格化され、帳簿の電子保存とe-Taxでの申告が必須になりました。従来の紙ベースでは最大55万円に縮小されるため、節税効果を維持するには電子化が避けられません。
また、インボイス制度が本格運用2年目を迎え、課税売上1,000万円以下の個人事業大家でも適格請求書発行事業者の登録を検討するケースが増えました。登録すれば家賃には消費税がかからないものの、駐車場賃料や更新料が課税売上に含まれる点を忘れないようにしましょう。
さらに、住宅ローン減税は自宅用制度であり、賃貸用マンションには適用されません。「投資用でもローン減税が受けられる」と誤った説明をする業者は今や少数ですが、念のため確認しておきたいポイントです。
節税狙いだけでは失敗する具体例
ここで、筆者が実際に相談を受けた事例を紹介します。年収1,200万円の会社員Aさんは、都内ワンルームをフルローン4,200万円で購入しました。初年度は減価償却と経費で課税所得を約130万円圧縮し、所得税・住民税合わせて45万円ほど節税できました。ところがローン返済と管理費で年間キャッシュフローは▲60万円。5年目に大規模修繕があり、さらに▲40万円の持ち出しが生まれています。
Aさんのケースでは、節税額より持ち出し額が大きいため純損失です。増税局面になれば赤字幅は縮小し、ローン金利が上がれば手残りはさらに減ります。言い換えると、節税だけに注目した投資判断がいかに危険かを示す好例です。
対照的に、自己資金を1,500万円投入して同規模物件を購入したBさんは、年間キャッシュフローが+15万円を維持しつつ、同程度の節税効果を得ています。自己資金を厚くすることでローン返済負担を軽くし、節税と手残りの両立を実現できたのです。
このように、節税メリットは投資全体の設計があってこそ生きます。節税額だけを追うと返済リスクを見落としがちなので、必ずキャッシュフローとのバランスを取る必要があります。
長期で得をする投資設計のポイント
重要なのは、節税を“目的”ではなく“副産物”と位置づけることです。本来の目的である資産形成に焦点を当てれば、最適な投資戦略が見えてきます。
まず、利回りと立地を総合的に比較します。不動産経済研究所のデータでは、2025年の東京23区新築マンション平均価格は7,580万円で前年比3.2%上昇しました。価格上昇が続くエリアではキャピタルゲイン(売却益)が期待できますが、利回りは下がりがちです。損益通算による節税は一時的でも、長期的な売却益が加わればトータルリターンが安定します。
次に、修繕積立金の推移や管理組合の財務状況を確認しましょう。修繕積立不足がある場合、後から一時金を徴収される可能性があります。これを見落とすと、想定以上に経費がかさみ節税効果を相殺しかねません。
さらに、物件保有期間ごとの税金をシミュレーションし、減価償却終了後の「税負担増」を織り込んだ売却計画を立てます。保有10年目に税負担が増すなら9年目で売却を検討し、売却益にかかる長期譲渡所得税20.315%も計算に入れて比較します。こうしてキャッシュフロー、節税、キャピタルゲインを総合的に最適化することが、長期で得をする秘訣です。
まとめ
本記事ではマンション投資の節税効果について、仕組みから最新税制のポイント、失敗例と成功のコツまで解説しました。減価償却や損益通算は確かに節税に役立ちますが、それだけを目的にするとキャッシュフローが不足し、結果的に損失を生むリスクがあります。大切なのは収益性と税金のバランスをとり、電子帳簿保存など2025年度の制度要件を満たしたうえで長期的な投資計画を描くことです。この記事を参考に、自分の資金力とリスク許容度を踏まえた現実的なシミュレーションを行い、節税を“副産物”として活用できる健全なマンション投資を始めてみてください。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp/
- 国税不服審判所 – https://www.kfs.go.jp/
- 国土交通省 不動産投資市場政策 – https://www.mlit.go.jp/

