不動産投資信託(REIT)は、少額で分散投資ができる手軽さから人気を集めています。しかし実際に検索すると「REIT デメリット 口コミ」という言葉が目立ち、始める前から不安になる人も多いでしょう。そこで本記事では、よく挙がる悩みに共感しつつ、デメリットの実態と克服方法を具体例とデータで解説します。読み終えるころには、口コミの真偽を自分で判断し、2025年時点で取れる最適な行動が見えてくるはずです。
REITとは?仕組みと魅力をおさらい
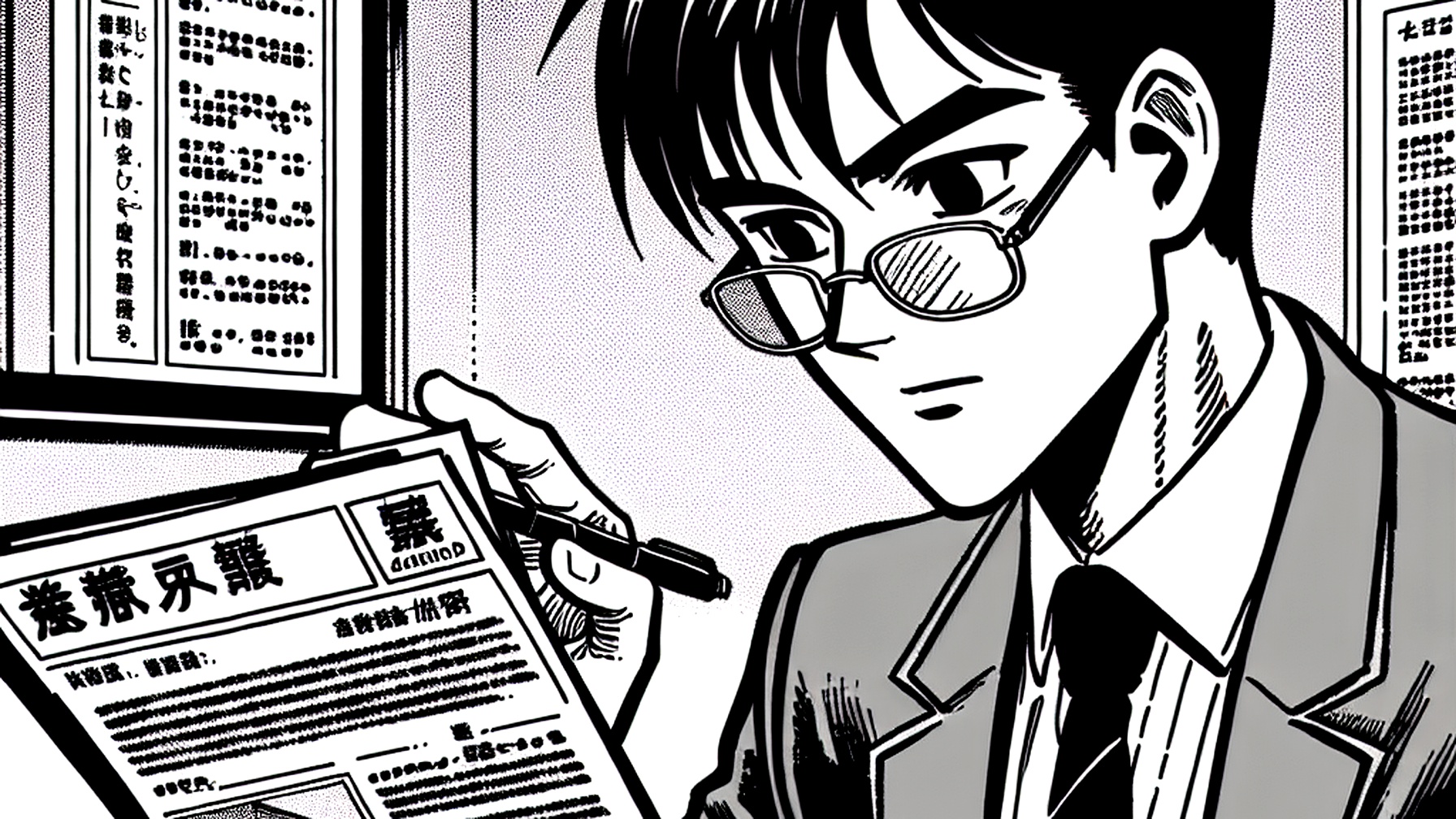
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を小口にして証券化した投資商品である点です。投資家は投資法人の口数を購入し、賃料収入や物件売却益から生まれる分配金を受け取ります。東京証券取引所のデータによると、2025年9月末時点で上場REITは63銘柄、時価総額は約18兆円に達しました。
REITの魅力は、物件管理をプロに任せながら、銀行預金より高い利回りを狙えることにあります。平均分配金利回りは3.5〜4%とされ、長期国債の利回りを上回る水準です。さらに、複数物件に分散投資しているため、単一不動産の空室リスクを軽減できます。
一方で上場株式と同じように価格が日々変動するため、値動きが苦手な人にはストレスになるかもしれません。また、分配金の原資が賃料に依存する点も、景気動向や賃料相場の影響を受けやすいという特徴につながります。
つまり、REITは不動産と株式の両方の性質を持つため、メリットとリスクをバランスよく理解する姿勢が大切です。
口コミから見える三つの主なデメリット
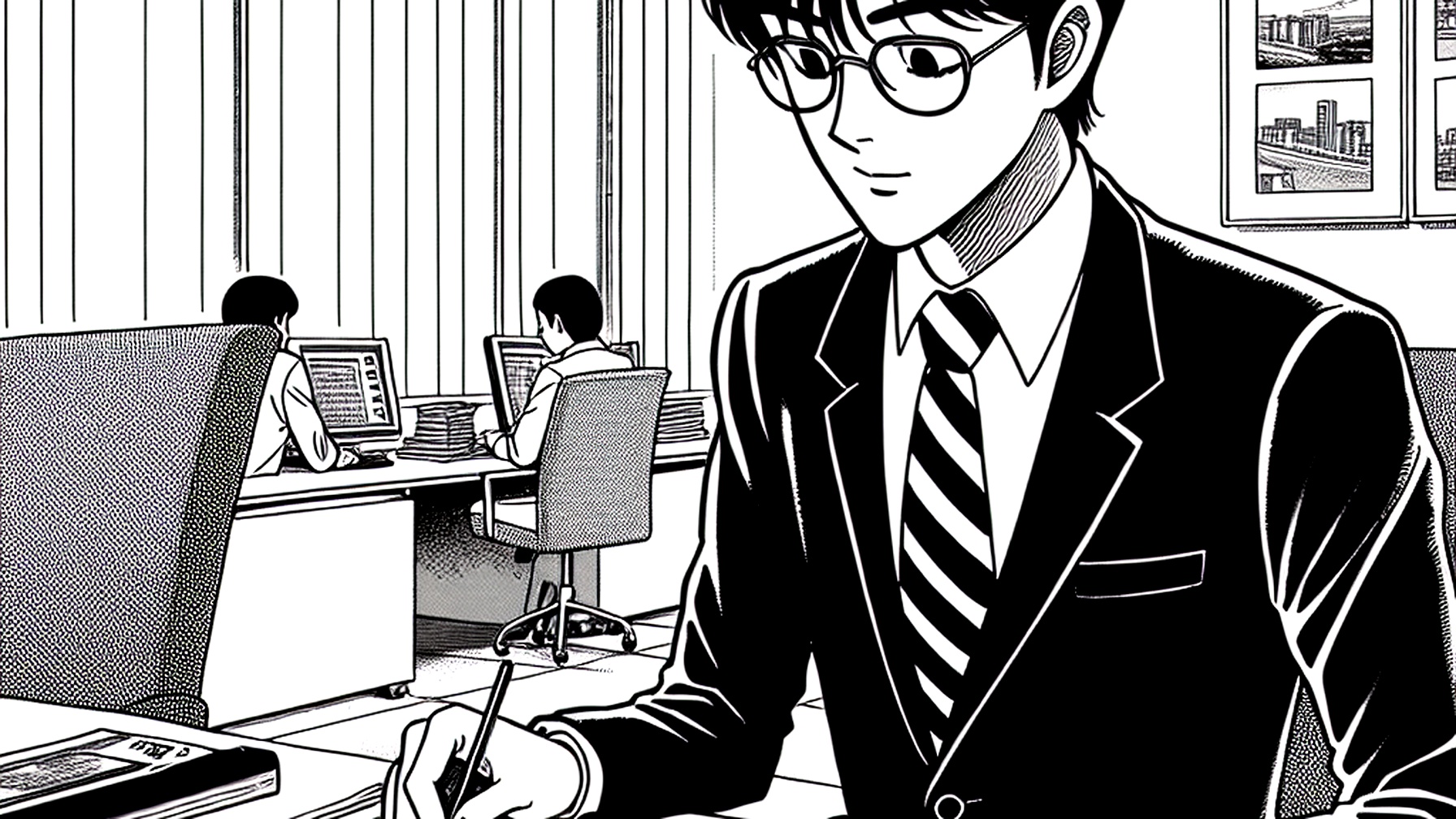
ポイントは、実際の投資家が感じる不安を整理することです。口コミを分析すると、大きく「価格変動」「分配金の減少」「物件老朽化」の三つに集約できます。
最初に価格変動ですが、2020年のコロナショック時にはJ-REIT指数が約35%下落しました。この急落が「REITは思ったより値動きが激しい」と語られる背景です。ただ日本取引所グループの統計では、下落後2年で指数はほぼ回復し、長期保有なら変動幅は平均年率10%前後に収まっています。
次に分配金の減少リスクです。オフィス系REITでは、テレワーク普及で空室率が高まり、2022年に分配金を前年より7%下げた銘柄もありました。口コミでは「安定と聞いたのに減った」という声が上がります。実は、物件用途を分散することで影響を抑えられるケースも多く、住宅系や物流系を組み合わせた投資家は分配金減少幅が小さい傾向が報告されています。
最後に物件老朽化への懸念です。築年数が進むと競争力が落ち、追加修繕費がかかります。REITは資産規模が大きいため、一棟の老朽化が全体収益に与える影響は限定的ですが、口コミでは「内部留保が少ない銘柄は要注意」との指摘もあります。この点は、外部成長(新規取得)を積極的に行うか、内部留保を積み増しているかを運用報告書で確認する習慣が有効です。
分配金の変動リスクを数値で確認
重要なのは、感覚ではなくデータでリスクを捉える姿勢です。金融庁「投資信託の概況」によれば、2020〜2024年度のREIT型投信の年間分配金増減率は平均+1.2%でしたが、最小は-12.5%、最大は+18.0%と振れ幅が大きい結果でした。
具体例として、住宅系Aリートとオフィス系Bリートの実績を比べると、2023年度の分配金はAが前年比+3%、Bが-8%でした。これは需要構造の違いが要因で、単にREITとひとくくりにせず、セクターごとの特徴を押さえる必要があります。言い換えると、REITは株式の業種分散と同じ発想でセクター分散することで、分配金の安定度を高められるのです。
また、日銀が公表する物価見通しでは2025年度のコアCPIは+1.6%と緩やかな上昇が予測されています。賃料は物価に連動しやすいため、インフレ局面では分配金が伸びやすい点も覚えておきましょう。反対にデフレや景気後退では賃料が下がり、分配金も圧迫されるため、景気サイクルを意識した保有年数の長期化が防衛策になります。
個人投資家が取れる対策と心構え
まず、長期・積立・分散の原則はREITでも有効です。特定銘柄に集中せず、住宅・物流・商業施設など複数セクターを組み合わせることで、一部の分配金が減っても全体への影響を緩和できます。さらに、価格変動を平準化したい場合は、毎月一定額を積立購入する「ドルコスト平均法」を活用すると平均購入単価が抑えられます。
2024年から恒久化された新NISAは2025年度も利用可能で、年間最大360万円までの投資枠に対し、REIT ETFを購入すれば分配金が非課税となります。この制度を使えば、課税口座より手取り利回りを約20%向上させる効果があります。ただし非課税枠は再利用できないため、投資対象を慎重に選ぶ視点が欠かせません。
加えて、物件老朽化リスクには運用報告書で修繕積立金比率や平均築年数を確認する方法が役立ちます。目安として、平均築年数が20年未満、修繕費予定額が資産総額の1%以上であれば、適切に維持更新を計画していると判断しやすいでしょう。
最後に、口コミを参考にする際は、投稿者の保有期間や投資目的を読み解く習慣が重要です。短期売買で損失を出した人の意見は、長期保有を前提とする読者には当てはまらない場合があります。情報の背景を考慮することで、自分に合った選択がしやすくなります。
2025年度の制度変更と税制ポイント
実は、2025年度はREIT投資に影響する二つの制度が注目されています。まず、金融庁が推進する「サステナブル投資開示ガイドライン」が4月に適用開始となり、REITも環境関連データの開示が義務化されました。これにより、省エネ性能の高い物件を多く保有するREITはESG資金の流入が期待でき、将来的な価格評価にプラスに働く可能性があります。
次に、国税庁は同年6月から「国内上場インフラファンド・REITの外国税額控除一部簡素化」を導入しました。外国人投資家にとって手続きが容易になるため、海外資金がJ-REIT市場に入りやすくなります。市場全体の流動性向上は、個人投資家にとっても売買コスト低減につながるメリットです。
なお、グリーン住宅ポイントなどすでに終了した補助金はREITには直接関係しません。制度の有無を見分けるには、必ず2025年度の施行日と期限を確認し、金融庁や国税庁の公式サイトで最新情報を参照する習慣を身につけてください。
まとめ
本記事では、口コミで語られるREITのデメリットを「価格変動」「分配金の減少」「物件老朽化」に整理し、それぞれの実態とデータを確認しました。そのうえで、セクター分散や積立投資、新NISAの活用といった具体的な対策を示しました。大切なのは、表面的な口コミに振り回されず、公的データと自分の投資目的を照らし合わせる姿勢です。適切な情報収集と長期視点を持てば、REITは安定したキャッシュフローづくりの有力な選択肢になります。今日から一歩踏み出し、デメリットを理解したうえで上手に活用してみてください。
参考文献・出典
- 金融庁 投資信託の概況 2025年7月版 – https://www.fsa.go.jp
- 東京証券取引所 REIT・ETF統計 2025年9月 – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 物価見通し(経済・物価情勢の展望)2025年4月 – https://www.boj.or.jp
- 国税庁 2025年度税制改正のポイント – https://www.nta.go.jp
- 不動産証券化協会(ARES) J-REITデータブック 2025年版 – https://www.ares.or.jp

