収益物件を購入したものの、管理会社にいくら払えばいいのか分からず悩む人は少なくありません。インターネットで調べても、手数料は物件やエリアで大きく異なると書かれているだけで、具体的な判断基準は見えにくいものです。本記事では、管理会社に支払う費用の内訳と相場を整理し、手数料を最適化するための考え方を初心者にも分かりやすく解説します。読み終える頃には、おおよその費用感をつかみ、自分の投資計画にどの程度組み込めばよいか判断できるようになるでしょう。
管理会社に支払う3つの基本費用
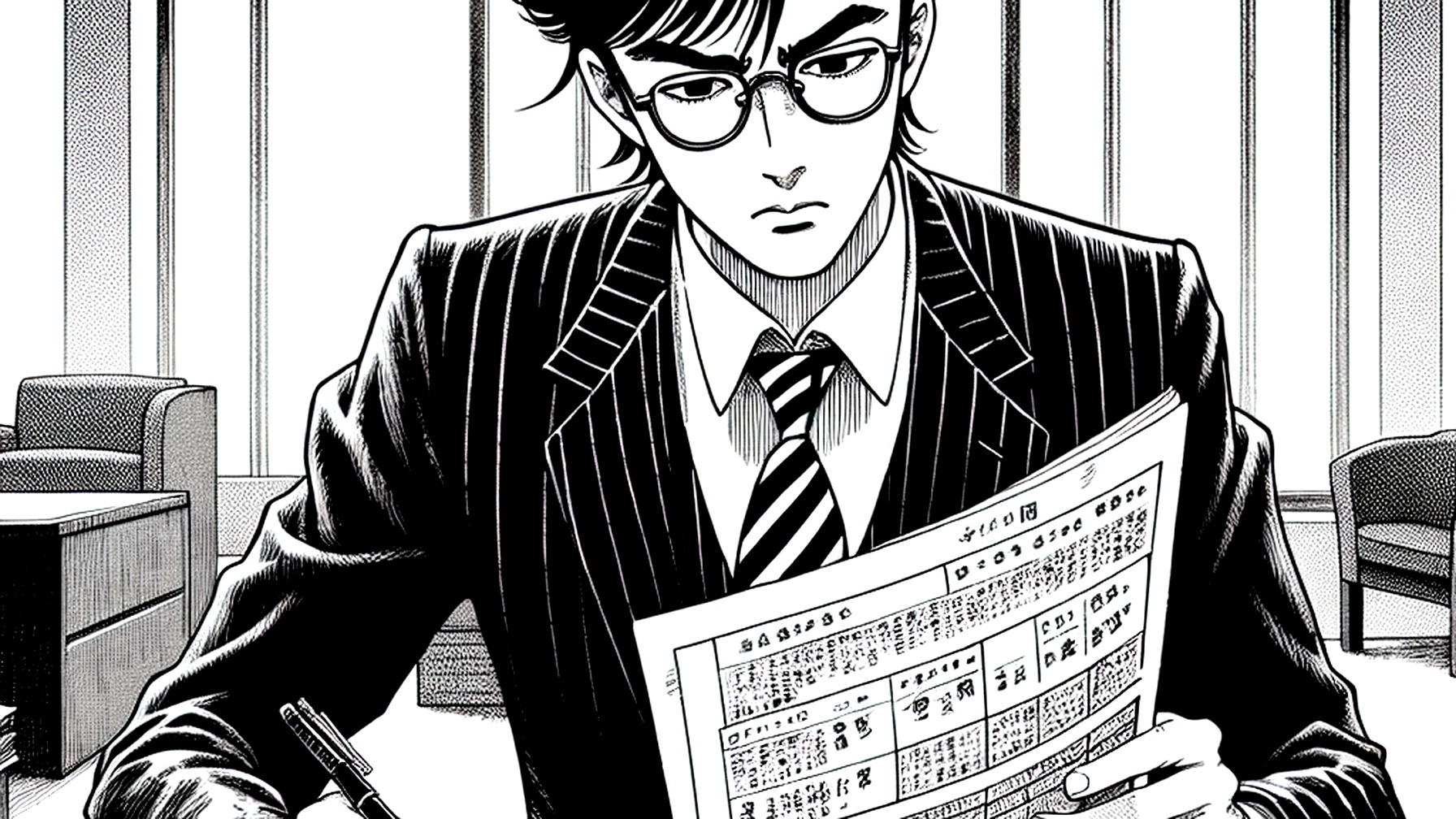
まず押さえておきたいのは、管理会社へ支払うお金が「月額管理手数料」「入居募集関連費」「臨時対応費」の三つに大別されることです。その内訳を理解すると、交渉の余地や費用削減ポイントが見えてきます。
月額管理手数料は家賃の一定割合として設定されるのが一般的で、国土交通省の2025年調査では集合住宅で3〜5%、戸建てで5〜7%が中央値と示されています。家賃10万円の部屋を10戸所有している場合、月額3万円から5万円が相場という計算です。固定額方式を採用する会社もありますが、その場合は月3千円前後が目安となるため、家賃が高い物件ほど割合方式より有利になる傾向があります。
入居募集関連費は、空室が出た際に発生する広告費や仲介手数料を指します。管理会社が仲介も行うケースでは、新規契約時に家賃の1カ月分を請求するのが平均的です。また外部仲介業者を利用する場合、広告料(AD)として0.5〜1カ月分を別途負担する例が増えています。これらは毎月ではなく空室発生時のみ発生するため、年間の空室率を見積もった上で予算に組み込む必要があります。
臨時対応費は設備故障やクレーム対応に伴う実費です。24時間駆け付けサービスを付帯する場合、月300円〜500円を各戸から徴収し、オーナー負担を軽減するプランが多いです。修繕そのものは原則としてオーナー負担になりますが、軽微な修理は月額管理手数料に含まれるかどうかを契約前に確認しましょう。
相場を左右する五つの要因

ポイントは、同じ間取りでも管理手数料が変動する要因が五つ存在することです。立地や築年数だけでなく、建物の構造や契約形態が複雑に絡み合います。
第一に立地です。東京都心六区では高家賃でも競争が激しいため、手数料率は3%台で落ち着く傾向があります。一方、地方中核都市では家賃水準が低く固定費の占める割合が大きいため、同じ仕事量でも5%前後になるケースが目立ちます。
第二に築年数と設備の状態が挙げられます。築20年を超える物件は故障リスクが高まり、管理会社の出動回数が増えるため、手数料率が0.5〜1ポイント程度上乗せされるのが一般的です。加えてエレベーター付きRC造(鉄筋コンクリート造)では法定点検が必要になり、その分コストも高くなります。
第三は戸数と規模です。10戸程度の小規模アパートでは一戸当たりの手間が大きく、手数料率を割高に設定する会社が多いです。逆に50戸を超えるマンションではスケールメリットが働き、3%未満まで下がる事例もあります。
第四は契約形態で、サブリース(家賃保証)契約だと10〜20%の保証料が発生します。表面上の空室リスクは無くなりますが、収益性が大きく下がる点に注意が必要です。最後に、管理会社のIT化度合いも見逃せません。オンライン明細やスマートロックを導入している会社は、手数料を下げつつサービス品質を維持している例が増えています。
管理委託か自主管理かの判断基準
実は、全てのオーナーが管理委託すべきとは限りません。時間やスキル、物件の立地によっては自主管理が合理的になる場合もあります。
自主管理の最大のメリットはコスト削減です。月額3%の手数料を節約できれば、年間のキャッシュフローが大きく改善します。しかし、家賃滞納の督促や深夜の水漏れ対応など、時間外労働を強いられる場面も少なくありません。副業で投資を行う会社員が遠隔地の物件を自主管理するのは現実的ではないでしょう。
一方で、物件から徒歩5分に住んでおり、賃貸実務を熟知している元不動産営業マンであれば、自主管理で手数料を抑えつつ入居者フォローを強化することが可能です。重要なのは、「手間を時給換算すると管理手数料を下回るか」という視点で比較することです。
さらに、2024年の賃貸住宅管理業法改正で、管理戸数200戸以上の自主管理オーナーにも一定の業務管理体制が義務付けられました。要件を満たせない場合は管理会社の利用が事実上必須となりますので、法令面の確認も怠らないようにしましょう。
手数料を下げる交渉とサービス比較のコツ
重要なのは、単に安い会社を探すのではなく、「支払額に見合う価値」を定量的に比較することです。
まず複数社に同条件で見積もりを依頼し、手数料率だけでなく対応範囲を表形式でまとめると差が明確になります。たとえば、夜間対応の有無やリーシング(空室募集)実績、長期修繕計画の提案力など、数字化しにくい項目こそ可視化が大切です。
交渉の際は、戸数や契約期間をテコにするのが効果的です。30戸以上を一括で委託する場合、手数料率を0.5ポイント下げてもらえるケースが多いです。また、新築時に募集を一任する代わりに、以降3年間の管理手数料を3%固定にするなど、長期的な関係を提示すると価格は下がりやすくなります。
それでも折り合いが付かない場合は、サービスを部分委託に切り分ける方法があります。入居募集のみ外部仲介に任せ、家賃集金や設備点検は自主管理する形です。このハイブリッド型は、2025年時点で都市部の若手オーナーを中心に採用例が増加しており、運営コストを年間10〜20%削減した事例も報告されています。
2025年度の税制と補助制度が費用に与える影響
ポイントは、管理費用が税務上「必要経費」として全額損金算入できる点です。家賃収入が800万円あるオーナーが年間60万円の管理料を払うと、課税所得をその分圧縮でき、実効税率20%なら12万円の税負担軽減効果が期待できます。
また、2025年度は国土交通省の「賃貸住宅省エネ改修支援事業」が継続しています。一定の断熱改修を行い、管理会社に継続点検を委託する場合、1戸あたり最大25万円の補助を受けられる仕組みです(交付申請は2026年3月末まで)。この補助を活用すれば、設備更新費を実質的に抑えつつ、管理契約の質も向上させることが可能です。
さらに、東京都では2025年度も「スマート管理システム導入補助」を実施しており、共用部IoT化費用の2分の1(上限100万円)が補助対象になります。スマートロックやクラウドカメラを導入すると管理会社の巡回コストが下がり、結果として手数料率の引き下げ交渉がしやすくなるという副次的効果も得られます。
このように、最新の税制と補助制度を組み合わせれば、表面的な手数料率を超えて実質負担を減らすことが可能です。制度には予算上限や年度末締め切りがあるため、管理会社と連携しながら早めに申請準備を進めることが大切です。
まとめ
ここまで「収益物件 管理会社 いくら」という疑問に対し、費用の内訳と相場、変動要因、交渉のヒント、税制・補助制度まで具体的に整理してきました。月額管理手数料3〜5%を中心に、空室時の募集費や臨時修繕費を合算すると、年間家賃収入の10%前後が管理コストの目安になります。しかし、立地や築年数、契約形態によって上下幅は大きく、複数社比較と制度活用が収益最大化の鍵となります。読者の皆さんも、自分の時給やリスク許容度を指標に自主管理との比較を行い、納得できる管理体制を構築してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省「賃貸住宅市場検討会 報告書2025」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局「住宅・土地統計調査2023」 – https://www.stat.go.jp
- 東京都住宅政策本部「賃貸住宅実態調査2024」 – https://www.metro.tokyo.lg.jp
- 日本賃貸住宅管理協会「管理料実態調査2025」 – https://www.jpm.jp
- 国税庁「令和7年度 所得税法令集」 – https://www.nta.go.jp

