不動産投資に興味はあるものの、「良い物件を買っても本当に利益が残るのか」と不安に感じていませんか。実際、収益物件を購入しても管理が甘ければ空室が続き、想定より手取りが減るケースは珍しくありません。そこで鍵を握るのが管理会社です。本記事では「収益物件 管理会社 儲かる」という視点から、初心者でも理解しやすい基礎知識と2025年現在の最新動向を解説します。読み終えるころには、管理委託の仕組みと選定基準を押さえ、安定したキャッシュフローを目指す具体的な行動イメージが描けるはずです。
収益物件が生むお金の流れを正しく理解する
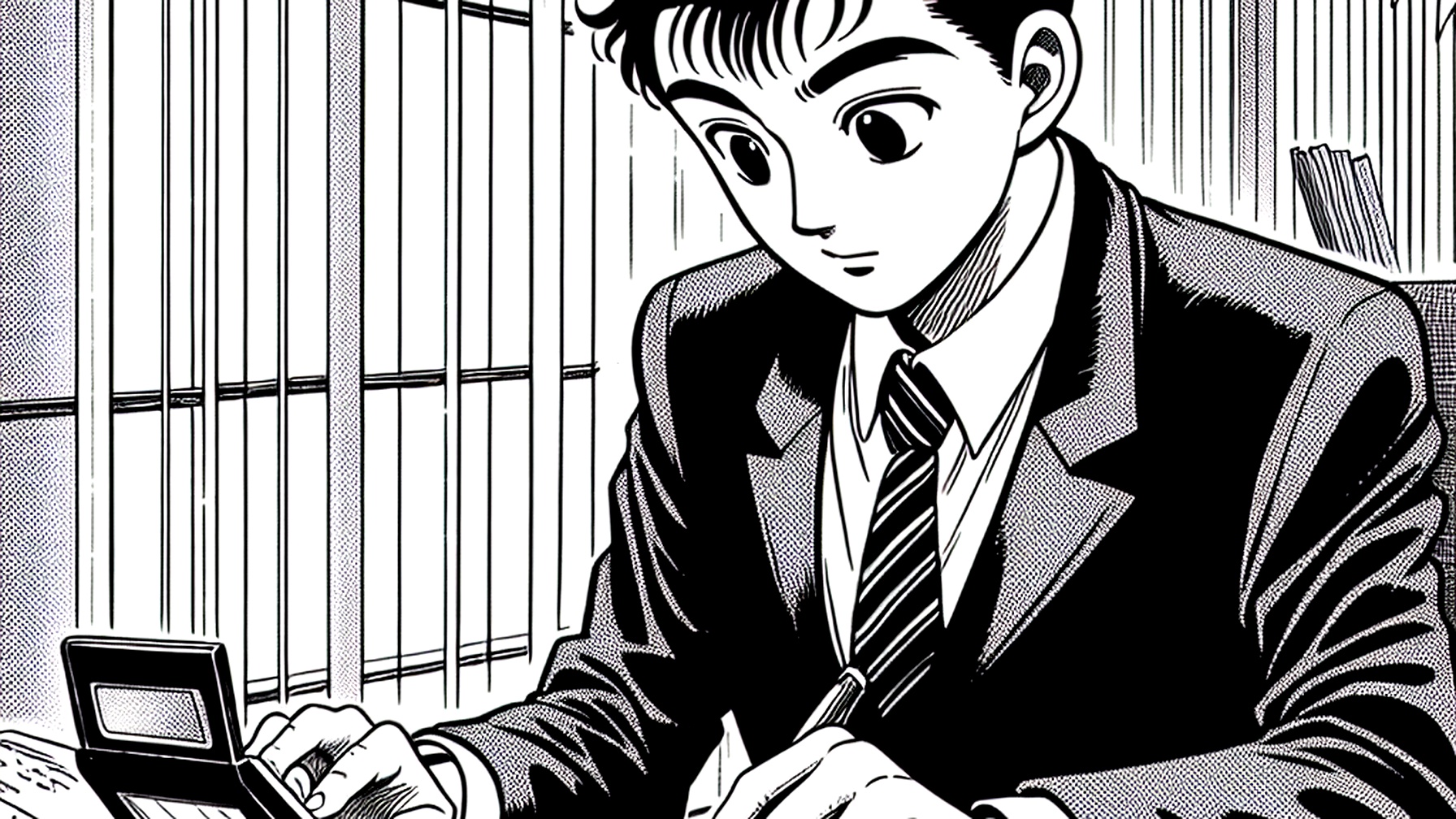
まず押さえておきたいのは、収益物件の利益構造です。家賃収入から運営費を差し引いた残りがキャッシュフローであり、この金額が多いほど「儲かった」と実感できます。
家賃収入は空室率に強く影響されます。国土交通省「賃貸住宅市場の実態調査2025」によると、全国平均の空室率は18.2%ですが、適切な管理を行う物件は10%未満に抑えられる例も報告されています。つまり管理品質がキャッシュフローを左右すると言い換えられます。
一方、運営費の中で最も比率が高いのが管理委託費です。賃料の5〜7%が相場と思われがちですが、2025年現在は高付加価値サービスの普及により、物件規模によって3%台のプランも増えています。表面利回りだけでなく、管理コストと空室率を合わせて考えることが重要です。
管理会社は家賃集金、入居者対応、修繕手配などを代行します。そのため投資家は本業に集中できる一方、業務の質が低いとクレーム増加や退去率上昇を招きます。効率良く儲けるには、家賃収入の最大化と運営費の最小化を同時に実現できる管理会社を見極める必要があります。
管理会社を選ぶときに外せない判断軸
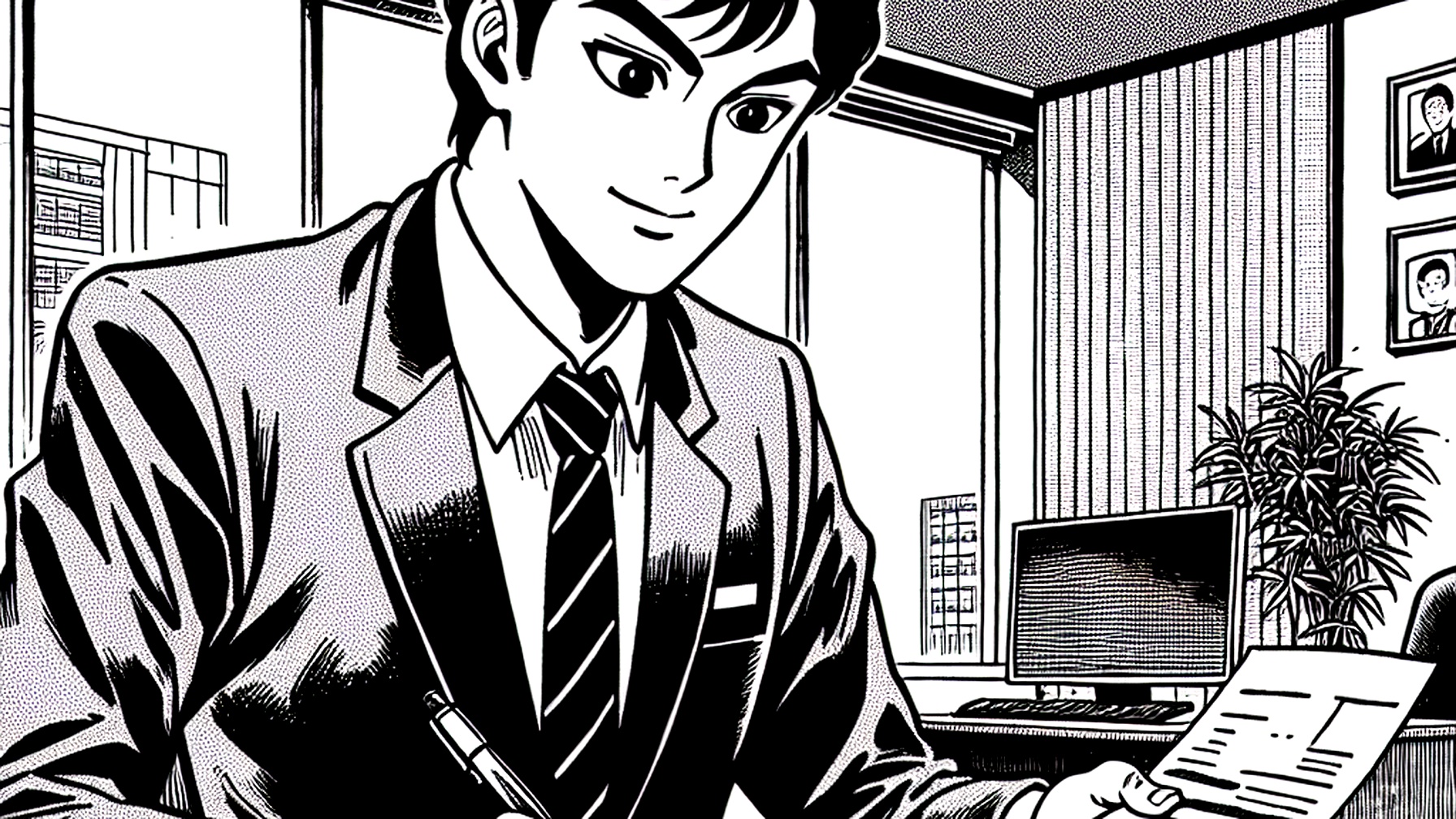
ポイントは、サービス範囲・実績データ・報酬体系の三つです。冒頭で述べたように、ただ安い会社を選ぶと結果的に空室増加で手残りが減る可能性があります。
まずサービス範囲を確認しましょう。24時間の入居者対応やIT重説(オンライン重説)の有無は、若年層の入居継続率を高める要素になります。次に実績データですが、総戸数だけでなく平均入居期間や年間退去率を提示できる会社は信頼性が高い傾向にあります。公益財団法人日本賃貸住宅管理協会の統計では、退去率が年15%以下の会社は家賃滞納率も1%未満に抑えている例が多いと示されています。
さらに報酬体系を詳細に比較します。「サブリース(家賃保証)」は空室リスクを抑えられる一方、保証賃料が相場の80〜90%となるため長期的な利益が減少する場合があります。一方で「集金代行方式」は空室リスクを負担する代わりに満室時の利益を最大化できます。投資家自身のリスク許容度に合わせた選択が欠かせません。
加えて、賃貸住宅管理業法の改正により2025年度も引き続き、管理戸数200戸以上の会社は国土交通大臣への登録が義務化されています。登録番号を提示できるかどうかは最低限の確認ポイントといえるでしょう。
管理委託コストとサービス品質のバランス
実は、管理委託費率を単純に下げるだけでは、長期のキャッシュフローが目減りする恐れがあります。なぜなら、質の高いリーシング(入居付け)と修繕提案が利益最大化に直結するからです。
たとえば築20年の木造アパートで共用灯のLED化を提案し、月々1,500円の電気代削減に成功したケースを考えてみます。年間で18,000円、10年間で18万円の経費削減となり、管理費率が1%高くても十分元が取れる計算です。このような改善提案を積極的に行う会社は、短期の管理費より長期の手残りを重視しています。
また、金融機関の融資条件にも管理会社が影響することがあります。住宅金融支援機構の「フラット投資プラン2025」では、管理実績の優良な会社と契約している物件に対し、金利を0.1%優遇する制度が継続中です。金利差は30年ローンで数十万円の節約になるため、管理会社選定が間接的に金融コストを下げる効果も期待できます。
重要なのは、提示された管理費率だけでなく、提案力と金融機関からの評価まで含めて総合的に比較することです。面談時には過去の改善提案書やリフォーム後の入居率推移を見せてもらい、数値の裏付けを確認しましょう。
2025年の市場動向と長期的に儲ける戦略
2025年は人口減少トレンドが続くものの、都市部への一極集中はむしろ強まっています。総務省「住民基本台帳人口移動報告2025」によると、東京都の転入超過数は11万人で前年より1.2万人増加しました。この流れは家賃需要を底支えし、収益物件の価格を押し上げている要因です。
一方、サブリース規制の強化やインボイス制度の本格運用で、利回り計算が複雑化しています。投資家は税務と管理の両面に強いパートナーが必要です。管理会社が税理士と連携し、家賃と消費税の仕訳データを毎月提供してくれる体制であれば、確定申告や消費税申告の手間が大幅に減ります。
さらに、環境性能の高い住宅への需要拡大も無視できません。2025年度の「ZEB補助金(小規模賃貸版)」を活用し、外皮断熱を強化したワンルームは、同一エリアの築浅物件より2,000円高い賃料で成約した事例が報告されています。ただし補助対象は着工前申請が条件で、予算枠に達すると受付終了となるため、制度を熟知する管理会社と連携することが成功の近道です。
長期的に儲けるためには、需要が堅調なエリアで高付加価値化を図り、税務・法務の変化に柔軟に対応できる管理会社をパートナーにすることが欠かせません。投資家単独の努力には限界があるからこそ、プロの知見を借りてアップデートし続ける姿勢が求められます。
まとめ
本記事では「収益物件 管理会社 儲かる」をテーマに、利益構造の基礎から会社選びの具体的な視点まで解説しました。空室率と管理費はキャッシュフローの両輪であり、サービス品質の高いパートナーを選ぶほど長期利益が大きくなることが分かったはずです。次の一歩として、複数社に資料請求し、退去率や改善提案事例といった定量データを比較してみてください。信頼できる管理会社を味方に付けることで、安定した家賃収入と時間的自由を同時に手に入れる未来が近づきます。
参考文献・出典
- 国土交通省「賃貸住宅市場の実態調査2025」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省「住民基本台帳人口移動報告2025」 – https://www.soumu.go.jp
- 公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「全国賃貸住宅管理業統計2025」 – https://www.jlma.or.jp
- 住宅金融支援機構「フラット投資プラン2025」 – https://www.jhf.go.jp
- 一般社団法人環境共創イニシアチブ「ZEB補助金情報2025」 – https://www.sii.or.jp

