投資で毎月の収入を増やしたいものの、株価の上下に振り回されるのは怖い―そんな悩みを抱える方に注目されているのが、手軽に不動産収益を得られるJ-REITと、中古物件への直接投資です。どちらも分配金や家賃収入という形で現金が入る点が魅力ですが、仕組みもリスクも大きく異なります。本記事では2025年10月時点の最新データをもとに、REITと中古物件それぞれの分配金の特徴を比較し、初心者でも無理なく安定したキャッシュフローを得る方法を解説します。読み終えるころには、自分に合った投資スタイルを選ぶための判断軸がクリアになっているはずです。
REITの基礎と魅力
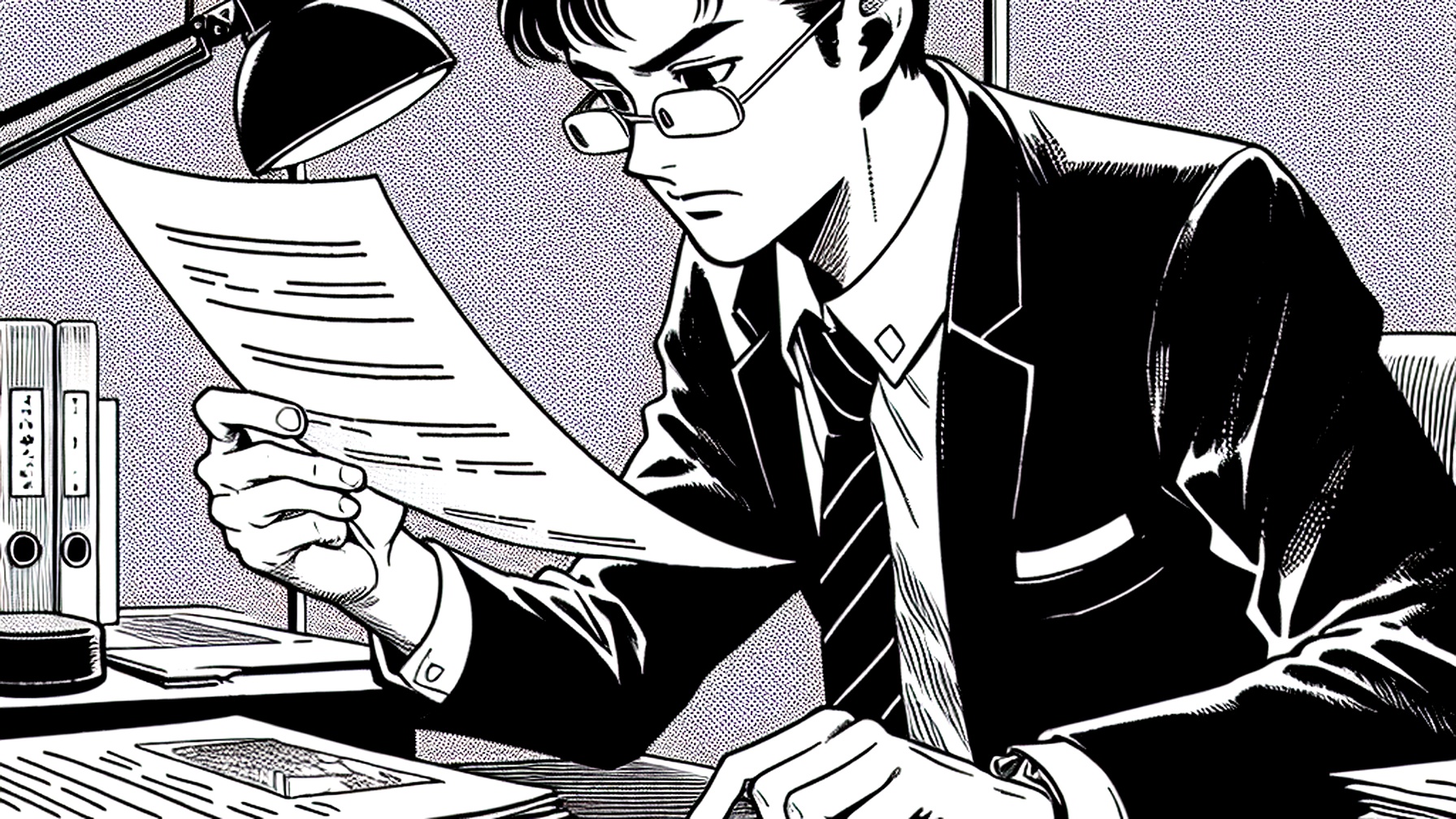
まず押さえておきたいのは、REITが不動産を小口化し投資家に分配金を支払う仕組みだという点です。証券口座さえあれば、数万円から日本全国のオフィスや住宅、物流施設に間接的に投資できます。
REIT(不動産投資信託)は、多数の物件から得られる賃料を合算し、運用経費を差し引いた九割以上を分配金として投資家に還元します。金融庁の「投資信託の現状2025」によると、2024年度のJ-REIT平均分配利回りは3.8%前後で推移しました。債券より高利回りで、株式より価格変動が穏やかな点が評価され、純資産総額は前年同期比6%増です。
一方で価格がゼロにはならないものの、市場環境によって基準価額は上下します。金利が上昇すると分配金利回りの相対的魅力が薄れ、価格が調整されるケースもあります。またテナント退去や大規模修繕が発生すると、分配金が減る可能性も忘れてはいけません。
重要なのは、複数銘柄に分散し、物件用途や地域をバラけさせることです。例えばオフィス主体のREITと住宅主体のREITを組み合わせるだけでも、景気変動への耐性が高まります。これによりリスクを抑えながら、年間を通じて安定した分配金を期待できます。
中古物件投資との違いと共通点
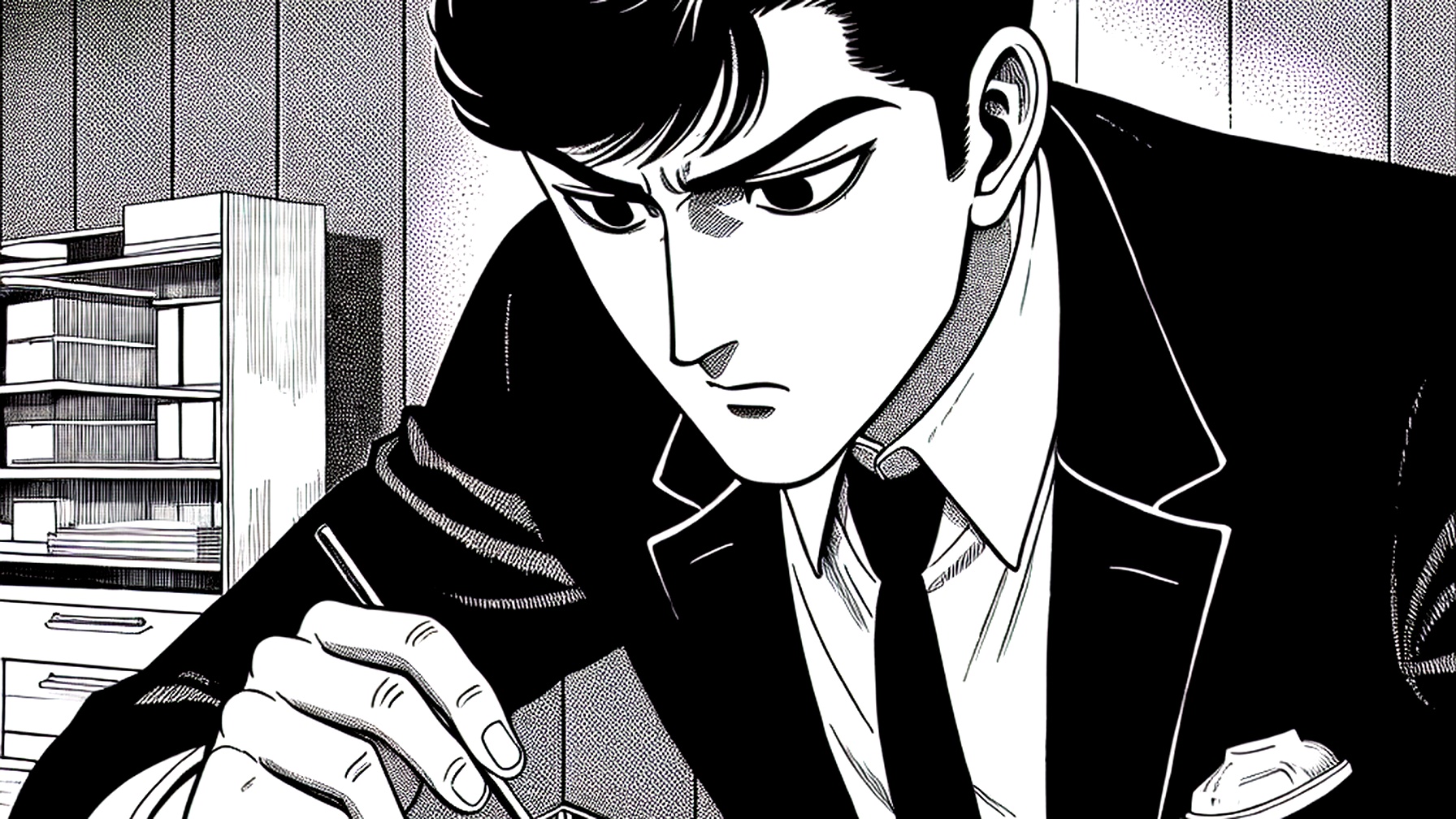
実は、中古アパートや区分マンションへの投資も「分配金」を得る点では同じ構造です。ただし、家賃収入は自分で物件を所有し管理するため、収益もリスクも直接的になります。
中古物件の魅力は、購入価格が新築より抑えられ、利回りが高くなりやすいことです。国土交通省「不動産取引価格情報」によると、東京都23区の築20年マンションは新築比で平均35%割安で取引されています。その分、表面利回りは6~8%を狙えるケースが多く、REITを上回ることも珍しくありません。
しかし、物件検索、融資交渉、入居者募集、修繕対応まで、オーナーが一手に担う点が大きな負担です。空室が続けば収入はゼロになり、多額の修繕費が突発的に発生することもあります。またエリア選定を誤ると、将来的に家賃下落リスクが高まります。
両者の共通点は、不動産から生まれるキャッシュフローを原資に分配金を得る点です。違いは、リスクと手間を自分で背負うか、運用会社に委ねるかというスタンスの違いになります。つまり、忙しい会社員はREITで分散を図り、時間と知識を投下できる人は中古物件を選ぶといった棲み分けが現実的です。
分配金の仕組みを数字で読み解く
ポイントは、表面利回りだけでなく手取り利回りを見ることです。REITでも中古物件でも、税金と経費を差し引いた後の数字が最終的な収益を決めます。
例として、2025年4月決算期に年間40円の分配金を出したオフィス系REITを考えましょう。株価が1,050円なら表面利回りは約3.8%です。個人投資家の場合、分配金は上場株式と同じく20.315%の申告分離課税が源泉徴収されるため、手取り利回りは約3.0%に下がります。
一方、想定利回り7%の中古区分マンション(価格1,500万円、家賃月9万円)を例にします。年間家賃は108万円ですが、管理委託費・修繕積立金・固定資産税で年20万円を見込むと、実質利回りは5.9%です。さらに所得税と住民税を合算した税率が20%なら手取りは約4.7%に落ち着きます。
この比較からわかるのは、経費割合と税制の違いが手取りを大きく左右する点です。REITは取引コストが少なく、手間もかからない一方、経費を自分でコントロールできません。中古物件は経費を最適化できる余地があるものの、空室リスクや突発修繕で数字がぶれることに留意しましょう。
2025年度の税制と実践的な受取戦略
基本的に、REITの分配金は株式配当と同じく源泉分離課税20.315%が自動で差し引かれます。これをそのままにしておくと損益通算はできませんが、2024年に制度刷新された新NISAの成長投資枠を使えば、年間240万円まで非課税で受け取れます。分配金再投資で複利効果を狙うなら、まずNISA枠の活用を検討しましょう。
中古物件の家賃収入は総合課税となり、所得が高いほど税率も上がります。ただし、減価償却費や借入利息を経費計上できるため、初期数年間は課税所得を圧縮しやすいメリットがあります。金融庁「家計金融行動調査2024」によると、年収700万円以上の個人投資家ほど中古物件の節税効果を評価する傾向が強いと報告されています。
重要なのは、税金を抑えることではなく、あくまで手取りキャッシュフローを最大化することです。REITはNISA枠や特定口座で管理しつつ、分配金を自動再投資するサービスを利用することで、毎年の購入手数料を削減できます。一方で中古物件は、修繕積立や空室リスクを見越して分配金(家賃)の20%程度を内部留保し、残りを再投資に回すと安定度が増します。
最後に、両者を組み合わせる「ハイブリッド戦略」も有効です。例えば、まずREITで市場全体の動きをつかみながら運用益を積み上げ、キャッシュが300万円ほど貯まったら中古ワンルームを購入する流れです。これにより手間とリスクを分散しつつ、多様な分配金源を育てられます。
まとめ
本記事では、REITと中古物件という二つの手段で得られる分配金の仕組みと違いを整理しました。REITは手軽さと分散効果が強みで、NISAを活用すれば手取り利回りを底上げできます。一方、中古物件は高利回りと節税効果が期待できるものの、空室や修繕と向き合う主体性が欠かせません。自分のライフスタイル、資金計画、リスク許容度を踏まえ、まず小規模に試しながら適切な比率を探る行動が、安定収入への近道です。
参考文献・出典
- 金融庁 – https://www.fsa.go.jp/
- 国土交通省 不動産取引価格情報 – https://www.land.mlit.go.jp/
- 日本取引所グループ JPXデータ – https://www.jpx.co.jp/
- 投資信託協会 J-REITデータ – https://www.toushin.or.jp/
- 総務省統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp/

