不動産投資を検討していると、手軽に分散投資できるREIT(不動産投資信託)に興味を持つ方は少なくありません。しかし「価格が安定しているようで本当に大丈夫か」「将来の金利上昇で損をしないか」と不安に感じる声も多いものです。本記事では、2027年までの中期スパンで考えたときに顕在化しやすいリスクを整理し、REIT デメリット 2027年という観点から注意点と対策をわかりやすく解説します。読み終えるころには、ご自身の資産形成プランにREITを組み込むべきかどうか、判断できる視点が得られるはずです。
REITとは何かと2027年の市場環境
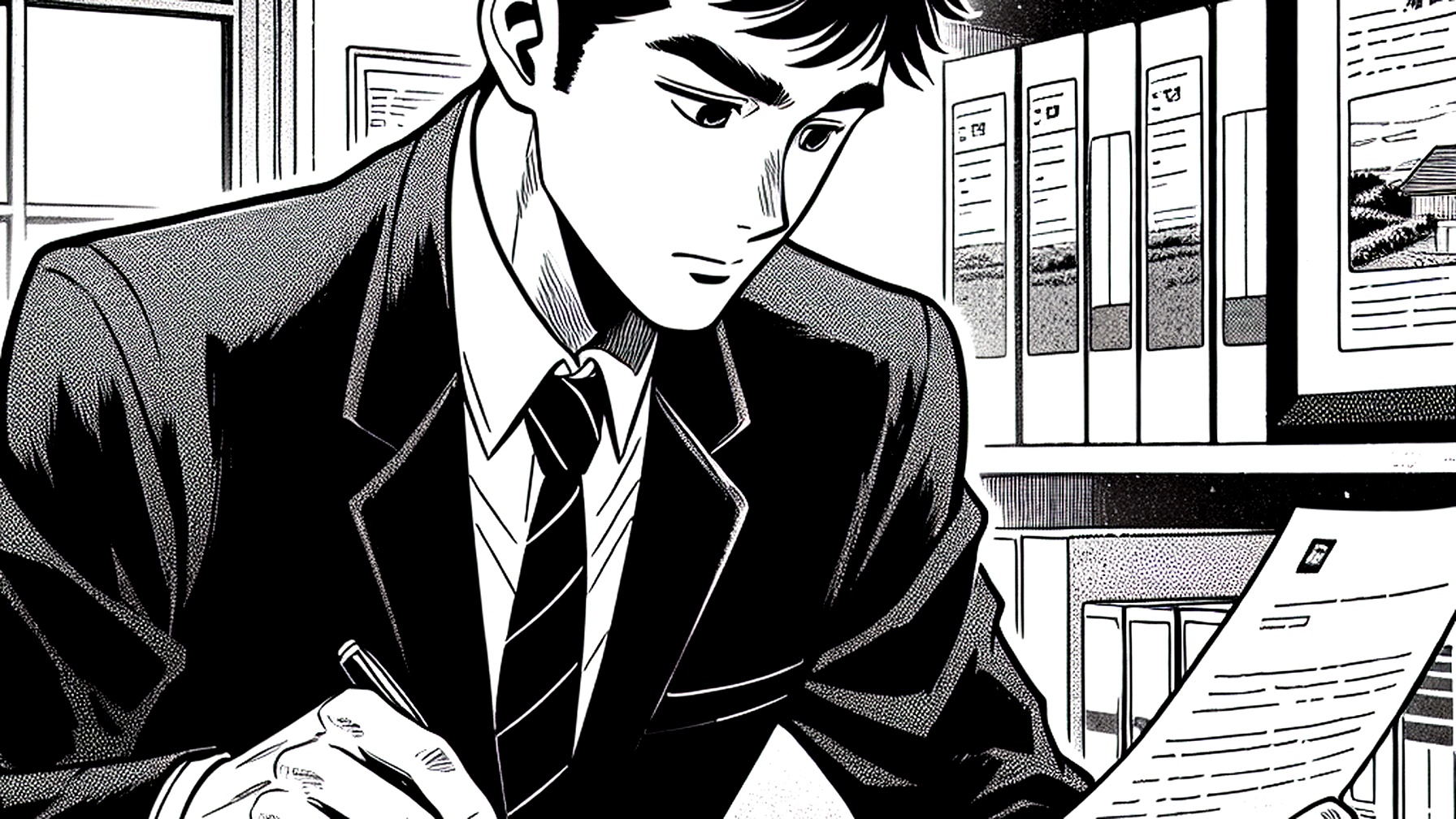
まず押さえておきたいのは、REITが多数の投資家から集めた資金で商業ビルやマンションなどを取得し、賃料収入を分配金として還元する仕組みだという点です。東京証券取引所のJ-REITは2025年10月時点で68銘柄に拡大し、上場時価総額は約17兆円と公表されています。実はこの規模は米国REIT総額の1割程度に過ぎず、成熟と拡大が同時に進んでいる段階といえます。
2027年を展望すると、日本銀行のマネタリーベース縮小と世界的な金利正常化が重なり、借入コスト上昇が確実視されています。つまりREITが保有する物件の借入利息が増えれば、分配金が圧迫される可能性が高まります。また、オフィス需要の動向にも目を向ける必要があります。国土交通省の「不動産市場動向調査」によると、都心部の空室率は2024年に底打ちしたものの、テレワーク浸透で2027年まで横ばいとの予測が示されています。今後の成長ストーリーを描くには、運用会社の資産入れ替え戦略がポイントとなるでしょう。
分配金減少リスクと金利動向
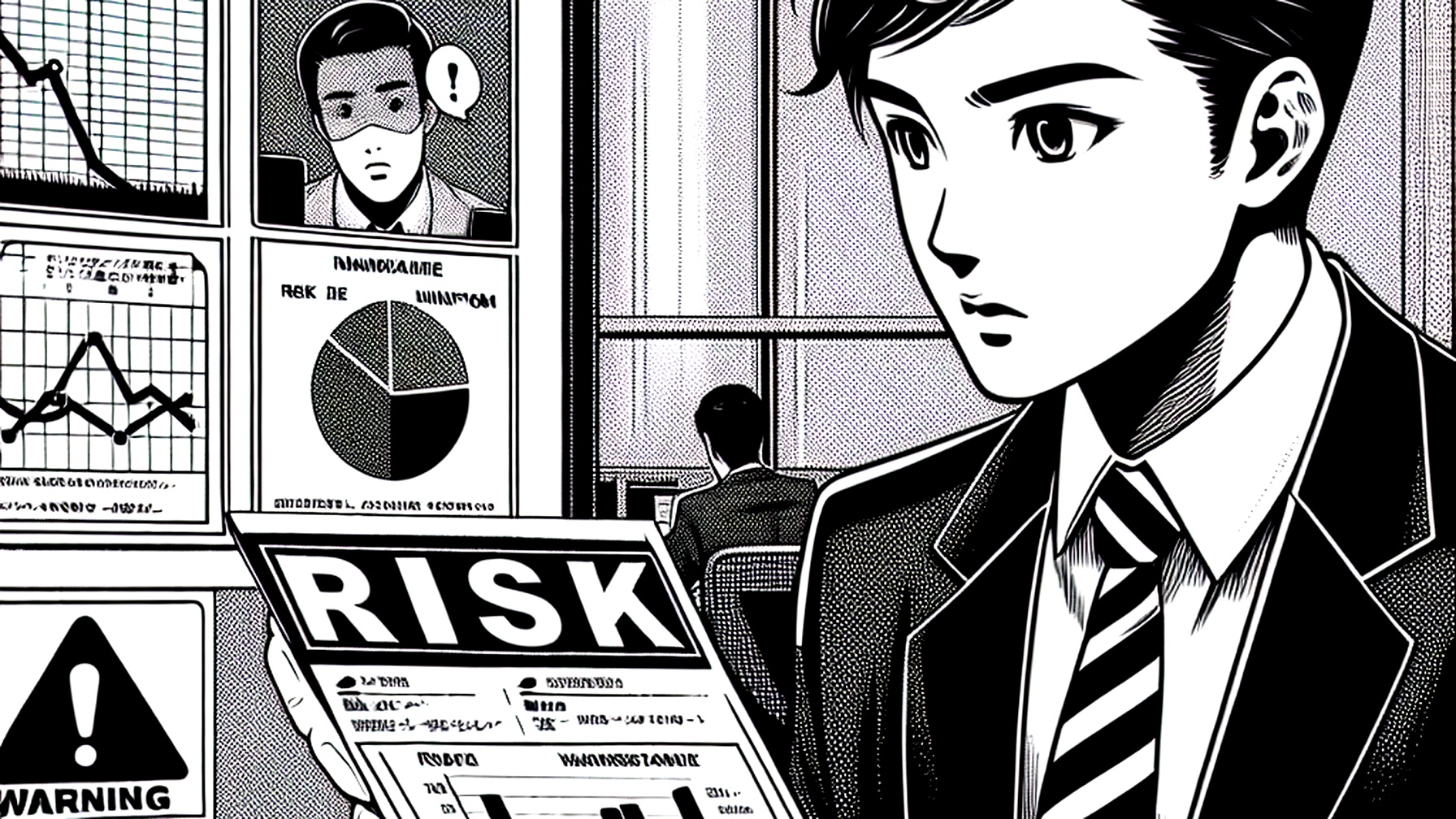
重要なのは、分配金の大半が変動金利の動きに影響される点です。J-REITの平均負債比率(LTV)は2025年時点で約45%と適度な水準に見えますが、その7割が短期・変動金利で調達されています。仮に2026年から政策金利が年0.5%引き上げられれば、単純計算で分配金利回りは平均0.3〜0.4ポイント低下する可能性があります。
一方で、2025年度税制改正によりREITへの機関投資家マネー流入が緩やかに増えると予測されています。これは上場インフラファンドとの損益通算ルールが整理されたためで、一定の下支え要因になるものの、個人投資家は配当利回り低下に敏感です。言い換えると、金利上昇局面では「利回りの低下幅が限定的な銘柄」を見極める必要があります。具体的には固定金利化比率が高い、あるいは平均借入期間が長い銘柄が候補になります。こうした指標は各REITの月次開示資料で簡単に確認できます。
資産価値変動と地政学リスク
ポイントは、物件価値がREITの基準価額を直接左右するという事実です。2022年以降、都心オフィスの鑑定評価は横ばいながら、物流施設はインフレヘッジ需要で上昇しています。ただし、日本経済研究センターのシミュレーションでは、アジアの地政学リスクが高まると観光客数が最大30%減少し、ホテル系REITの収益が大きく落ち込む可能性が示唆されています。
さらに、都市型物流施設は円安メリットを受けやすい半面、為替が反転すれば賃料上昇にブレーキがかかります。つまり資産タイプによる分散が不十分だと、想定外の外部要因で基準価額が大きくぶれる恐れがあります。個人投資家としては、ポートフォリオ内の物件種別や地域分散を確認し、特定セクターへの集中度が高い銘柄は比率を抑えるなどのコントロールが必要です。
税制面の注意点と2025年度制度
実は、REIT投資の税負担は配当課税と売却益課税の二重構造になっています。分配金は上場株式と同様に20.315%の申告分離課税が原則ですが、2024年から始まった新NISAでは年間360万円まで非課税投資枠が利用可能です。2025年度も同枠は維持される見通しで、期限は設けられていません。ただし非課税保有期間が無期限とはいえ、口座枠を使い切った分配金は課税対象に戻ります。
一方で、法人税関係では「REIT減価償却超過分の益金算入特例」が2027年3月期まで延長されました。この制度により運用会社は分配金原資を確保しやすい一方、物件売却時に利益圧縮効果が逓減しやすくなります。つまり2027年以降は減価償却余力の乏しい古いポートフォリオを抱える銘柄で分配金が伸び悩むリスクが高まるわけです。投資家は運用報告書の「減価償却累計額」と「含み益」のバランスを見て、税制変更の影響度を推測するとよいでしょう。
投資戦略を立てるためのチェックポイント
まず、保有期間とリスク許容度を言語化することが欠かせません。3年以内の短期で値上がり益を狙うなら、流動性が高い大型総合型REITを中心にする方が売却機会を確保しやすいからです。一方で、10年以上のインカム目的なら、物流や住宅特化型で長期賃貸契約比率が高い銘柄が候補になります。
次に、金利シナリオを複数想定した分配金シミュレーションが有効です。例えば政策金利が年1%まで上昇、空室率が2ポイント拡大という保守的条件で計算し、トータルリターンがプラスを維持できるか確認しましょう。さらに、海外REITを組み合わせて通貨分散を図ると、国内金利の上昇影響を緩和できます。ただし為替ヘッジコストが発生する点には注意が必要です。
最後に、REIT デメリット 2027年に対処するうえで欠かせないのが情報収集の継続です。運用会社が毎月公表する運用状況レポート、金融庁のEDINETに開示される有価証券報告書、そして日本取引所グループの統計データを定期的に確認することで、リスクの兆候を早期に察知できます。
まとめ
ここまで、金利上昇による分配金減少、資産価値の変動、税制変更といった複数の角度からREIT デメリット 2027年を整理しました。特に借入金利の固定化割合や物件種別の分散度は、リスク管理の要となります。記事で紹介したチェックポイントを踏まえ、まずは保有銘柄の負債構造とポートフォリオ構成を確認してみてください。自ら数字を追い続ける姿勢こそが、REIT投資で長期的な成果を得る最短ルートです。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 日本取引所グループ J-REIT統計 – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- 財務省 税制改正大綱(2025年度) – https://www.mof.go.jp
- 日本経済研究センター 地政学リスクと観光需要試算 – https://www.jcer.or.jp

