不動産投資を始めたいものの、「木造とRC造のどちらが良いのか分からない」と悩む方は多いものです。耐久性や修繕コスト、そして空室リスクまで考えると、構造の違いが長期収益に大きく影響します。本記事では、15年以上RC物件を扱ってきた視点から、初心者でも分かりやすくRC造の強みと物件選びのコツを解説します。読み終える頃には、自分の投資目的に合った物件を選ぶポイントが整理でき、最初の一歩を踏み出す自信が得られるはずです。
RC造とは何か、なぜ選ばれるのか
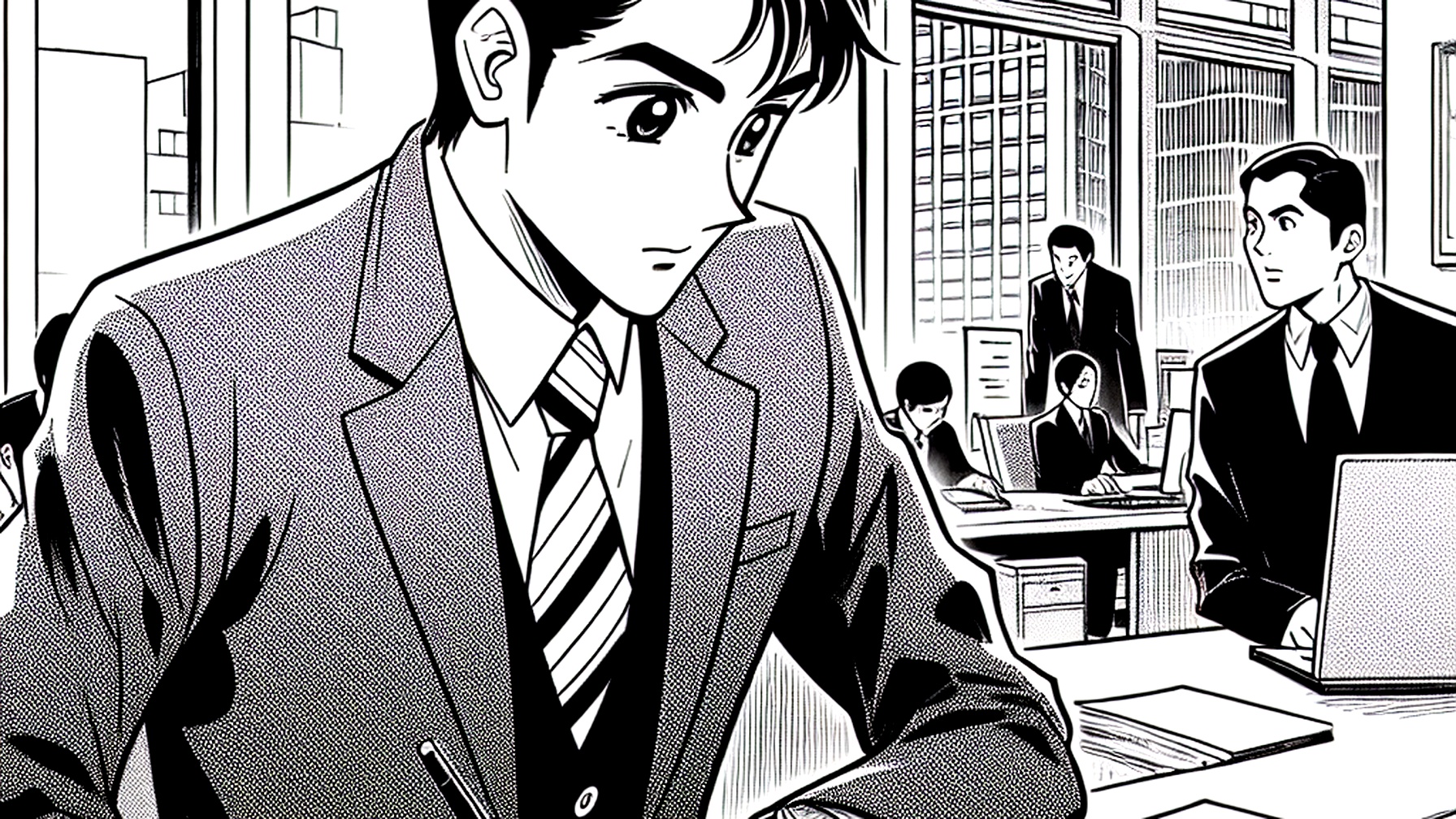
まず押さえておきたいのは、RC造が鉄筋コンクリート造(Reinforced Concrete)の略称であり、鉄筋で補強したコンクリートを用いる構造だという点です。頑丈な外壁と床が一体化するため、耐震・耐火性能が木造より高く、大規模災害後でも価値が保たれやすいとされています。
次に、国土交通省の2024年度「建築着工統計」によると、マンションの約九割がRC造で建てられています。つまり、RC造は賃貸住宅市場のスタンダードであり、入居者が設備や遮音性に対して抱く期待値も高い構造です。長期保有を前提とした投資家にとって、築二十年以降でも家賃水準が大きく下がりにくい点は見逃せません。
さらに、RC造は物理的耐用年数が四十七年と長く、減価償却を用いた節税効果も継続しやすい特徴があります。木造の耐用年数二十二年と比べると、帳簿上の資産価値を長く保てることが資金計画の安定に直結します。また、金融機関は耐用年数の長さを評価し、融資期間を二十五年以上に設定しやすいため、キャッシュフローがゆとりを持ったものになりやすいのです。
資産価値が落ちにくい理由を数字で確認
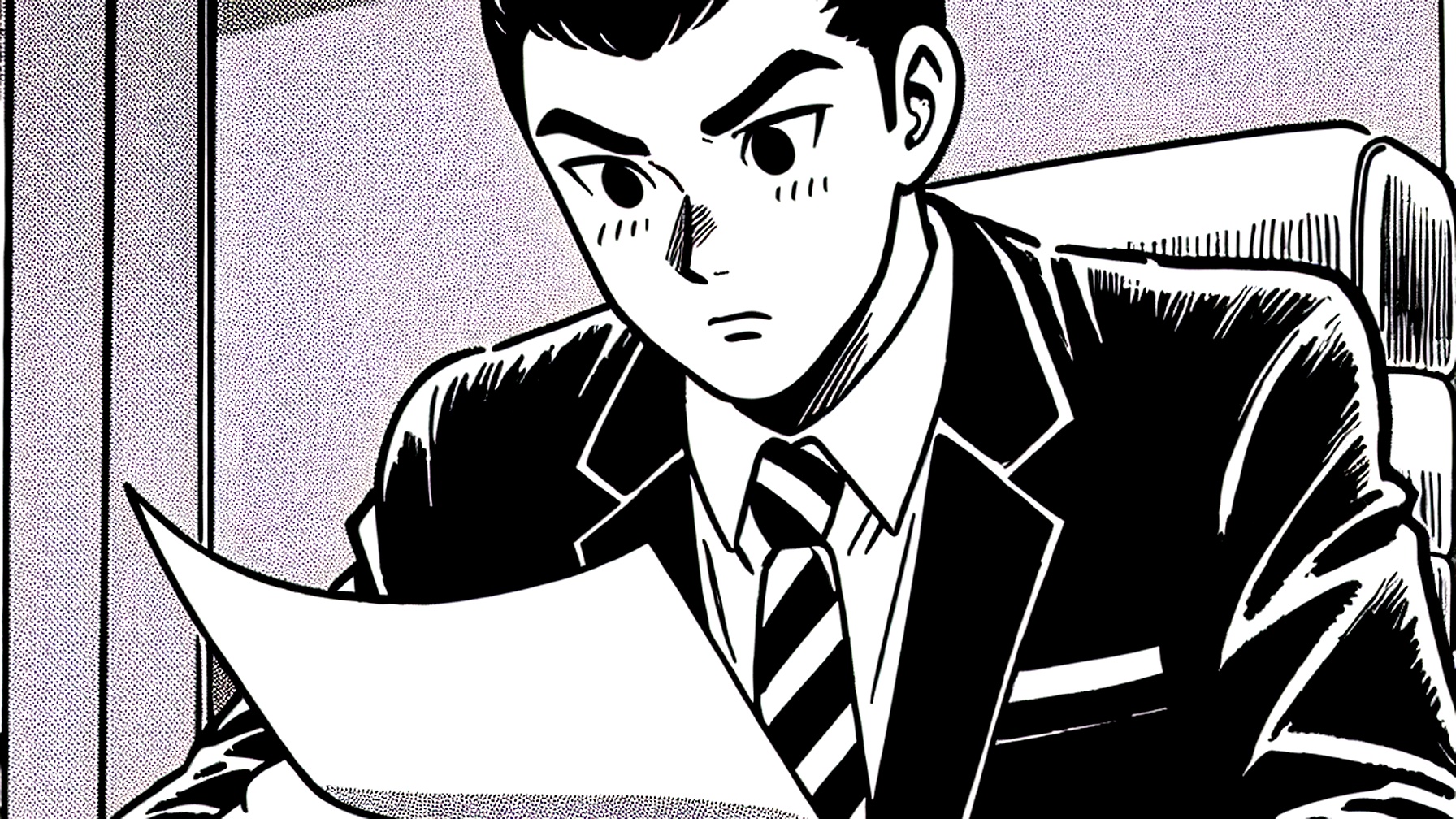
重要なのは、RC造が実際にどれほど価値を維持しているのかをデータで確かめることです。東日本不動産流通機構が公表する2025年上半期の首都圏中古マンション流通価格指数では、築三十年以上のRC造マンションでも新築時の約七割の価格を維持しています。これに対し、木造アパートは築二十年時点で新築時の五割を下回るケースが大半です。
つまり、出口戦略を考える際、RC造は売却益や担保評価の下落リスクが相対的に小さいと言えます。将来の借り換えや追加投資を見据えるなら、この差は無視できません。加えて、都市部のRCマンションは修繕積立金が計画的に積み上げられやすく、大規模修繕時の一時金負担が抑えられる点も資産価値維持を後押しします。
一方で、RC造は建築コストが高く、購入価格は木造の一・五倍前後になることが一般的です。しかし、空室率と修繕費を含めた総投資収益率(IRR)で比較すると、十年超の保有期間ではRC造が逆転するケースが多いと日本政策投資銀行の分析でも示されています。初期費用だけで判断せず、長期視点で収支を組み立てることが肝要です。
初心者に適したRC物件を見極めるポイント
ポイントは、立地と規模が投資家の資金力に合っているかを見極めることです。まず立地では、駅徒歩十分圏内かつ人口が増加傾向にあるエリアを選ぶと、家賃下落リスクを抑えられます。総務省「住民基本台帳人口移動報告」の最新データでは、二十三区では江東区や品川区が流入超過を維持しており、中長期的な賃貸ニーズが見込めます。
次に、規模の目安としては、総戸数三十戸未満のコンパクトなRCマンションが初心者向きです。大規模物件より価格帯が抑えられ、管理組合の意思決定もスピーディーなため、運営リスクを把握しやすくなります。物件価格は一億円前後が多いものの、自己資金二千万円と返済期間三十五年の融資で月々の持ち出しを抑える事例が増えています。
実は、内装や共用部のグレードもリーシングに直結します。宅配ボックスや高速インターネットを導入済みかどうかを確認し、未設置の場合は投資回収シミュレーションを行いましょう。設備投資を二百万円以内に抑え、家賃を一戸あたり三千円上げられれば、表面利回りは約〇・三ポイント改善します。細かな数字でも最終的な収益に大きく響くため、購入前に必ず試算することが大切です。
2025年度税制優遇と融資環境の最新動向
まず押さえておきたいのは、2025年度も住宅ローン控除が継続している点です。投資用物件は原則対象外ですが、自宅兼賃貸の区分マンションで一定条件を満たす場合、持分按分で控除が適用されるケースがあります。併せて、新築の賃貸住宅には固定資産税が三年間半額になる措置が引き続き設けられており、RC造の新築投資を後押ししています。
融資面では、2025年4月に日本銀行が長期金利の誘導目標を〇・七五%に引き上げたものの、地方銀行は投資用ローンの金利競争を継続中で、変動金利一・五〜二・〇%が主流です。RC造は耐用年数が長い分、三十年以上の長期融資が組みやすく、ローン期間を延ばすことで毎月のキャッシュフローを黒字化しやすい環境が維持されています。
また、環境性能を高めたRC新築物件には、2025年度「賃貸住宅省エネ改修等推進事業」の補助が活用できます。断熱性能等級四以上を満たし、省エネ性能ラベルを取得した場合、戸当たり最大六十万円の補助が受けられます。取得コストを抑えつつ、エネルギー効率の高い物件として入居者にアピールできるため、長期の空室リスク低減にも効果的です。
購入後の運用で押さえる三つの視点
重要なのは、購入後の運用フェーズで収益性を維持するための具体策を持つことです。第一に、賃料設定の見直しを年一回実施し、近隣競合物件と比較して五%以上乖離しないよう調整します。家賃改定の根拠を示すため、レインズや不動産情報サイトのデータを保存し、入居者との交渉材料にすると効果的です。
第二に、修繕計画を明確にし、共用部の塗装や防水工事を前倒しで実施します。国土交通省の「長期修繕計画作成ガイドライン」では、築十二年で屋上防水の改修を推奨していますが、RC造は構造体が堅固な分、表面劣化が目立ちにくい傾向があります。だからこそ、劣化が見え始める前に対応し、入居者満足度と資産価値を守る姿勢が欠かせません。
第三に、管理会社とのKPIを共有し、月次レポートで入居率・修繕履歴・苦情内容を確認します。データを蓄積すれば、次の物件購入時の与信審査で説得力のある資料として活用できるうえ、金融機関との交渉材料にもなります。つまり、日々の運営を可視化する仕組みを構築することこそ、複数棟保有へスムーズに進むための鍵なのです。
まとめ
RC造は購入価格こそ高めですが、耐震・耐火性能、長い耐用年数、資産価値の維持といった強みが総合収益を底上げしてくれます。立地と規模を慎重に選び、2025年度の税制優遇や長期融資を活用すれば、初心者でも過大なリスクを負わずに安定したキャッシュフローが期待できます。記事で紹介した選定基準や運用のコツを実践し、データに基づく意思決定を積み重ねることで、長期的な資産形成への道が開けるでしょう。まずは、自身の予算と投資目的を整理し、現地調査と収支シミュレーションから始めてみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 建築着工統計調査報告 2024年度版 – https://www.mlit.go.jp
- 東日本不動産流通機構 首都圏中古マンション価格指数 2025年上半期 – https://www.reins.or.jp
- 日本政策投資銀行 不動産市場動向レポート 2025年春号 – https://www.dbj.jp
- 総務省 住民基本台帳人口移動報告 2025年1月〜6月 – https://www.soumu.go.jp
- 国土交通省 長期修繕計画作成ガイドライン 改訂版2024 – https://www.mlit.go.jp
- 経済産業省 賃貸住宅省エネ改修等推進事業 2025年度概要 – https://www.meti.go.jp

