アパート経営を始めたばかりのオーナーの多くは、「管理をどうすればいいのか」と悩みます。入居者対応や修繕、家賃回収など業務は多岐にわたり、判断を間違えると収益が目減りしかねません。本記事では15年以上の実務経験をもとに、初心者でも理解しやすい管理方法の選び方を解説します。メリット・デメリットを具体例で示し、2025年現在の空室率や法律改正も踏まえて、あなたに合った「おすすめ」の管理スタイルを見つける手助けを行います。
管理スタイル選択が収益を左右する理由
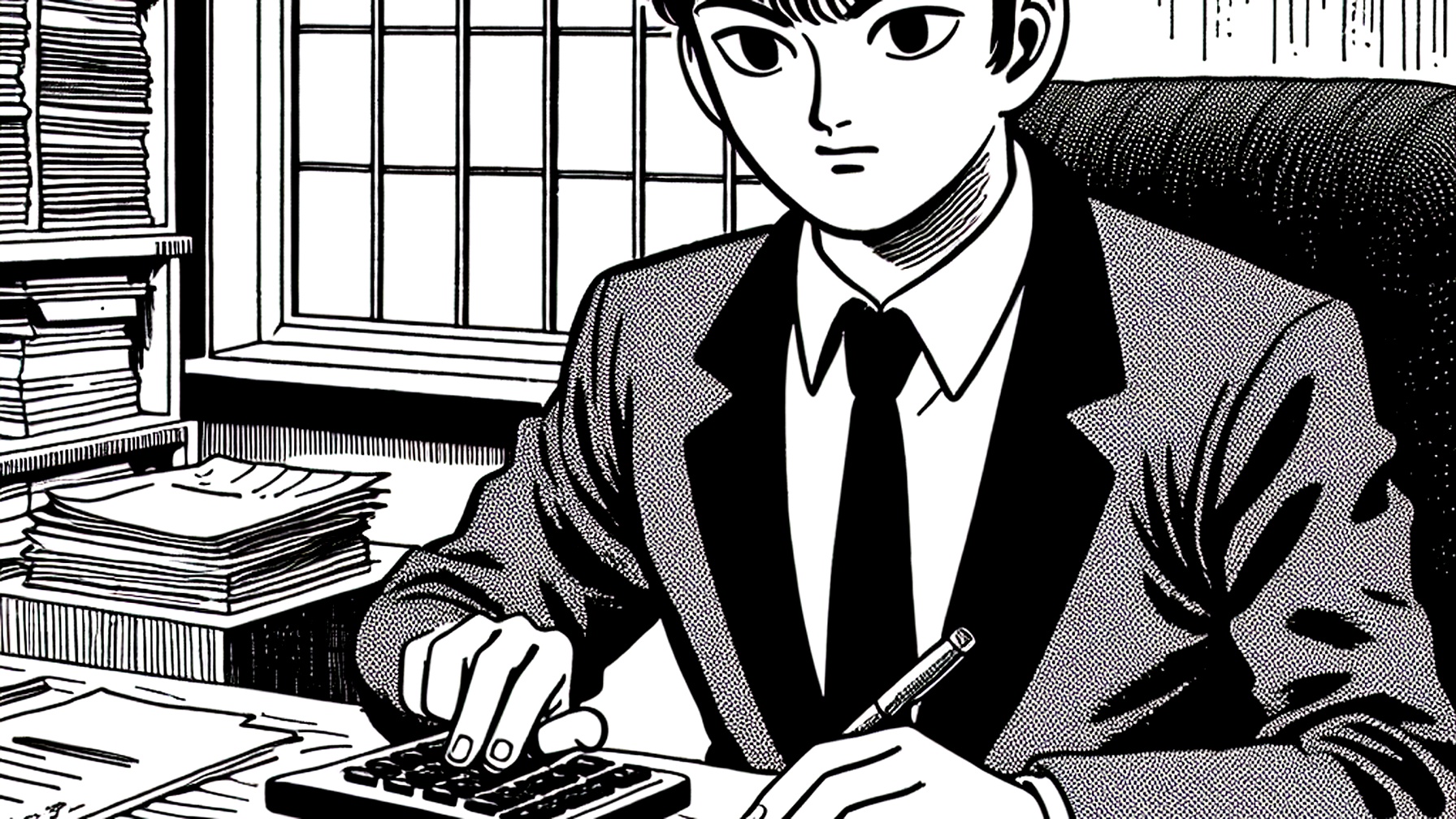
重要なのは、管理方法によって時間的コストと収益性が大きく変わる点です。国土交通省住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント低下しましたが、依然として高水準にあります。この状況下で空室期間を短く保つには、迅速な入居者募集と的確な賃料設定が欠かせません。その成否を決めるのが管理スタイルなのです。
まず、管理方法は大きく「自主管理」「一部委託」「一括委託」の三つに分かれます。自ら全業務を担えば手数料は不要ですが、専門知識と時間を要します。一方で管理会社に全面委託すれば業務負担は激減しますが、手数料として家賃の3〜5%が差し引かれます。つまり、労力を取るかコストを取るかのバランスが収益を左右します。
さらに、立地や物件規模によって最適解は変わります。都心の築浅ワンルームであれば広告力の強い管理会社に委託し、回転率を高めた方が有利です。一方、郊外のファミリータイプで長期入居が見込めるなら、オーナー自らきめ細かいフォローを行う戦略も成立します。このように、「物件特性×オーナーの目標」で管理スタイルを選び直すと無駄な支出を削減できます。
自主管理のメリットとリスクを正しく理解する

まず押さえておきたいのは、自主管理ならキャッシュフローが最大化しやすい点です。手数料を支払わないため年間で数十万円規模のコストカットが可能になり、その分を修繕や設備更新に回せます。また、入居者と直接コミュニケーションを取れるため、賃料交渉や退去理由をリアルタイムで把握できることも利点です。
しかし、実はリスクも同じくらい大きいことを忘れてはいけません。家賃滞納が起こった場合、督促から法的手続きまでを自分で行う必要があります。経験が浅いオーナーが対応を誤ると、回収不能に陥り損失が拡大します。また、建物の法定点検や契約更新書類の作成など、細かな決まりを怠ると行政指導や入居者トラブルを招きます。
さらに、入居者募集で苦戦しやすい点も見逃せません。不動産ポータルサイトへの掲載には専門業者のIDが必要な場合が多く、オーナー個人では露出が限定的になります。結果として募集期間が伸び、前述の高空室率と相まって機会損失が増大します。自主管理を選ぶなら、これらのリスクに備えた知識と外部ネットワークを構築することが前提となります。
管理会社委託で得られる専門サービス
ポイントは、管理会社を上手に活用すれば費用以上の価値が得られる点です。一般的な管理手数料は家賃の3〜5%ですが、募集広告費や24時間コールセンター費用を含む場合が多く、結果的に空室損失を抑えられます。特にオンラインでの入居申込やAI査定を導入する会社では、平均募集期間を20%短縮した実績も報告されています。
加えて、法改正への対応が迅速なのも大きな利点です。2025年4月に改正された賃貸住宅管理業法では、管理受託契約の透明性向上が求められ、敷金精算や修繕積立のルールが明確化されました。管理会社に委託していれば、これらの実務を自動的にアップデートしてくれるため安心感があります。
ただし、委託先の選定を誤ると手数料が高いだけで成果が伴わないケースもあります。比較する際は①入居率の実績、②対応エリアと担当者数、③IT活用度合い、④解約違約金の有無を確認しましょう。複数社に「収支シミュレーション」を提示してもらい、同じ条件で見積もることで適正価格を判断できます。
テクノロジーを活用して管理効率を高める方法
実は、近年の不動産テックの進歩により「自主管理+部分的なITツール」という第三の選択肢が注目されています。例えば、家賃の自動集金システムを利用すれば滞納率を1%未満に抑えた事例があります。また、スマートロックと連動したオンライン内見システムを導入すると、管理会社任せの場合より約30%多く反響を獲得できるといわれます。
オーナーアプリを使えば、入居者からの修繕依頼が写真付きで届き、業者手配の進捗もリアルタイムで確認できます。これにより、従来は電話とFAXで半日かかっていた業務が数分で完了し、入居者満足度の向上と早期退去の防止につながります。さらに、AIを用いた賃料査定ツールを活用すれば、周辺相場と過去の成約事例を自動分析し、適正賃料を迅速に設定できます。
ただ、導入コストと学習コストのバランスが課題です。初期費用が数十万円に上るシステムもありますが、家賃売上が年間1000万円を超える規模なら、回収に要する期間は1〜2年程度と試算できます。つまり、物件規模が大きいほどテクノロジー投資の費用対効果は高くなります。小規模オーナーは、まず無料ツールや低価格サブスクから試す方法が現実的です。
2025年時点で押さえたい法制度とコスト削減策
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続中の「住宅省エネ改修補助金」です。賃貸住宅であっても断熱改修や高効率給湯器の導入に対し、工事費の1/3(上限120万円)の補助が受けられます。省エネ性能を高めれば光熱費が下がり、入居者の満足度が上がるため、結果として空室対策にも寄与します。申請は工事着工前に登録事業者を通じて行う必要があり、予算枠が埋まり次第終了する点に注意が必要です。
また、固定資産税の軽減措置にも目を向けてください。耐震・省エネ改修を行った場合、翌年度の固定資産税が1/3または1/2減額される制度が2025年度まで延長されています。改修費用の5〜6年分を税金で回収できる場合もあり、中長期的に見ると管理コスト全体を圧縮できます。
一方で、サブリース契約に関する規制も強化されています。2025年10月時点では、賃料減額リスクや中途解約条件を事前に書面で説明しなければ行政処分の対象になります。管理会社任せにせず、契約書の条文を自ら確認する姿勢が欠かせません。オーナー自身が制度を正しく理解し、補助金と税制を組み合わせて運用コストを抑えることが、競争が激しい賃貸市場を生き抜く鍵となります。
まとめ
ここまで「アパート経営 管理方法 おすすめ」をテーマに、自主管理、管理会社委託、テクノロジー活用、最新制度という四つの視点から整理しました。自ら時間を投資して収益を高めるか、専門家に任せて安心を得るか、あるいはITツールで両者の良いとこ取りを目指すかは、物件規模とあなたのライフスタイルで変わります。まずは現在の収支と空室率を正確に把握し、自分に不足している機能を補う方法を段階的に導入してみてください。行動を起こすことでしか最適解は見えてきません。今日学んだ選択肢を試し、安定したキャッシュフローと資産価値の向上を手に入れましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査(2025年8月速報) – https://www.mlit.go.jp/toukeijouhou
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp
- 独立行政法人 住宅金融支援機構 2025年度 金利動向レポート – https://www.jhf.go.jp
- 一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 賃貸管理実態調査2025 – https://www.zenkan.jp
- 環境省 住宅省エネ改修補助金2025概要 – https://www.env.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート2025年4月号 – https://www.boj.or.jp

