不動産投資を始めたいけれど、「ローンを組んだ後、実際には誰が返済負担を背負うのだろう」「数字が苦手でシミュレーションに自信がない」という悩みは多くの初心者が抱えています。家賃収入で返済できると聞いても、空室や金利上昇を考えると不安は尽きません。本記事では、賃料と返済のバランスを見える化する方法を中心に、2025年10月時点の金利や制度を踏まえた最新の考え方を丁寧に解説します。読み終えるころには、自分で不動産投資ローンの返済シミュレーションを作り、リスクに備える具体的な行動が取れるようになるはずです。
不動産投資ローンの基礎を押さえる
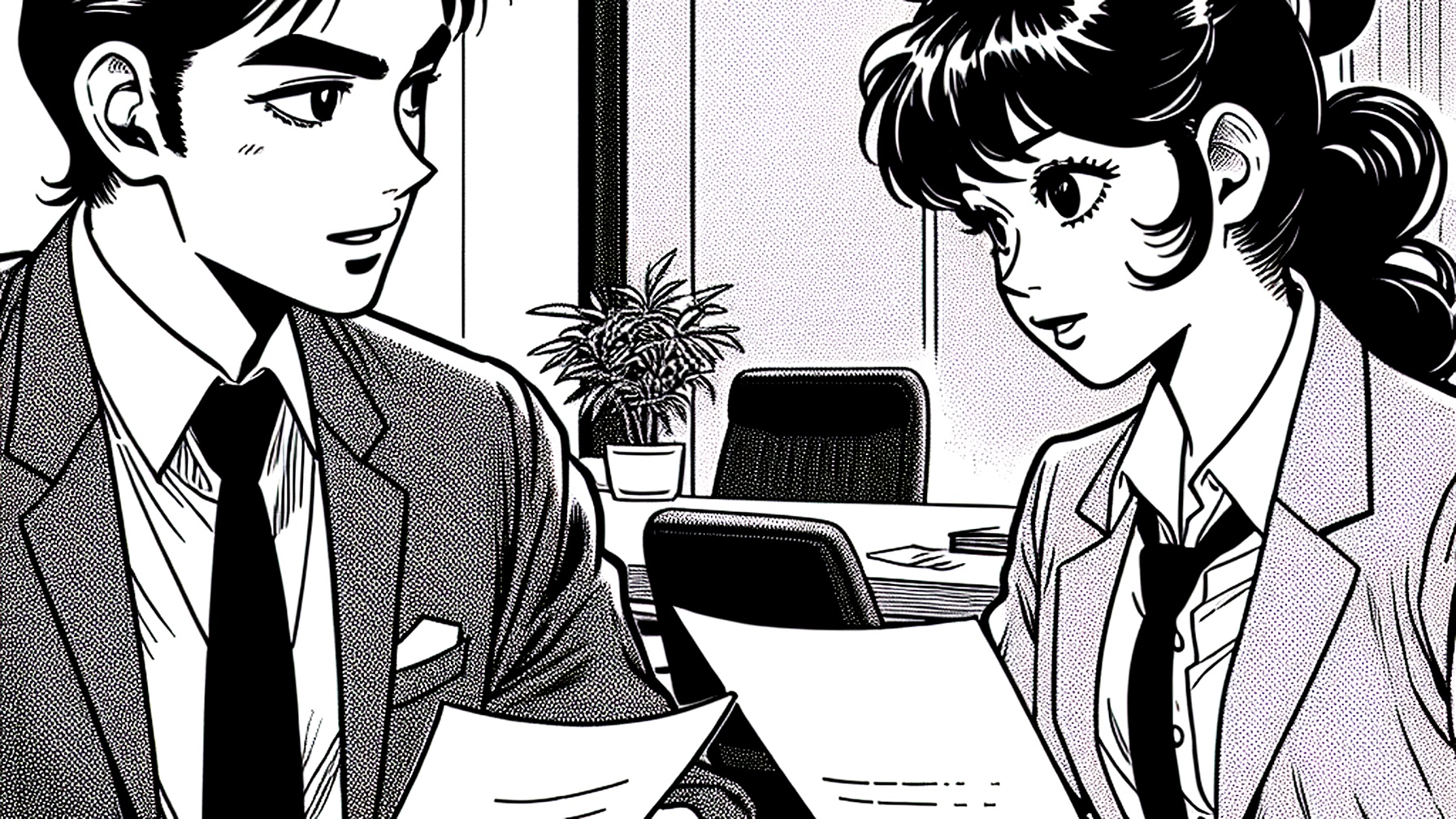
まず押さえておきたいのは、住宅ローンと不動産投資ローンの性格が異なる点です。自宅購入用の住宅ローンは本人の居住を前提に低金利や優遇税制が適用されます。一方で投資ローンは事業性を問われ、金利がやや高く、融資審査も厳格です。2025年10月時点で全国銀行協会が公表する平均金利を見ると、変動型が1.5〜2.0%、固定10年型が2.5〜3.0%となっており、自己資金が少ないほど金利は上振れしやすい傾向にあります。
重要なのは、金利だけでなく融資期間や元利均等返済か元金均等返済かといった条件が、毎月のキャッシュフローに大きく影響することです。たとえば同じ3,000万円を2%・30年で借りる場合、元利均等なら月々約11万円、元金均等なら初回およそ15万円から徐々に減る計算になります。投資用物件は利回りと返済額の兼ね合いが命綱となるため、返済方式の違いを十分理解しておきましょう。
返済義務は「誰が」負うのか
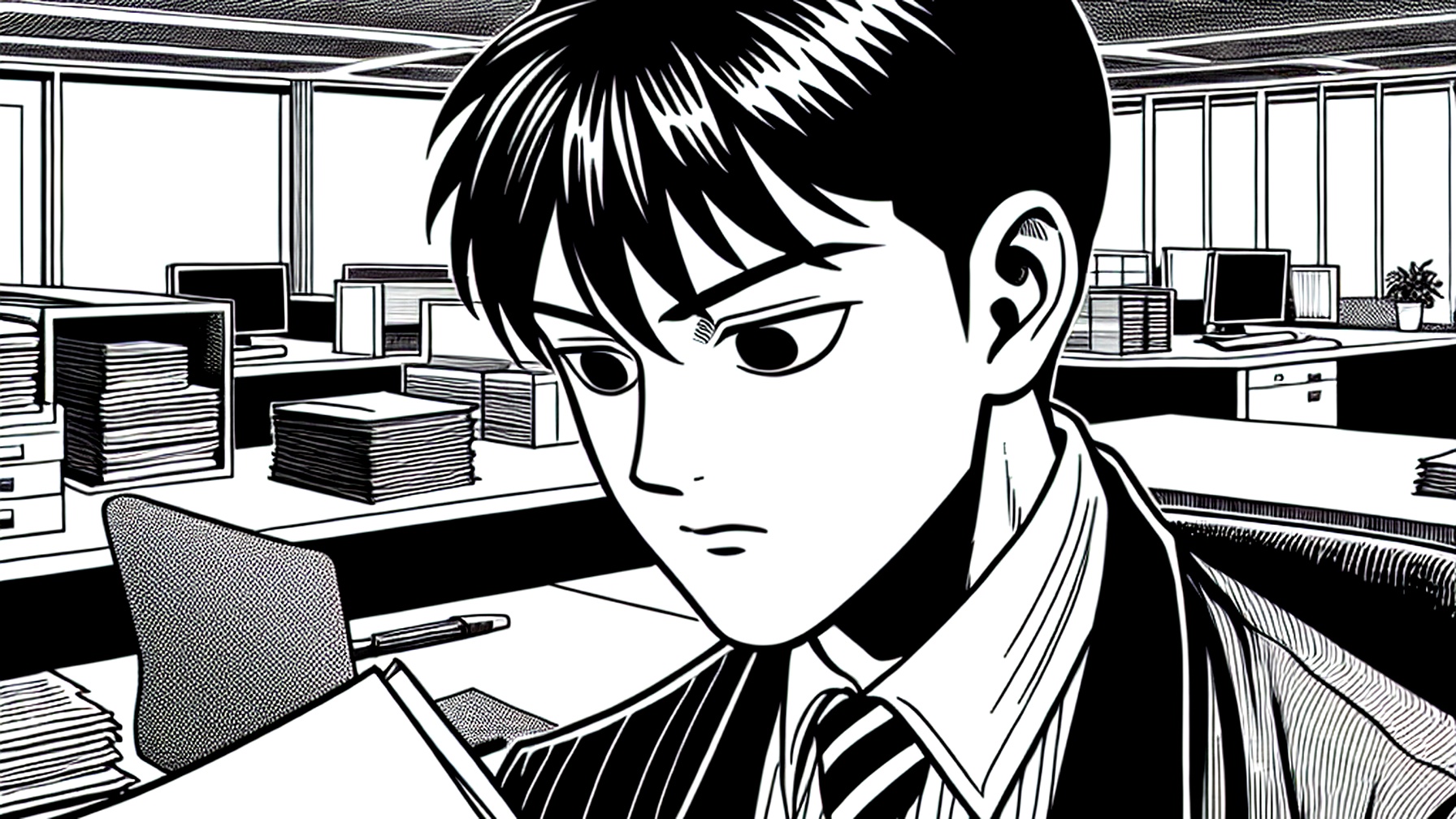
ポイントは、名義と実質負担を混同しないことです。契約上の債務者はもちろん投資家本人ですが、実質の返済原資は入居者が支払う家賃です。つまり「不動産投資ローン 誰が 返済シミュレーション」という疑問の答えは、「法律上は投資家、経済的には入居者やテナント」という二層構造にあります。
しかし、満室経営が永続する保証はなく、日本政策投資銀行の2024年度調査でも平均空室率は全国で11%程度と報告されています。万が一の空室時には債務者である投資家が不足分を補う必要があるため、手元資金が心許ない場合は返済リスクが一気に顕在化します。また、連帯保証を求められるケースでは配偶者や法人代表が責任を負うこともあるため、契約前に保証内容を細部まで確認しましょう。
返済シミュレーションの作り方
実はシミュレーションの手順自体はシンプルで、①年間家賃収入、②年間経費、③年間返済額、④税引後キャッシュフローを順番に並べるだけです。まず、公租公課や管理費、修繕積立といった経費を家賃の20〜30%と見込み、さらに空室ロスを平均空室率の11%よりやや厳しめの15%で設定します。こうすることで、想定外の出費が起きても赤字に転落しにくい計算になります。
次に返済額を算出します。3,000万円を2%・30年・元利均等で借りると年間返済は約132万円です。家賃収入が年間300万円、経費と空室を差し引いた手取りが180万円なら、返済後の税引前キャッシュフローは48万円になります。ここで金利上昇シナリオも忘れずに組み込みましょう。日本銀行が公表する長期金利見通しが1%上昇した場合、返済額は月1万円強増える試算となり、年間でおよそ12万円のキャッシュフローが削られます。
最後に税金を加味します。2025年度の不動産所得は総合課税で累進税率が適用され、課税所得が695万円以下なら所得税率は20%、住民税と合わせるとおよそ30%です。先ほどの48万円に税率30%をかけると手残りは約34万円となり、次年度以降の修繕に備えて積み立てておくと安心です。
数値例で学ぶキャッシュフロー分析
基本的に数字は具体的に把握してこそ意味があります。ここでは区分マンションと一棟アパートのケースを比較し、キャッシュフローの違いを体感してみましょう。
区分マンションを2,000万円で購入し、80%を2%・25年で借り入れる場合、年間返済は約102万円です。家賃収入が年間120万円、経費率30%とすると手取りは84万円、差し引きキャッシュフローは▲18万円となり、自己資金で穴埋めが必要になります。一方、郊外の木造アパートを6,000万円で取得し、70%を1.8%・30年で借りると、年間返済は約331万円です。年間家賃が600万円、経費率25%、空室率15%で計算すると手取りは382万5千円、キャッシュフローは51万5千円となり、空室が増えない限り黒字が期待できます。ただし木造は大規模修繕費が早めに発生しやすいため、純粋な利回りだけで優劣を判断しない姿勢が重要です。
このように同じ自己資金比率でも、物件タイプや融資条件で結果がガラリと変わります。シミュレーションは一度作って終わりではなく、年に1回は家賃動向と金利をアップデートし、将来のキャッシュフローをチェックしてください。
2025年度の制度・金利動向を踏まえた戦略
2025年度は、不動産投資家にも関係する「中小企業経営強化税制」が延長され、一定の省エネ設備を導入した賃貸物件では特別償却が適用可能です。期限は2027年3月までとされ、早めの計画が節税メリットを高めます。また、国土交通省の「賃貸住宅管理業法」施行状況によって管理会社の質が底上げされつつあり、適切な管理委託先を選ぶことで空室リスクを低減できる環境が整ってきました。
金利面では、全国銀行協会の統計が示す通り、変動型1.5〜2.0%という低金利が続いていますが、日本銀行は2025年7月に長短金利操作の柔軟化を発表しました。長期金利が1%前後で推移する中、固定型の上昇余地が意識されており、借り換えのタイミングを見極める目が求められます。実務的には、変動型で借り入れ、将来の金利リスクをヘッジするために繰上げ返済資金を別口座に積み立てる戦略も有効です。
さらに、金融機関は2024年に続き、属性よりも事業計画を重視する審査方針を強めています。銀行担当者に提出する返済シミュレーションの精度が高いほど、好条件を引き出しやすくなるため、この記事で紹介した手順をベースに綿密な計画書を作成して臨みましょう。
まとめ
本記事では、不動産投資ローンの基礎、返済義務の所在、具体的な返済シミュレーションの手順、数値例によるキャッシュフロー分析、そして2025年度の制度や金利動向を順に解説しました。要するに、名義上の債務者は投資家自身でも、家賃が返済の原資である点を正しく理解し、空室や金利変動に備えた保守的なシミュレーションを行うことが成功の鍵です。読者の皆さんも、手元の電卓や表計算ソフトを使って今すぐ自分の計画を可視化し、リスクとリターンのバランスを数字で把握してください。そうすれば、 bankenとの交渉や物件選定でも自信を持って判断できるようになるでしょう。
参考文献・出典
- 全国銀行協会 – https://www.zenginkyo.or.jp
- 日本銀行「金融政策決定会合結果」 – https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「賃貸住宅管理業法に関する資料」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本政策投資銀行「全国空室率調査2024」 – https://www.dbj.jp
- 財務省「令和7年度税制改正資料」 – https://www.mof.go.jp

