アパート経営に興味はあるものの、「物件をどう選べばいいのか」「修繕費はどれくらい見込むべきか」と悩む方は多いでしょう。物件選びを誤ると空室が長引き、修繕費を甘く見積もるとキャッシュフローが崩れます。本記事では、2025年10月時点の最新データを交えながら、初心者でも実践できる選び方のコツと修繕費の考え方を解説します。読み終えるころには、自分に合った物件を見極め、長期的に安定収益を生む計画を立てる力が身につくはずです。
アパート経営を始める前に知っておきたい市場動向
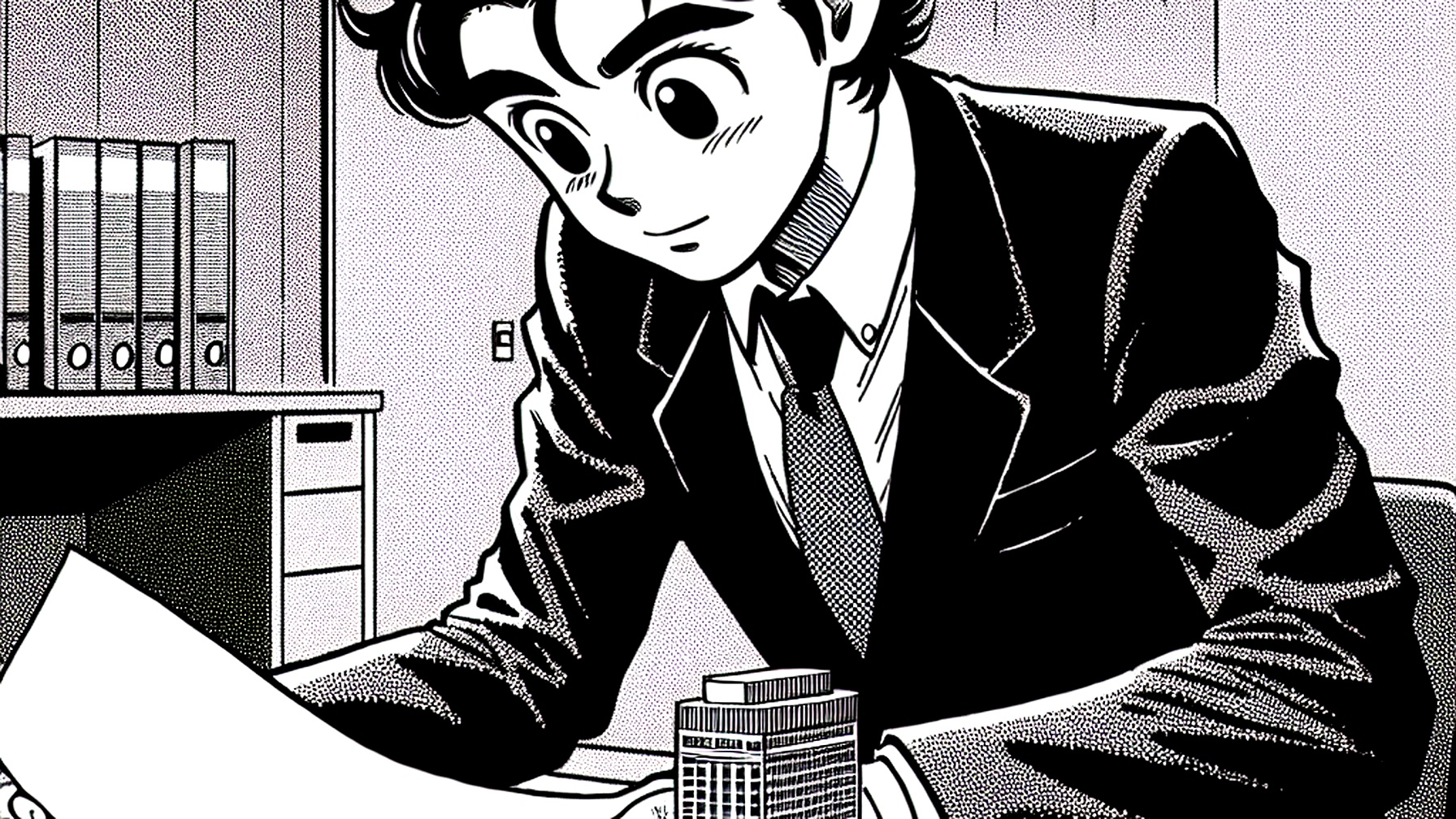
まず押さえておきたいのは、全国的な空室率の推移です。国土交通省の住宅統計によると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年比0.3ポイント改善しました。つまり需給バランスはやや好転していますが、依然として5戸に1戸が空いている計算になり、立地と管理の差が収益を大きく左右します。
さらに注目すべきは人口動態です。総務省の住民基本台帳ベースでは、都市圏への人口集中が続き、地方中核市でも二極化が進んでいます。実は同じ県内でも駅徒歩圏は入居ニーズが底堅い一方、郊外では空室率が30%を超えるエリアもあります。この違いを理解せずに物件を選ぶと、家賃を下げても入居者が集まらないリスクが高まります。
一方で金利環境は依然として低水準です。日本政策金融公庫の2025年度融資金利は長期固定で1.5%前後にとどまり、借入コストは抑えやすい状況です。低金利は投資家にとって追い風ですが、収入減や空室リスクに備えてキャッシュフローを厚めに確保する姿勢が欠かせません。
成功する物件選びのチェックポイント
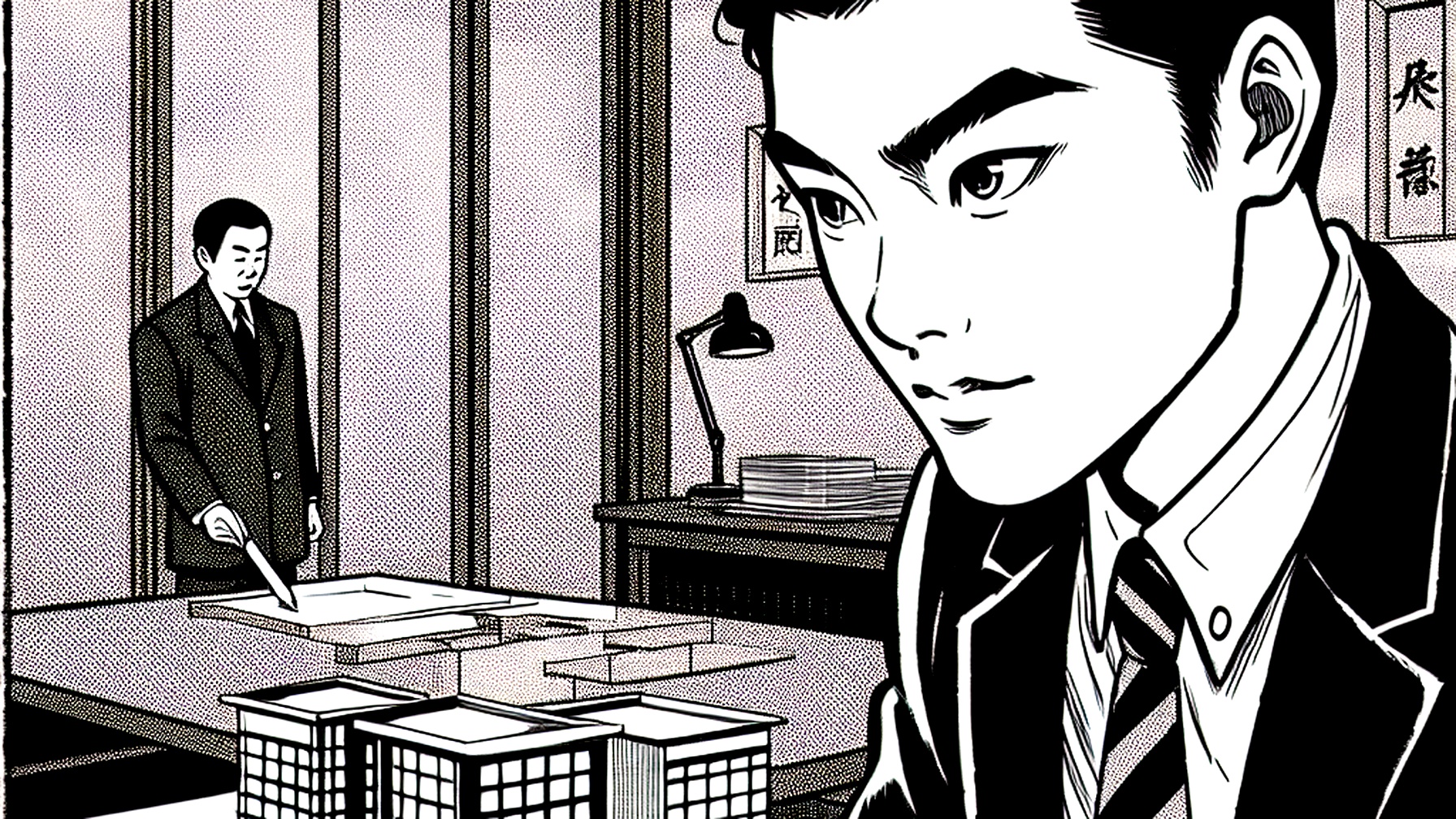
ポイントは「立地・建物・収支」の三位一体で判断することです。立地では駅からの徒歩分数だけでなく、周辺の雇用環境や大学、商業施設の分布を調べると入居ターゲット像が具体化します。例えば、単身者中心なら家賃6万円前後が相場の駅近ワンルームが有効ですが、ファミリー層狙いなら学校区や公園も確認しておきたい要素です。
建物については築年数だけでなく構造と設備を見逃せません。鉄骨造は木造より耐用年数が長く融資期間を伸ばしやすい一方、修繕費は高くなりがちです。一方、木造アパートは初期費用を抑えやすいものの、屋根や外壁のメンテナンス周期が短いため、長期的な修繕計画が不可欠です。つまり構造ごとの修繕コストを理解したうえで利回りを試算する姿勢が求められます。
収支シミュレーションでは、家賃下落率と空室率を保守的に設定することが肝心です。具体的には、家賃を年間1%下落、空室率を25%と置いても黒字になるか確認しましょう。さらに管理委託費や固定資産税に加え、後述する修繕積立を月額収支に組み込むと、想定外の出費に慌てずに済みます。
修繕費を見抜くための建物診断と費用計画
重要なのは、購入前にプロによるインスペクション(建物診断)を実施し、修繕が必要な部位と時期を把握することです。外壁クラックや屋上防水の劣化は放置すると雨漏りを招き、1回の補修で数百万円かかるケースも珍しくありません。事前診断で10年以内の大規模修繕費を予測し、取得価格に上乗せして利回りを計算する姿勢が求められます。
言い換えると、修繕費は確率ではなく必然のコストです。国土交通省の「住宅リフォーム実態調査」では、築20年超の共同住宅で外壁・屋根修繕に要した平均額は1戸当たり年13万円という結果が出ています。この数値を参考に、戸数×13万円を年間修繕予算の最低ラインとし、設備更新費を別途加味するのが現実的です。
具体的な積立方法として、毎月の家賃収入のうち10〜15%を修繕積立口座に移すと、大規模工事の支払い時に自己資金を崩さずに済みます。また、2025年度の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」では、耐震補強や省エネ改修に対して最大100万円/戸の補助が受けられます。補助条件を満たす改修は積極的に検討し、実質負担を軽減することが賢明です。
キャッシュフローに与える修繕費の影響
基本的にキャッシュフロー(手残り資金)は「家賃収入−運営費−ローン返済」で求めますが、運営費の中でも修繕費は金額変動が大きく、予算取りが甘いと黒字と赤字が逆転します。たとえば年間家賃収入が1,000万円、ローン返済が600万円、その他運営費が150万円の場合、修繕費を50万円と見込めば年間手残りは200万円です。しかし実際に屋根防水工事で200万円かかった年は−50万円に転落します。
このような事態を防ぐには、長期修繕計画を作成し、5年ごとに必要額を見直すことが効果的です。加えて、減価償却費を活用した節税も見逃せません。国税庁の通達では、木造アパートの法定耐用年数は22年ですが、中古物件は残存年数で計算できるため、毎年の課税所得を抑えられます。つまり減価償却という「紙面上の費用」をプラスし、実際のキャッシュアウトと切り分けることで、資金繰りを安定させられるわけです。
一方で、設備故障は突然発生します。給湯器の交換は1台20万円前後、エアコンは1台10万円程度が相場です。複数戸の同時故障に備え、短期的な予備資金として家賃収入の3か月分を別途プールしておくと、金融機関への返済を滞らせずに対応できます。
2025年度の税制・補助制度を活かすコツ
実は税制や補助制度を理解するだけで、修繕費の負担を数十万円単位で軽減できる場合があります。2025年度の所得税法では、白色申告でも30万円未満の修繕資材は全額経費計上が可能です。細かい交換部材は分割発注し、1回の請求を30万円未満に抑えることで即時経費化しやすくなります。
また、固定資産税については築年数25年以上の木造アパートで、断熱材補強や高効率給湯器を設置すると翌年度の税額が最大1/3軽減される自治体もあります。期限付きの措置が多いため、工事発注前に自治体窓口へ確認し、適切な申請スケジュールを組むことが収益力向上につながります。
さらに、前述の長期優良住宅化リフォーム推進事業を活用する場合、エネルギー計算や耐震診断を専門家に依頼する必要があります。その費用も補助対象となるケースがあり、トータルコストを抑えやすい点は見逃せません。補助申請は年度内予算に限りがあるため、物件取得前から計画を立て、工事スケジュールと並行して書類準備を進めるとスムーズです。
まとめ
ここまで、空室率の現状から物件選びの具体策、修繕費の予測方法、税制・補助制度の活用まで解説しました。最も大切なのは、立地・建物・収支を一体で考えながら、修繕費を“予想外”ではなく“予定通り”のコストとして扱うことです。インスペクションと長期修繕計画を活用し、家賃収入の一部を積み立てておけば、突然の工事でも資金繰りに困りません。これから物件を探す方は、必ず修繕積立を含めたシミュレーションを行い、補助制度の期限も確認しながら行動を起こしてみてください。安定したキャッシュフローを実現し、長期にわたるアパート経営の成功を目指しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月速報 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 住民基本台帳人口移動報告 2025年版 – https://www.stat.go.jp
- 日本政策金融公庫 融資金利情報(2025年度) – https://www.jfc.go.jp
- 国土交通省 長期優良住宅化リフォーム推進事業 2025年度概要 – https://www.mlit.go.jp
- 国税庁 タックスアンサー「不動産所得と必要経費」2025年改訂版 – https://www.nta.go.jp

