年収はそこそこあるのに預金はなかなか増えず、「このまま働き続けても将来が不安」と感じる人は多いはずです。とくに年収700万円前後の会社員は税負担が重く、手取りの伸びが鈍いため資産形成の速度が落ちがちです。そんな悩みを解決する選択肢として、安定収益が期待できる不動産投資が注目されています。本記事では、同じ年収帯の会社員が実際に物件を取得してキャッシュフローを生み出した成功事例を紹介しながら、2025年10月時点で有効な制度や市場データを交えて、初心者でも失敗しにくい進め方を解説します。
年収700万でも不動産投資は十分に可能か
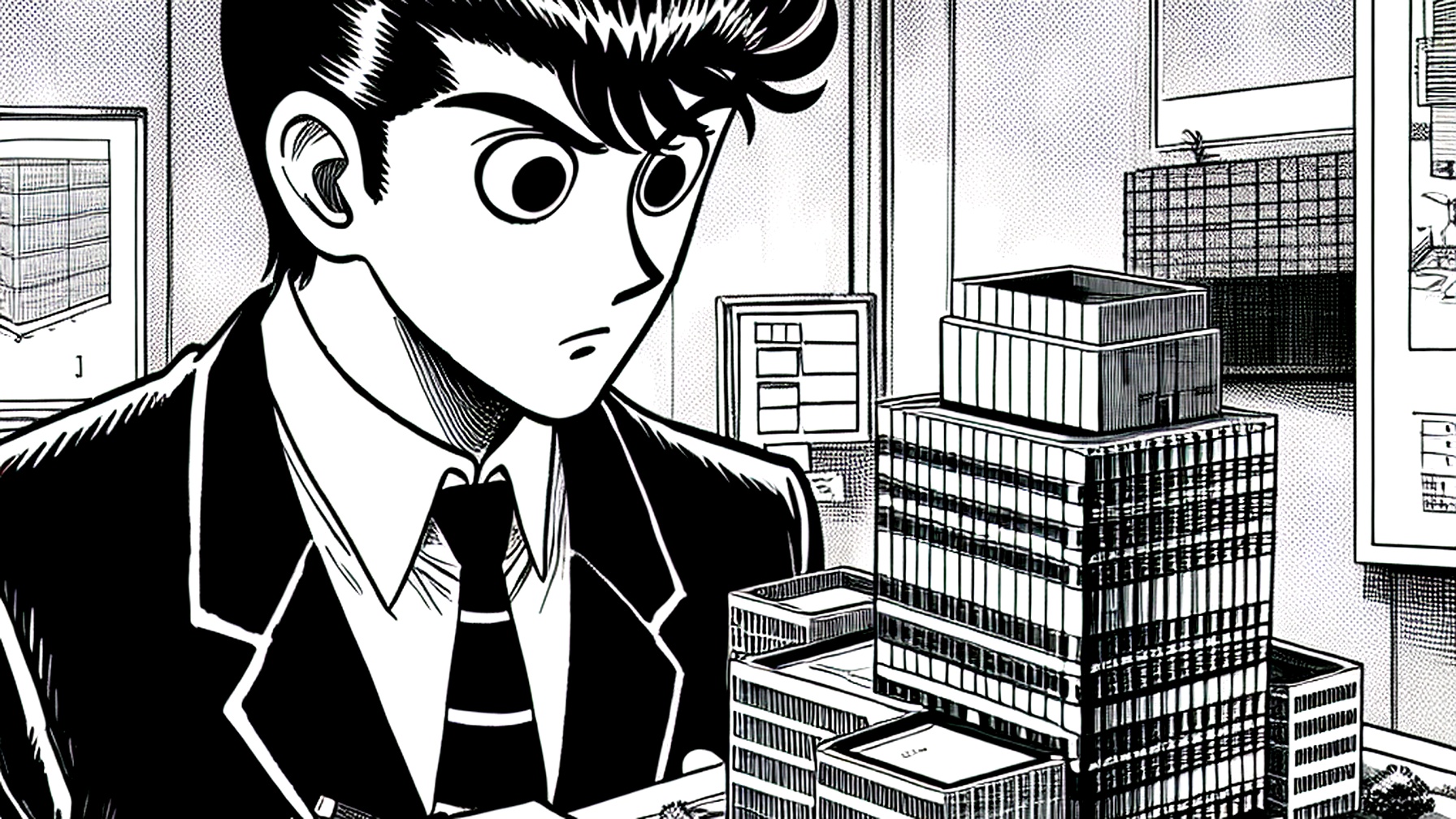
まず押さえておきたいのは、年収700万円という水準が金融機関の融資審査で有利に働く点です。国土交通省の「民間住宅ローンの実態調査」(2024年度版)によると、投資用ローンの平均年収は約660万円で、700万円は平均をわずかに上回ります。つまり標準的な自己資金を確保できれば、信頼度の高い借り手として扱われやすいのです。
次に自己資金の目安ですが、成功事例では物件価格の20%前後を用意した人が多数派でした。たとえば3,000万円の中古マンションなら600万円が必要です。この程度なら、退職金の前借りや過度なカードローンに頼らずに達成できます。重要なのは、自己資金を厚くすると返済比率が下がり、賃料収入でローンを支払ったあとに残るキャッシュフローが安定する点です。
さらに金融機関の審査基準は「年間返済額÷年収」が30〜35%以内が目安とされます。年収700万円なら最大返済額はおよそ210〜245万円です。金利2.0%、期間25年、元利均等返済なら借入上限は約3,800万円となり、自己資金との合わせ技で4,500万円程度の物件まで狙えます。つまり購入対象が十分に確保できるため、地方ワンルームだけでなく都心の築浅区分や小規模アパートも検討可能です。
成功事例に学ぶ資金計画の立て方
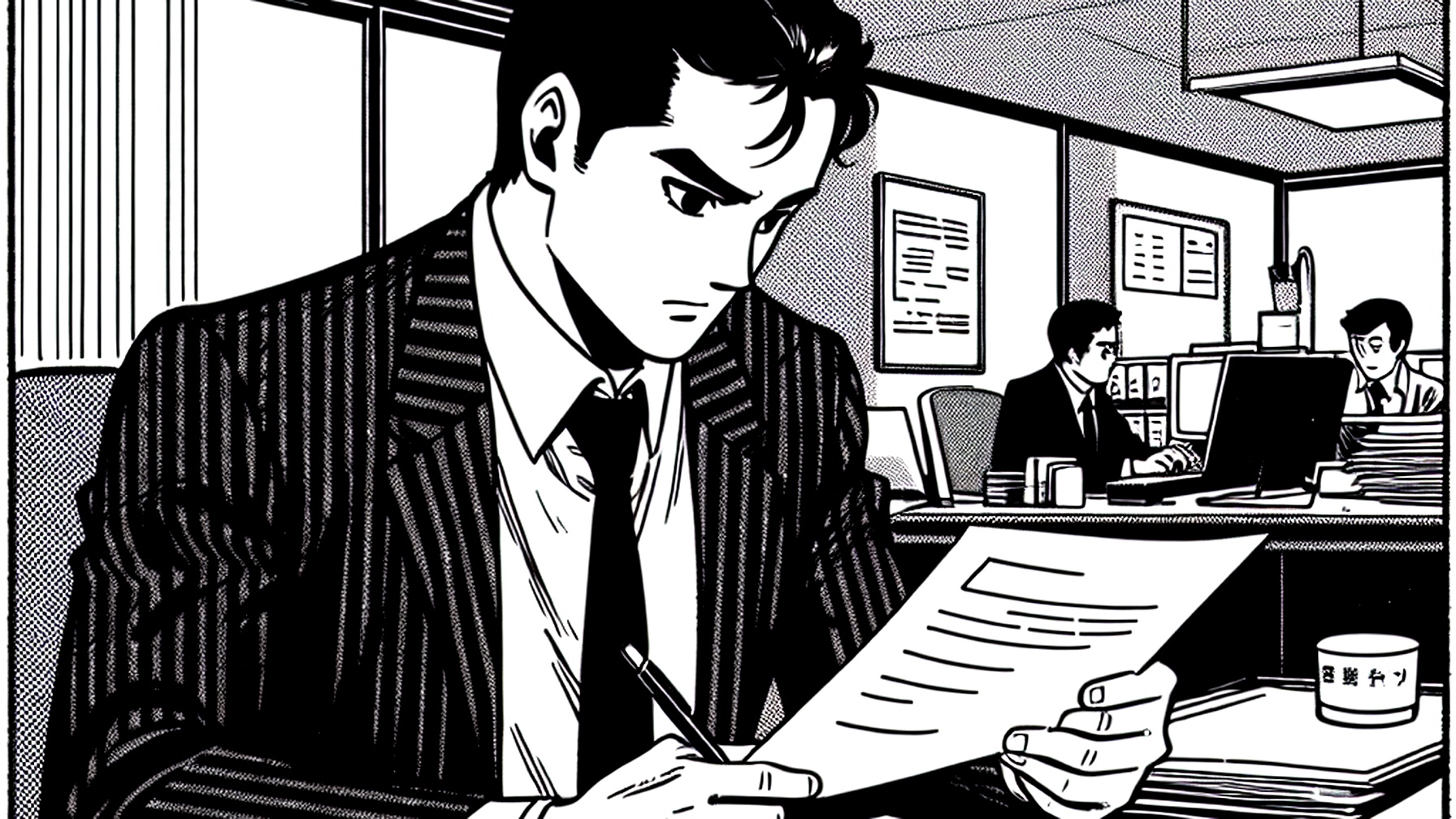
ポイントは「保守的なシミュレーションで先にリスクを見積もる」ことです。東京都内在住のAさん(38歳、年収700万円)は、利便性の高い郊外駅近マンションを選択しました。物件価格は2,980万円、自己資金600万円、ローンは変動金利1.4%、期間30年です。毎月返済は約9万7,000円、管理費と修繕積立金を合わせて約1万5,000円、固定資産税は月換算で6,000円でした。
Aさんは家賃11万円で賃借人を確保したため、手取りキャッシュフローはおよそ1万2,000円です。一見すると利益は小さく見えますが、ローン元金が毎月6万円程度減少している点に注目です。言い換えると、年間約72万円の資産が自動的に積み上がる構造になっています。実はこの「元金返済益」を加味すると、実質利回りは6%を超えます。
また、Aさんは修繕リスクを想定し、別口座に毎月1万円を積み立てました。結果として突発的な設備交換にも動じず、キャッシュフローを赤字にせず運営を継続しています。つまり成功事例の共通項は、「楽観シナリオで突っ走らず、最悪を想定して資金を寝かせる余裕を持つ」ことだといえます。
キャッシュフローを最大化する具体策
重要なのは、家賃収入を増やすだけでなく支出を減らす二方向の工夫を同時に行う点です。まず家賃については、国土交通省の賃貸住宅市場データによれば、築10年以内の物件は築20年超より平均1割高い家賃水準を保っています。そのため少し高くても築浅の区分マンションを選ぶと、長期にわたり収入が落ちにくくなります。
一方で支出削減の切り札が「管理コストの最適化」です。管理会社の手数料は賃料の5%が一般的ですが、複数社に見積もりを取り、4%以下に抑えた成功事例もあります。さらにインターネット無料設備を導入し、広告費を削減したオーナーもいました。この施策は初期投資が15万円ほどかかるものの、空室期間を平均で半減させたとの報告があります。
また、2025年度の所得税法上の減価償却費を最大限活用する戦略も有効です。中古木造アパートを購入したBさんは、法定耐用年数の残存期間を基に4年間で一気に償却し、課税所得を圧縮しました。短期では帳簿上の赤字となったものの、手取り収入を増やしつつキャッシュフローを黒字化できた点が特徴です。つまり節税と実質収益を両立させる仕組みを理解すると、同じ物件でも手残りが大きく変わります。
2025年度の制度と市場環境を味方にする
実は、2025年度は不動産投資家にとって追い風となる制度がいくつか継続しています。たとえば「住宅ローン減税」は居住用ですが、マイホームとの併用で借入総額を抑えやすくなるため、投資用ローンの審査が通りやすくなるケースがあります。また、地方自治体が実施する空き家活用補助金も2025年度まで延長されており、特定エリアでのリフォーム費用を最大100万円まで支援しています。期限付きのため対象地域や応募時期を事前に確認すると良いでしょう。
日本銀行のマイナス金利政策は2025年10月時点でも小幅緩和が続き、民間金融機関の投資用ローン金利は1〜3%台が主流です。内閣府「中長期の経済財政に関する試算」では今後数年間も低金利環境が続く前提が示されており、長期固定金利を確保する好機といえます。ただしインフレ率が徐々に上昇している点を考慮し、固定と変動を組み合わせるミックスローンも検討したいところです。
一方で空室リスクについては、総務省「住民基本台帳人口移動報告」によると都心5区の転入超過が再び拡大しています。この流れに乗れば、ワンルーム需要が底堅く推移する見込みです。しかし地方の人口減少が進む地域では供給過多が深刻化しているため、エリア選定はより慎重に行う必要があります。つまりデータを読み解き、成長エリアへ資金を集中させる発想が欠かせません。
ポートフォリオ拡大までのロードマップ
まずは1戸目を安全に運営し、キャッシュフローの実績を金融機関に示すことが次の融資への近道です。実績が1年間安定すると、追加融資の審査難易度が一段階下がるケースが多く、レバレッジを高めやすくなります。たとえばAさんは2年目に中古区分をもう1戸購入し、家賃合計を22万円に増やしました。
次のステップは「法人化」の検討です。課税所得が900万円を超える水準になった段階で、法人税率の方が低くなる場合があります。法人成りにより、給与所得控除や役員報酬の分散が可能になり、手取りを増やせることがメリットです。ただし設立費用や経理負担も増すため、税理士と試算を行い、損益分岐点を把握してから決断しましょう。
最後に出口戦略です。築25年を超えたタイミングでリノベーションを行うか、売却益を確定して次の物件に乗り換えるかを検討します。国土交通省「不動産価格指数」によれば、築30年超でも駅近物件は価格下落が緩やかな傾向があります。つまり立地の良い物件は出口が広いため、長期保有と売却の両方の選択肢を残せるのです。
まとめ
年収700万円の会社員でも、自己資金とリスク管理を適切に行えば不動産投資で安定収益を得られます。大切なのは保守的なシミュレーション、管理コストの最適化、そして2025年度に継続中の低金利と補助制度を賢く利用する姿勢です。まずは小さく始めて実績を積み上げ、金融機関からの信頼を得たうえでポートフォリオを拡大する流れが成功への王道と言えるでしょう。今こそデータを読み解き、行動を起こす絶好のタイミングです。将来の自分に後悔を残さないために、一歩踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「民間住宅ローンの実態調査(2024年度)」 – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省「不動産価格指数」 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省「住民基本台帳人口移動報告」 – https://www.soumu.go.jp
- 日本銀行「金融政策決定会合議事要旨」 – https://www.boj.or.jp
- 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(2025年7月) – https://www5.cao.go.jp

