不動産投資は「ミドルリスク・ミドルリターン」と言われ、株式より安定しやすいと紹介されることが多いです。しかし、実際に物件を持つと「家賃が入らない月がある」「想定外の修繕費が続く」といった声も聞こえてきます。この記事では、私自身と受講生たちのデメリット 体験談をもとに、初心者がつまずきやすいポイントを整理します。読めば、物件選びや資金計画で避けるべき穴が見え、失敗確率を大幅に下げる手助けになるはずです。
なぜデメリットに目を向けるべきか
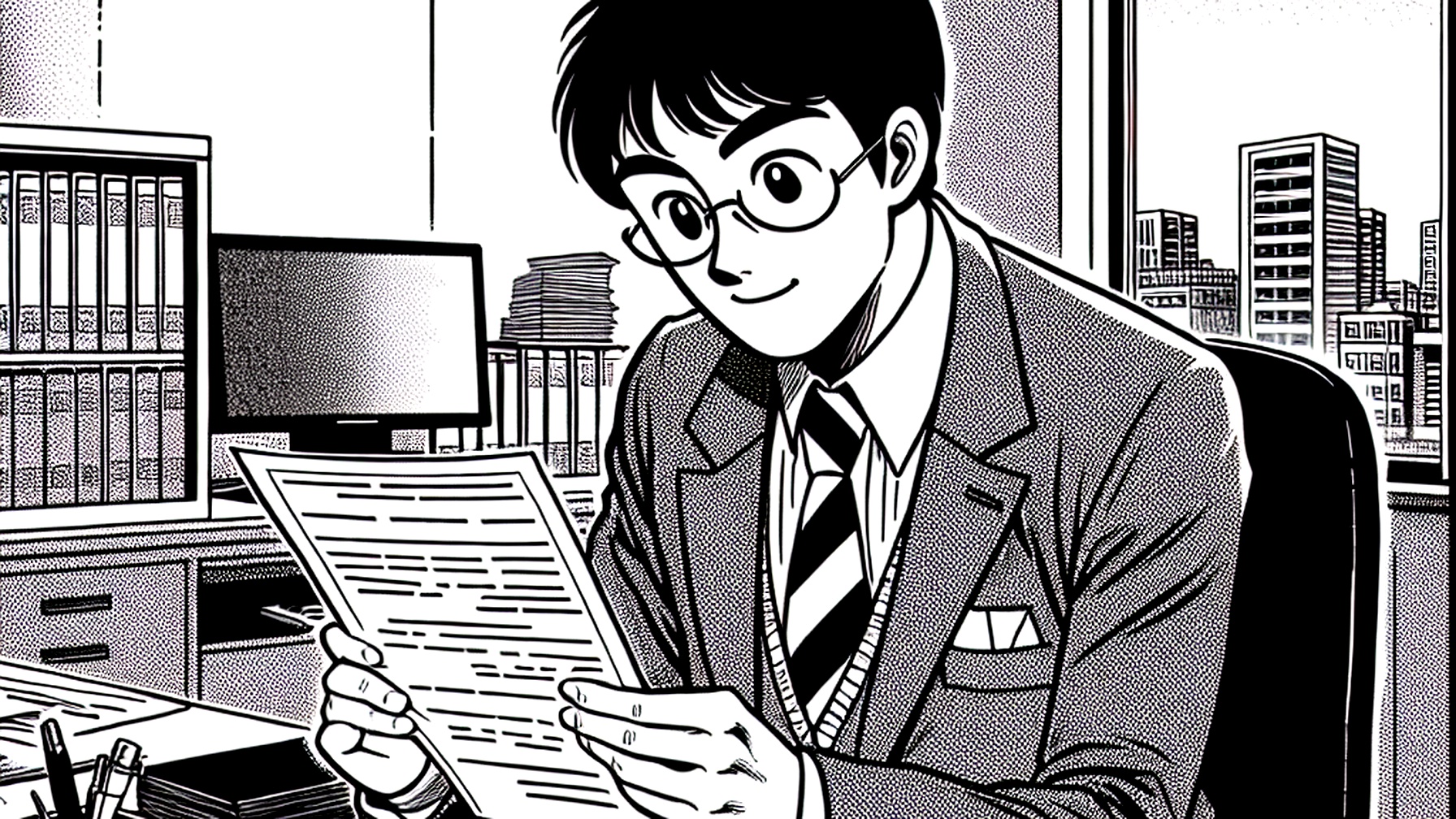
重要なのは、メリットより先にリスクを把握する姿勢です。不動産は額が大きく、出口戦略を誤ると修正が難しいからです。国土交通省の令和7年版住宅市場動向調査によると、一棟アパートを購入した個人投資家のうち約18%が「当初想定より収支が悪化した」と回答しています。
まず、メリットだけを信じて動くと判断基準が甘くなります。利回りが高い地方物件を買ったものの、人口減少で空室が増え、毎月赤字に転落する例は後を絶ちません。一方で、リスクを数字で検証すれば、同じ物件でも融資条件や価格交渉で守備を固められます。言い換えると、デメリットを丁寧に掘り下げることが最短のリスクヘッジなのです。
空室リスクのリアルな体験談
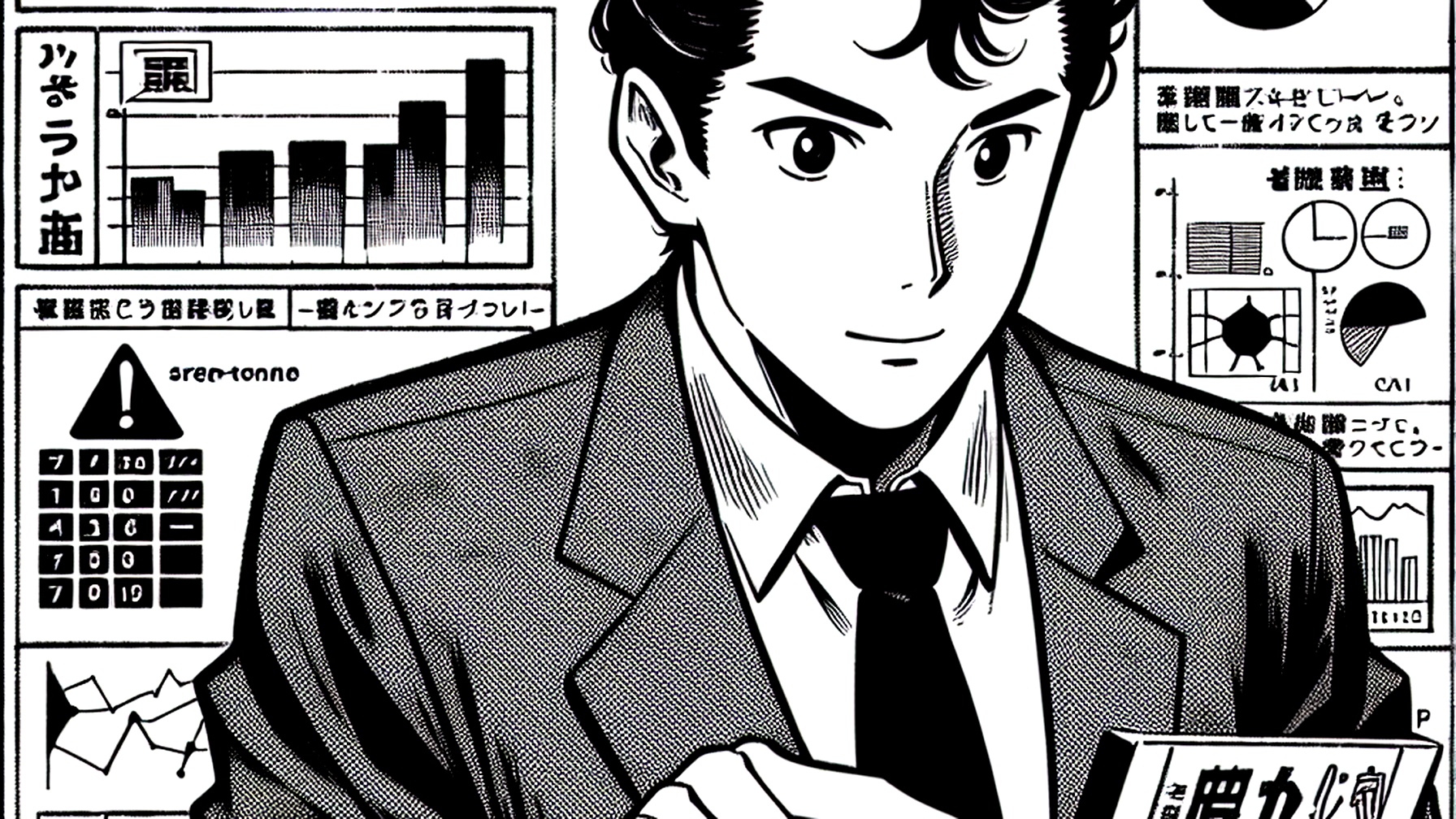
ポイントは、想定空室率を「感覚」ではなく「根拠あるデータ」で設定することです。私は2018年に地方政令市で築20年の区分マンションを購入しました。仲介会社は空室率5%と試算しましたが、蓋を開けると年間の実質空室率は22%に達しました。総務省の家計調査を参照すると、同エリアの30代単身世帯は5年間で6%減少しており、需要そのものが弱かったのです。
さらに、入居が決まってもキャンセルが続き、広告費を追加する悪循環に陥りました。広告費とは、不動産会社に支払う客付け手数料のことで、家賃1〜2か月分が相場です。2年で6回も払い、当初の収益計画は完全に崩壊しました。この経験から、募集家賃の相場や人口移動データを市区町村レベルで確認し、空室率は最低でも15%でシミュレーションするようになりました。
予想外の修繕費が家計を圧迫
実は、修繕費こそ初心者が最も見落としやすいコストです。私の受講生Aさんは2022年に築28年の木造アパートを取得しました。管理会社の概算見積もりは年間30万円でしたが、2024年の大雨で屋根から雨漏りが発生し、1回で180万円を支払う羽目に。日本政策金融公庫の2025年度資料によれば、築25年以上の木造物件は10年以内に大規模修繕が必要になる確率が60%を超えています。
また、外壁塗装や給排水管の交換といった大型工事は、金融機関から追加融資を受けにくいのが現状です。自治体の耐震化補助金を利用できるケースもありますが、2025年度は着工前申請が必須で、上限額も物件規模で変動します。つまり、自己資金プールが小さいと、突発的な修繕でキャッシュフローが一気に悪化するのです。
税金・キャッシュフロー計算の落とし穴
まず押さえておきたいのは、帳簿上の利益と実際の手残りは全く別物だという事実です。家賃収入から減価償却費を差し引くと赤字申告になり、所得税が戻る例があります。しかし翌年、固定資産税・都市計画税が一括で請求され、手元資金が足りずに慌てる投資家が多いのです。日本銀行の2025年10月金融システムレポートでは、個人大家の約3割が税負担を過小評価していると指摘しています。
私自身も初年度に還付金を喜んでいたら、2年目の税金と管理費、さらに空室の家賃減少が重なり、キャッシュフローは月−3万円に転落しました。固定費を平準化するため、毎月収支から税金相当額を別口座に積み立てる仕組みに変えたことでようやく安定しました。つまり、会計処理と現金管理を分けて考えることが、長期運営の鍵となります。
メンタルへの影響と時間コスト
一方で、数字に表れにくいデメリットがメンタル面です。Bさんは会社員で、夜間や休日に入居者対応をしていました。深夜の水漏れ連絡や、家賃滞納の電話が続き、半年で心身が疲弊したのです。東京都都市整備局の空室率調査では、自己管理物件のオーナーは管理委託物件に比べ、退去時のトラブル件数が1.5倍になるとの報告があります。
また、融資を受ける際の事業計画書作成や確定申告など、学習コストも積み重なります。時間をお金に置き換えると、本業の残業代より低い時給で動いていることに気づくケースも少なくありません。最終的にBさんは管理会社へ委託し、手取りは減りましたが、精神的負担が激減し本業に集中できるようになりました。時間と心の余裕も収益の一部だと実感した瞬間です。
まとめ
ここまで、空室リスク、修繕費、税金計算、メンタル面という四つのデメリットを体験談ベースで掘り下げました。共通する教訓は「楽観シナリオだけでは危うい」という点です。物件購入前に公的データを確認し、空室率は高めに、修繕積立金は多めに、税金分は確実に先取りしておきましょう。そして時間やストレスもコストと認識すれば、物件選定や管理方法の判断軸が明確になります。失敗事例を自分の危機管理マニュアルに組み込み、安定した不動産運営を目指してください。
参考文献・出典
- 国土交通省 令和7年版住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省統計局 家計調査 2025年版 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融システムレポート 2025年10月号 – https://www.boj.or.jp
- 日本政策金融公庫 2025年度 中小企業・事業資料 – https://www.jfc.go.jp
- 東京都都市整備局 民間住宅の空室率調査 2024年度 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

