アパート経営を始めたいものの、「もし設備が壊れたら誰が費用を出すのだろう」「想定外の出費でキャッシュフローが崩れないか」と不安を抱く人は多いです。実際、修繕費は空室率や家賃収入と並んで、投資成績を大きく左右する重要なコストです。本記事では、「アパート経営 誰が 修繕費」という疑問に応えつつ、オーナーと入居者、そして管理会社の役割分担を整理します。さらに、将来の大規模修繕に備える資金計画や、2025年度に利用できる公的支援策まで解説するので、最後まで読めば修繕費の不安をぐっと軽減できるはずです。
修繕費にはどんな種類があるのか
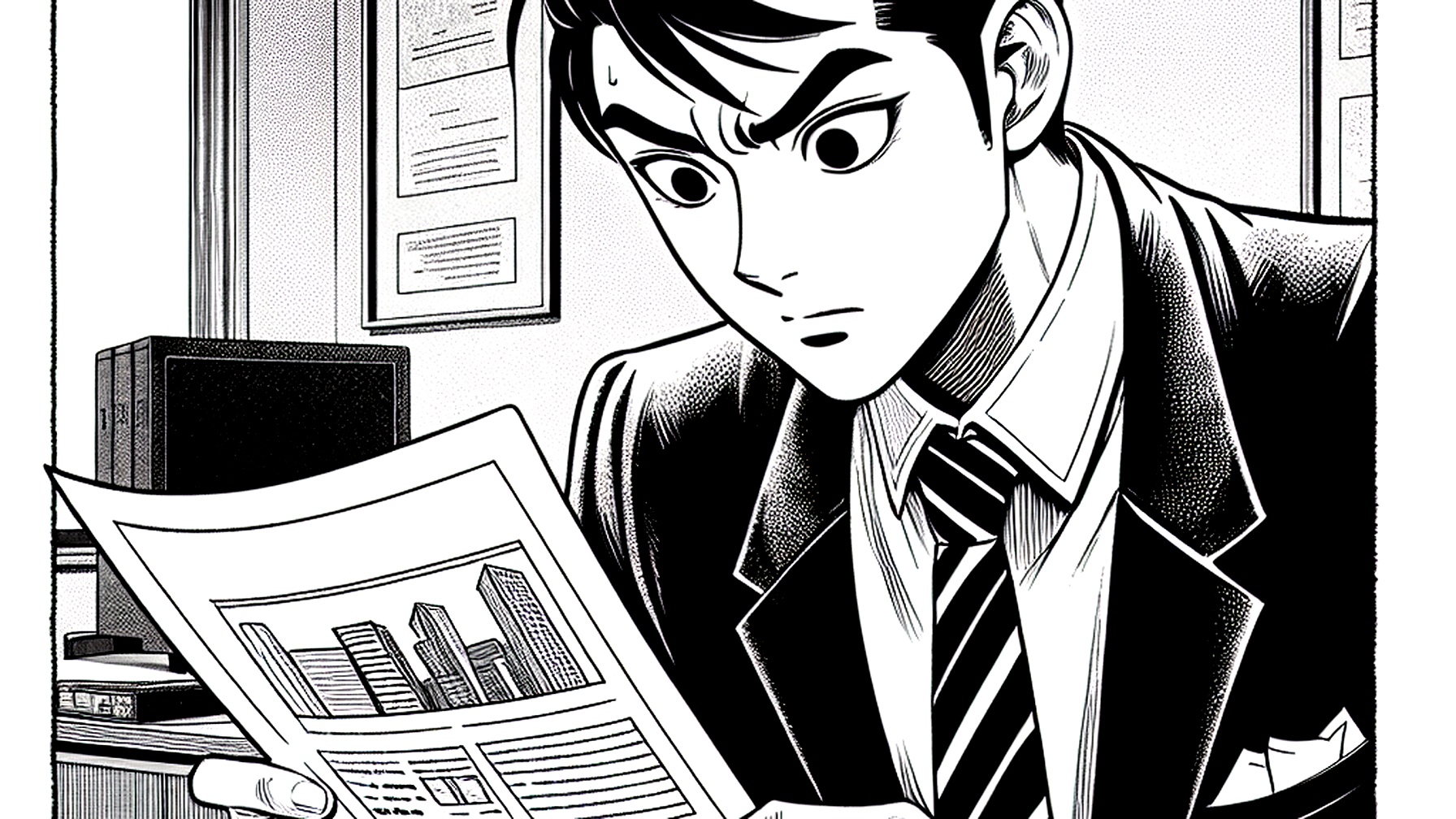
まず押さえておきたいのは、修繕費が「小規模」と「大規模」に大別される点です。小規模修繕は水栓パッキン交換や壁紙の張り替えなど、入居中の生活に直結する軽微な作業で、1回あたり数千円から数万円で済むことが多いです。一方、大規模修繕は屋根や外壁、防水層など建物全体の性能維持を目的とし、数百万円からときに数千万円を要します。国土交通省の調査では、築15年時点で外壁塗装を行うオーナーは全体の62%に上り、平均費用は戸当たり約190万円とされています。つまり、規模が違えば資金準備の方法も大きく変わるため、費用区分を理解することが第一歩となります。
小規模修繕は突発的に発生しやすく、年間家賃収入の5〜10%程度を目安に予備費として確保しておくと安心です。例えば家賃収入が600万円なら、毎年30万〜60万円を内部留保する計算になります。一方で大規模修繕は周期と費用を前もって見積もれます。屋根防水は12〜15年、外壁塗装は10〜12年が標準的周期とされるため、年単位で積み立てることで資金ショックを避けられます。これらを区分して管理すれば、日常のキャッシュフローに過度な負担をかけずに済むのです。
オーナーと入居者、負担の線引きを理解する
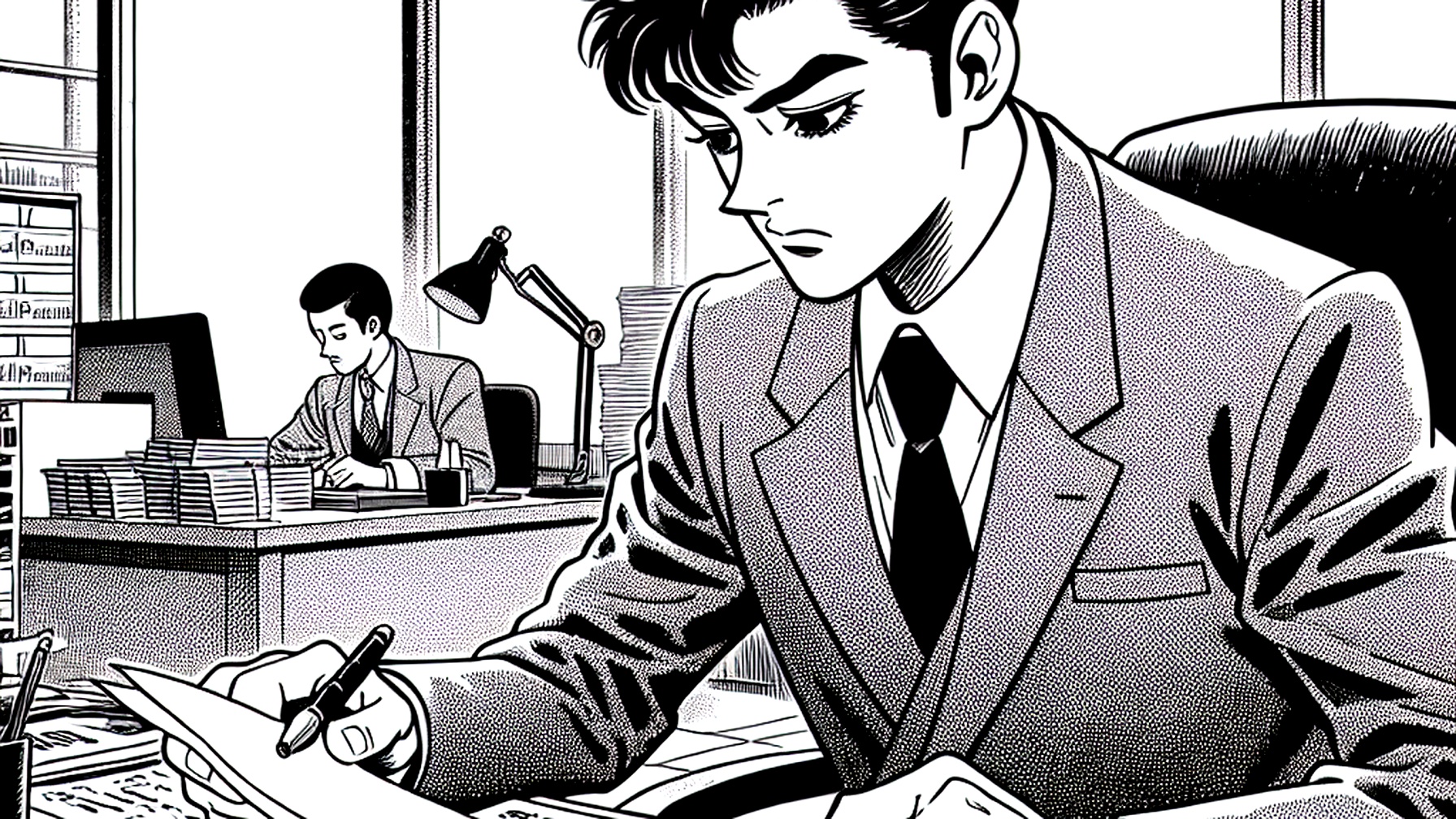
ポイントは、民法改正(2020年施行)によって「通常損耗(にんぷうじょうのふくれつき)※※」の考え方がより明確になったことです。通常損耗とは、入居者が普通に生活するだけで生じる壁紙の色あせや床の擦り傷を指し、これらの修繕費は原則としてオーナーが負担します。反対に、入居者の故意・過失による破損や、喫煙によるヤニ汚れなどは入居者負担となります。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(2025年版)」でも、この線引きが繰り返し強調されています。
実は、トラブルの多くは基準の曖昧さよりも「説明不足」から生じます。入居前に重要事項説明書で修繕の負担区分を詳しく示し、写真付きの現況確認書を交付しておくと、退去時の紛争リスクを大幅に減らせます。また、長期入居者の場合は途中でクロスを張り替えるなど適切なタイミングでオーナー負担の修繕を行うことで、物件価値を保ちつつ入居者満足度を上げる効果も期待できます。
さらに、2024年の民法改正で導入された「修繕権行使通知義務」は2025年も有効です。入居者が急迫の事情で修繕した場合、速やかにオーナーへ通知する義務を負うため、負担割合の判断材料が増えました。オーナーはこの制度を活用し、可能な限り自分で手配してコストを抑えつつ、責任の所在をクリアにすることが肝心です。
管理会社が果たすべき役割と契約のチェックポイント
重要なのは、管理委託契約で「どこまで管理会社が修繕を代行するか」を明文化することです。管理会社は入居者からのクレーム一次対応や業者手配を請け負うのが一般的ですが、費用立て替えの有無や上限金額は契約によって異なります。たとえば、月額管理料5%のプランでも「3万円までの修繕は管理会社負担」とするケースもあれば、完全実費精算のところもあります。前者は手離れが良い反面、管理料が高めになる傾向があるので、費用対効果を入念に比較しましょう。
一方で、共用部の定期点検や清掃を管理会社に任せるかどうかも、長期的な修繕コストに影響します。小まめな清掃で排水口の詰まりを防げば、後々の高額な配管交換工事を回避できるからです。加えて、国土交通省が2025年に改訂した「賃貸住宅メンテナンス指針」では、点検・清掃記録を電子化して保存することが推奨されています。記録が残れば工事履歴が明確になり、売却時の物件評価も向上しやすくなります。
つまり、管理会社に「委託すべき範囲」と「自主管理で十分な範囲」を見極めることで、無駄な修繕費を抑えつつトラブル対応スピードを確保できます。契約時は費用負担ルールだけでなく、緊急時の連絡体制や業者選定プロセスまで確認しておくと安心です。
大規模修繕に備える資金計画と税務メリット
実は、大規模修繕費をいかに平準化するかで事業の安定度は大きく変わります。外壁塗装や共用廊下の防水工事は10〜15年周期で訪れますが、これを突然実行するとキャッシュフローが一時的に赤字化しかねません。そのため、多くのオーナーは家賃収入の15〜20%を「修繕積立金」として毎月別口座に移す方法を採用しています。たとえば年間家賃収入800万円なら、毎月約10万円を積み立てれば10年後に1,200万円が確保できます。
さらに、修繕費は税務上「必要経費」に計上できるため、課税所得を圧縮する効果があります。耐用年数を延ばす工事の場合は資本的支出として減価償却になりますが、その分毎年の経費計上が可能です。どちらの処理が有利かは、法人か個人か、合計所得金額によって異なるため、税理士と相談すると無駄がありません。
2025年度は国交省と経産省が連携して実施する「住宅省エネ2025キャンペーン」が継続中で、賃貸住宅の断熱改修や高効率給湯器交換に補助率1/3、上限120万円が適用されます(申請期限は2026年3月末予定)。これを活用すれば、必須の大規模修繕を省エネ工事と同時に行い、実質的な負担軽減と賃料アップを同時に狙えます。補助金は交付決定後に着工が原則のため、スケジュール管理を怠らないよう注意してください。
空室リスクと修繕費を同時に管理するキャッシュフロー戦略
基本的に、修繕費と空室率は表裏一体の関係にあります。最新データによると、2025年8月の全国アパート空室率は21.2%で前年より0.3ポイント改善しましたが、依然として5室に1室が空いている状況です。つまり、修繕を怠り設備スペックが見劣りすると、競合物件との差が家賃下落や長期空室となって跳ね返ってきます。
そこで、家賃収入の予測モデルに「修繕効果」を組み込みましょう。例えば、築10年目に外壁塗装と共用LED化を実施すると、満室維持率が5ポイント改善し、年間家賃が2%上昇するという試算があります。投資額500万円に対し、年15万円の純増収入が得られれば、利回り3%を確保しつつ物件価値も維持できる計算です。長期保有を前提とするなら、このような「収益を生む修繕」に積極的になることが重要です。
また、突発的な修繕と空室期間が重なる最悪のケースに備え、6カ月分の返済額をプールする「安全資金」を別枠で用意しておく方法も有効です。仮に月返済額が15万円なら90万円が目安となり、修繕積立金とは別管理にすることで心理的な安心感が増します。さらに、金利上昇リスクを考慮し、長期固定金利ローンや繰上げ返済を併用すれば、修繕費・空室・金利という三つの変動要因を同時にコントロールできます。
まとめ
本記事では、アパート経営で誰が修繕費を負担するのかを整理し、費用区分と責任分担、そして資金計画の立て方まで解説しました。通常損耗はオーナー負担、過失損耗は入居者負担という基本ルールを踏まえつつ、管理会社との契約や補助金を活用することで支出を最適化できます。さらに、長期的な修繕積立と空室対策を同時に進めれば、キャッシュフローの安定性は格段に高まります。今回紹介した考え方を自分の物件に当てはめ、今日から具体的な積立計画と管理契約の見直しを進めてみてください。計画的な修繕こそが、将来にわたり安心してアパート経営を続ける鍵になります。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年8月公表データ – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(2025年版) – https://www.mlit.go.jp
- 国土交通省 賃貸住宅メンテナンス指針 2025 – https://www.mlit.go.jp
- 経済産業省 住宅省エネ2025キャンペーン 公式サイト – https://www.meti.go.jp
- 総務省 住生活基礎調査 2024 – https://www.stat.go.jp

