子どもの進学費用が年々膨らむ中、「学資保険だけでは足りないかもしれない」と感じている親御さんは多いはずです。実際、文部科学省の調査でも大学進学時に必要な総費用は自宅外通学でおよそ550万円に達します。本記事では、不動産クラウドファンディングを活用して教育資金を計画的に用意する方法を解説します。仕組みの基本から2025年度時点の税制のポイント、運用のコツまで丁寧に紹介しますので、投資が初めての方でも安心して読み進めてください。
教育資金準備の現状と課題
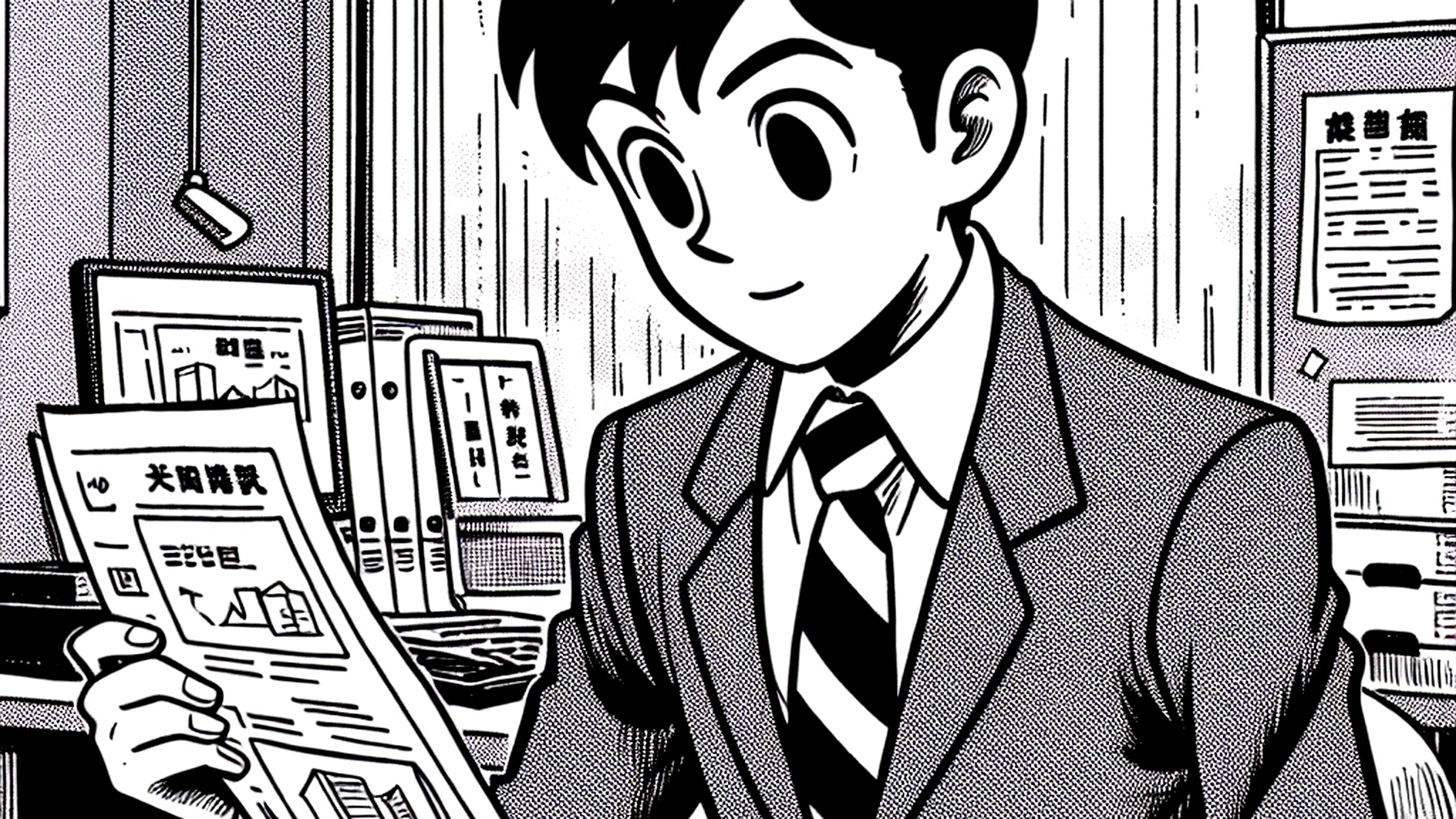
まず押さえておきたいのは、日本の家計が直面する教育費の重さです。総務省「家計調査」では、子どもが高校生になる頃から年間支出が平均で70万円以上増える傾向が示されています。にもかかわらず、学資保険の受取総額は満期時に300万円前後にとどまりがちです。つまり、進学費用の全額を賄うには別の資金源が必要になります。
一方で超低金利が続く現状では、預貯金だけでは資金はほとんど増えません。普通預金の金利が0.001%の場合、100万円を10年間預けても利息は千円程度にしかなりません。そこで、ミドルリスク・ミドルリターンの資産運用に目を向ける家庭が増えています。株式や投資信託も選択肢ですが、価格変動が大きい点が親世代にとって心理的ハードルになっています。
このような背景から、安定した賃料収入に裏付けられ、比較的小口から始められる不動産クラウドファンディングが注目を集めています。教育資金という明確な目的を持つことで、期間や利回りの計画が立てやすい点も魅力です。
不動産クラウドファンディングとは
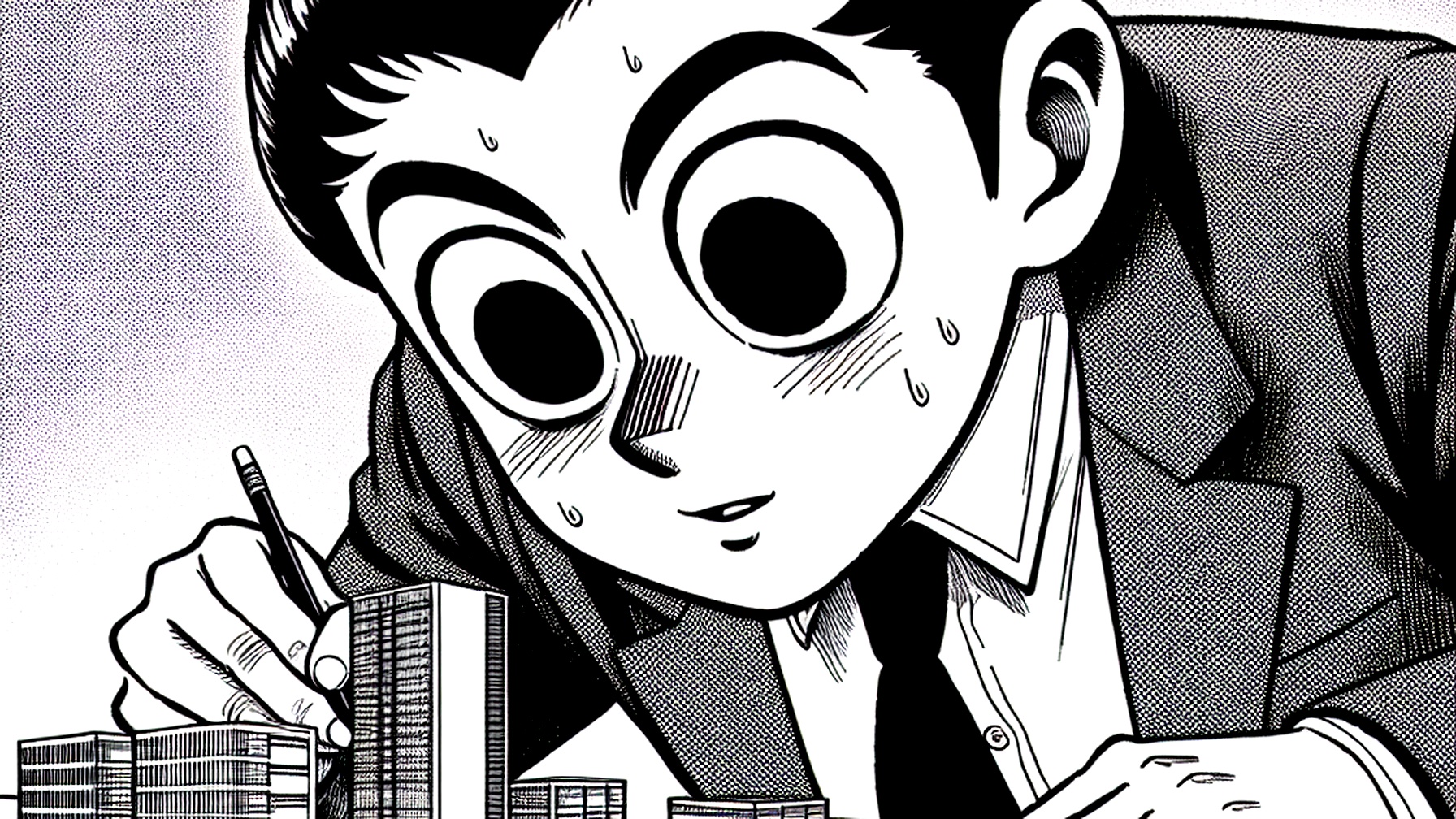
ポイントは、複数の投資家がインターネットを通じて一つの不動産プロジェクトに出資し、その収益を分配金として受け取る仕組みにあります。不動産特定共同事業法に基づき、運営会社は国土交通省の許可または登録を受けており、2025年10月現在で100社を超える事業者がサービスを提供しています。
実は、従来の不動産投資に比べて参入障壁が大幅に低いことが特長です。通常の区分マンション投資では数百万円の自己資金が必要ですが、クラウドファンディングなら1口1万円からでも出資できます。運用期間は半年から2年程度の商品が多く、教育資金の使用時期に合わせて組み合わせやすい点がメリットです。
さらに、物件管理やテナント対応などの業務は事業者が担うため、投資家は運用報告を確認するだけで済みます。言い換えると、時間が取れない子育て世帯でも低ストレスで不動産収益を取り込めるのです。ただし元本保証ではないため、運営会社の信頼性や物件の立地、賃料水準を十分にチェックする必要があります。
教育資金に活用するメリットと注意点
重要なのは、分配金のタイミングと利回りが比較的読みやすいことです。利回りは年4〜6%の案件が主流で、元本と合わせて複利運用すれば8〜10年で目標額を達成するシミュレーションを描けます。たとえば年率5%で毎年30万円ずつ追加投資すると、10年後にはおよそ390万円に達し、学資保険の不足分を補える可能性があります。
一方で注意すべきは流動性の低さです。運用期間中は原則として途中解約ができません。したがって、入学金など大きな支出時期が確定している場合は、満期が重ならないよう複数案件の運用期間をずらす工夫が欠かせません。また、分配金が雑所得として課税対象になる点にも留意してください。
リスク管理という点では、案件選定時に「優先劣後方式」の比率を確認することが有効です。これは事業者が一定割合を劣後出資し、損失が発生した際にはまず劣後分から充当される仕組みで、投資家の元本毀損リスクを軽減します。劣後比率が20%前後あれば、賃料下落や想定外の修繕費にもある程度耐えられると考えられます。
2025年度の制度・税制を押さえる
まず、「新NISA」は2024年から恒久化され、2025年度も引き続き年間360万円まで非課税投資枠が利用できます。ただし、不動産クラウドファンディングは新NISAの対象外であるため、教育資金づくりの全体設計ではNISA枠を株式や投資信託に充て、クラウドファンディングで利回りを底上げする分散が効果的です。
また、贈与税の基礎控除は年間110万円までと従来どおりですが、教育資金一括贈与の非課税特例は2025年10月時点で適用対象が絞られています。大学入学までに贈与を受け、払い出しは30歳までという要件があり、拠出先が金融機関に限定されるため、不動産クラウドファンディングへの直接充当はできません。したがって、祖父母から資金を受け取る場合はまず預貯金として受領し、その後自己名義で出資する形を取る必要があります。
さらに、クラウドファンディングで得た分配金は総合課税になるため、所得が増える年度は住民税や高校無償化の所得判定に影響する可能性があります。年末調整や確定申告時に「私立高校授業料の減免」を受ける家庭は、分配金を含めた試算を早めに行うことで想定外の負担増を防げます。
ポートフォリオに組み込む実践ステップ
まず、教育資金のゴール設定が欠かせません。中学受験から私立大学進学まで想定する場合と、公立中心で考える場合では必要額が大きく変わります。必要額とタイミングを一覧にし、運用期間を逆算することで、クラウドファンディング案件の選別基準が明確になります。
次に、月々のキャッシュフローを点検します。住宅ローンや保険料を差し引いたうえで、無理なく回せる金額を算出し、その範囲内で複数案件に分散投資するのが基本です。例えば月3万円を3案件に1万円ずつ投じれば、運用期間や物件タイプを分散でき、リスクを抑えつつリターンを安定化できます。
最後に、定期的なレビューを行います。運営会社から届く運用レポートを読み、賃料動向や空室率に異変がないか確認してください。もし予定利回りを大きく下回る兆候が見えたら、新規出資を控える、あるいは次回更新を見送るなど早めの軌道修正が大切です。こうした運用管理を習慣化することで、教育資金の目標達成確度が大幅に高まります。
まとめ
不動産クラウドファンディングは、小口から始められ、比較的安定した利回りが期待できるため、教育資金づくりに適した選択肢と言えます。運用期間を分散し、優先劣後方式などリスク軽減策を確認すれば、低金利環境でも資金を効率的に殖やせます。さらに、2025年度の税制や教育費支援制度と組み合わせることで、家計全体の負担を抑えられます。まずは必要額を明確にし、無理のない範囲で一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 文部科学省「子どもの学習費調査」 – https://www.mext.go.jp
- 総務省統計局「家計調査」 – https://www.stat.go.jp
- 国土交通省「不動産特定共同事業の概要」 – https://www.mlit.go.jp
- 金融庁「クラウドファンディング利用者保護等に関する報告書」 – https://www.fsa.go.jp
- 国税庁「令和7年度(2025年度)税制改正のあらまし」 – https://www.nta.go.jp

