将来の家賃下落や金利上昇が心配で、不動産投資に踏み出せない方は多いものです。特に、政策変更や人口動態が大きく動くといわれるデメリット 2027年を前に、何を準備すべきか悩む声をよく耳にします。本記事では、二年後に迫った市場の変化を具体的データで読み解き、初心者でも実行できるリスク対策を提案します。読み終えるころには、先行き不透明な環境でも冷静に判断できる視点が身につくはずです。
2027年を見据えた市場動向の読み方
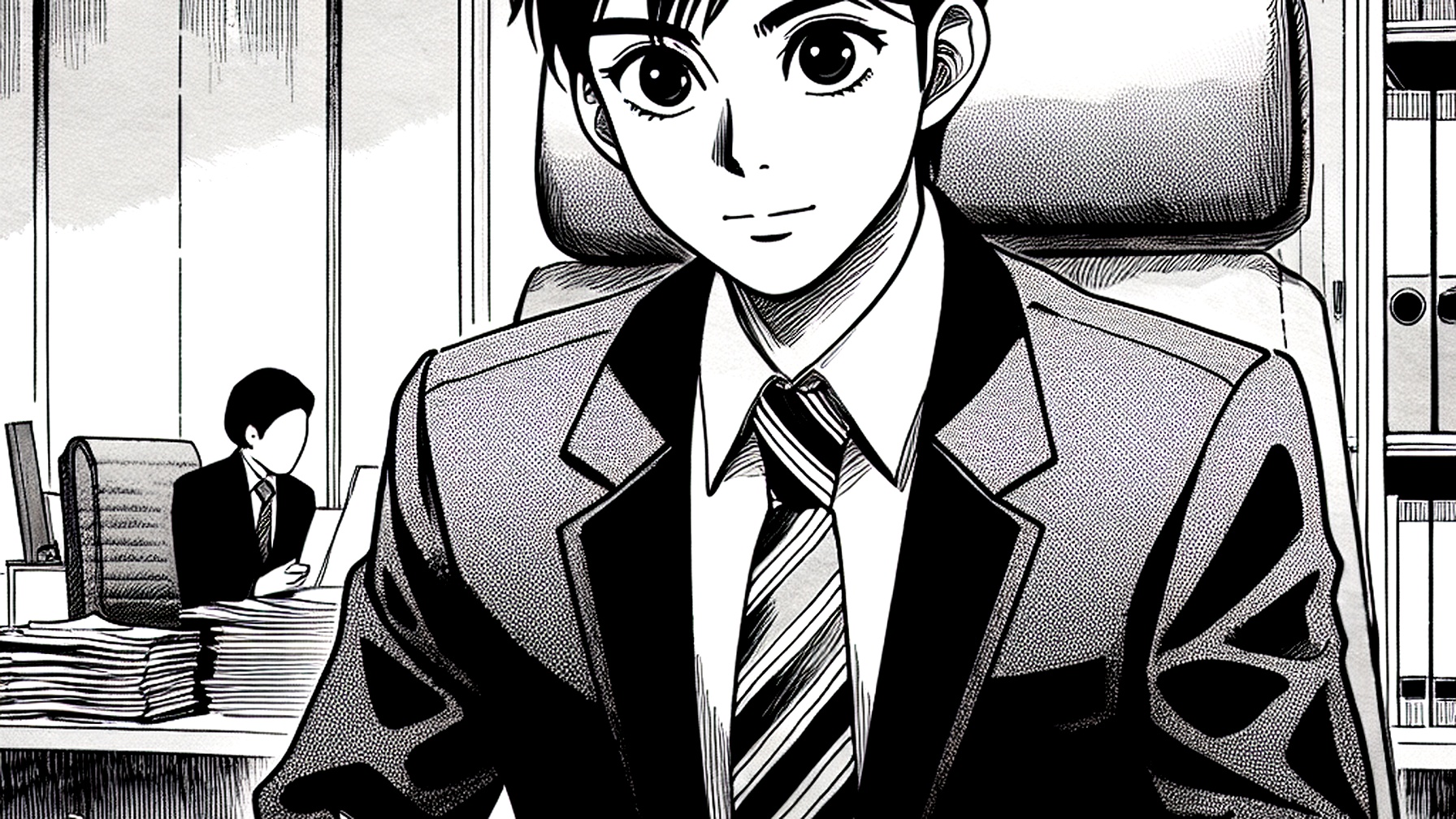
まず押さえておきたいのは、今後二年間で予想される供給量と需要のバランスです。国土交通省の「住宅着工統計」によると、2024年から2025年にかけて賃貸用共同住宅の着工戸数は微増していますが、2026年は大型再開発が一巡し横ばいになる見込みです。
直近の供給増は一見するとチャンスのように映ります。しかし、東京都区部では既に空室率が高止まりし、地方主要都市でも築古物件の入居付けが難しくなっています。つまり、供給過多が地域ごとの温度差を広げ、立地選びの重要度がさらに高まるということです。地方に目を向ける場合でも、人口流入が続く駅近エリアか、強い大学や工業団地があるエリアに絞る必要があります。
一方、需要側を見ると総務省の推計では2027年時点の20〜39歳人口が全国で約2%減少するとされています。若年層の減少はワンルーム需要を直撃しやすく、賃料の伸びを抑える要因になります。これから物件を選ぶなら、家族世帯までカバーできる間取りや、家具家電付きで単身転入に対応するなど、需要の分散が鍵となります。
金利上昇リスクと資金計画
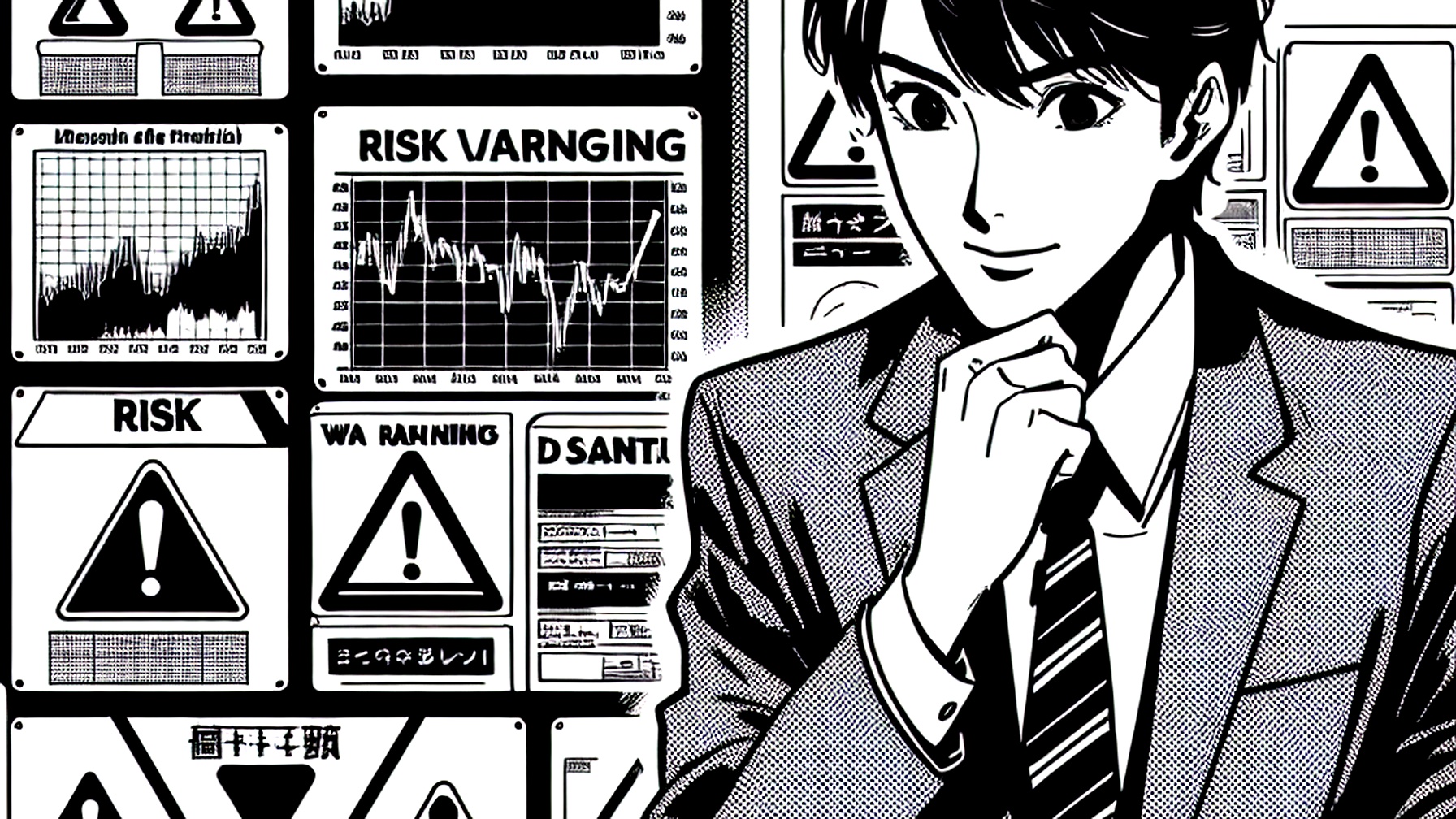
ポイントは、金利変動が返済額に与えるインパクトを定量化しておくことです。日本銀行は2024年にマイナス金利を解除し、2025年10月時点で政策金利は0.5%台にあります。市場金利は緩やかに上昇傾向にあり、2027年までにさらに0.3〜0.5%上振れするシナリオが想定されています。
例えば、残債3000万円を金利1.5%・25年返済で借りている場合、金利が2.0%へ上がると月々の返済は約7000円増えます。表面利回り6%の物件でも、管理費や修繕積立を考えるとキャッシュフローが一気に薄まる水準です。したがって、購入時点から実質利回りで8%以上を狙う、あるいは自己資金比率を3割程度入れて安全域を確保することが現実的です。
2025年度の住宅ローン控除は投資用物件に適用されませんが、金融機関によっては新築一棟アパート向けに最大35年、固定2%前後の商品を用意しています。固定で借りれば金利上昇リスクを封じ込められますが、途中解約時の違約金が高い点がデメリットになります。変動か固定かで迷う場合は、借入額の半分を固定にし、残り半分を変動にするハイブリッド型がリスク分散につながります。
空室率の高止まりが招くデメリット
実は、空室は単に収益を減らすだけでなく、修繕費を押し上げる要因にもなります。入居者がいない期間は換気不足で湿気がこもり、壁紙や設備の劣化が早まるからです。さらに、空室期間が長いほど広告費やフリーレントなどのコストも膨らみます。
リクルート住まい研究所の調査では、首都圏ワンルームの平均空室期間は2023年の40日から、2025年には55日に伸びています。空室が二週間延びるだけで、年間利回りは0.5ポイント下がる計算です。空室対策としては、内装をおしゃれにする以前に、Wi-Fi無料や宅配ボックスを設置するほうが費用対効果が高いというデータもあります。
また、築20年以上の区分マンションでは、家賃を3000円下げても入居が決まらない事例が増えています。家賃を下げ続けると資産価値も下落し、売却時の価格交渉で不利になります。つまり、購入前から出口戦略を描き、需要が細りにくいエリアかどうかを見極めることが、空室デメリットの根本的解決につながります。
2025年度の税制を活かす対策
重要なのは、現行制度を正しく理解し、余計な税負担を回避することです。2025年度の不動産取得税の軽減措置は、新築住宅なら床面積50〜240平方メートルに適用され、税率は4%から3%へ下がります。この優遇は2026年3月までと期限が明示されているため、2027年を待たずに仕込みたい投資家にとって大きな後押しとなります。
所得税面では、損益通算による節税が引き続き有効です。ただし、赤字が大きいと税務署に事業性を問われやすく、過度な減価償却計上は否認リスクが高まります。適正な青色申告で計上するためには、専門家と連携し、減価償却を実勢価格に合わせることが安全策です。
地方自治体の固定資産税減免は、2025年度も耐震・省エネ改修を行った住宅に対して継続されています。改修費用の10%相当が減税されるケースもあるため、古い木造アパートを再生させる戦略と相性が良いです。補助金を活用しながら、物件価値を底上げすることで、デメリット 2027年の空室リスクを抑えられます。
不確実性に強いポートフォリオ構築
まず押さえておきたいのは、単一物件への依存を減らすことです。ワンルームのみを複数持つよりも、戸建てや店舗併用物件を組み合わせたほうが、家賃下落の影響を分散できます。用途が異なれば、景気循環やテナント層の変動を受けるタイミングがずれるからです。
次に、管理会社の複線化も効果的です。物件ごとに得意分野の異なる管理会社を採用すれば、リーシングの提案力が高まり、空室期間を短縮できます。また、二社以上と関係を作っておくことで、修繕見積もりの競争原理が働き、コストダウンにつながります。
最後に、キャッシュポジションを常に10%程度確保し、想定外の修繕や金利上昇に備えることが重要です。現金余力がある投資家は、景気後退局面で割安物件を素早く取得できます。つまり、リスク管理を徹底することが、そのままチャンスをつかむ武器になるのです。
まとめ
ここまで、市場動向、金利、空室、税制、そしてポートフォリオ戦略まで幅広く見てきました。2027年に向けた最大のリスクは、供給過多と金利上昇が同時に進む可能性にあります。しかし、立地を厳選し、資金計画を保守的に組み、現行の税制優遇を活用すれば、大きなデメリットを回避できます。まずは、自身の投資目的を再確認し、紹介したチェックポイントを一つずつ行動に移してみてください。不透明な時代だからこそ、準備を整えた投資家にこそ安定収益のチャンスが訪れます。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅着工統計 – https://www.mlit.go.jp
- 総務省 人口推計 – https://www.stat.go.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 – https://www.boj.or.jp
- リクルート住まい研究所 住宅市場データ – https://suumo.jp/edit/sumai
- 財務省 税制改正の概要(2025年度) – https://www.mof.go.jp

