不動産投資を始めたばかりの方は、「管理会社に任せたほうが安心なのか、それとも自主管理でコストを抑えるべきなのか」という迷いを抱きがちです。実際に空室やクレーム対応の負担を考えると専門家に委託したい気持ちも分かりますが、管理手数料がキャッシュフローを圧迫するのも事実です。本記事では、管理会社を利用するメリットとデメリットを最新データと実例で検証し、収益物件を長期的に運営するうえで「本当に」必要なのかを多角的に解説します。読み終えるころには、自分に合った管理スタイルと、その判断基準を明確にできるはずです。
管理会社に委託する基本的な仕組み
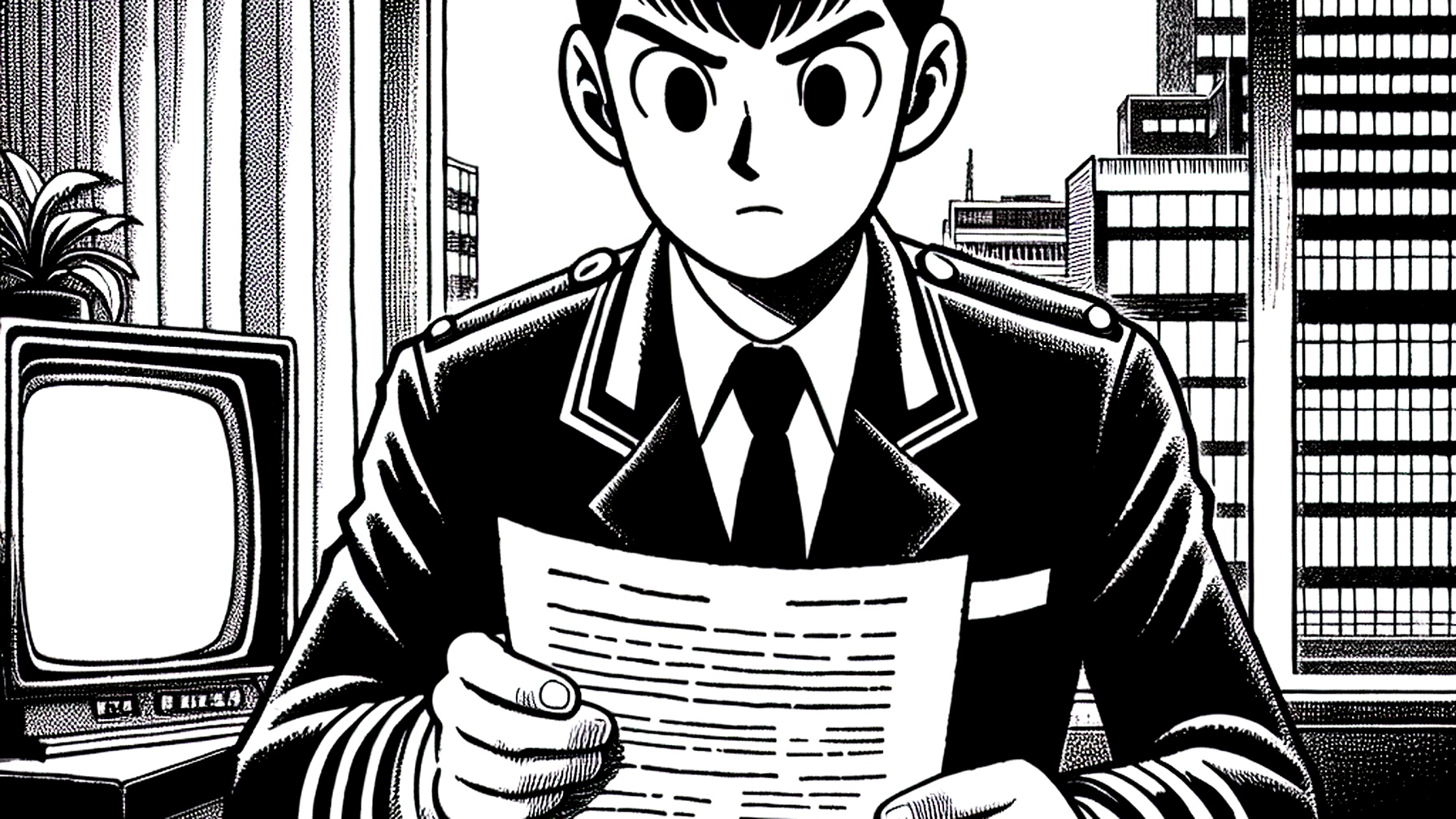
まず押さえておきたいのは、管理業務の範囲と手数料の仕組みです。管理会社は入居者募集、賃料回収、設備トラブル対応などを代行し、月額賃料の3〜7%を手数料として受け取ります。
日本賃貸住宅管理協会の2025年調査によると、専任媒介での平均手数料は5.2%でした。つまり月額10万円の家賃なら5,200円が毎月のコストになります。一見小額に見えますが、年間では6万円を超え、築年数が進むほど修繕費と重なって負担が増します。また、管理会社が入居者対応を24時間受け付ける場合、別途「サポート料」が月額数百円加算されるケースもあります。
一方で、同調査では管理会社を利用したオーナーの85%が「入居率が安定した」と回答しています。広告ネットワークや既存顧客リストを活用し、空室期間を平均20日短縮できたとの報告もありました。空室対策に要する広告費とストレスを考えると、手数料を支払う価値は十分にあるといえます。
自主管理で得られるメリットと潜むリスク
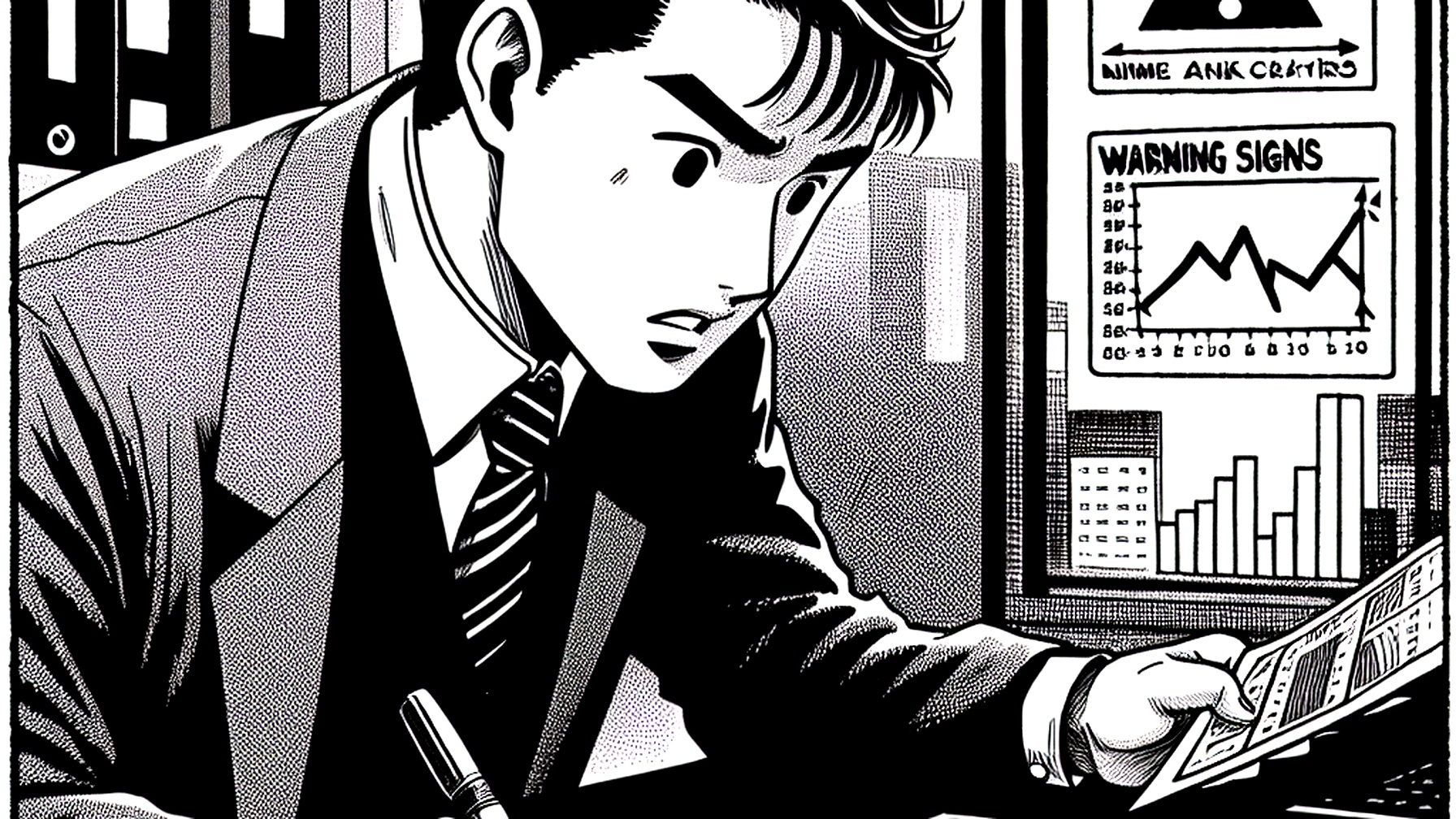
実は、自主管理を選択すると手数料を削減できるだけでなく、入居者と直接コミュニケーションを取ることで物件の改善点を早期に発見できます。国土交通省調査(2024年空家・住宅市場レポート)では、直接管理を行うオーナーの物件は設備更新のタイミングが平均1.3年早く、長期的な修繕費が抑えられた事例も報告されています。
しかし、重要なのは時間的・精神的な負担です。夜間の水漏れ連絡や家賃滞納への督促は想像以上に労力を要します。さらに2021年に完全施行された賃貸住宅管理業法により、200戸超の賃貸住宅を管理する場合は国への登録が義務となりました。2025年時点でもこの規制は継続中で、無登録のまま業務を行えば罰則の対象になります。少戸数なら登録は不要でも、法令遵守や個人情報管理の責任は同じだけ重くのしかかります。
言い換えると、空室が少なく規模が小さいうちは自主管理でキャッシュフローを最大化し、戸数が増えてきたら専門会社に切り替える段階的な戦略も現実的です。また、IT重説(重要事項説明のオンライン化)が普及したことで、遠隔でも管理を続けやすくなりましたが、トラブルの現場対応は依然として地域密着の力が問われます。
管理会社を選ぶ際のチェックポイント
ポイントは、手数料よりも「入居率」と「対応スピード」です。都心部と地方では家賃相場が大きく異なるため、同じ5%でも実質サービス内容に差が出ます。東京都心の平均空室率は、日本不動産研究所の2025年レポートで3.9%と報告されていますが、地方では8%を超えるエリアもあります。空室が長引くほど、手数料のわずかな差は吹き飛んでしまいます。
また、賃料滞納発生時の督促フローや訴訟サポートの有無を事前に確認しましょう。保証会社と提携する管理会社なら、滞納リスクを移転できるため心理的安心感が高まります。加えて、原状回復工事の見積もりを外部業者と比較できる「セカンドオピニオン制度」を採用する会社も増えています。透明性が高いほどオーナーと管理会社の信頼関係は強化されるからです。
さらに、2025年度の固定資産税減額特例(長期優良住宅に適用、2026年3月末着工分まで)を活用する場合、管理会社が申請サポートを無償で行うケースがあります。制度は期限付きであるため、運用中の物件が条件を満たすかどうか相談できる体制が整っていることも選定基準に加えると良いでしょう。
キャッシュフローへの影響をシミュレーションで検証
まず、家賃月10万円、戸数10戸、年間稼働率95%の物件を例にします。管理手数料5%を支払うと、年間コストは約57万円です。これに対し、空室期間が管理会社利用で平均20日短縮された場合、追加家賃収入は約6.5万円となり、コストの約11%が相殺されます。
自主管理なら手数料はゼロですが、広告掲載料や仲介手数料を毎回自費で支払う必要があります。1入替あたりの平均広告費用を5万円と仮定し、年間3戸が入れ替わると15万円の支出です。空室が長期化すれば、収益はさらに目減りします。つまり、単純な手数料率の比較ではなく、空室期間と付随費用を含めた総合的なキャッシュフロー分析が欠かせません。
また、インボイス制度が2023年に導入され、課税売上1,000万円超のオーナーは適格請求書の発行が必須です。管理会社が請求書代行を行う場合、帳簿管理の手間が大幅に減ります。税理士報酬の削減や青色申告特別控除の適用を考慮すると、間接的なキャッシュフロー改善につながることも見逃せません。
迷ったときの判断基準と実践ステップ
基本的に、自己のライフスタイルと投資の規模が最大の判断材料です。副業として始めた段階では本業に支障が出ないことが最優先であり、管理会社に委託するほうが精神的余裕を保ちやすいでしょう。一方、専業投資家を目指す場合やリタイア後の時間が確保できる人は、自主管理で収益率を高める選択肢も現実味を帯びます。
迷ったときは、次の順序で決定すると失敗が少ないです。まず、現状の家賃収入と支出を洗い出し、手数料を上乗せした場合の利回りを計算します。次に、自分が対応できる作業と外注したい作業を区分けし、部分委託の可否を管理会社に相談します。最後に、複数社の提案を比較し、サービス内容と費用のバランスを検証しましょう。
部分委託としては、入居者募集のみを管理会社に任せ、入居後の賃料回収やトラブル対応を自分で行う方式があります。この場合、手数料は1〜2%に抑えられるケースが多く、キャッシュフローと時間のバランスが取りやすくなります。将来的に戸数が増えれば、同じ会社にフル委託へ切り替えることでスムーズに拡張できる点も利点です。
まとめ
本記事では、管理会社に支払う手数料の実態、自主管理がもたらす裁量と負担、そしてキャッシュフローへの影響を多角的に検証しました。最も重要なのは、空室期間やトラブル対応に要する時間を金額換算し、手数料と比較する姿勢です。自主管理で得られる利回り向上が、生活の質や本業への支障を上回るかどうかを冷静に見極めてください。管理スタイルを柔軟に切り替えられる体制を整えれば、変動する市場環境でも安定した収益が期待できます。まずは現状分析と複数社の比較から始め、あなたの投資目的に合った最適解を掴みましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅局「令和6年 空家・住宅市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 日本賃貸住宅管理協会「賃貸住宅管理業実態調査2025」 – https://www.jpm.jp
- 日本不動産研究所「賃貸住宅空室率レポート2025」 – https://www.reinet.or.jp
- 総務省「インボイス制度に関するガイド」 – https://www.soumu.go.jp
- 東京都不動産鑑定士協会「家賃相場と稼働率の地域差分析2025」 – https://www.tokyo-kantei.or.jp

