投資初心者の多くは「REIT(不動産投資信託)なら少額から始められそうだけれど、本当に安全なのか」という疑問を抱きます。また、魅力的な利回りを追い過ぎてリスクを見落とすのではないかという不安もつきまといます。本記事では、人気のREITがなぜ支持されるのか、安全性をどう判断すべきか、さらに利回りを評価するときのポイントまでを体系的に解説します。最後まで読むことで、自分に合ったREITを選ぶ視点と、2025年時点で活用できる投資ステップが身につくでしょう。
REITの基本構造と仕組みを押さえよう
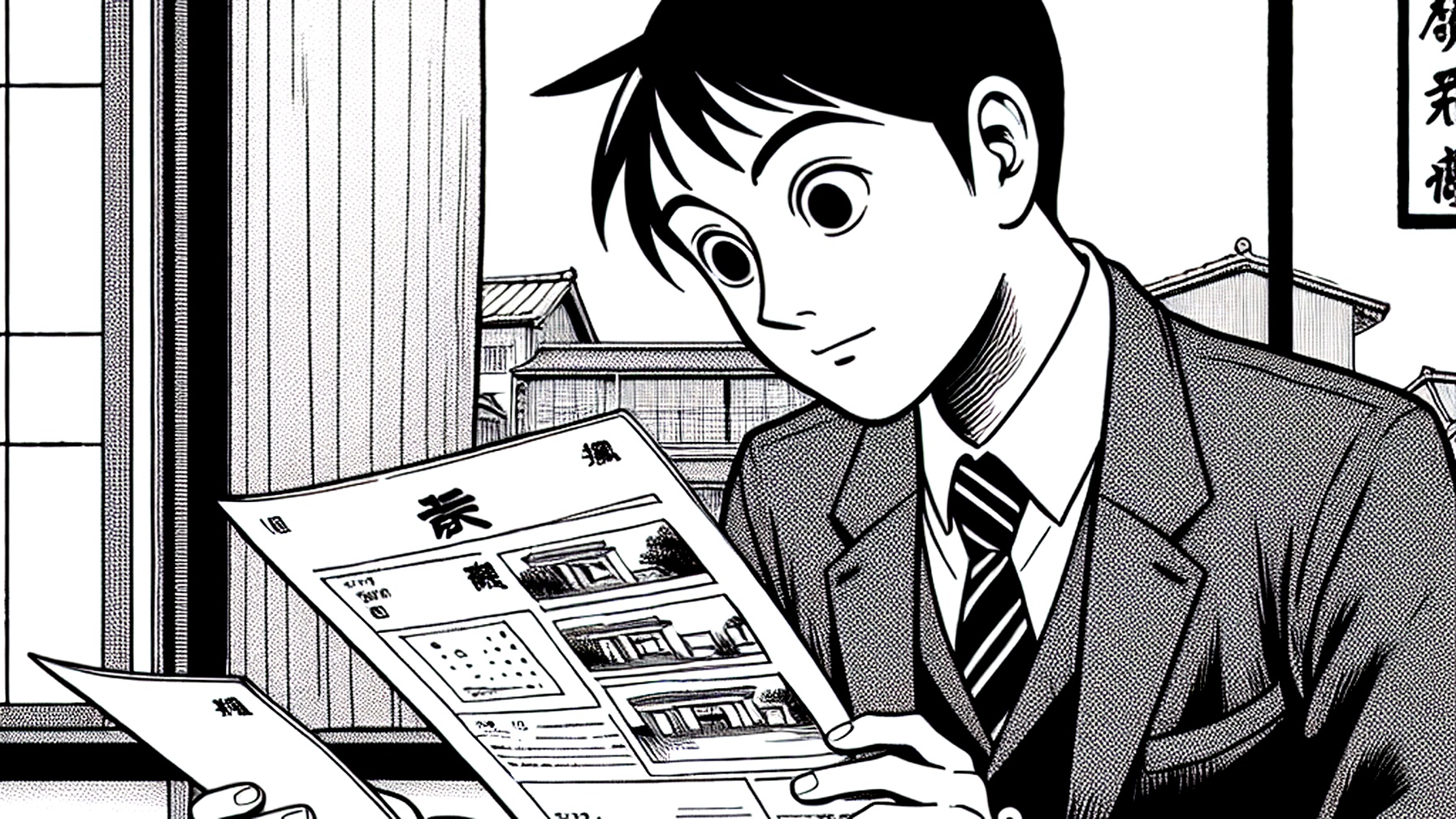
まず押さえておきたいのは、REITが投資家から集めた資金で複数の不動産を取得し、その賃料収入や売却益を配当として還元する仕組みです。株式と同じように証券取引所で売買できるため流動性が高く、数万円から投資可能である点が人気を支えています。
実は、REITには「総合型」「オフィス特化型」「住宅特化型」などのタイプがあります。総合型は物件用途を分散し、単一市況の影響を緩和できる一方、特化型は専門性を武器に高い運用効率を狙うのが特徴です。つまり、自分が重視するリスク許容度や市場観に合わせてタイプを選択することで、安全性と利回りのバランスを調整できます。
また、法律上REITは利益の90%以上を分配すると法人税が実質的に免除されるため、配当利回りが相対的に高くなりやすい仕組みです。2025年10月末時点で東証REIT指数の平均分配利回りは3.7%前後となっており、長期国債利回り(おおむね1.2%)より2%以上高い水準を維持しています。
安全性を左右するポイントは「資産の質」と「LTV」
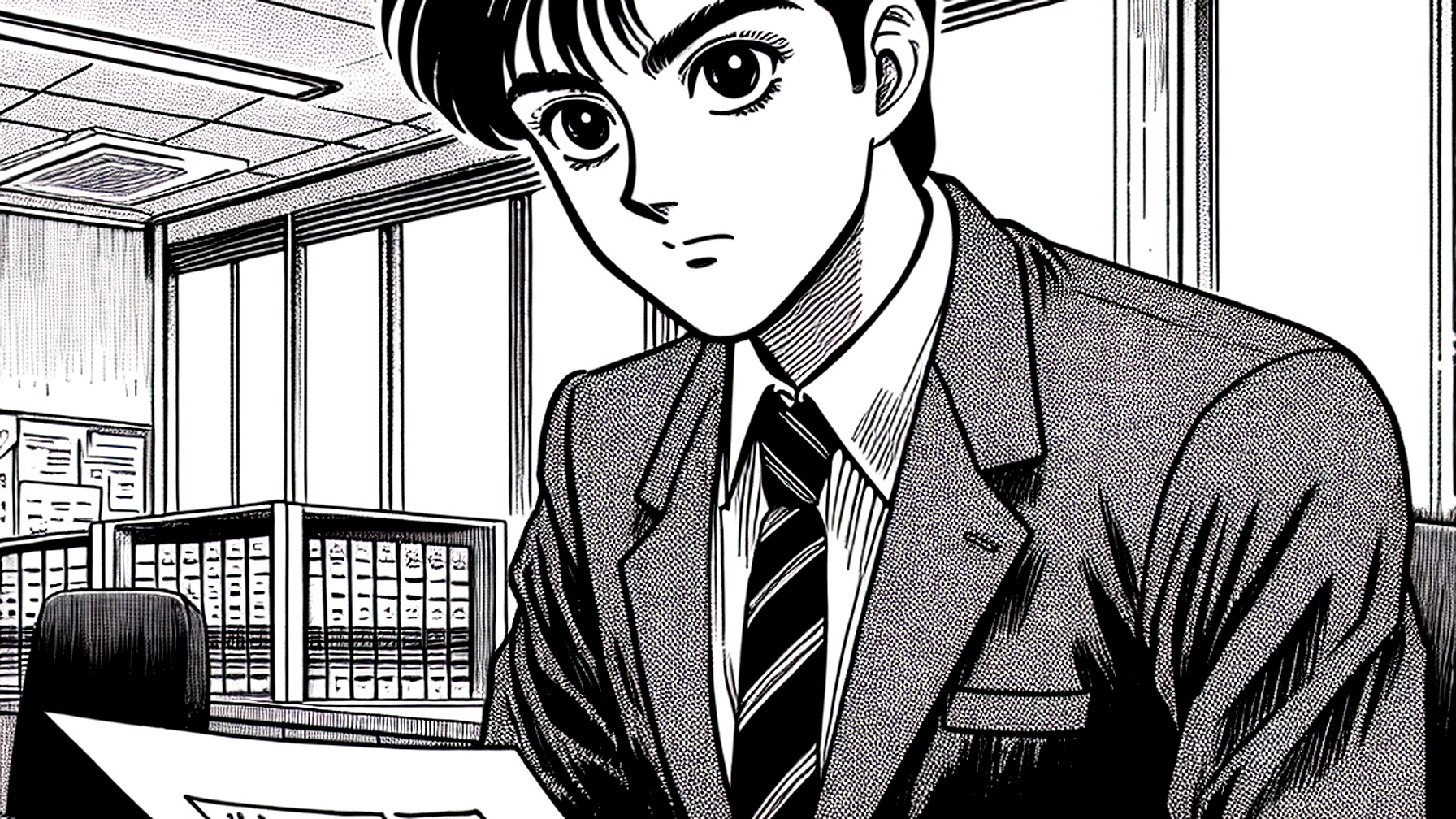
ポイントは、安全性を測る軸を複数持つことです。具体的には、保有物件の立地や築年数といった「資産の質」、借入金比率を示す「LTV(Loan to Value)」、そしてテナントの分散度合いが代表的な指標になります。
まず資産の質について、都心Aクラスオフィスや駅近レジデンスを多く保有するREITは空室リスクが低く安定収益を期待できます。日本不動産研究所のデータでは、2025年の東京23区ワンルーム平均表面利回りが4.2%に対し、郊外は5.5%ですが、都心は売却時の価格下落リスクが抑えられる点で安全性が高いといえます。
次にLTVですが、50%を超えると金利上昇局面で負担が重くなりやすいため注意が必要です。東京証券取引所の開示資料によると、住宅特化型REITの平均LTVは約45%、物流特化型は約40%と比較的低めです。利回りだけでなく、借入金管理がうまい銘柄ほど安全度が高いと理解できます。
最後にテナントの分散度合いも確認しましょう。物販やオフィスが一社依存になっている場合、撤退リスクがそのまま分配金の減少につながります。一方、多数のテナントを抱える物流施設REITは賃料が安定しやすく、長期契約が多いためキャッシュフローが読みやすいメリットがあります。
利回りを見るときに注意したい三つの落とし穴
重要なのは、表示利回りがそのまま将来の配当を保証するわけではない点です。まず、直近の分配金を年換算した「表面利回り」は、物件売却益を一時的に乗せているケースがあるため、継続性を必ず確認してください。東証REITデータベースには「一過性利益調整後利回り」が示されていますので参考になります。
二つ目は金利環境です。日銀が2024年にマイナス金利を解除した影響で、2025年10月の短期プライムレートは1.4%台に上昇しました。利払い負担が増すと分配金が目減りする可能性があるため、固定金利比率が高いREITは相対的に安全といえます。
三つ目は増資リスクです。人気のあるREITほど追加物件取得のための公募増資を行う傾向があります。増資によって一口当たり分配金が希薄化しないか、取得資産の収益力が上回るかを決算説明資料で精査すると安心です。言い換えると、利回りだけでなく成長戦略の質を見極めることが長期リターンにつながります。
人気REITはなぜ選ばれるのか
まず、多くの投資家が注目するのは「時価総額の大きさ」と「流動性」です。時価総額が3,000億円を超える大型REITは売買が活発で価格変動が比較的マイルドになりやすく、結果として安全感が生まれます。たとえば、日本ビルディングファンド投資法人は安定的なオフィス賃料と適度なLTVで、東証の売買代金ランキングでも常に上位に位置しています。
また、人気の背景にはスポンサー企業の信用力があります。大手不動産デベロッパーや金融機関がスポンサーとなるREITは、物件取得ルートや資金調達面で有利です。2025年4月に実施された住友商事系REITの公募増資では、わずか一日で応募額が完了し、投資家の信頼の厚さが示されました。
さらに、ESG(環境・社会・ガバナンス)に配慮する姿勢も重視されています。グリーンボンドの発行実績やエネルギー消費原単位の削減計画を開示するREITは、世界的なESGマネーの流入を受けて価格下支え効果が期待できます。つまり、財務だけでなく非財務情報を丁寧に開示する姿勢が、人気と安全、そして利回りの持続性を生み出しているのです。
安全にREIT投資を始める実践ステップ
実践に移す前に、まずネット証券でREITのスクリーニング機能を使い、利回り3.5〜5%、LTV50%未満、時価総額1,000億円以上の条件で候補を絞り込みましょう。この段階で10銘柄前後に整理できるはずです。
次に、各銘柄の決算説明資料を読み、テナント分散や借入金の金利タイプ、さらには物件ポートフォリオの築年数を確認します。加えて、直近2年間の増資実績と調達目的を比較し、分配金の希薄化がないかチェックしてください。
最後に、購入は一度に集中させず時間分散を図ります。日経平均や東証REIT指数が下落した日に少額ずつ買い増す「押し目投資」を採用することで、平均取得単価を抑えられます。なお、つみたてNISA口座ではREIT個別銘柄を直接買えませんが、REIT比率の高いインデックスファンドを活用すると税制メリットも享受できます。
結論として、人気 安全 REIT 利回りの三拍子を満たす銘柄は存在しますが、指標の裏側にある資産の質と財務健全性を自分で検証する姿勢が不可欠です。
まとめ
この記事では、REITの基本構造、安全性を評価する主要指標、利回りを見る際の注意点、そして人気銘柄が支持される理由を説明しました。安全にREIT投資を始めるには、LTVやテナント分散といったリスク指標を確認し、時間分散で購入することが重要です。まずは証券会社のスクリーニング機能を活用し、候補銘柄の決算資料を読み込むことから始めましょう。自らの基準で「人気 安全 REIT 利回り」を満たす銘柄を選び、長期的な資産形成に役立ててください。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 東京証券取引所「REIT データブック 2025年10月版」- https://www.jpx.co.jp
- 金融庁「金融レポート2025」- https://www.fsa.go.jp
- 日本銀行「金融経済統計月報 2025年10月」- https://www.boj.or.jp
- 国土交通省「不動産市場動向レポート 2025年秋号」- https://www.mlit.go.jp

