不動産投資を始めたいけれど、REITやシェアハウスの違いがわからず、税金面も複雑で不安――そんな悩みを抱えていませんか。この記事では、2025年10月時点の最新制度に基づき、REITとシェアハウスそれぞれの特徴と税金の扱いをやさしく解説します。読み終えるころには、自分に合った投資スタイルを選び、適切な節税策を取るための具体的なヒントを得られるはずです。
REITとは何かを押さえる
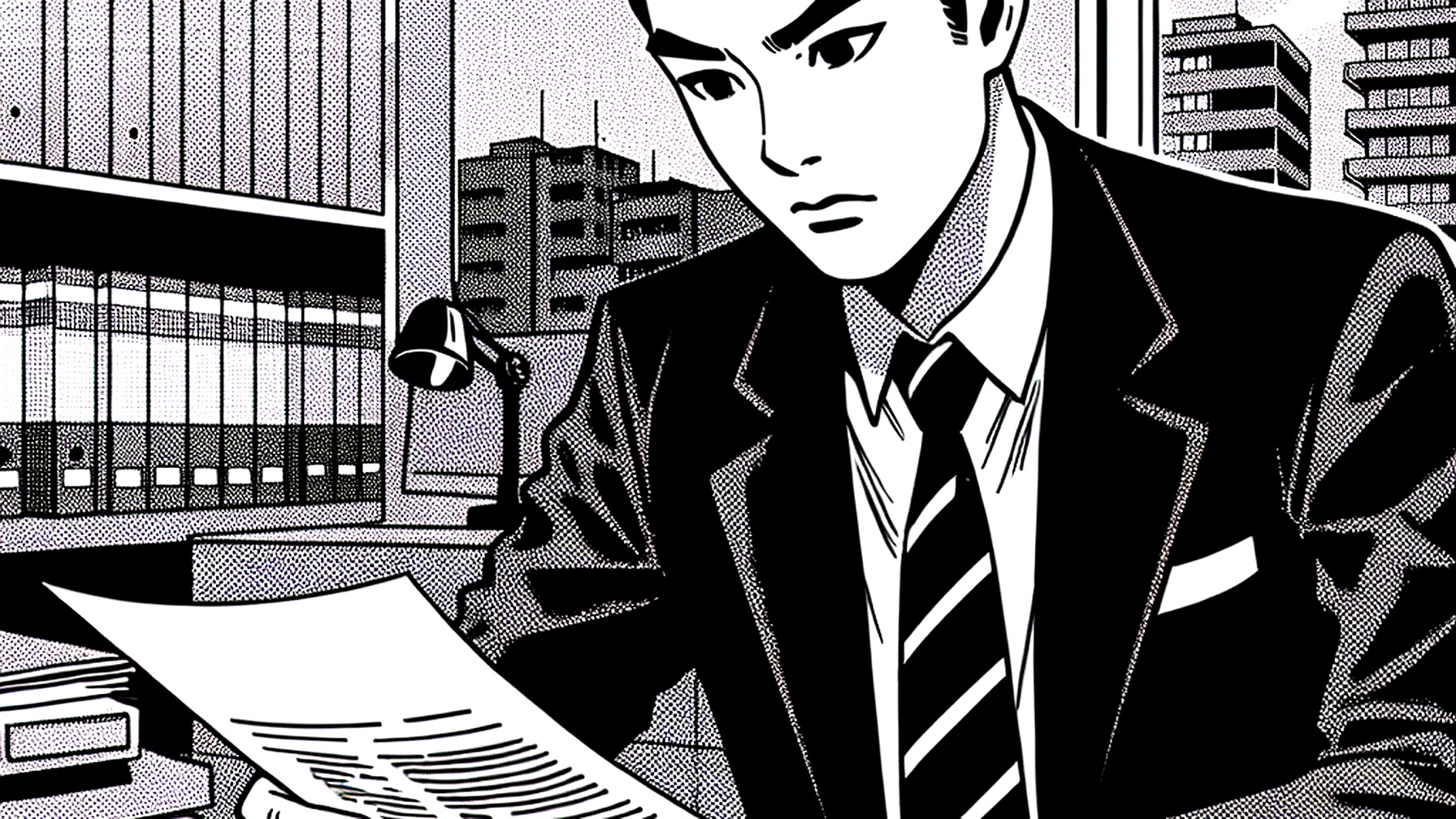
重要なのは、REIT(不動産投資信託)が「間接型」の不動産投資である点です。投資家は証券取引所を通じて口数を購入し、運用会社が複数の物件に投資する仕組みになっています。少額から分散投資ができ、売買も株式と同様に迅速に行えるため、流動性の高さが魅力です。
まず、REITの収益源は賃料収入と物件売却益であり、配当の90%以上を投資家に還元することで法人税が実質的に免除されます。この仕組みが高い分配利回りを支える一方、景気変動や金利動向による価格変動リスクも伴います。例えば、日本取引所グループの統計では、2025年上期の東証REIT指数は年初来で約7%上昇しましたが、金利上昇局面では値下がりする局面も見られました。
次に、REITの税金はシンプルです。配当は「配当所得」として総合課税または申告分離課税を選択できます。多くの投資家は上場株式等と同じ20.315%の源泉徴収で完結させていますが、所得の状況によっては確定申告により税率を下げられる可能性もあります。つまり、手間をかけずに安定したインカムゲインを得たい人に向いていると言えます。
シェアハウス運営の仕組みと魅力

実は、シェアハウス投資は「直接型」の不動産投資であり、物件を自ら所有して運営する点がREITと大きく異なります。複数の入居者でキッチンやリビングを共有するため、通常のワンルームに比べて家賃単価が高く設定でき、満室時の収益性が高まるのが特徴です。
さらに、賃貸契約は1〜6か月の短期が中心で、入居希望者の属性が多様なため、適切なマッチングと管理ができれば空室リスクを低減できます。国土交通省の調査では、2024年度のシェアハウス平均稼働率が85%前後で推移し、都市中心部では90%を超えるケースも報告されています。つまり、マーケットニーズが高いエリアを選べば、安定収益を期待しやすいのです。
一方で、運営コストと手間は通常の賃貸より増えます。家具家電の維持管理、入居者同士のトラブル対応、消防法に基づく設備点検など、多岐にわたる作業を外注する場合は管理委託費がかさみます。また、改修に伴い旅館業法や住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)に抵触しないかも確認が必要です。ここを怠ると収入停止や行政指導のリスクが出るため、事前の許認可チェックが欠かせません。
2025年度の税金ルールを押さえる
まず押さえておきたいのは、2025年度税制改正で不動産所得に関する基本的な枠組みは大きく変わっていない点です。個人オーナーが得る家賃収入は「不動産所得」として総合課税され、経費計上により課税所得を圧縮できます。青色申告を選択し、複式簿記と電子帳簿保存を満たせば、2025年度も最大65万円の控除が利用可能です。
減価償却費も節税の柱です。木造シェアハウスなら耐用年数22年で定額法を選択することが一般的ですが、中古取得の場合は「簡便法」により残存耐用年数が短縮され、年間償却費を増やせます。ただし、2025年度の国税庁通達では4万円未満の資産一括計上ルールに変更はなく、取得価格の判定基準に注意が必要です。
加えて、インボイス制度が2023年に導入されて以降、課税売上高1,000万円以下でも「適格請求書発行事業者」として登録するオーナーが増えています。2025年10月時点では、課税事業者選択届出書の提出期限や2割特例の経過措置が継続中です。シェアハウスにおける共用部分の水道光熱費やリフォーム費を仕入税額控除したい場合、インボイス登録の可否がキャッシュフローに影響しますので検討が欠かせません。
REITとシェアハウスの税務比較
ポイントは、課税方法と経費計上余地の違いです。REIT配当は源泉徴収で完結させれば追加の手続きが不要ですが、損益通算はできません。一方、シェアハウスは家賃収入に対して必要経費を差し引けるため、減価償却や借入金利息を計上して税負担を抑えられます。つまり、税効果を最大化したい場合はシェアハウスが有利に働くケースが多いのです。
ただし、シェアハウスで赤字を出した場合でも、給与所得などとの損益通算は2021年改正以降の制限に注意が必要です。具体的には、区分所有の賃貸住宅で一定の要件を満たさない場合、赤字部分が他の所得と通算できない可能性があります。2025年度もこの措置は継続されているため、木造一棟物件で規模要件を満たし、事業的規模を認められるかがポイントになります。
さらに、譲渡所得課税にも違いがあります。REITは売却益が株式譲渡所得として20.315%で課税され、保有期間による税率差はありません。一方、シェアハウスを個人で売却すると、所有5年以内は39.63%、5年超は20.315%と二段階で税率が変わります。長期保有を前提とするなら、売却時の税率軽減を活用できる点は見逃せません。
節税だけに頼らない資産形成戦略
まず押さえておきたいのは、節税はあくまでも投資リターンを高める手段であり、目的そのものではないということです。REITは様々な物件に分散投資しているため、インカムとキャピタルのバランスを取りたい投資家に向いています。加えて、NISA(少額投資非課税制度)の成長投資枠で購入すれば、配当と譲渡益は非課税になります。2025年制度では年間投資枠240万円、非課税保有期間無期限というメリットを活用しやすい点も魅力です。
一方、シェアハウスはレバレッジを効かせやすく、自己資金に対して高いリターンを狙えます。しかし、空室や修繕費のリスクを踏まえ、保守的なシミュレーションを行うことが不可欠です。金融機関の金利上昇シナリオや入居率70%の試算でも赤字にならないか確認し、減価償却費が尽きた後の税負担増にも備えましょう。
結論として、REITとシェアハウスは互いに補完関係にあります。生活防衛資金や老後資金など流動性を重視する部分はREITで保守的に運用し、長期的な資産拡大を図る部分はシェアハウスで積極的に攻めるといったポートフォリオ設計が現実的です。税金面でも、NISAの非課税枠と不動産所得の経費計上を組み合わせれば、全体の手取り収益を高めることができます。
まとめ
REITは少額で始めやすく、税手続きもシンプルな一方、価格変動リスクを受けやすい商品です。シェアハウスは手間とリスクこそ増えますが、減価償却や青色申告を駆使して税負担を抑え、高い利回りを狙える投資手法と言えます。あなたの資金量、リスク許容度、運営に割ける時間を見極め、両者を組み合わせたバランスの良い投資計画を立てましょう。まずは小さく試しながら、数字と実績で判断を重ねることが、2025年以降も安定して資産を増やす近道になります。
参考文献・出典
- 日本取引所グループ – https://www.jpx.co.jp
- 国土交通省 住宅局 – https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/
- 財務省 税制改正資料 – https://www.mof.go.jp/tax_policy/
- 国税庁 法人課税課 – https://www.nta.go.jp/
- 総務省 統計局 家計調査 – https://www.stat.go.jp/data/kakei/

