神戸でこれからアパート経営を始めようとしている方の多くは、「本当に利益が出るのか」「空室は大丈夫か」と不安を抱えています。物件価格や家賃相場は都市ごとに差があり、地方での失敗談を聞くと尻込みしてしまうのも無理はありません。しかし神戸は、港町としての歴史と観光地としての魅力を併せ持ち、安定した賃貸需要が見込めるエリアです。本記事では、初心者でも理解しやすいように「アパート経営 収益性 神戸」をキーワードに、立地選定から資金計画、リスク管理まで体系的に解説します。読み終えるころには、具体的な数字をもとにご自身の投資戦略を描けるようになるでしょう。
なぜ神戸でアパート経営が注目されるのか
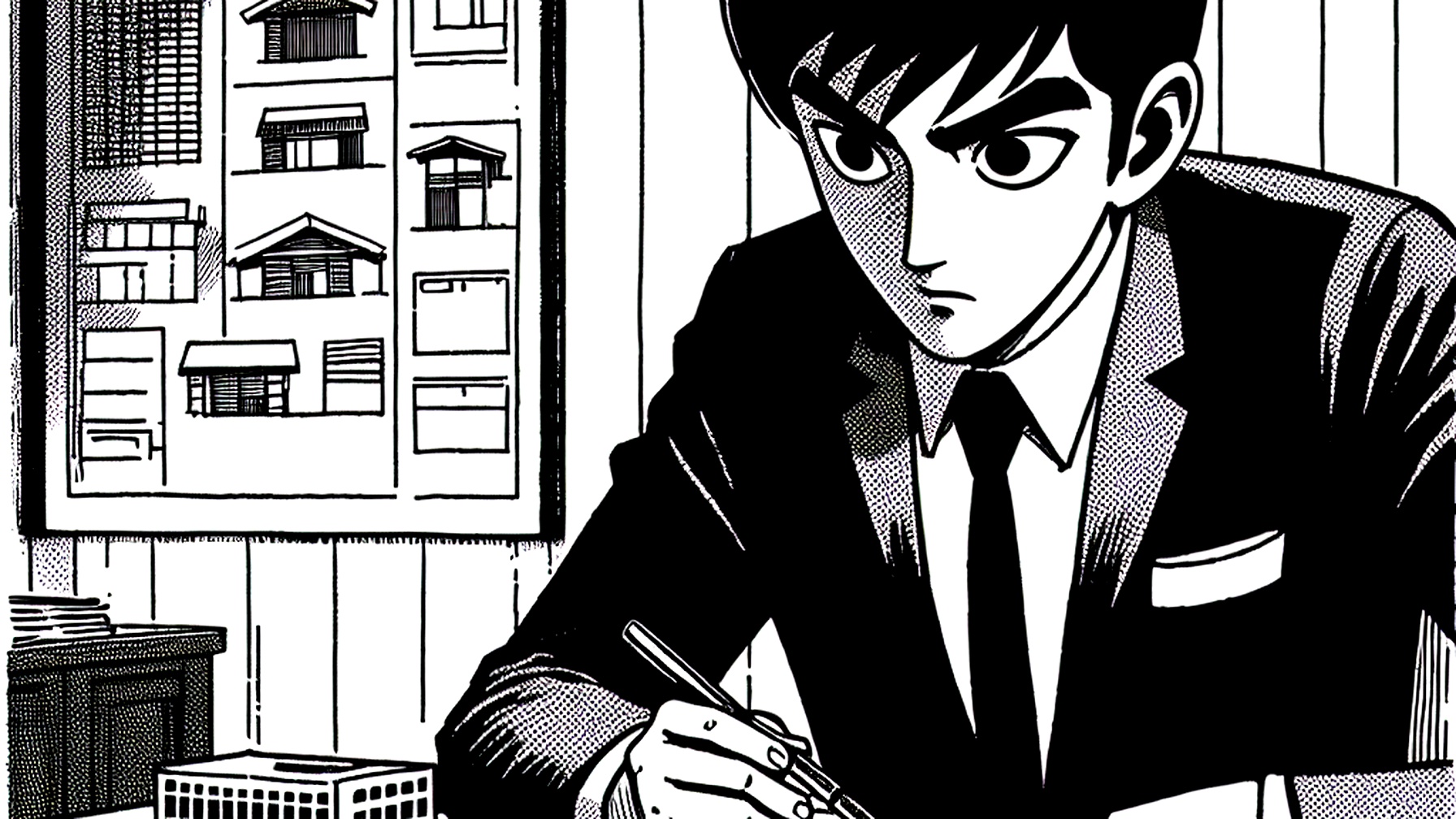
まず押さえておきたいのは、神戸特有の賃貸需要です。神戸市統計書によると2025年1月時点の人口は約152万人で、直近3年間の減少率は−0.3%にとどまりました。全国平均が−0.5%であることを考えると、比較的安定したマーケットと言えます。また、神戸港の再開発やポートアイランドの拡張計画が進み、IT関連企業の移転が相次いでいる点も追い風です。特に20〜34歳の単身世帯割合は34.8%と高く、ワンルームや1Kタイプの需要が底堅いことがデータで裏付けられています。実は、需要が底堅いにもかかわらず物件価格は大阪市中心部より15〜20%割安なエリアが多く、利回り面での優位性が際立ちます。
もう一つ見逃せないのが交通網の充実です。三宮駅を中心にJR、阪急、阪神、市営地下鉄が交差し、梅田まで最短21分、新大阪まで32分でアクセス可能です。通勤圏が広いため、神戸に住み大阪へ通う層も多く、平日と休日で家賃需要がぶれにくい特徴があります。つまり「神戸に住む必然性」と「大阪につながる利便性」の両面が収益安定化に寄与すると理解しておきましょう。
収益性を左右するエリア選定
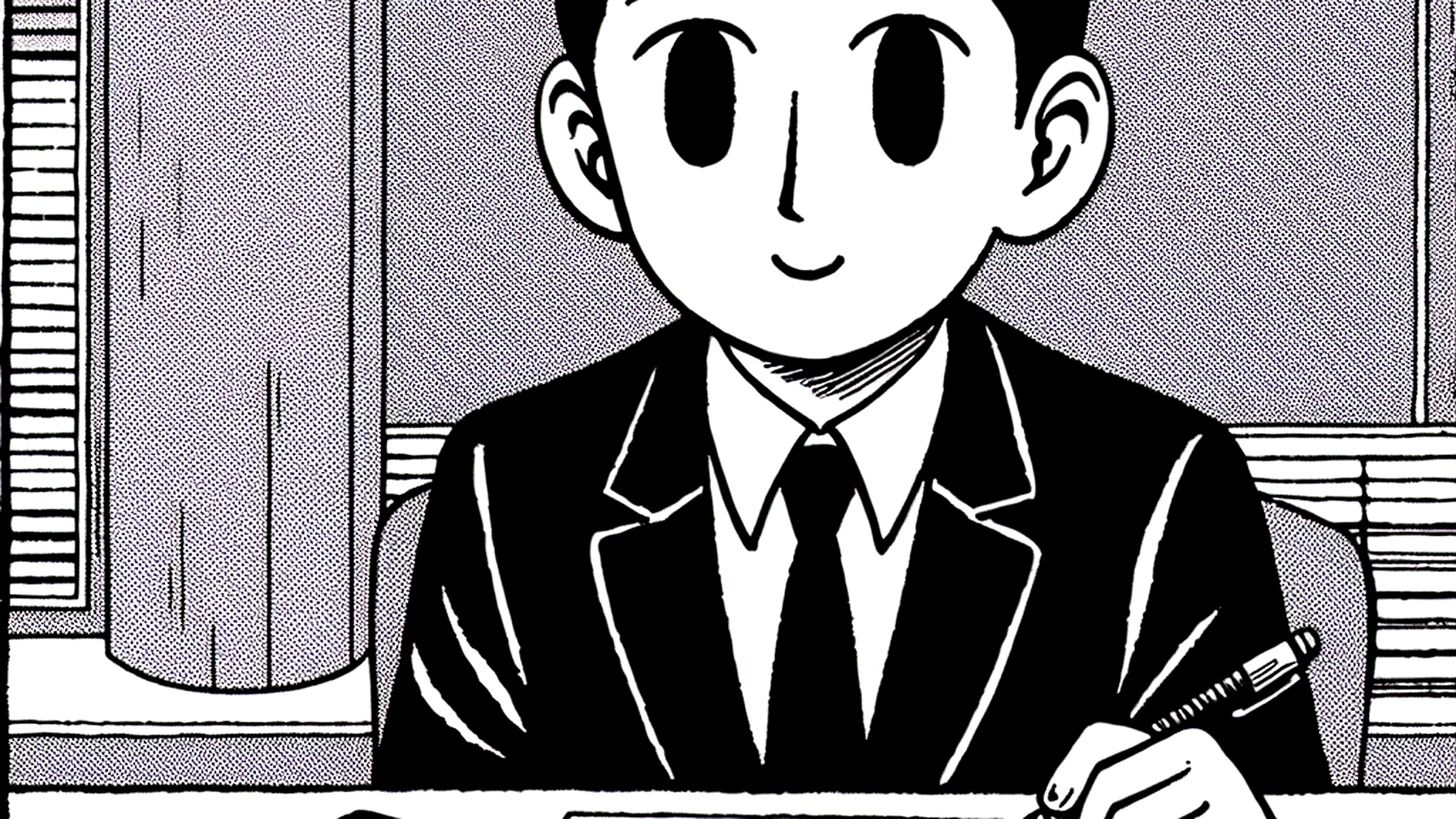
ポイントは「エリア特性」と「将来計画」を同時に読むことです。例えば三宮周辺は家賃が高く回転も早い反面、物件取得コストが大きいため初期投資がかさみます。一方で兵庫区や長田区は地価が抑えられており、表面利回りは三宮より1.0〜1.5ポイント高くなるケースが一般的です。しかし、将来の人口動態や再開発予定を考慮せずに利回りだけで判断すると、のちの空室リスクに直結します。
国土交通省が公表した2025年8月の全国アパート空室率は21.2%、兵庫県は20.5%と全国平均よりやや低い水準でした。この差は微々たるものですが、駅徒歩10分圏内に絞ると空室率は一気に14%台に下がります。つまり「駅近・再開発エリア」の組み合わせが最も空室リスクを抑える近道になります。また、神戸市が進める「三宮クロススクエア計画」や「新港突堤西地区再開発」は、完成後の居住人口増と地価上昇が期待されるため、周辺の賃貸需要を押し上げる可能性が高いです。こうした計画は市のホームページで随時更新されているので、購入前に必ずチェックしましょう。
実際のキャッシュフローシミュレーション
重要なのは、表面利回りだけでなく手元に残るキャッシュを把握することです。ここでは、兵庫区で築浅木造アパート(総戸数8戸、購入価格8,800万円)をフルローンで取得するケースを見てみます。家賃は平均5.8万円、稼働率95%、20年元利均等返済で金利は固定1.5%と仮定します。固定資産税と管理費、修繕積立を含めた運営費率は25%です。
‐ 年間家賃収入:5.8万円 × 8戸 × 12か月 × 0.95 = 528万円 ‐ 運営費:528万円 × 0.25 = 132万円 ‐ 年間返済額:8,800万円 × 1.5% 金利、20年返済 → 約510万円 ‐ 税引前キャッシュフロー:528万円 − 132万円 − 510万円 = ▲114万円
この数字だけを見ると赤字ですが、ここで忘れてはならないのが減価償却です。木造アパートの法定耐用年数22年に対し、築浅であっても年間約300万円の減価償却を計上できます。所得税・住民税を合算し35%の課税所得がある場合、課税額を約105万円圧縮できるため、実質キャッシュフローは-9万円に改善します。また、元金返済分約320万円が資産形成に回っている点も考慮すれば、純粋な投資効果はプラスと判断できます。
つまり初年度の手残りが少なくても、節税効果と元金返済による資産増加まで含めれば、神戸の木造アパートでも十分な収益性を見込めるわけです。さらに稼働率を97%に高め、運営費率を23%まで下げられれば税引き後キャッシュフローが70万円ほど増加しますので、管理会社の選定と賃料設定の精度が収益性を左右すると理解しましょう。
2025年度制度を活用した資金計画
まず押さえておきたいのは、2025年度も継続が決まっている「住宅取得等資金贈与の非課税枠」と「ZEH化補助金」です。前者は親子間での贈与に対し最大1,000万円まで非課税となる制度で、自己資金を厚くできるため金融機関の評価が上がります。後者はアパートに高断熱・高効率設備を導入した場合、1戸あたり最大40万円の補助が受けられる仕組みです。期限は2026年3月交付申請分までですが、予算枠に達し次第終了するため、早めの計画が肝心です。
一方で、融資環境も見逃せません。日本銀行は2025年7月の金融政策決定会合で短期金利ゼロ%誘導を維持し、長期金利の上限を1.5%程度に設定しています。これに伴い、地銀や信金のアパートローン金利は1.3〜1.8%で推移しており、2010年代後半の水準に比べておおむね安定しています。また、神戸市内に本店を置く兵庫信用金庫では、耐震・省エネ基準を満たす賃貸住宅向けに最大40年、LTV(融資比率)90%までの融資商品を展開中です。融資条件は随時変動するため、最新の金利と自己資金割合を複数行で比較し、シミュレーションを更新する習慣を付けましょう。
リスク管理と出口戦略
実は、収益性向上の裏側にはリスクが潜んでいます。空室期間が想定より長引けばキャッシュフローは一気に赤字化し、資金繰りを圧迫します。そこで、サブリースや家賃保証を検討する方もいますが、保証料が表面利回りを年間1〜2ポイント下げる可能性があります。短期的な安心感と長期的な収益性のバランスをどう取るかがカギとなります。
さらに、自然災害への備えも必要です。神戸は南海トラフ巨大地震の影響が懸念される地域に位置しているため、耐震等級2以上の建物を選ぶか、リノベーションで耐震補強を行うことが推奨されます。火災保険と地震保険の補償範囲と免責金額を確認し、実際の負担額を把握することで、万が一の損失を最小化できます。また、物件の出口戦略として、保有期間10年で売却益を狙うのか、20年以上保有して家賃収入を最大化するのか、購入前にシナリオを決めておくことがリスク低減につながります。
結論として、神戸でアパート経営を成功させるには「需要を支える人口動態」「再開発による将来価値」「制度と融資環境の活用」「緻密なリスク管理」の四つを有機的に組み合わせる必要があります。これらを踏まえた出口戦略が、収益性を最大化する最後のピースになるでしょう。
まとめ
ここまで「アパート経営 収益性 神戸」を軸に、市場動向から資金計画、リスク管理まで総合的に解説しました。神戸は人口減少が緩やかで再開発が活発なため、賃貸需要が底堅い点が強みです。駅近エリアを中心に物件を選べば、全国平均より低い空室率で安定した収入を期待できます。さらに、2025年度の非課税贈与枠やZEH化補助金を活用すれば自己資金を厚くし、金利負担も抑えられます。行動に移す際は、複数の金融機関で融資条件を比較し、空室リスクと自然災害リスクに対応した保険・補強策をセットで検討してください。早めに動くことで選択肢が広がり、神戸の魅力を最大限に生かしたアパート経営へ一歩踏み出せるはずです。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅統計調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 神戸市統計書(2025年版) – https://www.city.kobe.lg.jp
- 日本銀行 金融政策決定会合資料 2025年7月 – https://www.boj.or.jp
- 兵庫信用金庫 融資商品情報 2025年10月時点 – https://www.hyoshin.co.jp
- 国土交通省 ZEH補助金交付要綱(2025年度) – https://www.mlit.go.jp

