個人で事業を営みながら「もう一つの柱」を探している方は多いはずです。売上が季節や景気に左右されると、キャッシュフローが安定せず不安が募ります。そこで注目されているのが、少額から始められ比較的手間もかからない不動産クラウドファンディングです。本記事では、個人事業主がこの新しい投資手法を利用するメリットと注意点を分かりやすく解説します。読み終えたとき、あなたはサービスの選び方から税務管理まで一通りのポイントを把握でき、次の一歩を自信を持って踏み出せるでしょう。
個人事業主がクラウドファンディングを選ぶ理由

まず押さえておきたいのは、事業所得と投資所得を組み合わせることで資金繰りを滑らかにできる点です。国税庁の「個人事業主の平均年間所得」データによると、サービス業では年度ごとの変動幅が10%以上になる例もあります。この不安定さを補うために、家賃収入を原資とするファンドに分散投資すれば、売上が落ちた月でも最低限の収入を確保しやすくなります。
次に、運営会社が物件の選定から管理まで担うため、本業が忙しい個人事業主でも時間を取られにくい点が魅力です。従来の直接投資では物件調査や入居者対応が重荷になりますが、クラウドファンディングならクリック一つで完結します。つまり、専門知識が浅くても「レバレッジ」をかけて不動産の恩恵を受けられるわけです。
加えて、最低1万円前後から投資できるサービスが多く、手元資金が限られていても参加しやすいのが特徴です。金融庁の調査では、2025年時点で公募型ファンドの平均最低投資額は約8万円ですが、不動産クラウドファンディングはその十分の一程度に下がります。少額で複数案件に分散できるため、リスクコントロールもしやすいと言えるでしょう。
2025年時点の仕組みと利回りの目安
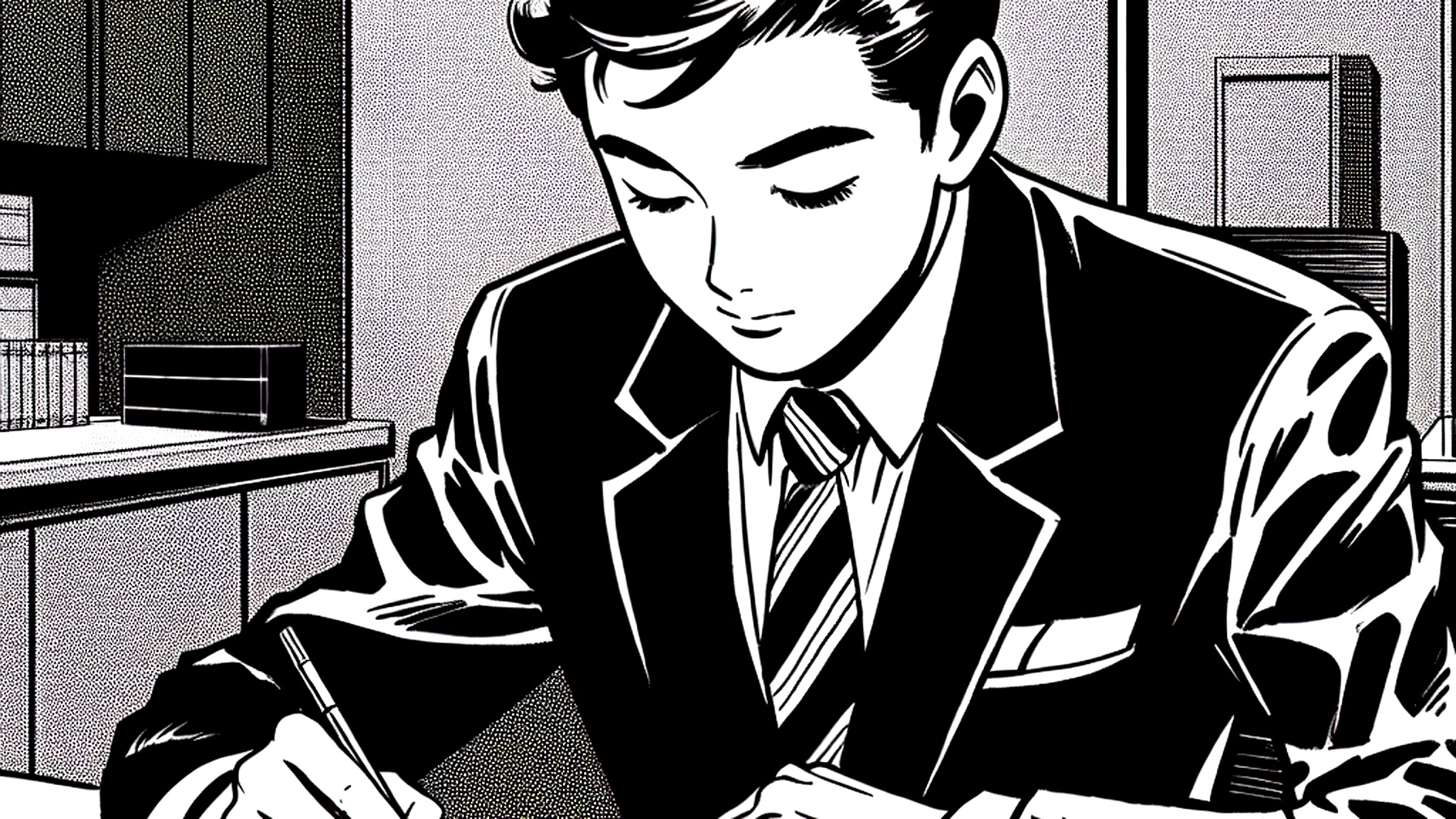
実は、不動産クラウドファンディングは大きく「任意組合型」と「匿名組合型」の二つに分かれます。両者の違いは、投資家が物件を直接保有するかどうかにあり、前者はより権利が強い一方、後者は手続きが簡便です。どちらも不動産特定共同事業法に基づき、2025年10月現在はオンライン完結型の契約が認められています。
利回りは物件タイプで差があります。東京23区内の新築レジデンスを対象にした案件では年利3〜4%が中心ですが、地方の築古再生案件になると6%を超える例も珍しくありません。国土交通省「不動産証券化市場の動向」によれば、2024年度の全国平均賃料上昇率は前年比1.3%。つまり、安定志向なら都心の低利回り案件、リスク許容度が高いなら地方高利回り案件を選ぶと合理的です。
運用期間は6カ月から3年程度が主流です。短期案件は資金回転を速めやすい一方、途中解約ができない点に注意が必要です。また、配当は年2〜4回に分けて支払われることが多く、青色申告をしている個人事業主なら「雑所得」として計上しておくと帳簿付けがスムーズになります。
リスク管理と税務のポイント
ポイントは、リスクを「案件リスク」と「制度リスク」に分けて把握することです。前者は空室や賃料下落、後者は法律改正や事業者倒産が該当します。そこで、運営会社の財務開示や過去の償還実績を必ず確認しましょう。金融庁の行政処分情報によると、2022年以降、延滞を理由に業務改善命令を受けた事業者は3社にとどまっていますが、ゼロではありません。
税務面では、配当が「雑所得」として総合課税になる点が重要です。所得が大きいほど税率も上がるため、青色申告特別控除65万円を確実に受けつつ、経費算入できる通信費やシステム利用料を漏れなく記帳すると節税効果が高まります。また、2025年度も継続している小規模企業共済は、掛金全額を所得控除できるため、他の節税策と組み合わせると手取りが増えやすくなります。
さらに、万が一の損失が出た場合は雑所得内でしか相殺できません。損金計上できない点は株式投資と大きく異なるため、投資額を年商の5〜10%以内に抑えるなど、定量的なルールを設けると安心です。
サービス比較で見るおすすめの選び方
まず、想定利回りと運用期間を軸に三つのタイプに分類してみましょう。
- 短期・低利回り型: OwnersBook(平均利回り3.8%、期間6〜12カ月)
- 中期・中利回り型: CREAL(平均利回り4.5%、期間12〜24カ月)
- 長期・高利回り型: ジャパンインフラファンド(平均利回り6.2%、期間24〜36カ月)
事業者の公式実績を元にまとめると、個人事業主が最初に選びやすいのは中期・中利回り型です。なぜなら、運用期間が長すぎると資金がロックされ、短すぎると再投資の手間が増えるため、事業資金の流動性を保ちやすいバランスが取れるからです。
加えて、サービスの管理手数料や途中譲渡制度の有無もチェックポイントです。たとえばCREALは投資家向けマイページで帳簿用CSVをダウンロードできるため、会計ソフトへの入力が簡単です。一方、OwnersBookは住宅系案件が中心で、安全性を重視する投資家に向きます。つまり、自分の事業サイクルとリスク許容度を照らし合わせて選ぶことが、長期的な成功への近道になります。
実践ステップと成功事例
重要なのは、準備・投資・検証の三段階をループさせることです。まず、会計ソフトで毎月の利益と支出を把握し、余剰資金を算出します。次に、その範囲内で複数案件に少額ずつ投資し、案件ごとの配当日と確定申告書類をカレンダーに登録しておきましょう。
実際の成功例として、都内でデザイン事務所を営むAさん(年商1,500万円)は、2023年からCREALとRimpleを併用し、余剰資金の8%を投資しています。2025年9月までに計12案件へ分散し、平均年利4.4%を実現しました。Aさんは配当をプリンタの買い替え費用に充当し、事業の生産性向上につなげています。言い換えると、不動産クラウドファンディングは「投資益を事業へ再投資する好循環」を作りやすいのです。
最後に、半年ごとにポートフォリオを見直し、賃料動向や金利環境を確認する習慣を付けると、リスクを機動的にコントロールできます。
まとめ
本記事では、個人事業主が不動産クラウドファンディングを活用する理由からサービスの選び方、税務上の注意点までを整理しました。多忙な事業オーナーでも、少額かつ非対面で不動産収益を得られる点は大きな魅力です。一方で、雑所得課税や損失通算制限など独特のルールもあるため、余剰資金の範囲内で複数案件へ分散し、半年ごとの検証を忘れないことが成功の鍵となります。まずは会計ソフトでキャッシュフローを可視化し、あなたの事業に最適なファンドを少額から試してみてはいかがでしょうか。
参考文献・出典
- 国税庁「令和6年度 民間給与実態統計調査」 – https://www.nta.go.jp/
- 国土交通省「不動産証券化市場動向レポート2025」 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁「クラウドファンディング業者に関する行政処分情報」 – https://www.fsa.go.jp/
- 中小企業庁「2025年度 小規模企業共済パンフレット」 – https://www.chusho.meti.go.jp/
- 総務省統計局「家計調査2024年版」 – https://www.stat.go.jp/

