不動産投資を始めようと思ったとき、「事故物件は利回りが高いらしい」と耳にして興味を持つ人は少なくありません。しかし実際には、説明義務や売却難易度など独特のリスクが潜んでおり、知らずに手を出すと後悔するケースも多いです。本記事では、上場不動産投資信託(REIT)を通じて事故物件に間接的に関わる場合と、現物で保有する場合の違いを整理しながら、2025年10月時点で考えられるデメリットを分かりやすく解説します。最後まで読むことで、事故物件のリスクを適切に見極め、より安全な投資判断ができるようになるでしょう。
REITと事故物件、それぞれの基本を整理する
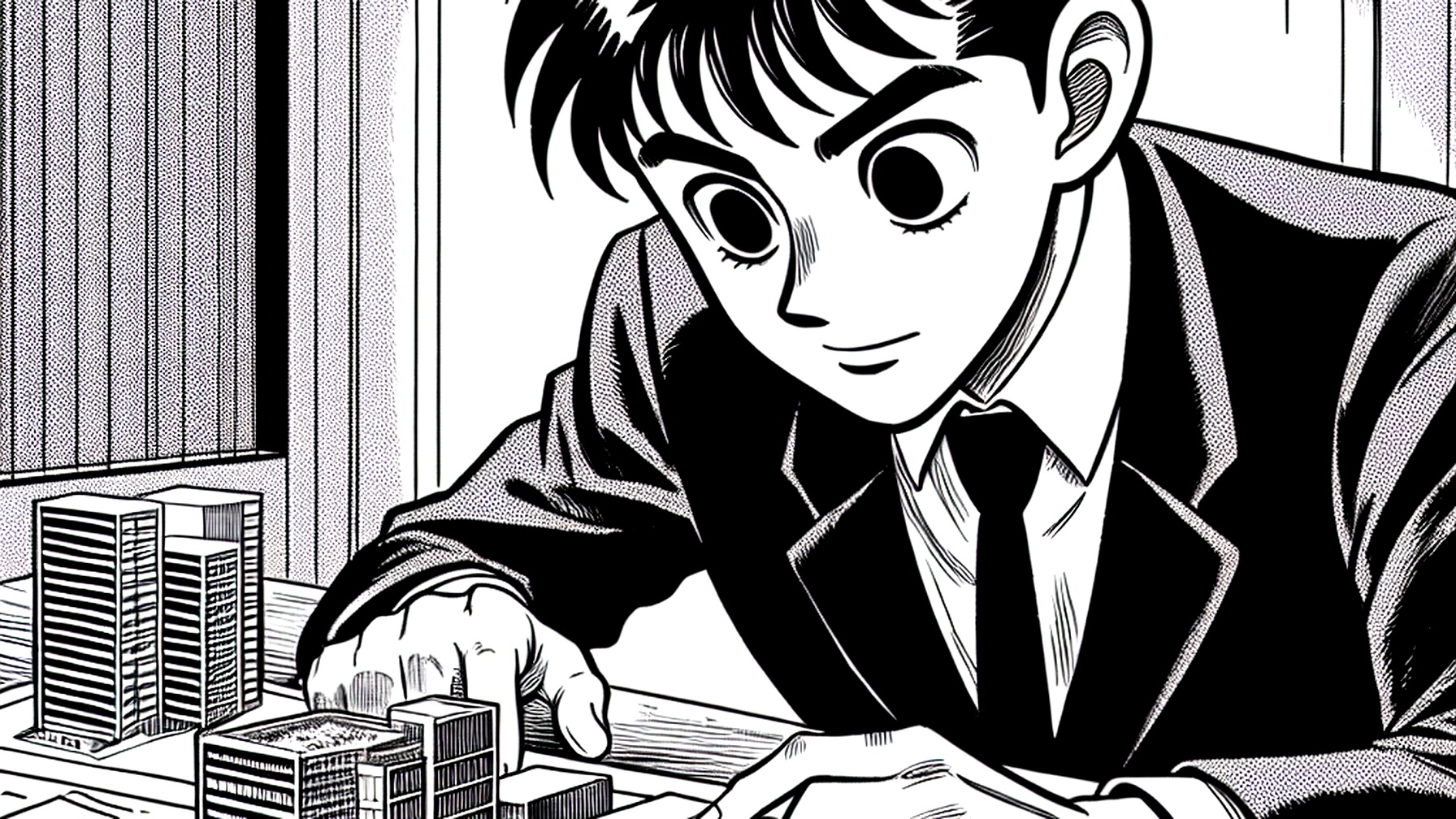
まず押さえておきたいのは、REITと事故物件の定義がまったく異なる領域にある点です。REITは投資家から集めた資金で複数の不動産を保有し、その賃料収入や売却益を分配する金融商品です。一方、事故物件とは殺人、自殺、火災など心理的瑕疵があるとみなされる物件の総称で、宅地建物取引業法の告知義務により取引時には情報開示が必要となります。
重要なのは、REITの組み入れ物件が必ずしも事故物件であるとは限らないものの、ポートフォリオ内に含まれる可能性がゼロではないという事実です。REITは数十から数百棟の不動産を保有するため、個々の物件の詳細まですべてを把握するのは一般投資家には難しい側面があります。また、事故発生後に早期対応が取られれば市場価格への影響が軽微にとどまることもあり、目立ちにくいまま保有されるケースもあり得ます。
一方で、事故物件は賃料が低く設定される傾向があり、表面利回りが高く見えることがあります。実は、この魅力的に映る数字が投資家を引きつける一方で、大規模修繕や入居募集の長期化といった隠れたコストを伴う点が見落とされがちです。言い換えると、事故物件のリスクを正確に把握しないまま数字だけで判断すると、想定外の損失を被る恐れがあるのです。
実物で事故物件を保有する場合のリスク
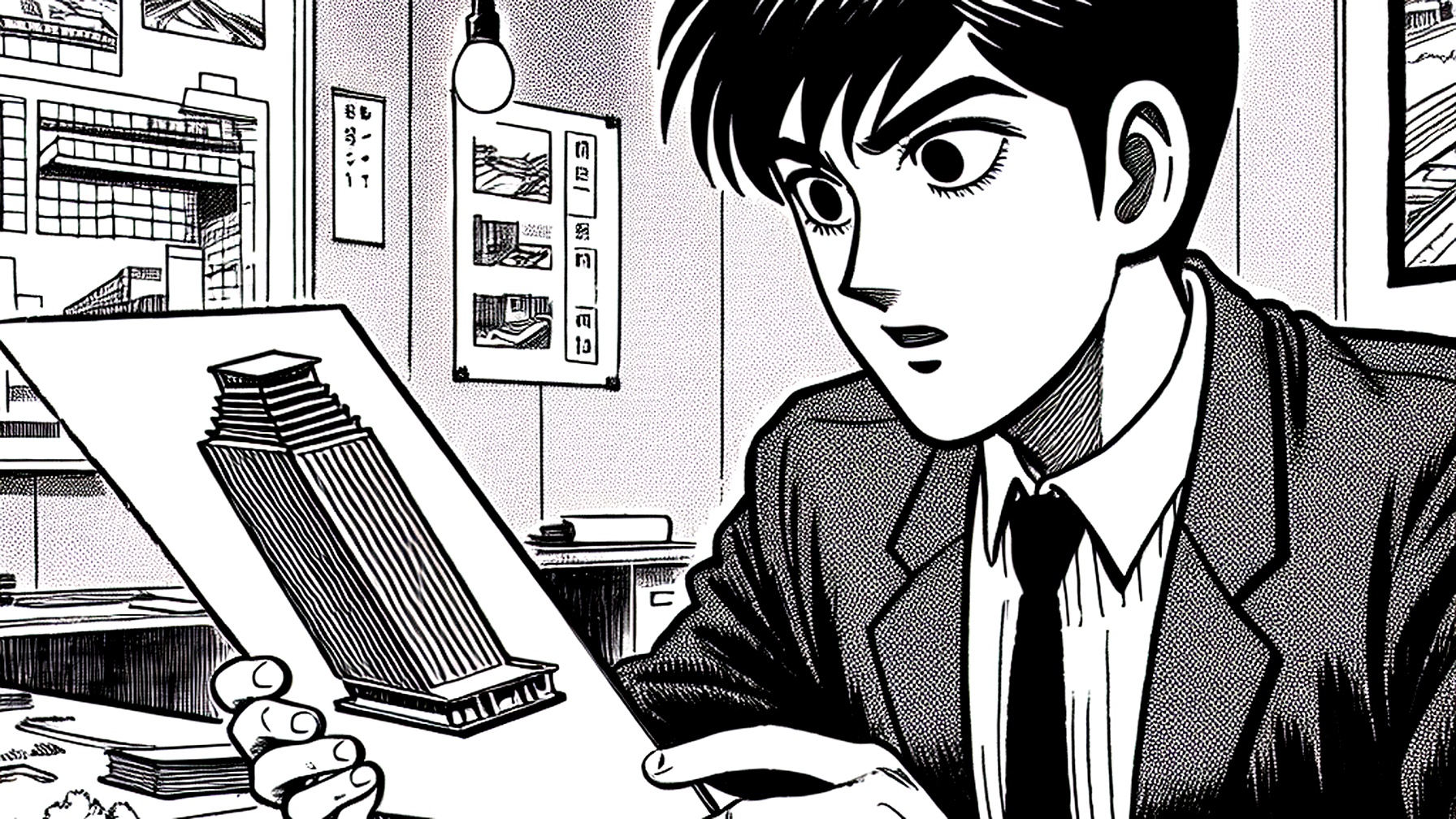
ポイントは、現物投資では買主が直接的に全責任を負うという点です。事故物件を購入すると、貸主として入居希望者へ事故歴を告知する義務が発生します。この告知を避けると宅地建物取引業法違反となり、最悪の場合は損害賠償請求を受けるリスクがあります。
さらに、入居率の低下はキャッシュフローを直撃します。国土交通省の「住宅市場動向調査(2024年版)」によると、心理的瑕疵が疑われる物件は同一立地の通常物件と比べ平均入居期間が約30%長くなる傾向が報告されています。空室期間が延びれば、家賃を引き下げてでも入居を促す必要が生じ、結果として手取り収益が減少します。
売却時にも課題が残ります。事故物件の履歴は不動産登記簿に直接記載されないものの、近隣住民やインターネット掲示板を通じて情報が共有されやすく、買い手が限定されやすいです。つまり出口戦略が取りにくく、長期的な資産価値の伸びを期待しづらい点が最大のデメリットと言えるでしょう。
REITを通じて事故物件に間接的に関わるリスク
重要なのは、REITに投資する場合でも事故物件リスクが完全に消えるわけではないことです。投資口価格はポートフォリオ全体の収益見通しで決まるため、保有物件の一部で重大な事故が起これば分配金の減額要因となり得ます。東京証券取引所が公表する「J-REIT市場レポート」では、2023年にあるREITが保有するホテルで火災が発生した際、当該銘柄の投資口価格が翌日に2.8%下落した事例が紹介されています。
また、REITは物件売却の損益を会計上で平準化することが多く、事故物件の存在がファンドの決算資料に明確に表れない場合があります。投資家は決算説明資料や物件概要図を読み込み、所在地や用途を確認する作業が欠かせません。一方で、運用会社が迅速にリノベーションを行い、稼働率を維持できればネガティブインパクトが限定的になることもあります。このように、リスクの存在をゼロにすることはできませんが、分散効果により影響は薄まる可能性があります。
それでもREITで事故物件が混入する最大のデメリットは、「投資家自身でコントロールしにくい」という点に尽きます。物件選定や売却のタイミングは運用会社の判断に委ねられるため、個別事情を理由に短期で売却してほしいと求めても応じてもらえません。したがって、リスク許容度に応じて銘柄を絞り、月次レポートを定期的に確認する姿勢が求められます。
知らずに買うことの危険性と見抜くポイント
実は、事故物件かどうかを完全に見抜く方法は存在しませんが、被害を最小限に抑えるための着眼点はいくつかあります。まずIR資料の「物件別稼働率推移」を時系列でチェックし、特定物件だけ極端に稼働率が低下していないかを確認します。もし低下している場合は、事故や大規模修繕が発生している可能性を疑う余地があります。
次に、運用会社が設定する「賃料減額損失引当金」の動向も重要です。日本公認会計士協会のガイドラインによると、心理的瑕疵が発生した物件について一定期間内の賃料減額が見込まれる場合に、この引当金を積むことが推奨されています。引当金の増減が大きい場合、その背景を決算短信や補足資料で探ることで、潜在的な事故物件リスクを把握できます。
個人で物件を購入する場合は、国土交通省が2025年に改訂した「宅建業者による心理的瑕疵の説明指針」を活用しましょう。指針では、死亡事故が発生した場合の告知期間を概ね5年間とする一方、賃貸物件では借主が特段の心理的不安を感じると判断される事例では告知が必要と明記されています。つまり期間が経過しているから大丈夫と安易に考えるのではなく、周辺調査や入居者アンケートを通じて実態を確認する作業が欠かせません。
2025年時点の情報開示ルールと投資家が取るべき行動
ポイントは、2025年度から段階的に導入されている「不動産取引DX推進ロードマップ」により、REIT運用会社の情報開示が拡充されている点です。具体的には、物件ごとのESGリスクとともに、心理的瑕疵事案の対応方針を開示することが東証の自主ルールで求められるようになりました。この流れを受け、主要J-REITの約7割が2025年6月期決算から該当情報を盛り込んでいます。
投資家としては、まず月次レポートやアニュアルレポートを読み、事故物件発生時の具体的な対応策が記載されているかをチェックしましょう。言い換えると、開示が不十分な銘柄はリスク管理体制が整っていない可能性があるため、投資対象から外す判断も合理的です。また、個別面談やオンライン説明会を活用し、運用会社に直接質問する姿勢も欠かせません。
最後に、REITと現物投資のどちらを選ぶにせよ、心理的瑕疵リスクを完全に排除することは不可能です。しかし、情報開示ルールの強化とデータ分析ツールの進化により、過去よりも早い段階で兆候を察知できる環境が整いつつあります。自らのリスク許容度と投資スタイルを踏まえ、定期的なモニタリングを続けることが、安全運用への近道と言えるでしょう。
まとめ
本記事では「REIT 事故物件 デメリット」という切り口で、不動産投資に潜む心理的瑕疵リスクを整理しました。実物保有では告知義務や売却難が重くのしかかり、REITでも完全に無視できるわけではありません。とはいえ、2025年以降は情報開示の強化が進み、データからリスクを推定しやすくなっています。投資家としては資料を読み込む習慣を持ち、疑問点を運用会社に確認する行動を欠かさないことが大切です。自分の許容できるリスクの範囲を明確にし、慎重かつ前向きに投資判断を下しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 住宅市場動向調査2024年版 – https://www.mlit.go.jp
- 東京証券取引所 J-REIT市場レポート2024 – https://www.jpx.co.jp
- 日本公認会計士協会 不動産評価ガイドライン2024 – https://www.hp.jicpa.or.jp
- 金融庁 サステナビリティ開示基準2025 – https://www.fsa.go.jp
- 消費者庁 心理的瑕疵に関する消費者相談事例集2024 – https://www.caa.go.jp

