不動産投資に興味はあるものの、「区分より一棟を買った方が収益は大きいらしい」と聞いて二の足を踏んでいませんか。確かに一棟買いは金額も責任も大きいため、初心者にはハードルが高く感じられます。しかし、正しい知識と準備があれば安定したキャッシュフローを得られる魅力的な手法です。本記事では「マンション投資 一棟買い」の基礎から2025年9月時点の融資環境、物件選定のコツまでを丁寧に解説します。読み進めることで、リスクを抑えながら一棟買いに挑戦するための具体的な道筋が見えてくるはずです。
マンション一棟買いとは何か
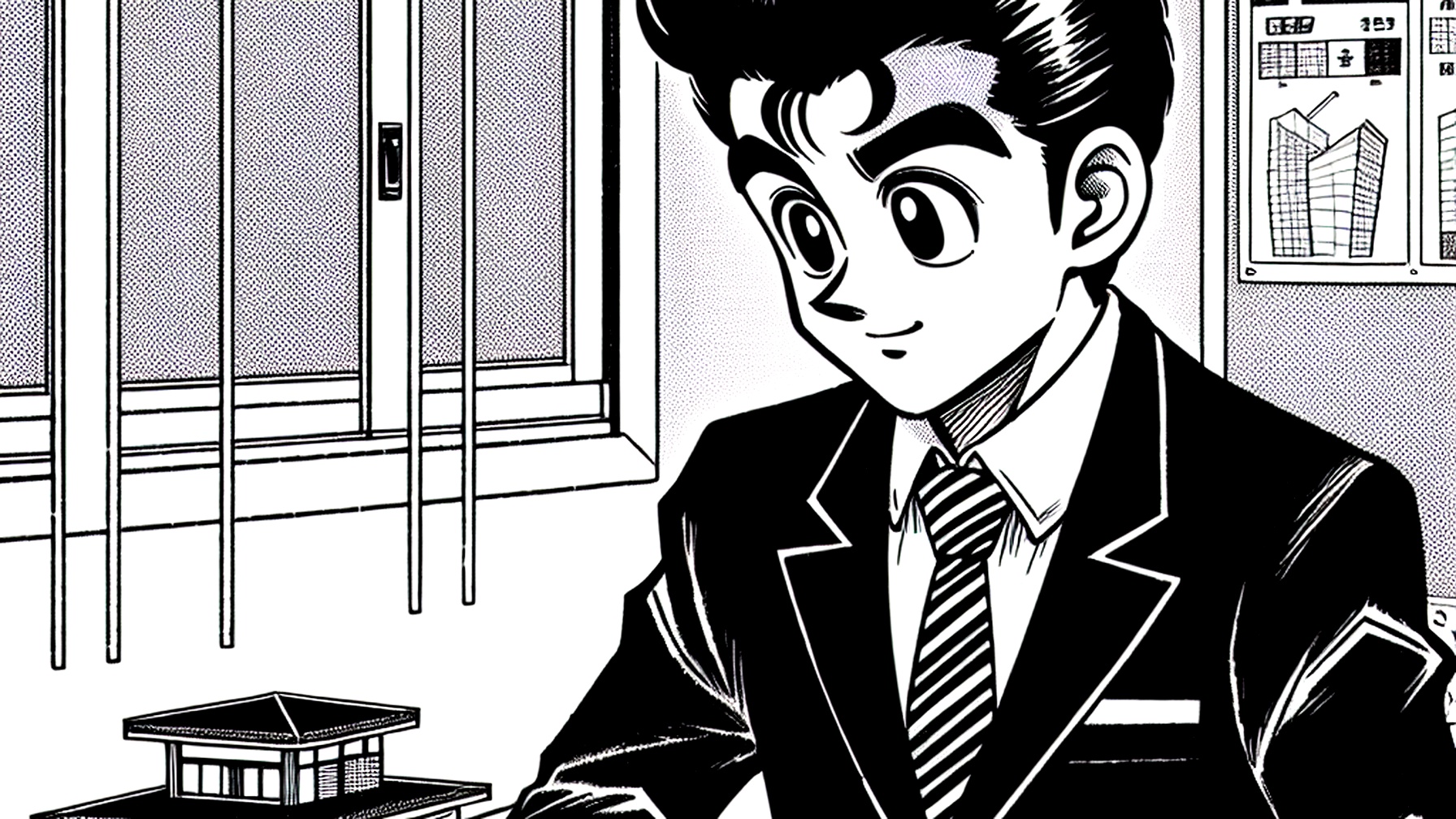
まず押さえておきたいのは、区分所有との違いです。一棟買いは建物と土地を丸ごと取得し、共用部を含む管理責任を引き受けます。つまり賃料設定、修繕計画、入居者募集などを自らコントロールできる一方、すべての運営コストも負担するという構造です。
一般的に一棟物件の利回りは区分より高めに設定される傾向があります。国土交通省の「不動産価格指数」を見ると、2025年上期の都心区分マンション利回りは平均3.4%ですが、同エリアの築15年前後の一棟マンションでは5.1%前後が目安です。利回りが高い理由は、空室や修繕のリスクを投資家自身が直接負う点が織り込まれているからだと理解しましょう。
一方で一棟買いには、金融機関が土地の担保評価を重視するという特徴があります。土地値がしっかり出る立地であれば、融資期間が長く条件も好転しやすいのが実情です。つまり、建物より土地の資産性が重要なファクターになるのです。
初心者が見落としやすいリスクと対策
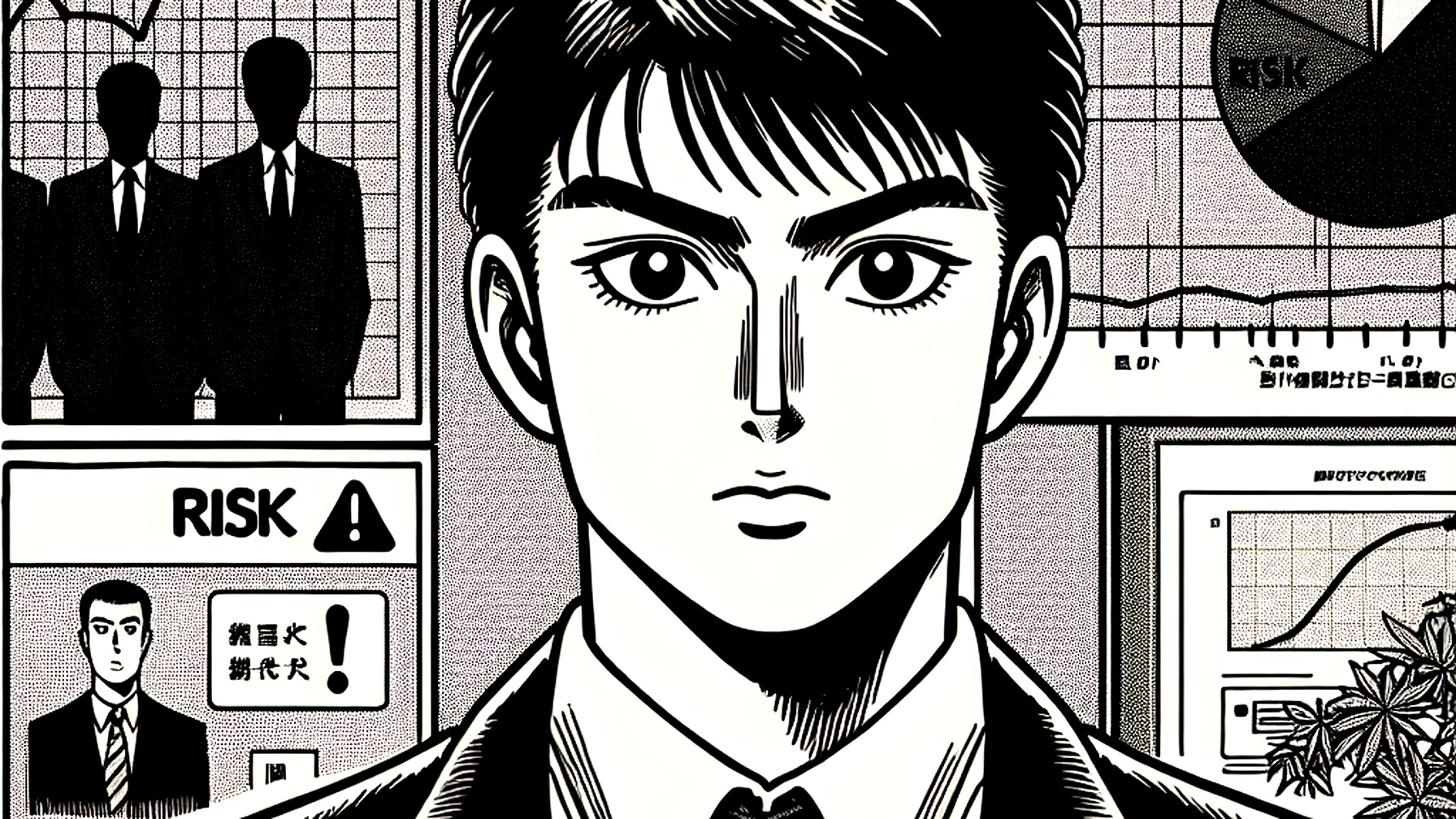
ポイントは、建物老朽化・空室・金利上昇という三つのリスクを同時に管理する必要があることです。まず建物老朽化ですが、築年が古いほど修繕積立不足が起こりやすく、大規模改修費用は一度に数百万円規模となります。実は築20年前後で最初の大規模修繕が必要になるケースが多いため、購入前に長期修繕計画の有無を必ず確認しましょう。
次に空室リスクです。総務省統計局の住宅・土地統計調査によると、2023年から25年にかけて東京23区の賃貸住宅空室率は平均11.6%で横ばいですが、郊外では14%を超えています。周辺の新築供給量や将来の人口動態を読み解き、家賃下落シナリオでも収支が成り立つか試算することが不可欠です。
最後に金利上昇リスクを見ていきます。金融庁のモニタリング資料によれば、2025年9月時点で主要地銀の変動金利は平均2.4%ですが、長期プライムレートは緩やかに上昇傾向です。返済期間30年の融資で1%金利が上がると、年間返済額は1億円の借入で約100万円増える計算になります。したがって、金利上昇2%まで耐えられるキャッシュフローシミュレーションを事前に用意しておくと安心です。
資金計画と2025年度の融資環境
重要なのは、自己資金と融資をバランス良く組み合わせることです。一般的に一棟買いでは物件価格の20〜25%を自己資金として用意すると、金融機関の評価が上がり、金利を0.2〜0.4%下げられるケースが多いとされています。
2025年度の融資トレンドを見ると、地銀や信金は一都三県の築浅RC造に対して融資期間35年、フルローン可という姿勢を維持しています。ただし、サブリース契約に依存した収支計画には慎重で、実際の入居実績を重視する傾向が強い点に注意してください。
また、政府系金融機関の「中小企業向け長期融資制度(2025年度)」を活用すると、環境性能が一定基準を満たすマンションについては最大1%の金利引き下げが適用されます。適用期限は2026年3月末までと明記されており、エネルギー効率証明書の取得が前提条件となるため、早めの準備が肝心です。
自己資金を投じたうえで長期固定金利を組むか、変動金利で初期キャッシュフローを厚くするかは投資家のスタンスによります。どちらの方法でも、返済比率を家賃収入の50%以下に抑えると資金繰りが安定し、突発的な修繕にも対応しやすくなります。
物件選定で押さえるべき三つの視点
まず立地です。東京都都市整備局の将来人口推計によれば、23区の中でも千代田・港区は今後10年で人口微増が見込まれる一方、足立・葛飾区は微減と予測されています。同じ都心でもエリアごとの違いを数値で把握し、需要が下がりにくい地域を狙うことが効率的です。
次に建物構造を見極めましょう。鉄筋コンクリート(RC)造は法定耐用年数47年と長く、長期融資を組みやすい一方、取得価格が高くなります。これに対し木造アパートは利回りこそ高いものの、融資期間が短い傾向があります。つまり、長期安定を重視するならRC、高利回り短期回収を狙うなら木造と方針を明確にすることが重要です。
三つ目は出口戦略です。将来の売却価格を考える際、土地値が物件価格の30%以上占めると価格下落のリスクを抑えやすいとされています。不動産経済研究所が公表する2025年9月時点の新築マンション平均価格7,580万円(東京23区)を基準に、土地値を逆算し、購入価格が適正かどうか判断しましょう。
運営開始後の収益最大化のコツ
まず家賃設定は「周辺相場×0.98」を目安にスタートし、入居率95%を超えた段階で順次改定する方法が効果的です。これにより初期の空室期間を短縮し、月次キャッシュフローを早期に安定させられます。
運営コストの適正化も欠かせません。管理会社へ委託する場合、管理料5%が相場ですが、一棟物件では4%未満まで交渉できる余地があります。さらに、LED照明や太陽光パネルを導入して共用部電気代を削減すると、年間で数十万円の経費削減につながります。
また、国土交通省の「住宅セーフティネット制度」を活用し、一定の要件を満たす住宅として登録すると空室を自治体が紹介してくれる仕組みがあります。登録にはバリアフリー改修などの条件がありますが、改修費の一部補助を受けられる場合もあるため、長期空室対策として検討する価値があります。
最後に、定期的な賃貸需要の調査を怠らないことが大切です。例えば近隣で大規模開発が進む場合、一時的に供給が増え賃料が下がる局面があります。インターネット上の募集データを月次でモニタリングし、必要に応じて広告費やフリーレントを調整することで、高い入居率を維持できます。
まとめ
一棟マンションを購入するメリットは、家賃や修繕計画を自由に設計できる点にあります。一方で空室・老朽化・金利という三つのリスクを自ら管理しなければなりません。記事で紹介したように、土地の資産性を重視した物件選定、保守的なキャッシュフローシミュレーション、そして2025年度の融資制度や補助金の活用が安定経営の鍵となります。まずは自己資金割合と返済比率を見直し、長期で耐えられる資金計画を立ててから物件を探しましょう。準備を着実に進めれば、マンション投資 一棟買いは初心者でも実現可能な資産形成の手段になります。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局 将来人口推計 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 金融庁 モニタリングレポート – https://www.fsa.go.jp
- 総務省統計局 住宅・土地統計調査 – https://www.stat.go.jp

