突然の金利上昇や物価高で、「少ない元手でも安定したリターンを得たい」と考える人が増えています。そんな中、ネットで完結し平均5万円から始められる不動産クラウドファンディングが注目を集めています。さらに近年は競売物件を対象にした案件も登場し、利回りが高いと話題です。しかし競売と聞くと「専門家でないと難しそう」「リスクが大きいのでは」と不安になるかもしれません。本記事では、2025年10月時点で有効な制度と最新の市場動向を踏まえつつ、仕組みからリスク管理まで基礎からわかりやすく解説します。読み終える頃には、自分に合った投資判断ができるようになります。
不動産クラウドファンディングの市場が広がる理由
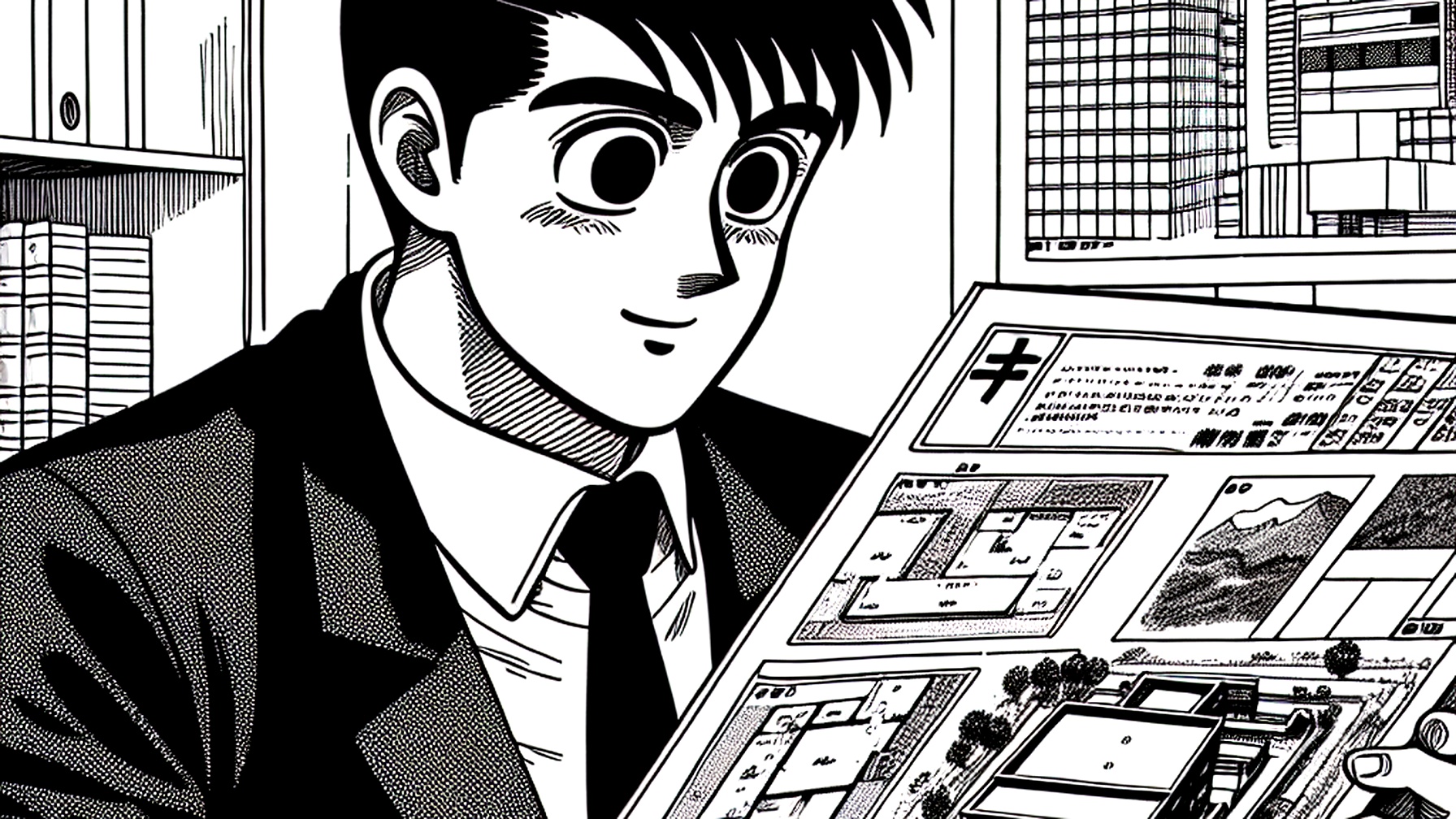
重要なのは、法律とテクノロジーの進化が投資ハードルを下げた点です。2017年の不動産特定共同事業法改正で少額オンライン取引が解禁され、2021年の電子取引業務ガイドラインにより契約から報告まで完全オンライン化が可能になりました。総務省の通信利用動向調査によると、2024年時点で20〜40代の約65%が投資アプリを月1回以上利用しており、資産形成の手段としてネット投資が一般化しています。
一方で、国内の賃貸住宅市場は国交省「住宅・土地統計調査」によれば空室率が2023年時点で13.6%と高止まりしています。運営コストを抑えにくい一棟買いより、分散投資できるクラウドファンディングへ個人資金がシフトするのは自然な流れです。運営会社にとっても、従来の私募ファンドより募集コストが約3割下がるとの試算があり、案件数が増えやすいのです。
加えて2025年度のNISA拡充で年間投資枠が大幅に広がりました。未上場不動産小口商品の配当はNISA対象外ですが、クラウドファンディングで得た分配金をNISAで再投資する動きが活発になり、プラットフォームの利用者数を押し上げています。
競売物件を活用する案件が増えている背景
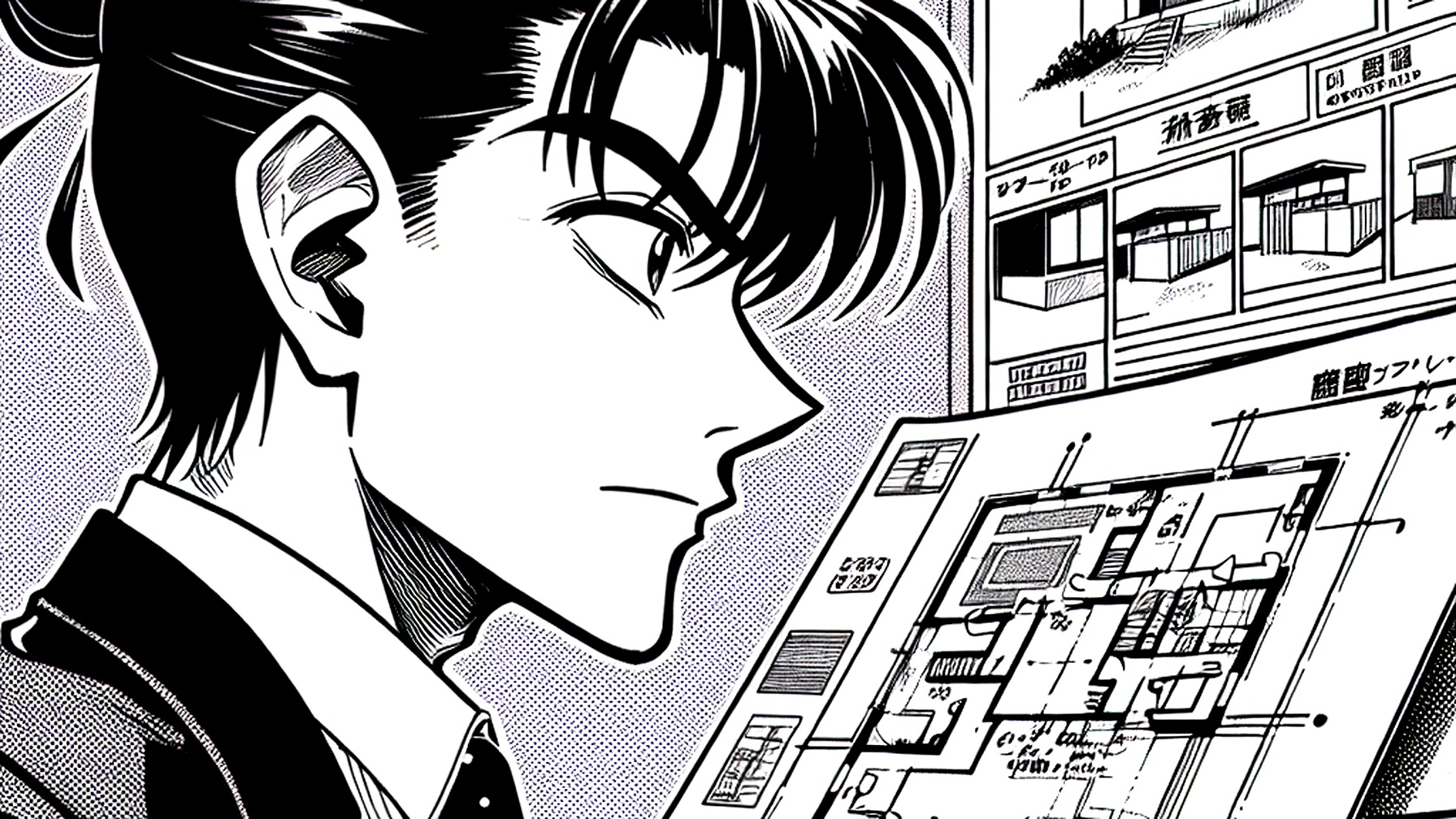
まず押さえておきたいのは、競売物件が市場価格より2〜3割安く取得できる点です。裁判所の期間入札という特殊な手続きが必要なため、個人投資家が単独で参加するのは困難でした。そこで専門業者が入札から再生までを行い、クラウドファンディングで資金を集めるスキームが注目されています。
実は、競売物件はリフォームや権利関係の整理が必須で手間がかかります。しかし取得価格が低いため、再販や賃貸運用後の利回りは通常物件より1〜2%高く出る傾向があります。プラットフォームAの2024年実績では平均表面利回り8.2%、完了案件の元本償還率100%と公表されています。
一方で、競売物件には滞納賃料回収や占有者立退きのリスクがあります。国交省のガイドラインでは、占有者対応費を想定コストの5%以内に抑えることが推奨されていますが、予期せぬ訴訟に発展すると分配金が遅れる可能性があります。そのため運営会社の経験値とトラックレコードを見極めることが欠かせません。
仕組みと法律上の保護はどうなっているか
ポイントは、不動産クラウドファンディングが二つの方式に大別される点です。ひとつは任意組合型で、投資家が持分を直接保有します。もうひとつは匿名組合型で、営業者が物件を所有し投資家は利益配分請求権のみを持ちます。競売物件案件の多くは匿名組合型を採用し、入札から運営までを一括で管理します。
監督官庁は国土交通省で、運営会社は不動産特定共同事業者の免許を取得し、第三者分別管理や定期報告が義務づけられています。また2023年施行の改正犯罪収益移転防止法により、オンライン本人確認(eKYC)が義務化され、不正利用リスクは低下しました。
分配金は普通配当と元本償還で構成されますが、2025年度税制では雑所得20.315%の源泉徴収が原則です。損失が出た場合、他の所得と損益通算できない点がデメリットです。したがって確定申告で節税メリットを期待する人より、源泉徴収だけで完結したい投資家に適しています。
リスクとリターンを見極めるチェックポイント
重要なのは、想定利回りではなく「貸付期間中のイベントリスク」を把握することです。競売物件は取得時点で瑕疵担保責任が免責となるため、シロアリ被害や違法増築が発覚しても売主に請求できません。この点をプラットフォームがどこまで調査しているかを確認しましょう。
次に、優先劣後構造の比率を確認することが不可欠です。劣後出資とは、運営会社が先に損失を負担する仕組みで、比率が高いほど投資家の元本が守られます。金融庁が2024年に公表した調査では、劣後比率が10%未満の案件は元本割れリスクが1.8倍になるとされています。
また、空室率シナリオを開示しているかも判断材料です。民族人口推計では、2040年までに20〜39歳人口が約14%減少すると予測されており、ワンルーム需要は長期的に縮小する可能性があります。駅徒歩10分以内など立地条件が公開されている案件を選び、保守的に利回りを評価する視点が求められます。
初心者が失敗しないための実践ステップ
まず、3社以上のプラットフォームに無料登録し、案件情報や運営レポートを比較しましょう。各社で想定利回りや劣後比率、運営期間が異なり、自分のリスク許容度に合った案件が見えやすくなります。
次に、初回は投資金額を5万円から10万円に抑え、運営会社の報告頻度やトラブル時の対応を体感することが大切です。実際に分配金が振り込まれるプロセスを経験することで、想定外の手数料や源泉徴収額を確認できます。
さらに、案件が募集開始されてから満額成立するまでのスピードを記録しましょう。人気案件は数分で満額になるため、事前に入金しておく準備が欠かせません。キャンセル待ち機能の有無も念頭に置くと投資機会を逃しにくくなります。
最後に、競売物件に絞ってポートフォリオを組むのではなく、区分マンション案件や商業施設案件と組み合わせることで分散効果が高まります。運営期間や地域をずらすことで、景気変動や災害リスクを軽減できる点を忘れないようにしましょう。
まとめ
ここまで、不動産クラウドファンディングと競売物件の関係、法律の枠組み、リスク管理の要点を説明しました。低コストで高利回りを狙える一方、物件調査や占有者対応といった固有リスクがあることを理解することが第一歩です。まずは少額で実践し、運営会社の報告体制や劣後出資比率を確認しながら投資判断を磨いてみてください。継続的に学び行動を重ねることで、安定したキャッシュフローを築くチャンスが広がります。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産特定共同事業に関するガイドライン(https://www.mlit.go.jp)
- 総務省 情報通信白書・通信利用動向調査(https://www.soumu.go.jp)
- 国土交通省 住宅・土地統計調査 2023年速報(https://www.stat.go.jp)
- 金融庁 不動産クラウドファンディングに関する研究会報告書 2024年(https://www.fsa.go.jp)
- 最高裁判所 競売物件の入札手続きに関する資料(https://www.courts.go.jp)
- 国税庁 タックスアンサー 配当所得の課税 2025年度版(https://www.nta.go.jp)

