資産形成を始めたいけれど、物件を丸ごと買うには資金も知識も足りない──そんな悩みを抱える人が近年急増しています。少額から参加できる「不動産クラウドファンディング」は、まさにその壁を取り払う仕組みです。しかし、投資となれば気になるのは利回りとリスクでしょう。特に競売物件を活用したファンドは高利回りを掲げる一方で、仕組みが複雑で敬遠されがちです。本記事では、2025年10月時点の最新データを用いながら、初心者でも理解できるように不動産クラウドファンディングの基礎から競売案件のポイントまでを丁寧に解説します。
不動産クラウドファンディングの基本構造
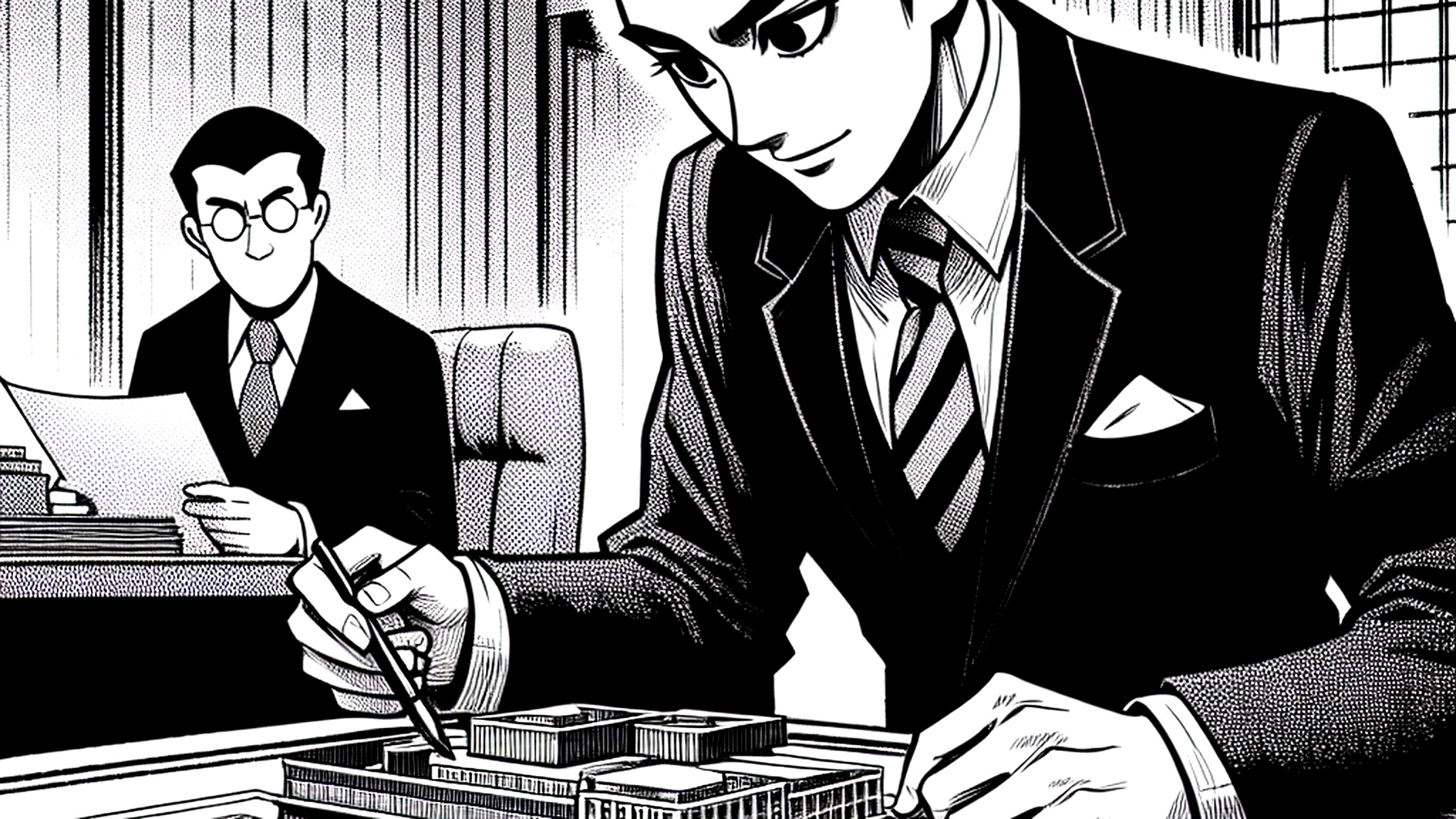
まず押さえておきたいのは、不動産クラウドファンディングが「多数の投資家がオンラインで資金を募り、不動産を共同で取得・運用する仕組み」だという点です。クラウドファンディング事業者(以下、運営会社)が物件を選定しファンドを組成し、投資家は1万円前後から出資できます。運営会社は賃料収入や売却益を得て、経費を差し引いた後、投資家に配当を行います。
一方、株式公開されているREIT(不動産投資信託)との違いは、個別物件ごとに期間と利回りが確定している点です。投資家は銘柄を選ぶというより、ファンド単位で目的や期間を比較しやすくなります。また、運営会社が借入を併用することで、レバレッジ効果を使った利回り向上を図る設計も一般的です。
実はこの仕組みを支える法的枠組みとして、2017年施行の「改正不特法(不動産特定共同事業法)」があります。これによりオンラインでの小口募集が可能となり、2024年度の市場規模は約1,700億円まで拡大しました(国土交通省調査)。つまり法的にも実務的にも、今やスタンダードな不動産投資手段と言えるのです。
最後に覚えておくべきなのは、元本保証が存在しない点です。投資対象が不動産であっても、運用成績次第では元本割れの可能性があります。この前提を理解したうえで、利回りの仕組みを見ていきましょう。
利回りはどう決まるのか
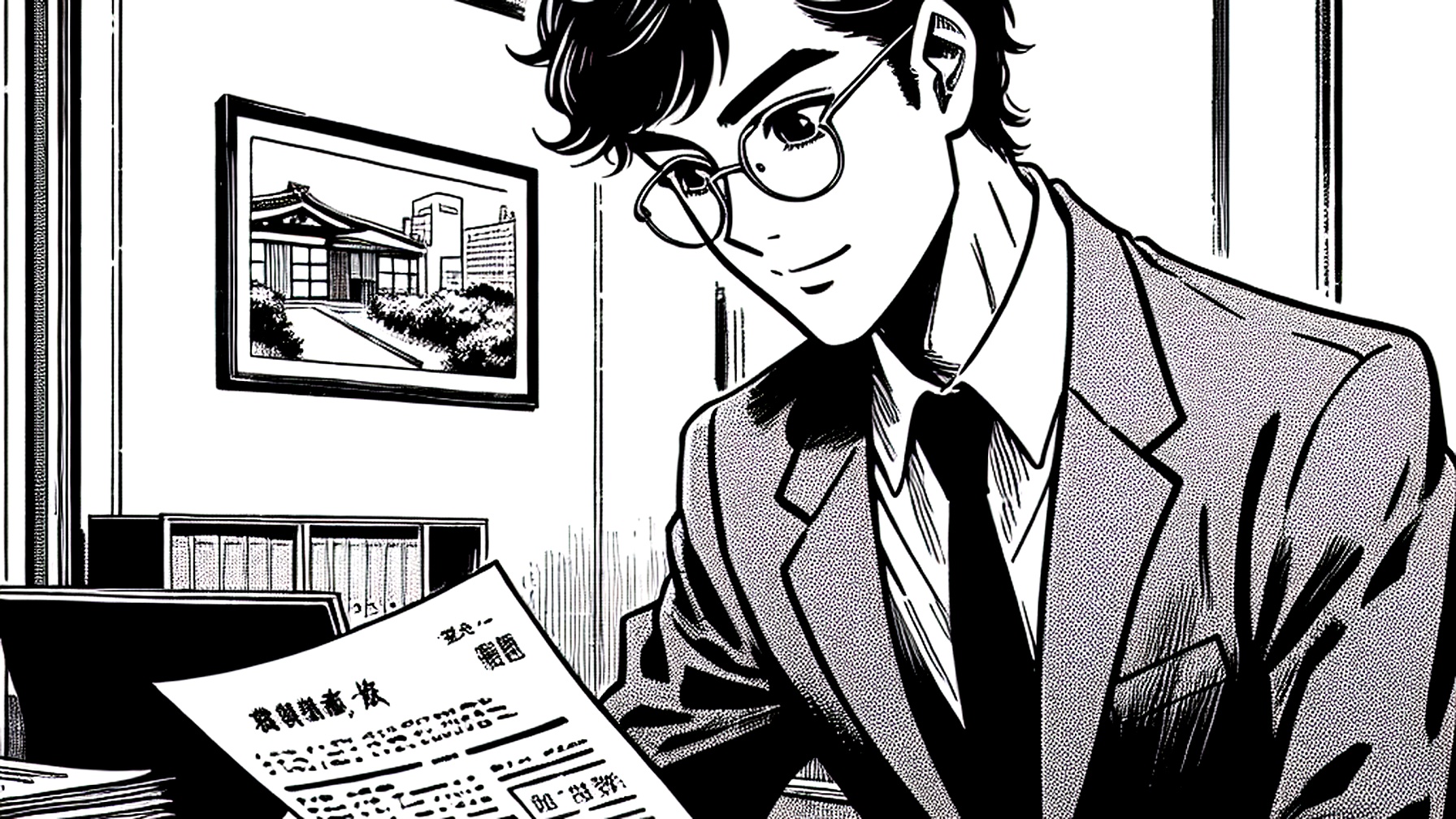
ポイントは、「表面利回り」と「実質利回り」を分けて考えることです。表面利回りは年間分配金を元本で割った単純なパーセンテージで、募集ページの最も目立つ位置に記載されています。対して実質利回りは、運営手数料や源泉徴収税、場合によっては修繕積立金まで差し引いた後に手取りで得られる率を指します。
例えば、出資額10万円、予定分配金が年5,000円のファンドの場合、表面利回りは5%です。しかし国内のクラウドファンディングでは通常、源泉徴収税20.42%が引かれます。そのため手取りはおよそ3,980円となり、実質利回りは約3.98%に下がります。この開きが大きいほど、手数料構造を詳しく調べる必要があると覚えてください。
2025年10月時点で、東京23区ワンルームマンションの平均表面利回りは4.2%です(日本不動産研究所)。クラウドファンディングの公募案件を見ると、競売物件を含まない保守的なファンドで4%台中盤、競売を活用したファンドでは6〜8%台が提示されることが多くなっています。つまり競売案件は平均より2〜3ポイント高い利回りを狙える設計になっているわけです。
一方で、分配金は賃料・売却益・遅延損害金など複数の項目から構成されます。特に競売物件の場合、短期的な転売益による比率が高まるケースが多いので、空室リスクよりも売却リスクを注視する必要があります。言い換えると、「賃料で安定、売却で跳ねる」という一般的な不動産投資とは利回りの源泉が異なる点を認識しておくと判断を誤りません。
競売物件が利回りを押し上げる理由
実は競売物件は市場価格より1〜3割安く取得できる傾向があります。裁判所の入札方式により、公開情報が限られ、物件の内覧ができない場合も多いからです。運営会社は専門の調査チームを抱え、権利関係や修繕履歴を精査したうえで入札し、一般流通より低コストで仕入れます。この仕入れ値の低さが、そのまま利回り向上につながる構造です。
また、競売物件は入札から落札、占有者の立ち退き、リフォーム、テナント付け、再販という一連のプロセスで付加価値を生み出します。運営会社はノウハウを持つため、個人が単独で競売に挑戦するよりもスムーズに投資成果を形にできます。つまり投資家は高利回りを享受しながら、手間や法的リスクを運営会社に移転できるメリットを得るわけです。
しかし、競売物件は取得後の瑕疵が発覚するリスクがある点を忘れてはいけません。例えば、雨漏りや配管劣化が見つかり、想定外の修繕費が発生すると短期ファンドでは利回りが大きく下がります。さらに、裁判所による開札が不調に終わると、取得自体が成立しない場合もあります。その際、ファンドは代替物件を探すか、計画を変更せざるを得ません。
こうした不確定要素に備え、運営会社は「優先劣後方式」を採用することが一般的です。これは出資金を優先出資と劣後出資に分け、損失が出た際に運営会社側の劣後出資から先に損失を負担する仕組みです。たとえば劣後出資比率が20%の場合、物件価格が20%下落しても投資家の元本には影響が及びません。この構造を理解すれば、競売物件の高利回りを取りに行く際の安全装置がどこにあるかを把握できます。
リスクを見極めるための視点
重要なのは、案件ごとにリスクとリターンのバランスを数字で確認する姿勢です。運営会社が開示する「重要事項説明書」には、賃料査定根拠や想定売却価格が詳細に記載されています。とりわけ競売案件では、内装工事費や立退費用がどの程度見込まれているかが成否を分けるポイントになります。
さらに、案件の運用期間もチェックすべきです。競売を活用したファンドは、取得から再販までの工程が多いため、6〜18か月の短期設定が主流です。この期間中に不動産市況が急変すると、売却価格が想定を下回るリスクが顕在化します。2024年から2025年にかけての金利上昇で、買主側の資金調達コストが上がり、売却益が圧縮された事例も報告されています。
一方で、短期ファンドは資金が早く回収できる利点もあります。つまり、長期保有型と短期転売型のポートフォリオを組み合わせることで、金利変動や市況変動に対する耐性を高める戦略が有効です。具体的には、安定分配を狙う賃料型ファンドを主軸に、競売転売型をサテライトとして混ぜるイメージです。
最後に、運営会社自体の財務健全性も欠かせません。金融庁が公表する「第二種金融商品取引業者」の登録情報を確認し、自己資本規制比率が140%を下回っていないかチェックしましょう。もし自己資本が薄い会社が高利回りを提示している場合、利回りの裏側にあるリスクを厳しく見極める必要があります。
2025年時点の市場動向とファンド選びのコツ
まず、2025年10月現在の不動産クラウドファンディングの平均表面利回りは5.5%前後で推移しています。日銀のマイナス金利解除後も住宅ローン金利は1%台半ばにとどまり、買い支えが続いているため、不動産価格は底堅い状況です。その中で競売活用ファンドは、短期で7%超の高利回りを掲げることで投資家の注目を集めています。
選び方のコツとしては、まず運営会社が公開する過去の募集実績を確認し、募集金額総計と償還遅延率を比較することです。たとえば、過去100件のファンドを組成し、遅延率が3%未満に抑えられていれば、運営や回収のノウハウが高いと判断できます。また、競売ファンドの場合、落札予定価格の公開有無もチェックしましょう。可能な限り情報開示が進んでいる案件ほど透明性が高く、想定外のトラブルに対する説明責任を果たせる会社と言えます。
次に、優先劣後方式の比率を確認することが大切です。劣後出資が10%未満の案件は、運営会社の自己責任部分が薄くリスクが高まります。逆に劣後が30%を超える案件では、運営会社のリスク負担が大きいため、万一の損失発生時でも投資家が守られやすくなります。ただし、劣後比率が高いほど運営会社の資金拘束が増えるので、案件数が限られる点には注意が必要です。
最後に、税制面にも目を向けましょう。2025年度も小規模投資なら総合課税よりも源泉分離課税の方が税率は低く済みます。具体的には、年間20万円以下の雑所得は確定申告不要制度が継続しており、副業での投資拡大を後押ししています。つまり、利回りだけでなく、手取り後のリターンを計算しておくことが納得感を高める鍵となります。
まとめ
本記事では、不動産クラウドファンディングの仕組みと利回りの考え方、そして競売物件を取り入れたファンドの特徴を解説しました。高利回りの背景には、市場より安く仕入れる競売と優先劣後方式のリスク遮断がある一方、瑕疵や市況変動といった不確定要素も潜んでいます。まずは運営会社の実績と情報開示度を確認し、短期と長期を組み合わせたポートフォリオでリスクを分散しましょう。小口で始められる手軽さを生かしつつ、数字と仕組みを理解して一歩踏み出せば、安定した不動産収益への道が開けるはずです。
参考文献・出典
- 日本不動産研究所 – https://www.reinet.or.jp
- 国土交通省 不動産クラウドファンディング市場調査 2025年版 – https://www.mlit.go.jp
- 裁判所 競売物件情報サイトBIT – https://www.bit.e-kenet.go.jp
- 金融庁 第二種金融商品取引業者登録一覧 – https://www.fsa.go.jp
- 総務省「源泉徴収税率表」2025年度版 – https://www.soumu.go.jp

