投資資金の目減りを防ぎたいものの、株式は値動きが激しく、預金は金利が低すぎると感じていませんか。実は、物価の上昇局面では家賃収入を基盤とする不動産投資信託(REIT)がバランスの取れた選択肢になります。本記事では「REIT 比較 インフレ対策」を軸に、仕組みの基礎から銘柄選びの視点、2025年度の制度までを具体的に整理します。読み終える頃には、自分に合ったREITの見極め方とリスク管理のコツがつかめるはずです。
インフレ時代にREITが注目される理由
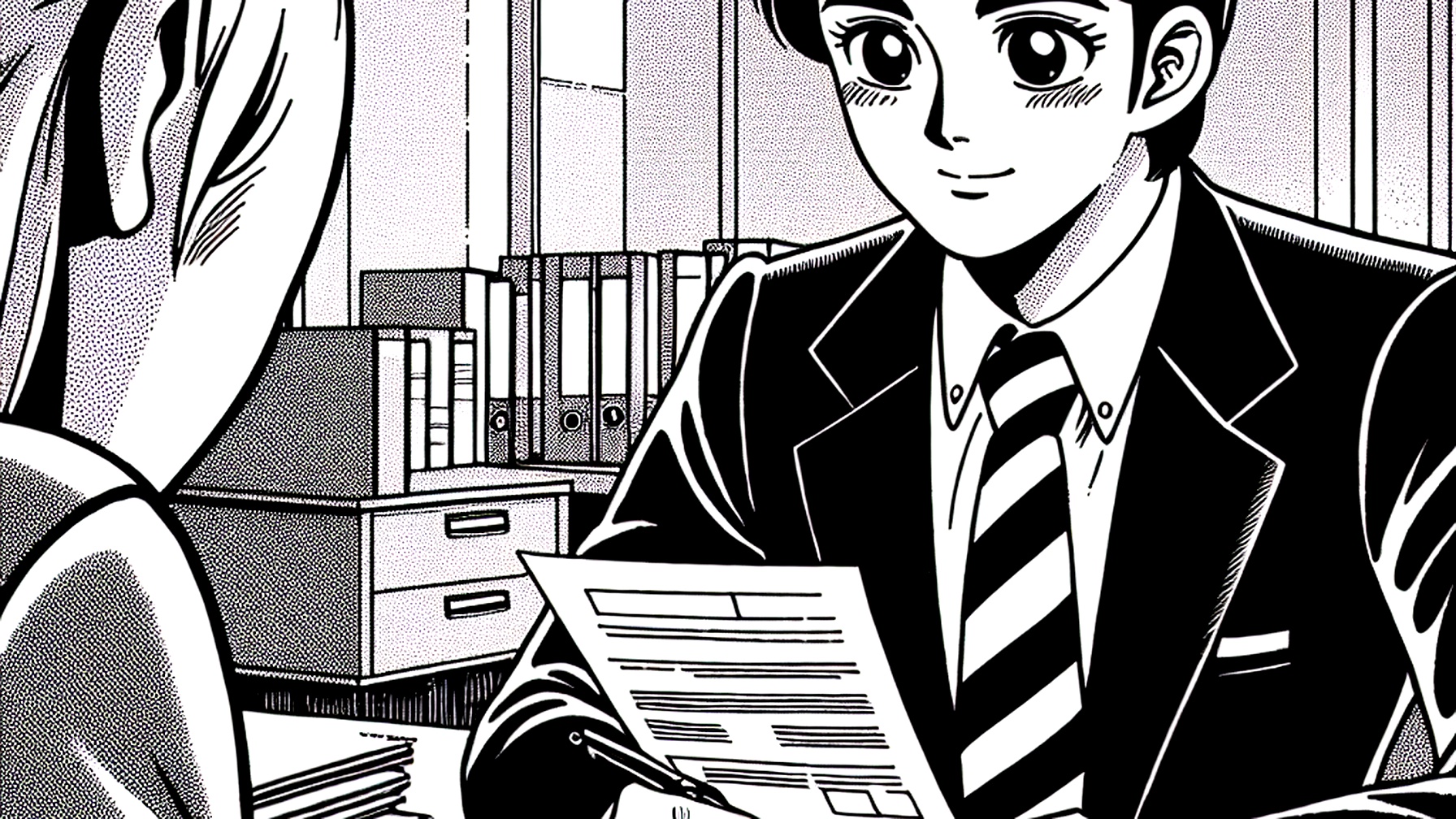
まず押さえておきたいのは、家賃収入が物価と相関しやすいという点です。総務省の消費者物価指数では2023年から2025年にかけて住居費が年平均1.8%伸び、家賃収益を源泉とするREITの分配金も緩やかに上昇しました。株価が乱高下する場面でも、賃料改定は比較的緩やかに進むため、収益のブレが抑えられます。
さらに、REITは法律上、利益の90%以上を分配すれば法人税が実質免除される構造です。つまりインフレで得た追加収益が投資家に還元されやすい仕組みが整っています。一方で固定金利の長期借入を活用している銘柄が多く、金利上昇に対する耐性も一定程度備えています。
もっとも、インフレが続く局面では資産価格の上昇期待から不動産価格が高止まりし、利回りが低下することもあります。したがって、インフレ対策として選ぶ際には分配利回りだけでなく、物件タイプや借入比率など総合的な比較が欠かせません。
REITの基本構造と収益の仕組み
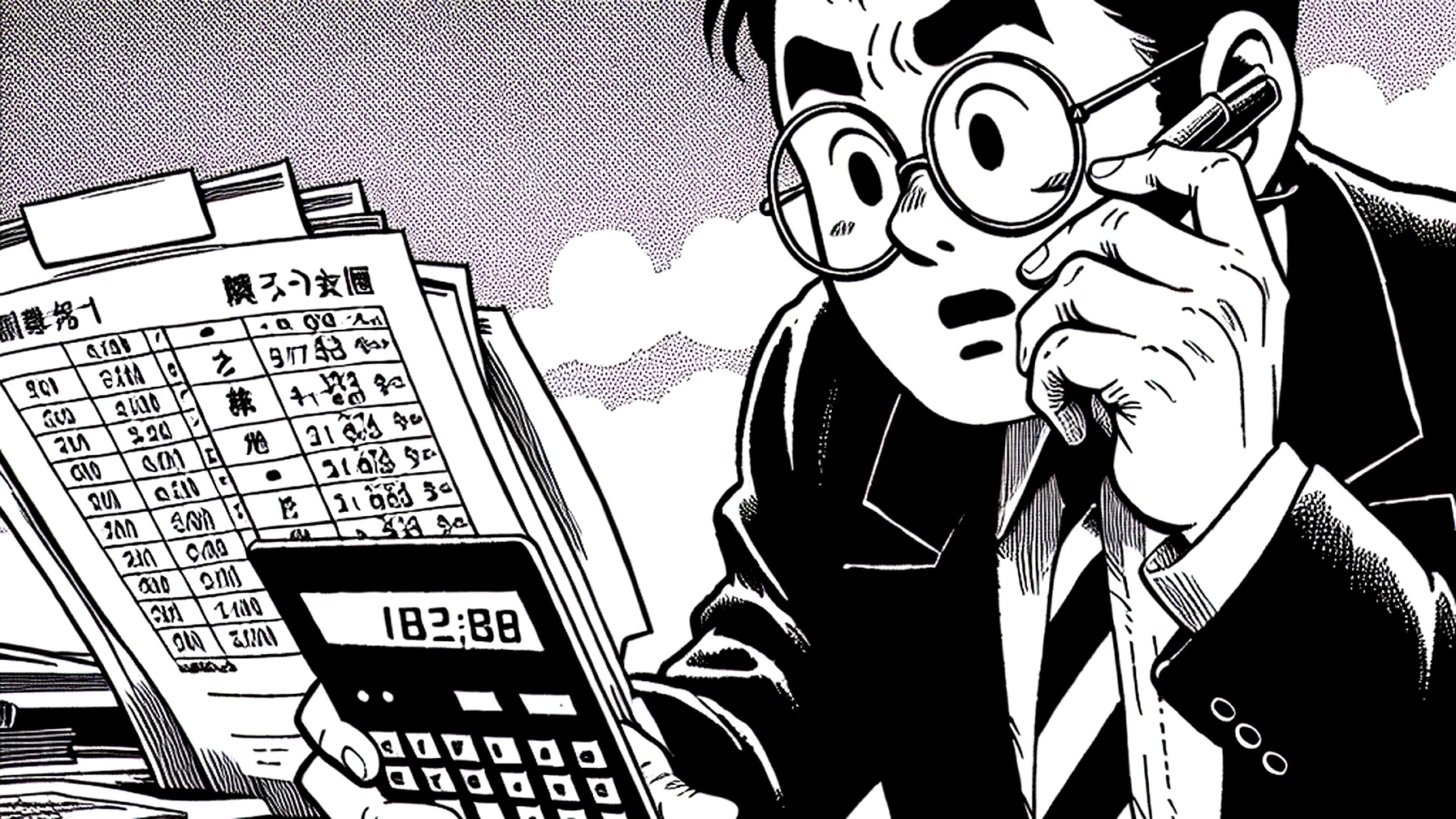
ポイントは、REITが投資法人、資産運用会社、資産保有先の三層構造で成り立つことです。投資法人は投資家から資金を集め、資産運用会社が物件選定や賃貸管理を担い、その結果得られた賃料が分配金の源になります。一般的に、運用コストは総資産の0.3〜0.5%程度で、同規模の上場投資信託より割安なケースも珍しくありません。
収益は賃貸収入と物件売却益で構成されますが、東証REIT指数の月次データによると、2020年以降の分配金総額の8割超は賃料由来です。つまり市場が不安定なときでも、テナント契約が続く限りキャッシュフローが保たれるわけです。
REITがインフレに強いとされる背景には、賃貸契約に盛り込まれた「賃料改定条項」があります。企業向けオフィス契約では、物価連動や再査定が3〜5年周期で行われるケースが増えています。また、商業施設や物流施設では売上連動賃料が採用されることもあり、景気拡大局面で分配金が伸びる可能性があります。
ただし、金利上昇が急激な場合は借入コストの増加が利益を圧迫します。固定と変動の比率、平均借入期間を確認し、ポートフォリオの耐久性を見極めることが大切です。
物件タイプ別REITを比較するポイント
重要なのは、物件タイプによってインフレ耐性とリスク特性が異なる点です。住宅系REITは入居者の回転が速く、1〜2年で賃料を見直せるため、インフレ反映が俊敏です。一方、オフィス系は長期契約が主流で反映は遅めですが、都心エリアの空室率が低いと安定感があります。
物流施設REITはEC需要の拡大と相まって稼働率が高く、賃料の上限改定余地が大きいことが特徴です。また、商業施設REITはテナント売上連動賃料がインフレ波及を後押ししますが、消費動向に左右されやすい弱点もあります。
ここで「REIT 比較 インフレ対策」を意識するなら、①平均利回り、②稼働率、③賃料改定の頻度、④借入金利の固定比率、⑤立地分散度を総合評価してください。たとえば、住宅系と物流系を組み合わせると、短期と中期で賃料改定のタイミングが分散し、ポートフォリオ全体のキャッシュフローが滑らかになります。
つまり、自分の投資目的が安定重視か成長重視かを明確にし、それぞれの物件タイプの特性を活かした配分を決めることが成功への近道です。
インフレ対策としてのリスク管理術
まず押さえておきたいのは、分配金利回りだけを追うとリスクが偏るという事実です。利回りが高い銘柄は地方比率や築年数が高いケースが多く、インフレ収益が伸びても修繕費の増加で相殺される可能性があります。そこで、築年数に応じた修繕積立額や設備更新計画を開示しているかをチェックしましょう。
また、価格変動リスクを抑えるには、日経平均株価やTOPIXとの相関係数を確認する方法があります。JPX公表データでは、住宅系REITの相関が0.3程度と低く、株式市場が荒れても値下がり幅が限定的でした。相関の低い銘柄を組み込むことで、ポートフォリオ全体のボラティリティ低減が期待できます。
さらに、分配金再投資を活用すると複利効果で名目利回りが上がり、インフレ調整後の実質リターンを底上げできます。証券会社の自動買付サービスを使えば、価格が低迷した局面でも機械的に投資でき、感情に左右されにくくなります。
最後に想定外リスクとして、災害や大規模修繕があります。物件の保険加入状況やテナントの業種分散を公開資料で確認し、基金繰入額が手厚い銘柄を選ぶことで、急な支出に備えられます。
税制優遇と2025年度の制度活用
実は、税制面でもREITは個人投資家に配慮されています。分配金は配当所得として総合課税か申告分離課税を選べ、所得控除を活用できれば税負担を抑えられます。加えて、2024年に拡充された新NISAは2025年度も非課税枠年間360万円が継続し、REITも成長投資枠で買付可能です。
2025年度の住宅・不動産関連補助では、環境性能を高めた物件に対するグリーンローン金利優遇制度が続いています。対象銘柄に投資するREITは借入コストを抑えやすく、分配金増額につながりやすい点が魅力です。具体的には、省エネ性能BELS認証を取得した物流施設やZEBオフィスを多く保有する銘柄がこれに該当します。
また、確定拠出年金(iDeCo)の商品ラインアップ拡大により、一部資産運用会社がREIT指数連動型投信を追加しました。老後資金づくりとインフレヘッジを同時に狙えるため、給与所得者でも活用しやすくなっています。
ただし制度は申請期限や利用条件が細かく定められています。証券会社やファンドの説明資料を確認し、最新の適用要件を把握したうえで投資判断を下すことが欠かせません。
まとめ
物価上昇が続く時代でも、REITは家賃収入を通じてキャッシュフローを維持しやすい金融商品です。インフレ対策を意識するなら、物件タイプや借入構造を比較し、相関の低い銘柄を組み合わせることで安定性と成長性を両立できます。さらに、新NISAやグリーンローン金利優遇など2025年度の制度を活用すれば、税とコストの両面でリターンを高める余地があります。行動に移す際は、開示資料を丹念に読み、分配金再投資を長期的に続ける姿勢が成果への近道です。
参考文献・出典
- 総務省統計局 – https://www.stat.go.jp/
- 日本取引所グループ(JPX) – https://www.jpx.co.jp/
- 国土交通省 不動産市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp/
- 金融庁 新NISA関連資料 – https://www.fsa.go.jp/
- 環境省 グリーンファイナンス支援制度 – https://www.env.go.jp/

