不動産投資に興味はあるものの、「税金はどこで払うのか」「役所が多くて混乱する」という声を頻繁に耳にします。確かに取得、保有、売却とフェーズごとに異なる税目が存在し、それぞれ支払先も手続き方法も変わります。本記事では、2025年10月時点で有効な制度を踏まえつつ、税金が発生するタイミングと支払う場所を整理します。読み終える頃には、納税先の区別がはっきりし、確定申告で慌てることもなくなるはずです。
税金が発生するタイミングと「どこで」の考え方
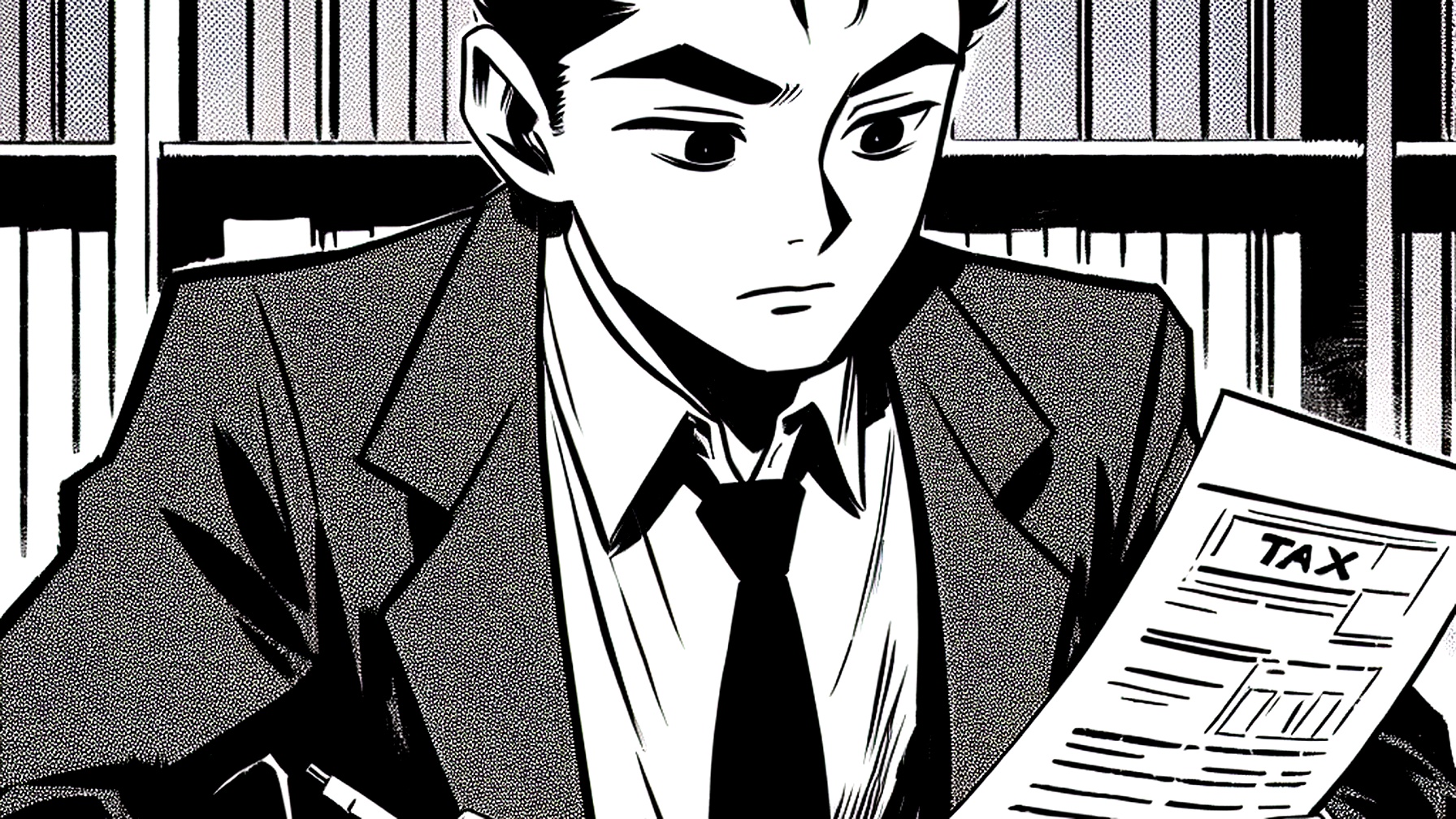
重要なのは、税金には国税と地方税があり、「どこで払うか」は税目ごとに法律で決まっている点です。国税庁の資料によると、所得税や登録免許税は国税、固定資産税や不動産取得税は地方税に分類されます。つまり、同じ不動産でもフェーズに応じて納税先が変わるわけです。
まず購入時には、国税として登録免許税を法務局に納めます。一方で不動産取得税は都道府県税であり、都道府県税事務所から納税通知書が届きます。保有中は固定資産税と都市計画税を市区町村に払うため、物件所在地の役所が窓口になります。売却益や家賃収入は所得税と住民税の対象で、確定申告時にまとめて精算する仕組みです。
このように、税金 どこで 支払うかは「税目×フェーズ×所在地」で決まります。混同しがちな点ですが、一覧表を自作しておくと後の管理が大幅に楽になります。次章からは、取得・保有・売却の順に具体的な税目と納税先を詳しく見ていきましょう。
取得時に支払う地方税:不動産取得税と登録免許税
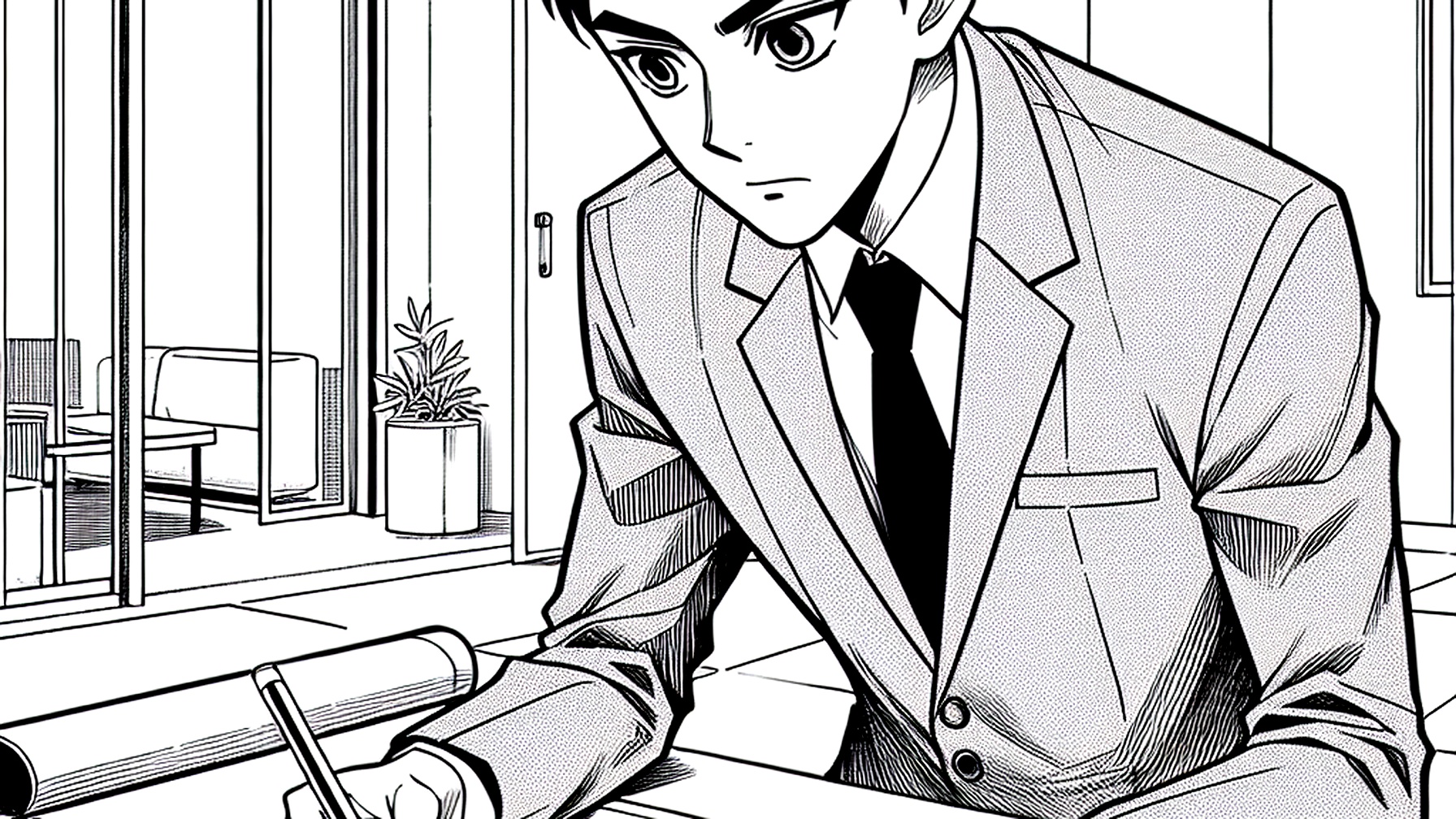
まず押さえておきたいのは取得時のコストです。不動産取得税は都道府県税で、物件価格(課税標準)の3%が基本税率とされています。ただし2025年度の住宅用軽減措置を利用すると、一定の要件を満たす住宅は課税標準が1,200万円控除されます。軽減後の通知書が届いたら、原則30日以内に都道府県税事務所へ納付します。
一方、登録免許税は国税庁が管轄し、所有権移転登記時に法務局で納める仕組みです。税率は建物が2%、土地が1.5%ですが、住宅用家屋の軽減で建物は0.3%まで下がります。法務局へ直接納付書を提出するため「どこで払うか」は非常に明確です。
取得時の地方税と国税を同日に支払うケースも珍しくありません。司法書士へ登記を依頼する際、登録免許税は預り金として事前に用意し、不動産取得税は後日自宅へ届く納税通知書で支払う流れになります。資金計画を立てる際、タイムラグを考慮して銀行口座に余裕を持たせることが大切です。
実は、この段階で交わす書類を整理しておくと、のちの確定申告で経費計上がスムーズになります。登記完了証や領収証はファイルにまとめ、取得費用を明確にしておきましょう。
保有中にかかる固定資産税・都市計画税はどこの自治体へ?
ポイントは、保有期間中の固定資産税と都市計画税は物件所在地の市区町村に納めるという単純なルールです。総務省の統計によると、全国平均の固定資産税評価額は毎年0.4%程度の増減にとどまり、急激な負担増は起こりにくいとされています。
納税通知書は毎年4〜6月に発送され、4期分割納付が一般的です。例えば東京都世田谷区の場合、固定資産税1.4%と都市計画税0.3%を合算し、クレジットカードやスマホ決済アプリで支払えます。2025年度から全国で「地方税統一QRコード」が導入され、自治体ごとに異なった払込書を持ち歩く手間が大幅に減りました。
ここで気を付けたいのは、賃貸中でも所有者に課税される点です。家賃収入があるからといって入居者が代わりに払うことはありません。家賃が1カ月入らなくても固定資産税は発生するため、キャッシュフロー表に税額を年ベースで組み込む必要があります。
また、賃貸管理会社に支払いを代行してもらう方法もあります。手数料は月額家賃の1%前後が目安ですが、納期遅延や延滞金を防げるメリットは大きいと言えます。管理委託契約を結ぶ際、納税代行の範囲を必ず確認しておきましょう。
売却・運用益にかかる所得税と住民税:申告はどこで?
基本的に、売却益や家賃収入から生じる所得税は国税、住民税は地方税です。確定申告書は毎年2月16日から3月15日までに住所地を管轄する税務署へ提出し、国税は同時に精算されます。その後、申告した所得額を基に住民税が6月以降に計算され、市区町村から納税通知書が届く構造です。
売却益に対する税率は所有期間で分かれます。国税庁の令和7年(2025年)資料では、5年超で長期譲渡所得20.315%、5年以下で39.63%と明示されています。さらに住民税は一律5%が加算されるため、実質25.315%または44.63%となります。売却時の「どこで払うか」はこれら二段階を意識するとわかりやすいでしょう。
家賃収入がある場合、青色申告特別控除(最大65万円)や減価償却費を適用すると所得税額を抑えられます。控除を受けるには複式簿記で帳簿付けを行い、期末に貸借対照表と損益計算書を提出する必要があります。クラウド会計ソフトを利用すれば、自動仕訳とデータ連携で手間が減るため、初心者にもおすすめです。
固定資産を複数年保有すると簿価が減り、売却益が増えて税負担が高まるケースがあります。つまり、計画的に修繕を行い、費用を適切に経費化することで、課税所得を平準化できる点は覚えておきましょう。
納税・申告の実務:インターネットでも「どこで」でも可能?
まず、2025年度時点でe-Taxは全国で利用可能です。マイナンバーカードとICカードリーダー、もしくはスマホ認証を使えば、自宅がそのまま「どこで」でも税務署に早変わりします。国税庁のデータでは、2024年度のe-Tax利用率は個人申告の71%に達し、対面提出は少数派になりつつあります。
地方税も「eLTAX(エルタックス)」経由で電子申告が可能です。固定資産税の電子納付は、地方税統一QRコードかインターネットバンキングを選べます。さらに、クレジットカード決済でポイントを得ながら納付する投資家も増えています。ただし手数料がかかるため、ポイント還元率と比較して判断しましょう。
それでも、「紙で確認したい」「相談しながら書きたい」場合は、税務署や都道府県税事務所、市区町村窓口を利用できます。2025年度は予約制の窓口が主流で、国税庁「確定申告書作成会場予約システム」から事前予約が必要です。窓口では職員が入力サポートを行ってくれるため、初年度は対面で学び、翌年以降にe-Taxへ移行するハイブリッド方式も有効です。
さらに、税理士へ依頼する選択肢もあります。日本税理士会連合会の調査では、個人不動産オーナーの約32%が確定申告をアウトソーシングしており、報酬相場は10万円前後です。時間対効果を考え、規模が大きくなった段階で検討するとよいでしょう。
まとめ
不動産投資に伴う税金は「取得・保有・売却」というフェーズごとに発生し、国税か地方税かで支払先が異なります。取得時は法務局と都道府県税事務所、保有中は物件所在地の市区町村、売却・収益は住所地の税務署と市区町村が窓口になります。納付方法は紙・窓口・オンラインの三つが併存しているため、自分に合った手段を早めに決めておくことが大切です。この記事を参考に納税カレンダーを作成し、キャッシュフロー計画に税負担を組み込めば、慌ただしい確定申告シーズンでも落ち着いて行動できます。
参考文献・出典
- 国税庁 – https://www.nta.go.jp
- 総務省 自治税務局 – https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/02gyosei02_04000018.html
- 東京都主税局 – https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp
- 日本税理士会連合会 – https://www.nichizeiren.or.jp
- 地方税共同機構(eLTAX) – https://www.eltax.lta.go.jp

