不動産投資に興味はあるものの、自己資金の不足や空室リスクが心配で一歩を踏み出せない人は少なくありません。さらに、土地を買うべきか、上場投資信託であるREITを選ぶべきかで迷う声もよく耳にします。本記事では、土地投資とREITの仕組みを基礎から解説し、それぞれのメリットとリスクを比較します。読み進めることで、自分の投資目的や資金計画に合った選択肢が見え、2025年以降の不動産市場で失敗しにくい戦略が立てられるはずです。
土地投資とREITの基本を押さえよう
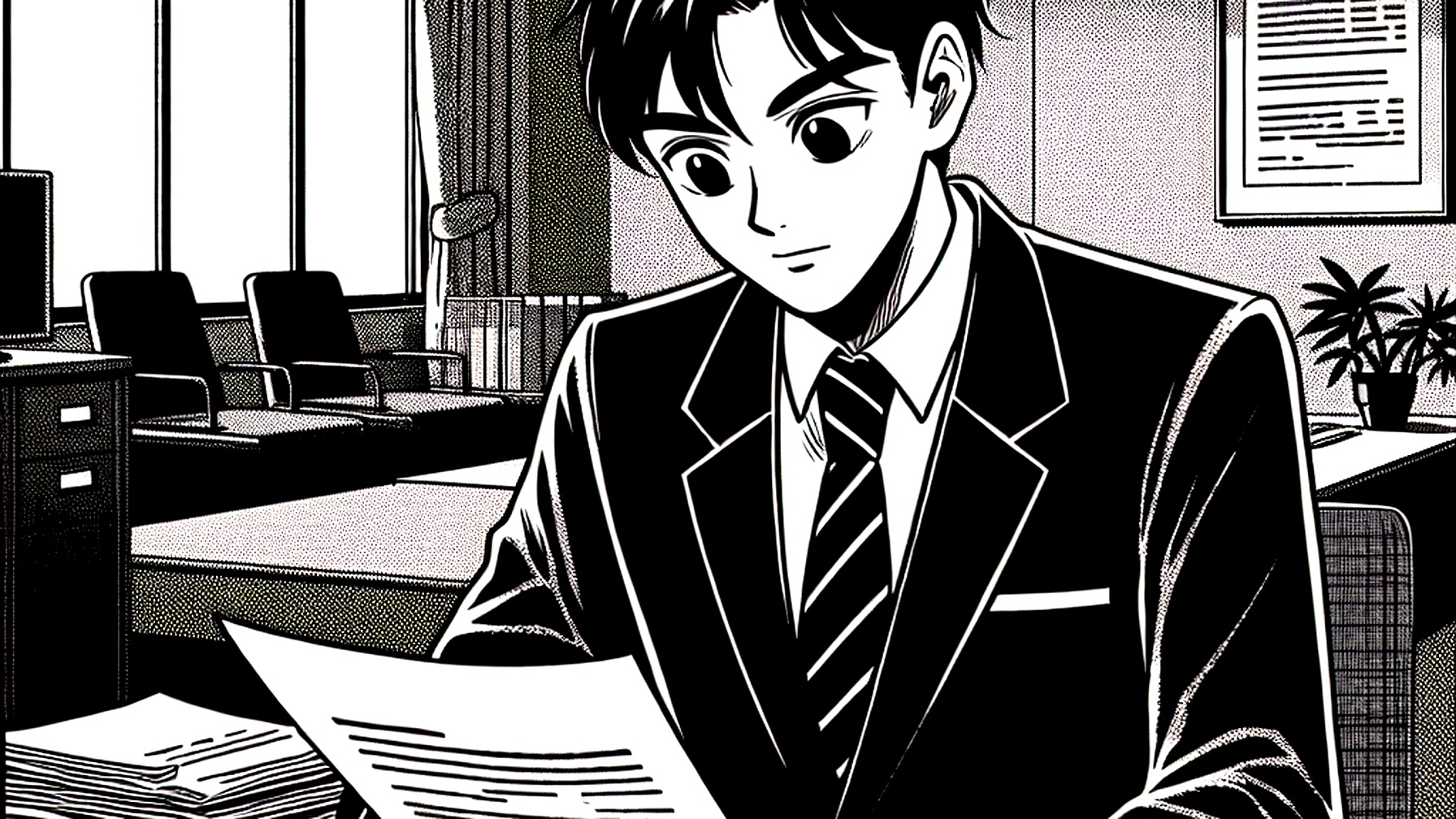
まず押さえておきたいのは、土地投資とREITが根本的に違う投資対象だという点です。土地投資は読んで字のごとく、実物の土地を取得して保有する手法であり、固定資産としての安定感や用途変更の自由度が魅力です。一方、REIT(不動産投資信託)は、多数の投資家から集めた資金で複数の不動産を運用し、その賃料収入や売却益を分配金として投資家に戻す仕組みになっています。どちらも不動産を裏付けとする投資ですが、必要資金、流動性、税制面などが大きく異なります。
実は、土地投資では登記費用や不動産取得税など初期コストが避けられません。加えて、建物を建てる場合には建築確認や開発許可が必要で、時間と手間がかかります。また、固定資産税や都市計画税も毎年発生するため、長期的な資金計画が欠かせません。一方で、REITは証券取引所で1口数万円から購入でき、購入手数料も株式並みに抑えられます。売買がしやすく、分散効果も働くため、初心者には取り組みやすい側面があります。
さらに、国土交通省が2025年7月に公表した不動産価格指数によると、都市部の商業地は前年同月比で2.3%上昇し、住宅地も1.1%伸びました。こうした上昇局面では土地投資がリターンを得やすい一方、REITも保有物件の含み益が評価され、分配金が増える傾向にあります。つまり、市場環境によっては両者とも好影響を受けるものの、価格調整局面での変動の仕方は異なるため、基本構造を理解することが先決です。
土地投資のメリットとリスク
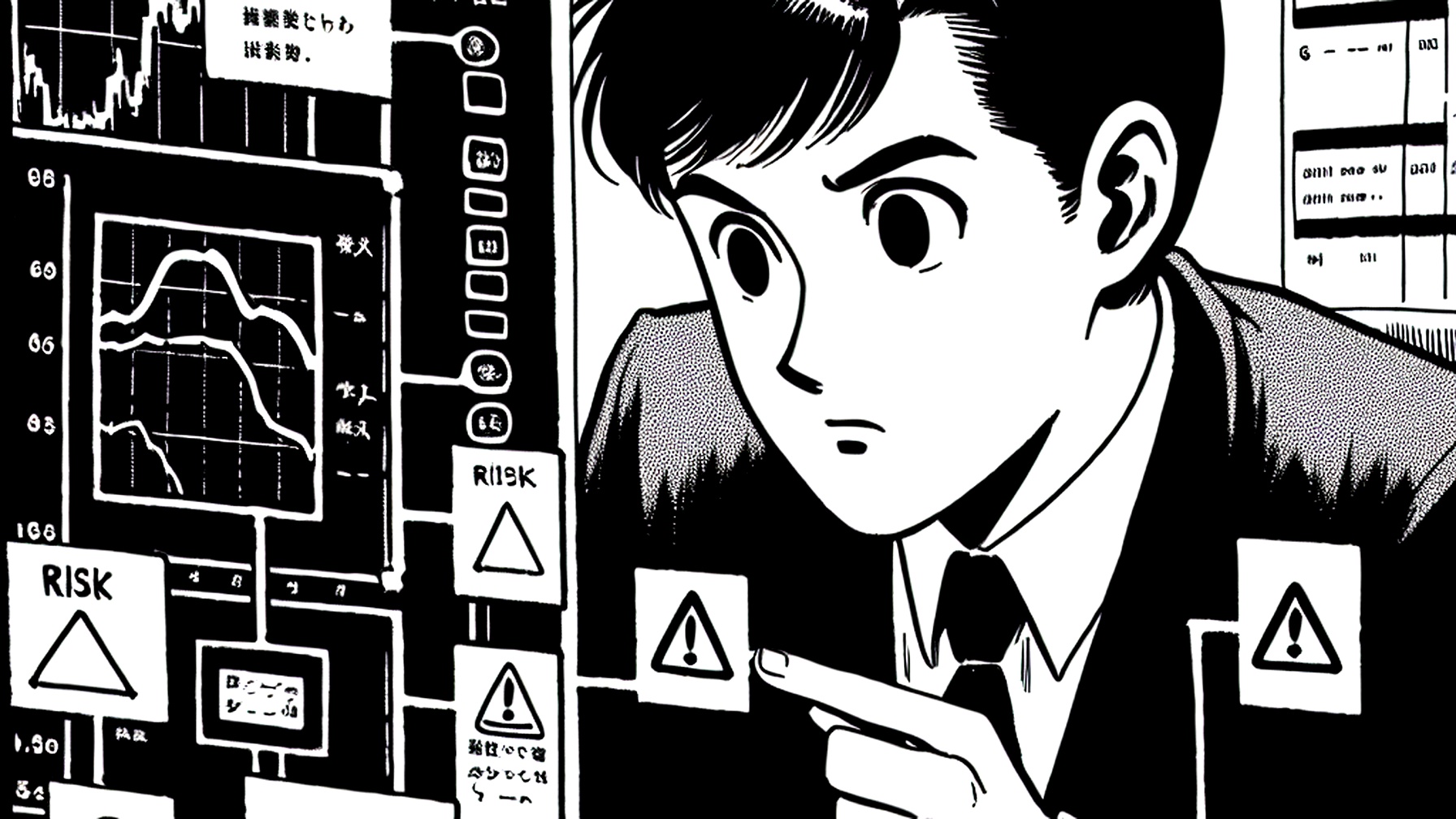
ポイントは、土地という現物資産を持つことが「所有の安心感」と「活用の自由度」を同時に生む点です。具体的には、賃貸住宅や駐車場に転用したり、需要次第で売却益を狙ったりと、多様な出口戦略が描けます。また、土地は建物と違い減価償却がなく、長期保有で価値が維持されやすいとされます。国税庁の路線価データを見ても、都心五区では2024年から2025年にかけて平均3%の上昇が確認され、実物資産への資金流入が続いています。
しかし、リスクも軽視できません。まず、購入時点で大きな自己資金を必要とし、融資を受ける場合は金利変動の影響を受けます。日本銀行が2025年4月にマイナス金利政策を解除したことで、長期金利は緩やかに上昇傾向にあり、借入コストは数年前より確実に高まっています。また、固定資産税評価額の見直しが3年ごとに行われるため、税負担が変動する点にも注意が必要です。
加えて、用途地域や都市計画の変更リスクも忘れてはいけません。将来的に建ぺい率や容積率が変わると、期待していた開発計画が実現できなくなる恐れがあります。さらに、地盤改良やインフラ整備が必要になれば追加費用が発生し、キャッシュフローを圧迫します。つまり、土地投資では収支シミュレーションに加え、行政動向や地域の人口推移まで総合的に分析する姿勢が不可欠です。
REITのメリットとリスク
重要なのは、REITが少額で始められ、しかも複数物件に自動で分散投資できる仕組みを備えていることです。東京証券取引所が公表するデータによれば、2025年9月時点で上場REITの平均分配利回りは4.1%と、長期国債利回りをおおむね3%上回っています。証券口座さえあれば購入でき、売買も即日成立するため、流動性の高さが光ります。加えて、投資法人が専門家を雇い運用するため、個人が物件管理に時間を割く必要がありません。
一方で、価格変動リスクは株式並みに存在します。2024年末から2025年初頭にかけてのグローバル金利上昇局面では、東証REIT指数が一時10%近く下落しました。分配金が安定していても、市場心理によって価格が上下する点は避けられません。また、分配金には所得税や住民税がかかり、特定口座で源泉徴収されるとはいえ、課税額は投資額に比例して増えます。
さらに、REITは投資法人が負う借入金の影響を受けます。金融庁の2025年6月レポートによると、上場REIT全体の平均LTV(負債比率)は44%で、金利が1%上がると利益が約5%減少する計算です。つまり、金利動向が収益に直結する構造を理解しておく必要があります。分配金の原資は賃料収入なので、テナント退去や賃料下落が続くと減配の可能性もある点に注意しましょう。
投資目的別の選択基準
まず押さえておきたいのは、自分の投資目的が「安定収入重視」か「資産形成重視」かで、適切な手法が変わるという事実です。定期的なインカムゲインを得ながら流動性も確保したい人にはREITが向いています。分配金が半年ごとに入るため年金的な役割を果たし、必要に応じて部分売却で資金化できるからです。一方で、長期で資産を積み上げ、将来的に大きなキャピタルゲインを狙うなら土地投資が有力です。人口増加や再開発が進むエリアを選べば、地価上昇と活用による複合的なリターンを狙えます。
予算面も大きな判断材料になります。自己資金が300万円程度しかない場合、都市部の土地取得は難しく、REITを中心にポートフォリオを組むのが現実的です。逆に、2,000万円以上の自己資金があり、金融機関からの融資枠も十分確保できるなら、土地購入と建物新築の組み合わせで表面利回り7%以上を目指すことも可能です。また、相続税対策としては、土地を賃貸用に活用することで評価額を下げられるため、節税効果まで含めて検討するとよいでしょう。
リスク許容度の面では、市場価格の変動幅をどこまで受け入れられるかが鍵になります。価格変動に一喜一憂したくないなら、現物資産である土地が精神的な安心感をもたらします。逆に、値動きをチャンスと捉え、分配金と価格差益の両方を狙いたいならREITが向いています。結局のところ、目的・資金・リスク許容度という三つの軸で、自分の立ち位置を明確にすることが最適解への近道です。
2025年度の市場動向と制度活用のヒント
実は、2025年度はインフレ率と金利の動向が不動産投資の成否を大きく左右すると予測されています。日本銀行の経済見通し(2025年7月時点)では、消費者物価指数が前年比2.2%の上昇とされ、緩やかな価格上昇が続く見込みです。この環境下では、土地価格も実質価値を維持しやすく、インフレヘッジとしての役割が強まります。他方、金利が上がる局面では、REITの借入コスト増加が懸念されるものの、賃料が上昇すれば分配金で吸収できる可能性があります。
制度面では、2025年度も「不動産取得税の軽減措置」が継続され、住宅用土地の課税標準が半減される特例が適用されます。また、所有期間5年以上の土地を譲渡した際に長期譲渡所得として20%課税になる点は従来通りですが、将来的な税率変更議論が出ているため、出口戦略を立てる際には注意が必要です。さらに、個人がREITを購入する際に利用できる「NISA成長投資枠」は年間360万円まで非課税で、2024年開始の新制度が2025年もそのまま活用可能です。REITの分配金や売却益が非課税になるため、中長期での資金効率を高める有力な手段といえます。
また、環境配慮型の不動産開発が増えている点も重要です。環境省の2025年版白書によると、ZEB(ゼロエネルギービル)や木造耐火ビルの導入が助成金の後押しで拡大しており、REIT各社もポートフォリオのグリーン化を進めています。これにより、ESG投資マネーが流入し、価格形成にプラスの影響が出る期待があります。土地投資でも、太陽光発電設備や蓄電池を併設したソーラーシェアリング用地など、再エネ関連の需要が高まっています。環境トレンドを押さえた投資先を選ぶことが、長期的なバリューアップにつながるでしょう。
まとめ
本記事では、実物資産である土地投資と、証券化商品であるREITを比較し、それぞれのメリットとリスクを整理しました。土地は所有と活用の自由度が高く、インフレに強い一方、初期コストと流動性の低さが課題です。REITは少額・高流動性で分散効果が得られますが、市場価格変動と金利影響を受けやすい性質があります。自分の投資目的、資金量、リスク許容度を三つの軸で整理し、場合によっては両者を組み合わせることで、相互補完的なポートフォリオを構築できます。まずは小口から始めて経験値を積み、実地調査や制度利用の知識を深めながら、2025年以降の不動産市場で着実な資産形成を目指しましょう。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/
- 東京証券取引所 REIT市場データ – https://www.jpx.co.jp/
- 日本銀行 経済・物価情勢の展望 – https://www.boj.or.jp/
- 国税庁 路線価図・評価倍率表 – https://www.rosenka.nta.go.jp/
- 金融庁 上場REITの財務分析レポート – https://www.fsa.go.jp/

