中古のマンションを買って家賃収入を得たいものの、予算として5000万円前後を想定すると、本当に資金を回収できるのか不安を覚える方は少なくありません。広告には「利回り7%」「節税効果あり」といった魅力的な言葉が並びますが、ローン返済や修繕費を差し引いた後に手元へ残る現金がどの程度か、具体的にイメージできない人が大半です。本記事では「マンション投資 中古 5000万円」をテーマに、メリットとリスクの整理、物件選びの手順、融資戦略、運営のコツ、そして出口戦略までを体系的に解説します。読み終えたとき、あなたは数字に基づいた判断軸を手に入れ、自分に適した投資プランを描けるようになるでしょう。
中古マンション5000万円投資の現実的なメリットとリスク
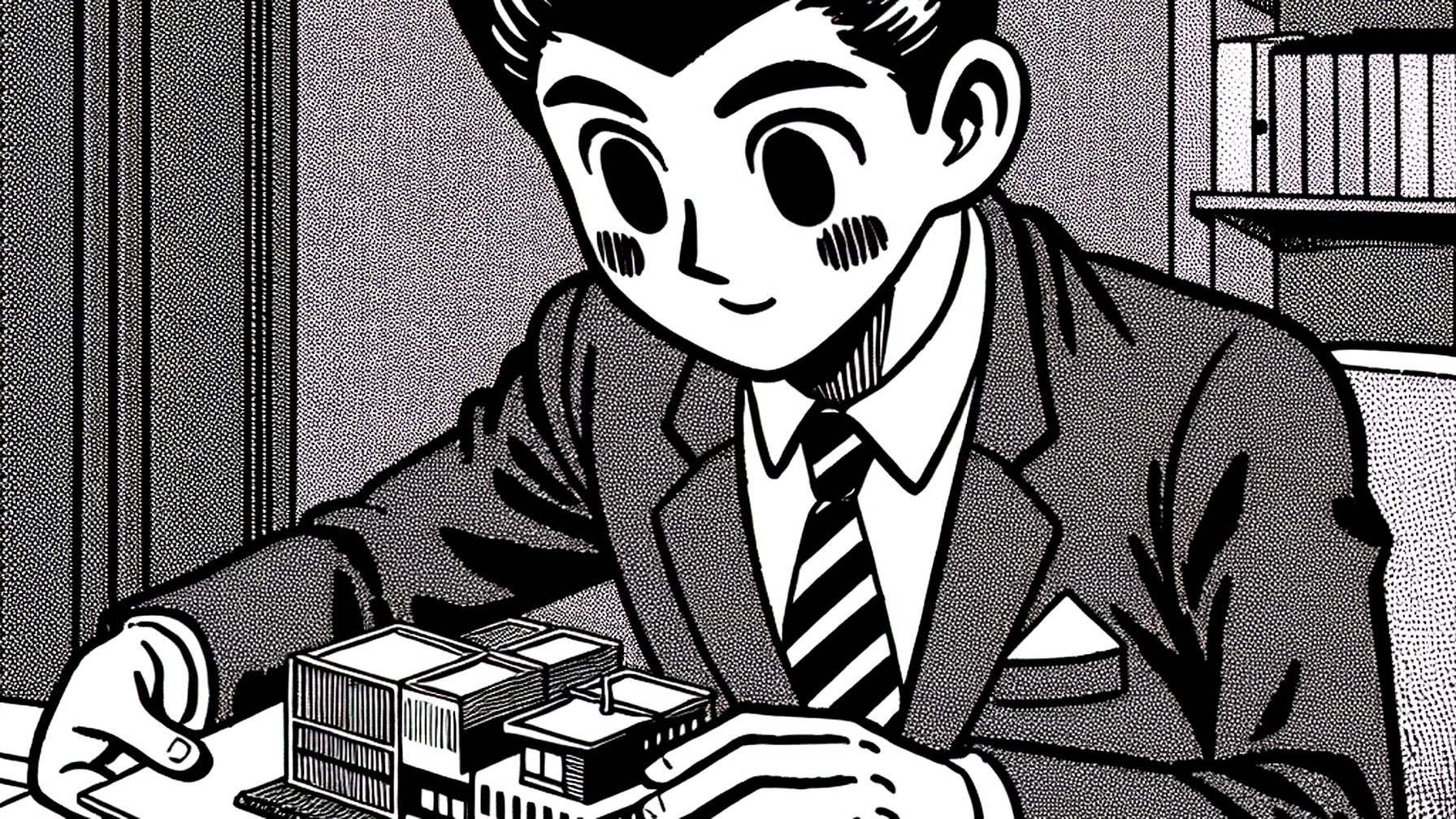
まず押さえておきたいのは、中古マンションに5000万円を投じたときに得られる具体的なメリットと、同時に背負うリスクです。メリハリのある判断をするために、数値を交えて両面から確認しましょう。
新築マンションの平均価格は2025年10月時点で東京23区が7,580万円と報告されています(不動産経済研究所)。同じエリアでも築10年前後の中古物件は5,000万円前後で購入できるケースが散見され、初期投資を2,000万円以上抑えられる点は大きな強みです。購入価格が低いぶん、同じ家賃設定でも表面利回りは高まり、ローン返済比率も下げやすくなります。
一方で築年数が進むと、室内設備や共用部の老朽化が加速します。国土交通省の「住宅市場動向調査」によると、築20年を超える区分所有マンションの年間修繕積立金は平均で月額約3.5万円と、築5年未満の2倍近くに達します。想定外の大規模修繕が発生すると突発的に100万円単位の資金が必要になる場合もあるため、キャッシュフローの余裕を確保しておくことが必須です。
また中古市場の価格は周辺の新築供給量と金融環境に大きく左右されます。日本銀行のデータでは、金利が1%上昇すると首都圏中古マンション価格は平均で4〜6%下落する傾向が確認されています。つまり購入時点で割安感があっても、将来の売却価格を確約できるわけではない点を肝に銘じましょう。
物件選びは収益性と資産性を両立させる

重要なのは、家賃収入を最大化しつつ資産価値を保てる物件を探すことです。そのためには立地・広さ・築年数の三要素を総合的に見極める必要があります。
立地については駅徒歩10分以内かつ二路線以上が利用できるエリアを基本線にすると、単身者からファミリーまで広く需要を取り込めます。人口動態を確認すると、東京23区では2025年時点でも20〜34歳の社会人口流入が続いており、ワンルームの賃貸需要は依然高い状態です。一方、郊外駅から徒歩15分以上離れると空室率が急上昇するデータもあるため、多少価格が高くても駅近を優先するほうが長期的には安全と言えます。
部屋の広さは25㎡前後のワンルームと50㎡前後のファミリータイプで悩む方が多いでしょう。利回りを取るならワンルーム寄りですが、将来価格の下支えを考えると40㎡台の1LDKはバランスが良い選択肢です。築15年以内であれば、最新の耐震基準や宅配ボックスなどの設備が整い、家賃下落スピードも緩やかだからです。
最後に確認したいのが管理状態です。国交省「マンション総合調査」によれば、修繕積立金不足を抱える物件は将来的に管理費の急騰や資産価値の下落リスクを抱えやすいと報告されています。購入前に重要事項調査報告書を取り寄せ、長期修繕計画や管理組合の合意形成状況を必ずチェックしましょう。
融資と資金計画:5000万円を無理なく回す
ポイントは、自己資金と借入金のバランスを適切に保ち、返済比率をコントロールすることです。特に初めての投資では安全マージンを十分に取る姿勢が欠かせません。
2025年度の主要地銀・信金の不動産投資ローン金利は、変動型で年2.3%前後が平均的です。物件価格5,000万円に対し、自己資金1,500万円(30%)を投入し、残り3,500万円を35年ローンで借りた場合、毎月返済額は約12万円となります。一方、都心ワンルームの家賃相場は月12万〜13万円なので、家賃だけでローンを完済する構図は極めてタイトです。管理費・修繕積立金・固定資産税を合計すると月3万円程度かかるため、表面利回りが5%ではキャッシュフローが赤字になる可能性があります。
したがって実効利回り(諸経費差し引き後)は最低でも6.5%以上を目安にし、空室率10%でも黒字を保てる設計にしておくと安心です。また銀行審査ではDSCR(債務返済余裕率)1.2倍以上が指針になることが多いので、家賃収入÷年間返済額の数字を必ず試算しましょう。
さらに手元資金として購入時諸費用とは別に100万円以上の予備費を用意しておくと、突発的な設備故障にも慌てず対応できます。資金ショートを回避する備えは、長期で安定経営を続けるうえで何よりのリスクヘッジになります。
安定運営の鍵はキャッシュフロー管理と修繕対応
まず押さえておきたいのは、入居率を高く維持しつつ予期せぬ支出に備える管理体制を構築することです。ここが機能しないと、どんなに好条件で買った物件も赤字に転落します。
入居募集は実績豊富な管理会社へ委託し、空室が発生したら2週間以内に募集条件を見直す仕組みを整えましょう。都心ワンルームの場合、賃料を5000円下げるだけで問い合わせ数が2倍になるケースも珍しくなく、機動的な調整が空室期間の短縮につながります。
一方で修繕計画は「予防保全」が鉄則です。給湯器は耐用年数10年前後、エアコンは12年前後で故障率が跳ね上がるため、入居者クレームになる前に計画的に交換すると信頼感が高まります。国税庁の減価償却制度では中古設備でも一定の耐用年数が設定され、交換費用の経費計上が可能ですから、税務メリットも見逃せません。
キャッシュフロー表を作る際は毎年の修繕積立金を実額で計上し、家賃下落率を年1%ずつ織り込むとより現実的になります。こうして保守的な数字で黒字化できれば、実際の運営で余裕が生まれ、追加投資への原資も確保しやすくなります。
将来の売却戦略と出口を見据えた施策
実は、購入前に出口戦略を描いておくことで投資の成功確率は格段に高まります。売却益と運用益のトータルで収益を最大化する視点が不可欠です。
築20年を迎える前後で大規模修繕が完了している物件は、次の買い手から高く評価されやすい傾向があります。そこで購入直後から管理組合に積極的に関与し、修繕計画の透明性を高めておくと、将来の譲渡時にプラスポイントとなります。また室内をリノベーションする場合、トレンドを意識した内装よりも「清潔・機能的」を徹底したほうが費用対効果が高いことが多く、100万円の投資で家賃を1万円上乗せできれば理論上10年で回収可能です。
売却タイミングは金利動向と新築供給量がカギです。日本銀行が金融緩和を縮小し始めた局面では買い手の融資条件が厳しくなるため、需要が冷え込む前に譲渡を検討する選択肢もあります。一方で新駅開業や再開発計画が発表されたエリアは資産価値が一時的に上昇することが多く、地元自治体の都市計画決定情報を定期的にチェックしておくとチャンスを逃しません。
最後に譲渡所得税の取扱いにも注意が必要です。所有期間5年超になると長期譲渡扱いとなり、税率が約20%に軽減されます。5年目の境目で売るか、7〜8年保有して減価償却メリットを使い切ってから売るかは、キャッシュフローと市場動向をにらんで判断しましょう。
まとめ
本記事では「マンション投資 中古 5000万円」を軸に、購入のメリットとリスク、物件選びの視点、融資計画、運営のコツ、そして出口戦略までを立体的に解説しました。5000万円という金額は、自己資金とローンのバランスを工夫すれば初心者でも手が届く一方、空室や修繕で簡単に赤字へ転落する規模でもあります。だからこそ立地と管理状態を吟味し、実効利回り6.5%以上を確保しつつ、保守的なシミュレーションを行う姿勢が欠かせません。もし今日から情報収集と数字の整理を始めれば、半年以内に具体的な投資判断を下せる土台が整うはずです。焦らずに準備を重ね、チャンスを確実にものにしてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅局「住宅市場動向調査」 – https://www.mlit.go.jp
- 東京都都市整備局「住宅市場関連データ」 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp
- 国税庁「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」 – https://www.nta.go.jp
- 日本銀行「短観・金融政策決定会合資料」 – https://www.boj.or.jp

