マンション投資に興味はあるものの、「マンション投資 やめとけ」という声が気になって踏み出せない人は多いでしょう。高額なローンや空室リスクを想像すると、不安が先立つのも無理はありません。しかし実際には、リスクの成り立ちを知り、対策を講じれば安定した収益源になり得ます。本記事では、初心者が感じる疑問に寄り添いながら、世間で語られる否定的な意見の真相をひも解き、2025年10月時点の制度・市場データをもとに安全な投資手順を解説します。読み終えたとき、リスクを避けつつ自分に合った投資スタイルを描けるようになるはずです。
マンション投資をやめとけと言われる理由
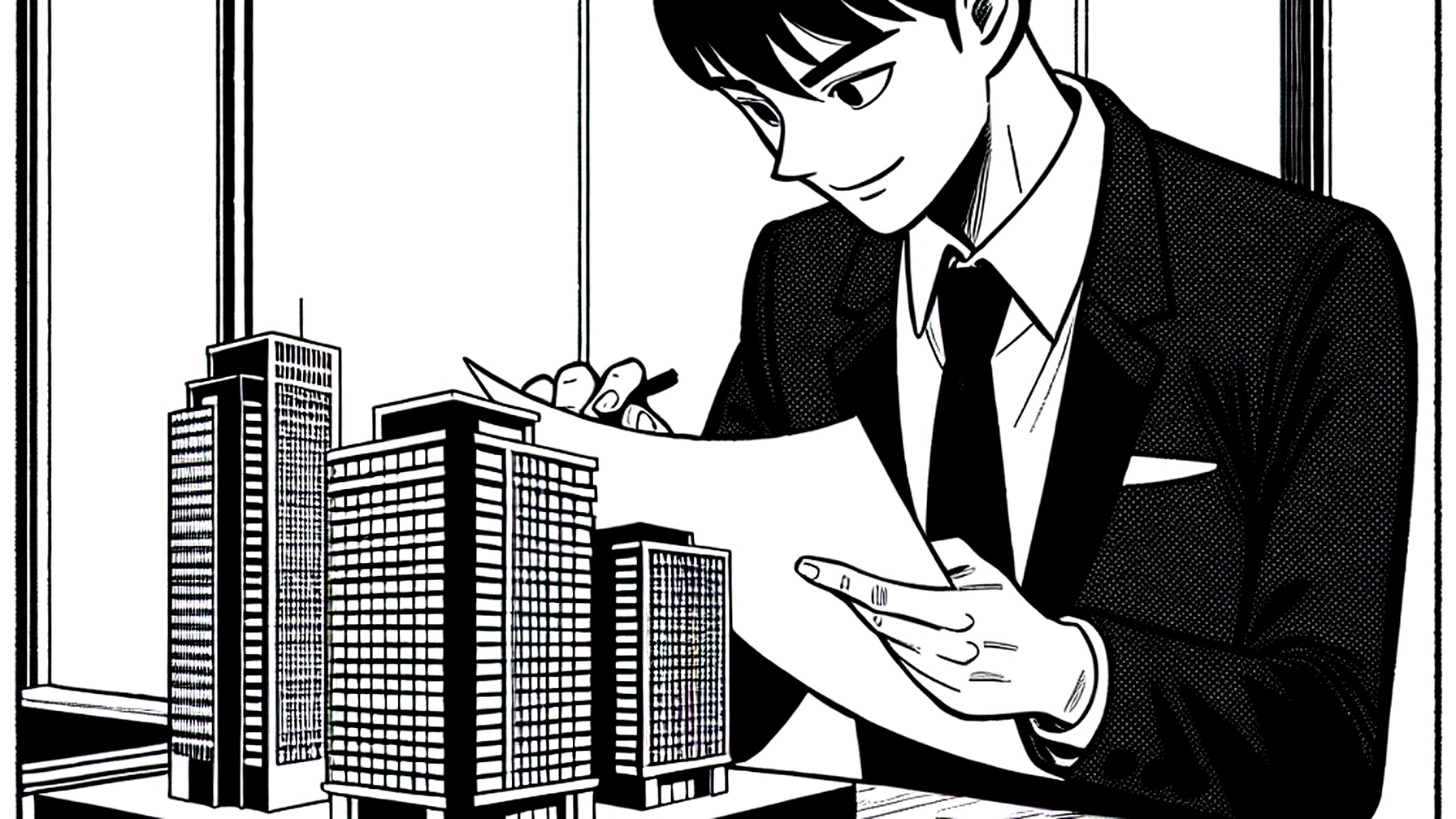
重要なのは、否定的な意見がどこから生まれたかを把握することです。まず空室リスクが挙げられます。人口が減る地域では入居者が集まらず、家賃を下げても収益が出ない事例が報告されています。次に修繕費です。国土交通省の調査では、築20年を超える区分マンションの平均修繕積立金は月1万7,000円とされ、当初計画より費用が膨らむケースが多いのが実情です。一方、ローン返済が苦しくなる「返済比率の悪化」もあります。日本銀行の統計によると、2025年10月の住宅ローン平均金利は変動型で0.51%、固定10年で1.23%と低水準ですが、将来的な金利上昇が懸念されます。この三つの要因が重なるとキャッシュフローが赤字になり、「やめとけ」との声が強まるわけです。
また、投資会社による強引な営業が悪いイメージを増幅させています。十分な説明を受けないまま契約した場合、想定外の費用や空室に悩まされやすいからです。つまり、マンション投資自体が危険なのではなく、準備不足が失敗を招くと理解することが第一歩になります。
それでも投資価値があるケースとは
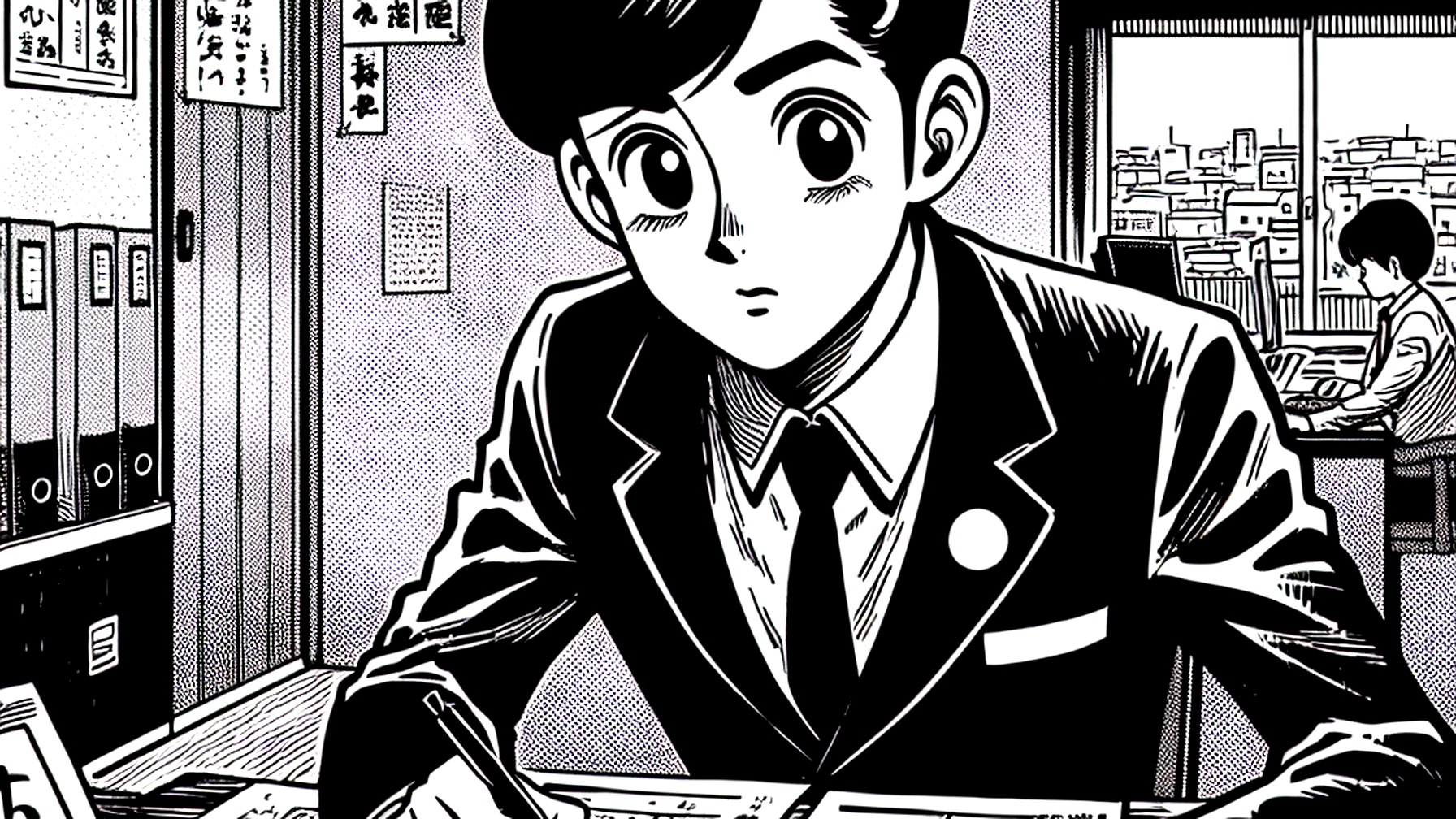
実は、立地とターゲットを明確にすれば安定運用は可能です。東京23区の2025年新築マンション平均価格は7,580万円と高騰していますが、不動産経済研究所の空室率データでは1Kタイプで3%台を維持しています。この数字は、企業の単身赴任や大学進学需要が集中するエリアで根強い賃貸ニーズがあることを示します。そのため、学生向けワンルームや法人契約が見込める物件は依然として投資妙味があると言えます。
一方、地方都市でも医療従事者やIT企業の集積地では需要が底堅い例があります。たとえば福岡市の博多駅周辺では、民間調査会社が発表した平均空室率が5%前後で推移し、表面利回りも6%前後を確保しています。ここでのポイントは、人口増加率と雇用が安定しているエリアかどうかを確認することです。人口動態や雇用統計を読み解けば、地方でも「やめとけ」とは言い切れない市場が見つかるでしょう。
リスクを最小限にする資金計画
まず押さえておきたいのは、自己資金と返済比率のバランスです。金融機関は返済額が年収の35%以内かを重視します。自己資金を物件価格の20〜30%用意すれば、返済額が抑えられ金利上昇の影響を受けにくくなります。さらに、家賃収入がゼロでも半年はローンを払えるキャッシュリザーブを確保することで、空室リスクに耐えられる体制が整います。
次に収支シミュレーションです。表面利回りだけでなく、管理費・修繕積立金・固定資産税・火災保険料を差し引いた実質利回りを計算しましょう。たとえば家賃年収84万円の物件でも、これら支出が年28万円かかれば実質利回りは7%から4.7%に下がります。厳しめの空室率20%、金利上昇1.5%など複数のシナリオで試算すれば、失敗確率を大幅に減らせます。
2025年度の制度と市場動向を正しく理解する
ポイントは、活用可能な制度を押さえつつ過大な期待をしないことです。2025年度の代表的な支援策として「住宅ローン控除」が挙げられます。投資用区分マンションでは利用できませんが、自己居住用から投資へ転用する際の出口戦略を描くうえで押さえておく価値があります。また、長期譲渡所得への税率軽減特例(所有5年超で税率20%)は2025年度も有効です。将来的に売却益を狙うなら、保有期間を意識するだけで税負担を下げられる点は見逃せません。
市場動向では、賃貸需要を左右するテレワーク普及率が注目されています。総務省「通信利用動向調査」によると、2025年は在宅勤務が31%と横ばい予想です。つまり、大都市中心の需要構造は大きく変わらず、駅近物件の価値は継続すると見込まれます。一方、郊外でファミリー向け需要が微増しているため、間取りや広さを変えたリノベーションによる差別化も有効です。
失敗しない物件選びと管理のコツ
基本的に、物件選びでは「駅徒歩10分以内」「築15年以内」「総戸数30戸以上」を目安にすると管理コストが安定します。築浅物件は修繕費が抑えられ、総戸数が多いほど修繕積立金の負担が分散されるからです。なお、賃貸管理を委託する場合は管理会社の実績と報告体制を確認しましょう。管理手数料が安くても、募集力が弱いと空室期間が長くなり収益を損ないます。
さらに、退去後のリフォームを迅速に行う体制を組むことが重要です。国交省のデータでは、原状回復を含む空室期間の平均は首都圏で37日ですが、人気エリアでは2週間以内で次の入居者を決めるケースも珍しくありません。クリーニング業者や内装会社を事前に手配し、写真撮影から募集まで一括で進める仕組みを作れば、機会損失を防げます。
まとめ
世間で言われる「マンション投資 やめとけ」という意見の多くは、情報不足や準備不足がもたらす失敗事例に基づいています。本記事で示したように、立地選び、資金計画、制度理解、管理体制を丁寧に整えればリスクは大幅に下がります。まずは人口動態と雇用の安定したエリアに絞り、保守的なシミュレーションで収支を確認しましょう。そして、信頼できる管理会社と連携し、空室や修繕に迅速に対応できる体制を構築することが成功への近道です。今日から一歩ずつ情報を集め、数字でリスクを測りながら、自分に合ったマンション投資をスタートしてください。
参考文献・出典
- 不動産経済研究所 – https://www.fudousankeizai.co.jp
- 国土交通省 住宅市場動向調査 – https://www.mlit.go.jp
- 日本銀行 統計データ – https://www.boj.or.jp/statistics
- 総務省 通信利用動向調査 – https://www.soumu.go.jp
- 東京都都市整備局 人口動態統計 – https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp

