不動産投資に興味はあるけれど、転売かREITか、どちらを選ぶべきか迷っていませんか。周囲の成功談を聞く一方で「本当に損をしない方法はあるのだろうか」と不安になる人も少なくありません。本記事では2025年10月時点で押さえておきたい最新情報を基に、転売とREITそれぞれの仕組みとデメリットを中心に解説します。違いを理解し、自分に合った戦略を見つけるヒントが得られるはずです。
転売とREIT、そもそもの仕組みを押さえよう
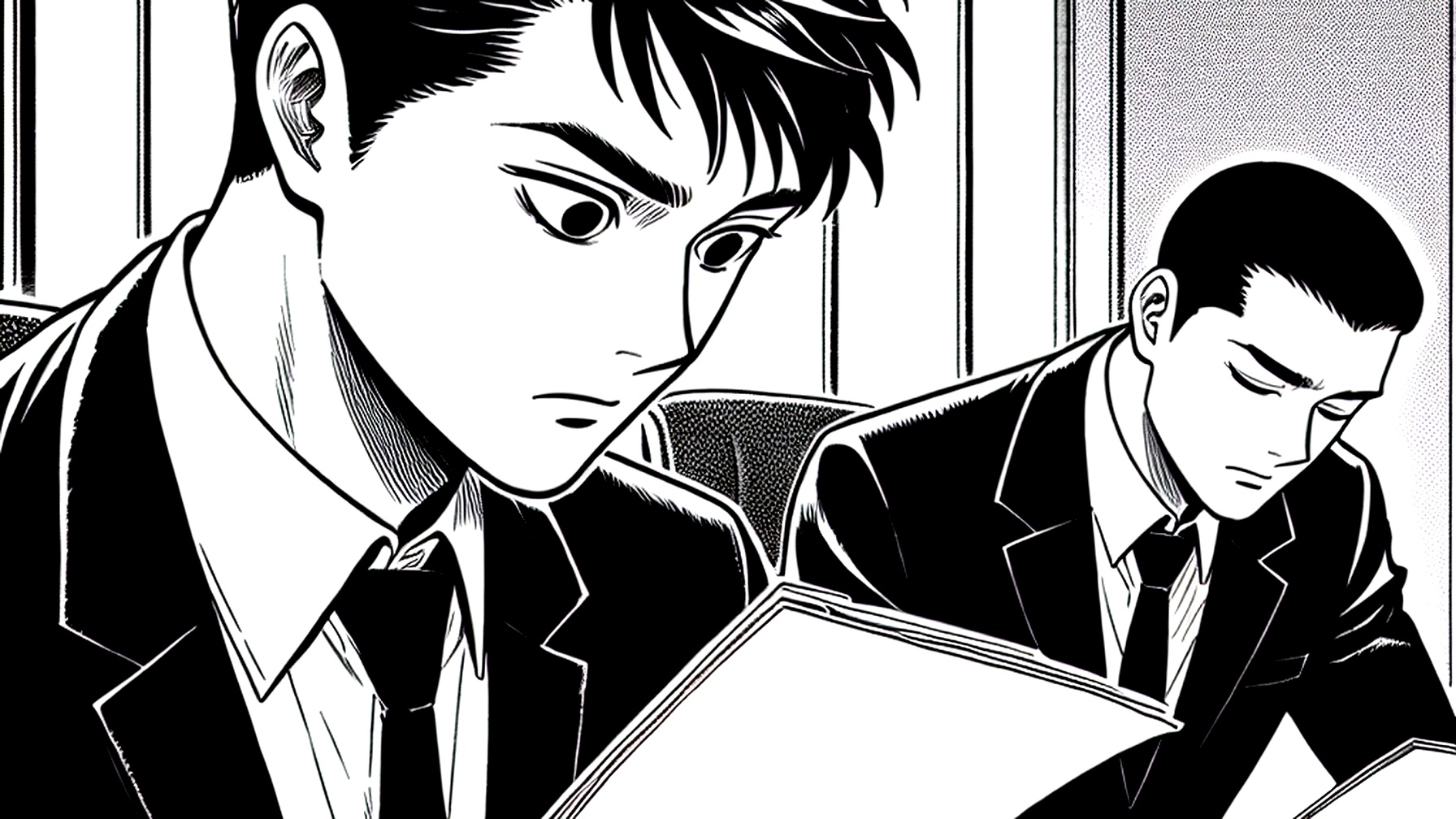
ポイントは、まず両者のビジネスモデルを正しく把握することです。転売は物件を購入し、短期間で売却して差額を利益とします。一方、REIT(不動産投資信託)は投資家から集めた資金で複数の物件を保有し、賃料や売却益を配当として分配します。
転売では個人が直接物件を所有します。購入後のリフォームや広告戦略も自分で考える必要があり、収益は「売却益」に集中します。つまり空室期間の心配は少ないものの、短期での価格変動リスクを強く受けます。
対照的にREITは、東京証券取引所に上場している投資信託を株のように売買する形です。投資家は証券口座を介して間接的に不動産に関わり、少額から分散投資が可能になります。ただし自分では物件を選べない点が特徴です。
このように、転売は「自己裁量が大きい実物投資」、REITは「運用会社に任せる金融商品」と整理できます。ここを誤解したままスタートすると、期待した収益と実際のパフォーマンスが大きくずれるため注意が必要です。
転売投資のメリットと見落としがちなデメリット
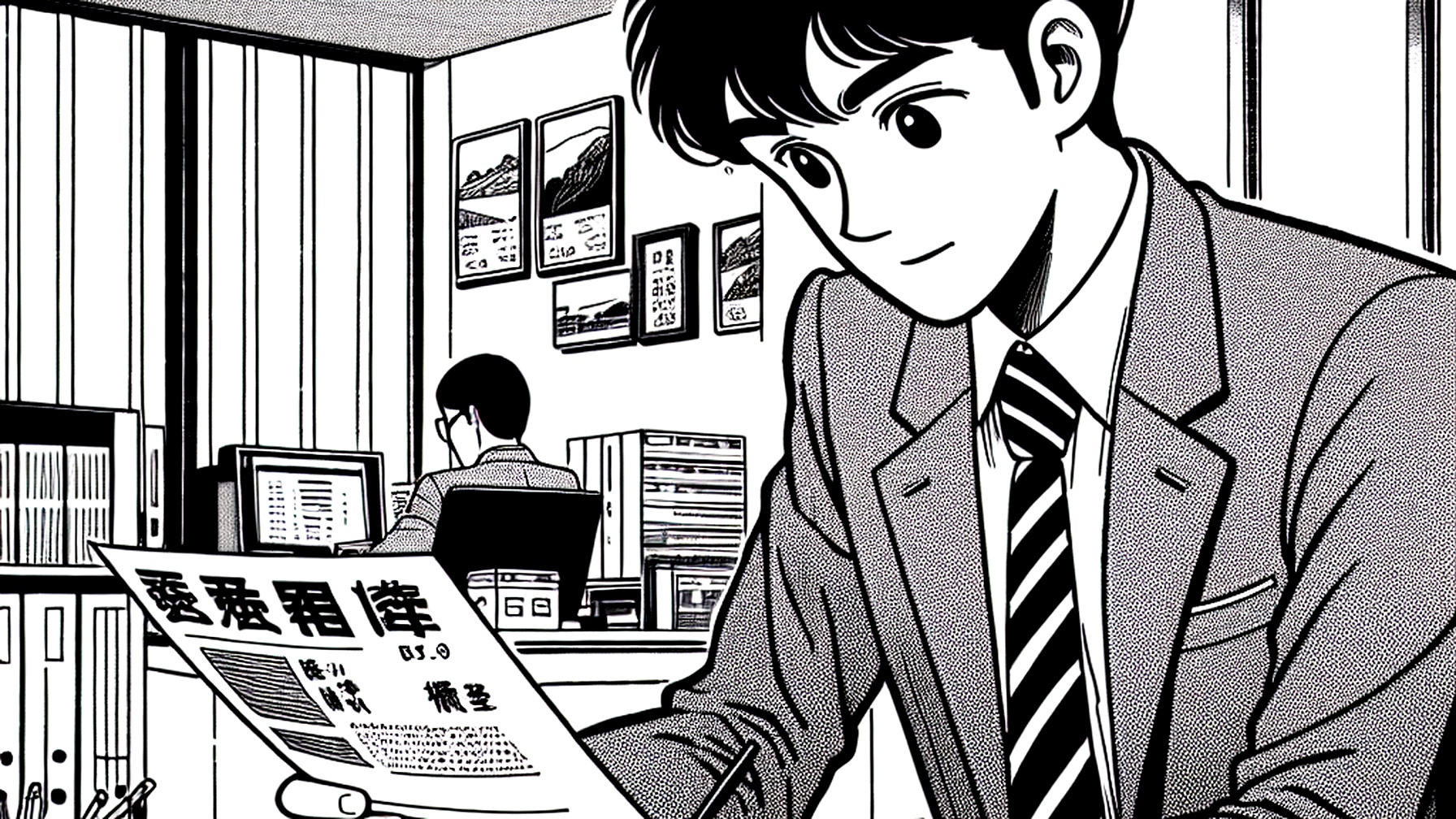
まず押さえておきたいのは、転売が「短期間で高いリターンを狙える手法」である一方、リスク管理が難しい点です。国土交通省の不動産価格指数では、2020年以降の首都圏中古マンション価格は年平均5%程度で上昇しました。しかし2024年後半からは伸び率が鈍化し、2025年上期の平均上昇率は1%台にとどまっています。
この鈍化は転売の前提である「短期値上がり」に直接響きます。実は、物件取得から販売までにかかる諸費用が想定以上に利益を削るケースが増えています。登記費用、仲介手数料、リフォームコスト、そして短期譲渡所得に対する最高39%の税負担が代表例です。さらに、融資を利用する場合はブリッジローン(つなぎ融資)の金利が4%を超えることもあり、利益確定前に資金繰りが圧迫されやすい点も見逃せません。
また、買主側のローン審査が厳格化している影響で成約までの期間が延びる傾向にあります。住宅金融支援機構の調査によると、2023年は平均45日だった住宅ローン承認期間が、2025年には平均52日へ伸びました。この遅延は「保有期間コスト」を押し上げ、運用シミュレーションを狂わせる原因になります。
つまり転売で安定的に利益を確保するには、購入価格だけでなく「販売期間の長期化」と「総費用の増大」を織り込んだシビアな計算が欠かせません。高く売れる見込みが立たない場合は、賃貸運用への切り替えプランも準備しておくとリスクを下げられます。
REIT投資が持つ魅力とリスクのバランス
重要なのは、REITが「分散投資と流動性」を提供する半面、価格変動が株式市場の影響を強く受ける点です。東京証券取引所REIT指数は、2022年から2025年にかけて年平均配当利回り3.7%前後を維持しています。一方、指数の年間変動幅は±18%と、実物不動産より大きい値動きが生じています。
値動きの背景には金利上昇があります。日本銀行が2025年4月に実施した誘導目標上限0.5%から0.75%への引き上げにより、REITの調達コストも上昇しました。結果として利回りが相対的に魅力を失い、価格調整が起きたのです。また、REITは保有物件の評価損が一気に反映されるため、オフィス空室率が高まる局面では配当原資が減少するリスクも抱えます。
さらに、REITは上場投信であるがゆえに「市場心理」に左右されやすい特徴があります。たとえば、地政学リスクや海外金利動向が報じられるだけで、実物の賃料収入に変化がなくても価格が下落することがあります。これは不動産そのものではなく「金融商品」としての性質が強いためです。
一方で、2025年度の新NISAではREITが成長投資枠の対象に含まれているため、税制優遇を利用して投資しやすい環境が整っています。言い換えると、長期保有で配当を積み上げる戦略には追い風が吹いているものの、短期的な価格変動には心構えが必要というわけです。
2025年度の法改正が与える影響
実は、2025年度に施行された不動産関連の法改正が転売とREITの双方に影響を及ぼしています。代表的なのが、不動産取引における電子契約の義務化範囲拡大です。これにより売買契約締結がオンラインで完結し、取引コストと時間の削減が見込めます。転売を手がける個人にとっては、書類の郵送や押印の手間が減り、販売スピード向上につながる可能性があります。
一方、REITに関しては「不動産特定共同事業法」の改正で、資産運用会社の情報開示義務が強化されました。運用会社はESG(環境・社会・ガバナンス)リスクや物件ごとのエネルギー消費量を詳細に公表する必要があります。投資家にとって透明性が高まる半面、報告作業のコスト増が配当にマイナス要因となる恐れもあります。
また、建物の省エネ性能表示制度が拡充されたことで、低性能物件を短期保有して転売する戦略は売却時の評価減リスクが高まりました。2030年の省エネ基準適合義務化を見据え、買い手が性能を重視し始めているためです。つまり、転売ではリフォーム費用だけでなく、断熱改修や再生可能エネルギー設備導入のコストも計算に入れる必要があります。
こうした制度変更は「情報収集が早い投資家ほど有利」という事実を際立たせます。最新法令を確認し、収支計画に反映させる習慣をつけることが、2025年以降の必須スキルと言えるでしょう。
初心者が後悔しないためのチェックポイント
まず、自己資金とリスク許容度を正確に把握しましょう。不動産流通推進センターの調査によれば、転売で利益を出している個人投資家の自己資金比率は平均28%です。自己資金が少ないまま高額物件に手を出すと、金利上昇や販売停滞で一気に資金繰りが悪化するからです。
次に、シミュレーションの前提を厳しく設定することが大切です。転売なら売却価格を市場予測の−5%で見積もり、販売期間も平均より1.5倍長く取ります。REITなら配当利回りを過去3年平均より0.5ポイント低めに設定し、価格下落率を最大20%まで想定します。保守的に見積もり、それでも運用が成立するか確認しましょう。
情報源の質も利益を左右します。国土交通省や東京証券取引所が公表する公式データを起点にし、SNSの体験談はあくまで「補足」として扱う姿勢が安全です。特に転売では、ピンポイントのエリアデータを自治体のオープンデータで確認する癖をつけると失敗を減らせます。
最後に、出口戦略を明確にしておく必要があります。転売であれば「半年以内に売れなければ賃貸へ転用」、REITであれば「配当利回りが2%を切ったら売却を検討」など、数値と期限を事前に決めておけば感情的な判断を避けられます。
まとめ
ここまで、転売とREITの仕組み、メリット、そして見逃しやすいデメリットを整理しました。転売は自己裁量が大きく高リターンが期待できるものの、短期的な価格変動や総費用増大のリスクに注意が必要です。一方REITは分散性と流動性の高さが魅力ですが、市場心理や金利動向による価格変動を無視できません。制度改正も収益に影響するため、最新情報を常に確認し、保守的なシミュレーションで備えることが成功の鍵となります。まずは自己資金と目標利回りを明確にし、自分に合った投資スタイルを選ぶ一歩を踏み出してみてください。
参考文献・出典
- 国土交通省 不動産価格指数 – https://www.mlit.go.jp
- 東京証券取引所 REIT指数データ – https://www.jpx.co.jp
- 日本銀行 政策金利情報 – https://www.boj.or.jp
- 不動産流通推進センター 年度別投資家調査 – https://www.retpc.jp
- 住宅金融支援機構 住宅ローン調査 – https://www.jhf.go.jp
- 金融庁 新NISA制度ガイド – https://www.fsa.go.jp
